
2020年読書マラソン『光』三浦しをん
2020年読書マラソン3冊目
『光』三浦しをん 集英社文庫
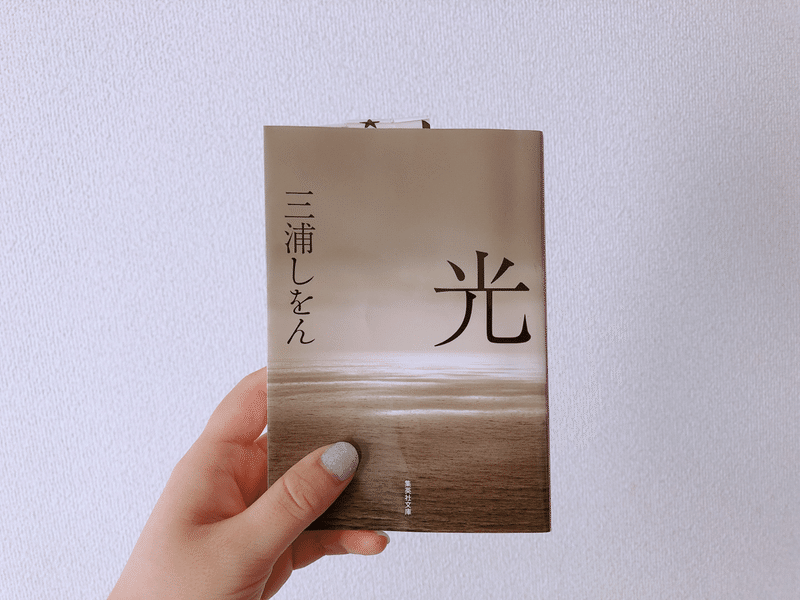
・作者および作品の有名度:★★★
・読書時の緊張度:★★★
島で暮らす中学生の信之は、同級生の美花と付き合っている。ある日、島を大災害が襲い、信之と美花、幼なじみの輔、そして数人の大人だけが生き残る。島での最後の夜、信之は美花を守るため、ある罪を犯し、それは二人だけの秘密になった。それから二十年。妻子とともに暮らしている信之の前に輔が現れ、過去の事件の真相を仄めかす。信之は、美花を再び守ろうとするが――。渾身の長編小説。
まずはじめに驚いたのは、この話が書き起こされたのが2006年だったということ。作中に出てくる津波の描写や、それによって被災者となった人間の心情があまりにリアルで、目を背けたくなるほど的確だったから、てっきり東日本大震災を基にできあがった話だと思っていた。これを想像や過去の情報から創作した三浦さんの才能に感嘆した。
津波という非日常度の高さとその描写の精緻さから、それがこの作品で最も大きなテーマかと思いがちだが、読んでみるとそんなことはなかった。津波は登場人物に影響を与えてはいるが、それは過去の一出来事に過ぎない。そして登場人物は「被災者」という日常と少しかけ離れた存在ではなく、誰しもがなり得そうな存在として作品の中に生きている。
※※以下、ネタバレを含みます
ポイント① 美浜島という"世界"について
信之が起こした事件は、津波がなければ起こらなかったものかもしれないが、もともと彼らの住む美浜島には、理不尽や大きな力に対する諦念のようなものが蔓延っていた。それは本州から離れた「島」という地理や、たいていが遠縁の親戚という島の近すぎる人間関係が生んだものなのだろう。
金も家族もない灯台守のおじいさんに対する
「島民の諦めとあきれまじりのなまぬるい受容」
母親に出て行かれ、父親からの暴力に耐え続ける輔に対し、見て見ぬふりをする島民の
「常識的な保身とわずかなうしろめたさ」
狭いコミュニティには往々にしてある、古くからの暗黙のルールに従わねばならない空気や、それが引き起こす思考の停止、そして距離感が近すぎるが故の妬み嫉みといったものが、島には存在していたようだ。
「美とも平安とも無縁だった。破壊の大波に飲みつくされるまえも、島は狭い世界に生きる人間の嫉妬と猜疑と惰性に満ちて、黒々と葉を繁らせていた。その木には血の色の花が咲いていた。」
ポイント② 津波が信之にもたらしたもの
先に記述したように、島にはもともと大きな力に対する諦念があった。しかしこれまでで最も「大きな力」である津波が起こり、信之は本格的に"すべてを"失ってしまった。家族を、家を、生まれ育った町のすべてを。
そうした経験が、社会や人と一定の距離を保った信之の姿勢を確立していく。諸行無常を受け入れ、それに対し激しく憤ったり嘆いたりすることなく、ただはなから希望は抱かない。それはあの夜、絶望に浸る余地もないほど一瞬のうちに、彼がすべてを奪われてしまったことと関係しているのかもしれない。
家族を愛そうと尽くす信之が、朝家を出て最寄り駅に着いたとき。
「向河原駅へ着くころには、家族を忘れた」
よその家庭とは違い、娘の写真を全く撮ろうとしないことを妻に咎められたとき。
「脳細胞は刻々と崩壊へ突き進む。俺の死とともに消える個人的な記憶を、記録にしてまで残して、なんの意味がある。」
娘の小学校受験や、そのための夏期講習の話を一方的にする妻を相手にしているとき。
「思いがけず一瞬で死ぬこともあるのだと、信之はよく知っている。幸せに対して確信を抱ける妻が、不思議で不気味な存在に感じられた。津波と同じくらい圧倒的な力を宿している。」
家族を大切にする「普通の夫」を務めようとする一方で、信之の意識の底にあるこうした静かな絶望とでもいうべきものが、彼と周囲との間に埋まらない距離をつくっていた。
ポイント③ 過去の美化
人間は誰しも、過去を忘れ、あるいは美化して生きている。そうしなければ到底、生きてなどいけないからだ。信之もそれは同じだった。彼はやがて、あの夜の出来事、そしてそれよりも前の島での生活に、「光」を求めるようになる。
「おまえと俺が、楽しく島で暮らしてたころの話だ」
「海に潜って魚を捕ったり、山で木イチゴを摘んで食べたりしただろう」
信之は、これは冗談だと前置きを入れることもなく、まるで事実のように幼なじみに同意を求めた。過去を楽しく明るい思い出に塗り替えようとするかのように。
そして、彼が最も光を見出そうとしたのが、あの夜だった。
「美花を暴力から救ったのは、信之の暴力だ。信之の振るった暴力が、そのあとの信之を救いつづけ、行く道を示しつづける。」
「だが、やはり美花も俺を忘れていなかった。俺を呼び、求めている。」
「美花はきっと、俺を待っているはずだ。」
あの夜、確かに美花を救い、それから美花が自分を求めるようになったと、信之はずっと考えている。事実がどうかはこの本を読めばわかるが、いずれにせよ信之は美花を大事に思っていたというよりは、「美花を自分が暴力から救ったという過去」を己の心の支えにし、生きているような節がある。彼にとって、そこに美花の本心は必要ないのだろう。
ポイント④ 信之と輔にとっての「光」
あの夜にかんして、信之と輔の中には共通している記憶がある。
「きれいに照らし出された海へつづく道。そこを通って、島の何もかもは持っていかれた。」
「あんたは見たことないだろうな。真っ暗な空に、白くて大きな月が出てるところを。夜の海に月の光で白い道ができる。本当にきれいだ」
「月が出ていた。凪いだ海に、水平線までつづく白い月光の道ができていた。」
すべてをなくした夜の、すべてが持っていかれた後の海にできた、月光の道。信之と輔と、そして美花が見て、共有した記憶。
この作品の題名について、作者の三浦しをんさんはこう述べている。
今回はもう『光』しかないなって思ったんですよ。珍しいケースでしたね。書きながら「人を暗いほうに導く光も、あるんじゃないかな」と思いました。
(引用)三浦しをん『光』刊行記念スペシャルインタビュー
http://renzaburo.jp/shinkan_list/temaemiso/081126_book03.html
人を暗いほうに導く光。信之や輔にとってそれが、あの夜の海にできた月光の道だったのかもしれない。
ポイント⑤ 狂信的な依存性
大震災を生き延び、記憶や経験、秘密を共有した彼らは、ときに狂信的なまでの依存性を見せる。
輔は信之に。
「俺たちだけが生き残り、俺たちだけが秘密の記憶を共有した。あの夜の島のにおいを覚えている。」
「島の王。輔が焦がれてやまない守護神。眠りに就いた輔の英雄は、美花の危機を感知したときにだけ目を覚ます。」
信之は美花に。
「どうしてだろう、と信之は思った。膿んだような甘い日の果てに生まれ落ちた秘密を、この世で共有するのはお互いだけなのに。」
「さあ、ここから創世の新しい神話をはじめよう。ひとを、家を、港を、美浜島にあったなにもかもを、二人で生む。死と壊滅の地をよみがえらせよう。」
生死の境をともにし、そこから生き残り、大きな秘密をともに抱えたあの夜は、彼らにとって互いの存在を神話的なほどに尊く、つよく感じた日ともいえるだろう。
ただし輔は信之に、信之は美花に、というように、それぞれの気持ちは一方的なものだった。
求めたものに求められず、求めてもいないものに求められる。俺も、美花も。まったくもって、よくある不幸だ。
・・・
このnoteの冒頭で述べたことを、ここに再度記してみる。
"津波は登場人物に影響を与えてはいるが、それは過去の一出来事に過ぎない。そして登場人物は「被災者」という日常と少しかけ離れた存在ではなく、誰しもがなり得そうな存在として作品の中に生きている。"
津波を生き延びたり、事件の秘密を抱えたりと、共感しづらい特殊な過去も抱えているが、彼らも一般的な人間であり、作中には共感できる点がたくさん出てくる。
田舎のコミュニティで、大きな力に対する諦めを背負って生きているところや、今の自分を保つために過去を正当化し美化していくところ。過去に負った傷が原因で、人や社会との間の溝を埋めることができずにいるところ。
彼らのもつこうした一般性は、彼らのような人間がごく身近にいる可能性、そして我々がある日突然彼らのようになってしまう可能性を示唆しているのかもしれない。
ある日突然、津波に遭遇しすべてを失う。罪を犯してしまう。知人が罪を犯した現場を、目撃してしまう。
そんなとき自分ならどう動くのか。何を感じ、考え、生きていくのか。
そんな風に自分の現実と置き換えながら読んでみると、さらに味わい深くこの作品を楽しめるかもしれない。
2020年読書マラソン、4冊目にバトンタッチです。
よろしければサポートお願いします。頂いたサポートでエッセイや歌集を読み、もっと腕を磨いていきます!
