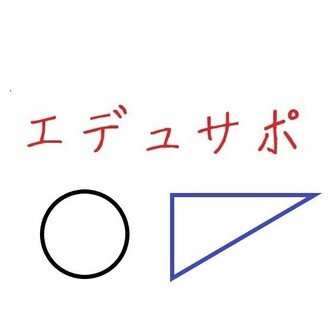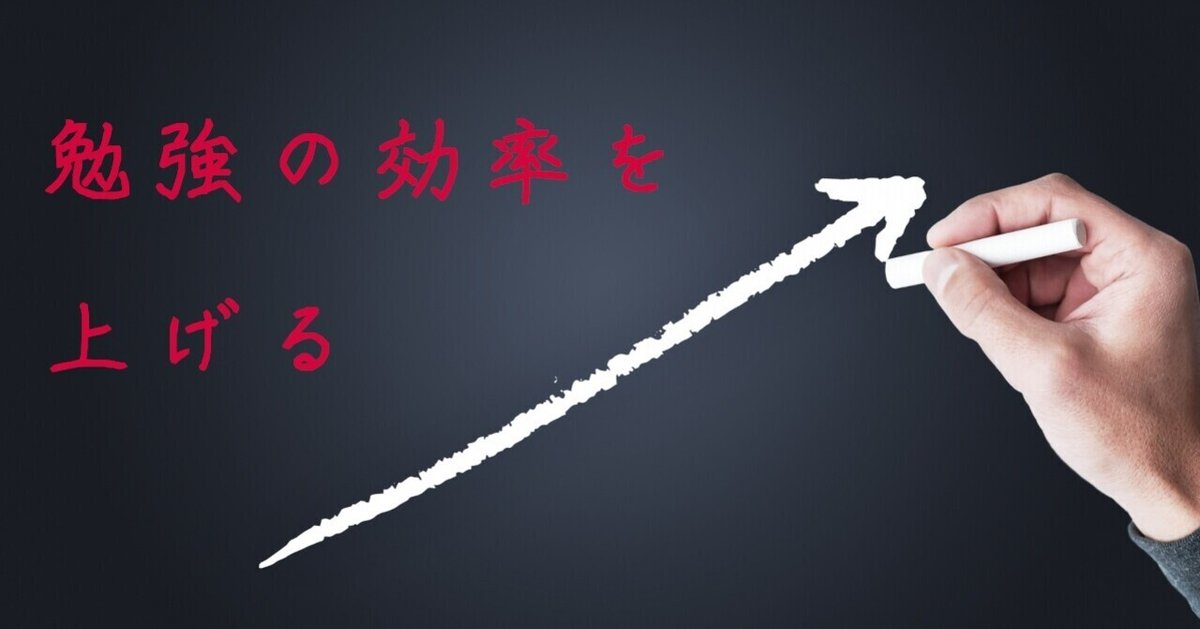
勉強の効率を上げる方法。それは効率の悪い勉強をすることです。
こんにちは。エデュサポです。
勉強を教えていると、保護者や生徒からよくこんな質問を受けます。
「勉強の効率ってどうすれば上がりますか?」
「漢字や英単語を覚えるコツはありますか?」
「そもそも勉強のやり方がわかりません。」
今回はこういった質問にお答えします。
「勉強の効率を上げる」ことをテーマに解説しますが、今回の記事は本当に基礎的なお話になります。基礎的で本質的なお話です。
本質的な部分から書き始め、少しずつ具体的なテクニックへと話をすすめていきます。
記事のタイトルを見て、「ああ、よく分かる」と思った方には基礎的すぎる話になると思います。
記事のタイトルを見て、「どういうことだろう?」と思った方を対象に解説します。今回解説する内容は以下の7つです。
1,勉強はまず量である。
2,教わって当たり前のマインドは早期に捨てる。
3,模試や定期テストをうまく使う。
4,問題集は1冊をやり込む。
5,漢字や計算練習は毎日取り組む。
6,結局基礎力。応用なんてない。
7,テストに出ない勉強も大事。
私は以前、塾講師の仕事をしていました。
集団塾と個別塾で講師と教室長を務め、オンライン教育系の塾運営の仕事をしていた時期もあります。小学生から高校生まで担当したことがあり、TOEIC対策として社会人に教えていたこともあります。
かれこれ20年以上、塾業界で働きました。
今までの経験を基に解説します。
あなたの参考になれば、とても嬉しいです。
1,勉強はまず量である

いきなり今回の記事のテーマを否定するような内容ですが、ここが勉強の効率を上げる一番の本質の部分になります。
勉強はまず量です。量がなければ質は上がりません。
コツや方法論を聞いてくる方の多くは、「これですべて解決!」という答えを期待されるのですが、少なくとも勉強の効率というテーマでは「これですべて解決!」という答えはありません。ガッカリされた方にはすみません。
まずは1日5時間から
まずは1日5時間勉強してみてください(学校の授業を除く)。時間の長さが正義ではありませんが、時間の長さは目安にはなります。勉強の効率のことを考えるのは、1日5時間勉強できるようになってからがよいでしょう。
地域や学校にもよるのですが、生徒たちに「1日5時間勉強しましょう。」というと、冗談だととらえられることも結構あります。
「先生!1日5時間も勉強できるわけないじゃないですか!」という感じです。
念の為確認しますが、1日5時間勉強というのは冗談ではありません。本気で言っています。受験生であれば、学校が休みの日は1日12時間や15時間が目安になったりします。5時間は序の口です。
「なかなか成績が上がらない。」という悩みは、この「勉強量を増やす」ということで、ほとんど解決します。逆に言えば、勉強が苦手だと思っている人のほとんどは、勉強量が足りていません。
勉強時間の確保→効率を考える
ただし、勉強時間が長ければ長いほど良いというわけでもありません。ここで初めて「効率」の話が登場します。まずは勉強時間を確保し、その上で効率を追い求めてください。
勉強量を確保しながら、勉強方法を少しずつ改善していきます。一つひとつの対策は小さな効果しか生みませんが、その積み重ねが大きな効果になっていきます。
この記事のタイトルの真意はここにあります。まずは効率が悪くてもたくさん勉強して、問題点を少しずつ改善していき、少しずつ勉強の効率を上げていくことが大切です。初めから上手くできる人なんてほとんどいません。失敗を重ねて、少しずつ成長していくのです。そういった意味で、勉強の効率を上げるためには、まずは効率の悪い勉強をする必要があるのです。
少し長くなってしまいましたが、一番本質で一番大切なお話でした。勉強の効率を上げるテクニックというものはいろいろとあるのですが、この本質が理解できていないとどれも活用することはできません。「ここまでの解説がよくわからなかった」という方は、ここまでを何度も読み返して理解してください。最重要です。
ここからは少しずつ具体的なことを解説していきます。
2,教わって当たり前のマインドは早期に捨てる

ここもかなり本質的なお話になります。
最後まで記事を読んでいただきありがとうございます!とても嬉しいです!サポートをいただけると大変大きな励みになります。