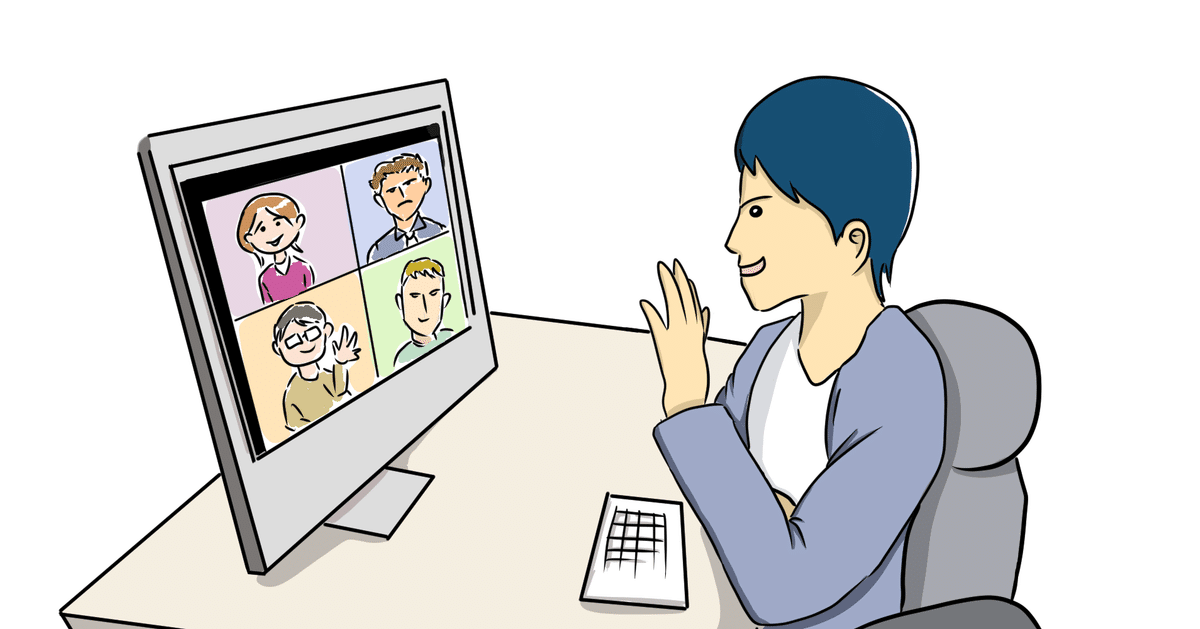
1400年前の理想の皇帝に学ぶ:「貞観政要」
「貞観政要」とは?
「貞観政要(じょうがんせいよう)」とは唐王朝の二代目皇帝・李世民(在位626-649)が、彼の臣下と話し合った事柄や上奏文・詔勅をまとめたものである。皇帝ー臣下の理想の関係を後代に伝えるために編纂され、日本でも北条政子、徳川家康、明治天皇が手に取ったという。中国の古典として、名前だけは知っていたものが、講談社学術文庫版で手に取る機会に恵まれた。
主な登場人物
太祖(李世民):
唐の二代目皇帝。絹をプレゼントするおじさん。本書のエピソードの大部分は彼の発言か、臣下への質問から始まる。臣下の的確な返答や鋭い上奏文に対して「卿の言うとおりだ」と締めくくり褒美を与えるのがお約束。
隋末~唐初の動乱期を戦い抜いた皇帝であり、隋の煬帝を度々批判するが、実は兄殺しの次男など共通点がいくつかある。
魏徴:
太祖の兄・李建成に仕えた人物。弟の人望を恐れた主君に離間策を授ける。兄を討った世民から後にそのことを責められるが、「彼が私の言う通りにしていればこうはならなかった」と言い、その率直さを買われる。
本書に登場する臣下のうち頭一つ抜けて出番が多く、本書の意図を考えれば皇帝に的確な意見と容赦ない突っ込みをする理想の臣下なのだろう。
房玄齢・杜如晦:
李世民の最古参の臣下の二人。魏徴の離間策で狙われたのは彼らである。
両者とも太祖の治世で政権の中枢を担ったが、杜如晦は630年の早くに死去しているため出番が少ない。
最良の皇帝の姿とは?
本書の概要や内容は冒頭で述べた通りなのだが、太祖が話題にしている事柄や本人の失敗談、太祖や重臣が過去の指導者に向ける批判を見ると、1000年以上の時の流れに耐えた「指導者像」が朧気ながら見えてくる。
1.優れた指導者は、諫言を愛する。
「貞観政要」で繰り返し説かれるのが、臣下からの意見を聞き、受け入れることの重要性である。口先だけで臣下の意見を聞くポーズを取るのはまったく不十分で、太祖はいかめしい雰囲気なので柔和な表情を取るよう気を付けたことから始まり、多くの意見を積極的に出させるために(周囲の反対を押し切って)わざわざ褒美を与え、詔勅に誤りがあったら意見することを奨励し、官僚が皇帝の命令を右から左に素通ししないよう指示している。さらに、仕えた主君によって働きがまるで違った人物を例に、臣下が忠臣かスタッフの一人で終わるかは上司の待遇に掛かっていることを示唆する。
太祖自身も、宮殿の中にいる自分は世の中が見えていないことを度々危惧している。
(もっとも、太祖も治世の後半は独裁色を強めていたようであり、魏徴にチクチクと指摘されている)
2.優れた指導者は、先人の過ちに学ぶ。
乱世から治世への過渡期に生きた指導者たちの記録であるため、先人の失敗について議論するエピソードも多い。特に槍玉に挙げられるのが煬帝だが、彼の暴政を止められなかった隋の重臣や、天下統一の後に自堕落になった晋の武帝(司馬炎)、自分の才能を誇って行政の役に立たない文学作品ばかり残した魏の文帝(曹丕)も批判の的になっている。三国志ファンならニヤリとすることもあるかも。
古典で伝わる失敗談についてもしばしば議論されており、「あれはそういう意味だったのか」と納得した太祖が見られる。
価値観のアップデートなどというのは、彼らには無縁のものだった。
教訓と規範は、過去から学ぶものなのである。
3.優れた指導者は、自分の非を認める。
唐の時代から1000年以上が過ぎた現代でも、地位や体面のある人物にとって難しいのが「非を認める」ことだろう。そのような特別な立場の人だけでなく、一般の人にとっても、身分制がなくなった現代、ウェブに言行が残り続ける現代ではなおのことかもしれない。
本書でも、自らの言行に対し、それは誤りだと臣下から指摘されて改める太祖の姿が度々見られる(なお、その指摘さえも撥ねつけてしまう太祖の姿もしっかり記録されている)。中国史で指折りの名君でさえそうなのだから、後世の読者もどれほど襟を正す思いだったろう。
4.優れた指導者は、世評を意識する。
中国の皇帝とは、地上世界=天下を治める天命を受けた君主である。したがって理論的には、統治する人民に対して責任を負う立場ではない(人民への奉仕はあくまで君主の「徳」=中華的ノーブレスオブリージュである)。
しかし現実の問題として、人民は統治者の力量に満足・不満の意を示すし、あまりに酷ければ王朝は倒れ、後世で酷評される。
隋を打倒した太祖と彼の重臣たちは、自分たちがそういう立場に立ったことをよく理解しており、課税や労役には慎重な姿勢を見せる。人民こそが自らの採点者だとよく弁えているのである。
5.そして理想の臣下は、上司への進言を恐れない。
中国の王朝には、皇帝に対して諫めることが仕事の官職があった。三権分立の概念もない時代に、皇帝へのブレーキは官僚機構の中に組み込むしかなかったのである。だが、それが機能するかどうかは当事者よりも皇帝の度量によるところが大きかった。魏徴は諫め役として、太祖の面子を立てつつ、故事や道理を引き合いにたびたびブレーキ役として行動する。太祖の政敵に仕えたキャリアがある彼にとって、どれほど勇気を必要としただろうか。
(ちなみに、魏徴は太祖からたびたび特別ボーナス的な報酬を受け取っている。これは読む側の立場によって解釈が変わるだろう、というのは、筆者の俗っぽい感想である)
