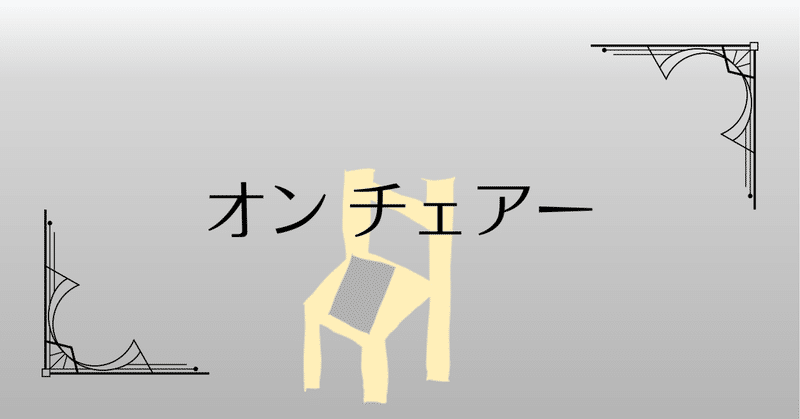
【小説】オン チェアー
「イサム先輩って、小説とか読むんですか?」
エレベーターを降りて会社入口へ向かう途中、
上司との空気感に耐えられなくなったのかまた
塩野が口を開く。汐見だったか。どっちでもいいか。
「俺はねぇ…小説はあんまし読まねえんだよなぁ…。」
「あー…そうなんですか…。
それはなんか、そのぅー、理由とかなんか、
あるんですか?」
ウィーン。
「んー…まあ、そうだなあ。
あんま人に言うことでも無いけど、あるにはあるよ。」
ウィーン。
「あっ、そうですか。それは、その、すいません。」
またか。昼食にこいつ誘ったのは失敗だったかな。
さっきから朝食はどうだの好きな色は何だの
どうでもいい質問を繰り返してはすいませんの一言。
こういう煮え切らない奴とは飯を食っても面白くない。
挙句にこいつはたった今
俺の唯一のタブーに触れやがった。
これは多少痛い目を見せてやらないと気が済まない。
「お前、俺が小説嫌いな理由気になるか?」
「えっ、あっ、いやそのー…はい。」
言ったな?
「じゃあ話してやるよ。少し長くなるけど良いよな?」
「ぁはい、大丈夫です。」
「おう。じゃあどっから話すかな…」
俺は生まれた時から要するに
シングルファザーの家ってやつでさ、
母親ってのを見たことがなかったんだよ。
まあ別に元々いて居なくなったとかいう訳じゃ
ないからさ、案外辛かったかって言うと
割とそうでもなかったんだな。
んで親父ってのが1人で俺を育てることになる訳で
そりゃもう頑張ってくれたわけだ。
何しろ養育費が必要ってことで、あんまし
家には居なかったな。保育園に入る前までは
物心も着いてなかった訳でそんな覚えてはないけど。
そんで園に入って…ってまあ、ここはいいか。
まあそこでは特に何事もなく過ごしてたんだよ。
純粋無垢な少年だった。
ただ問題は小学校に上がってから。
こっから今思えば俺の人生が悪いっていうか、
根が腐るような方向に行ったんだな。ん、人生?
まあいいや。で、園まではまだ良かったんだよ。
言った通り特に問題がなかった。ところが小学校だ。
ここは近くの幼稚園からの合流もあるだろ?
俺の通ってた小学校に入学してくる連中っていうのは
割と幼稚園組が多くて、まあその、要するに
親がどっちも居るやつが多かったんだな。
そこで授業参観とか弁当が必要な日とかあるだろ?
さっき言った通り親父も大変で、正直そんなの
時間割いてられないって具合だったんだろう。
別にそれを憎んじゃいないよ。しょうがない。
でも周りの連中はどうかと言うと、
こいつだけ、と囃し立てる訳だ。
俺は元々友達が多かった訳でもない…
と言うよりも、本当に上手く作れなかったんだな。
俺と同じく親がどっちか居ないやつは
他にも居て、そいつらが標的にならなかったのは
そこにあるんだろう。
低学年の頃は教員の力ってのも強かったんで
まだ良かった。それでも辛くはあったし、
1回親父を夜遅くまで待ってなんでだよってさ。
そん時俺の覚えてる中では唯一かな、
親父が相当溜まってるところもあったのか
1発もらったんだよ。ほらここ、少し窪んでるだろ?
まあそんなんで、中学年あたりからは学校には行くけど
少しの空き時間には図書室に逃げてたんだ。
1回だけ保健室登校はどうだなんて言われたけど、
やめたよ。最初はいいなと思ったんだけど、
結局迎えに来る親がいる奴が行く所だ。虚しくなった。
まあそんな訳で周りは敵だらけだし
教員の力は弱まるし親父には泣き言言ってられない。
俺はそこで俺の中に逃げ道を作ったんだ。
図書室にはだから、その時4年くらいか。
ずっと通ってて…ってそうか、
本な、
俺なんだかんだ逃げ場所とか言いつつ
好きになってたんだよ。読むのがな?
まあそれで、色々読む中でなんか物足りなさも
感じてたんだよ。
どれもこれも、結局は
真面目に勉強するとか親が大事だとか
綺麗事ばっかり並べ立ててあってさ。
果ては低学年なんか品の無い言葉を
書いておけばウケるみたいな節があるだろ?
うんことかハゲとかお前も笑ってたんじゃないか?
それでそうそう、俺の中に逃げ道を作ったんだ。
何となくもう分かるかと思うけど、
自分で書いちまうってことだな。
実はそうしようって思ったきっかけはもう一つあって、
俺の通学路に1箇所古い本屋があったんだけど、
そこで小説なんかをパラパラ見てたんだよ。
もちろん小学生だからさ、
幾ら図書館で本読んでるったって
難しい小説なんかは全くだったよ。
でも、俺はそこで足りない頭搾って
何とか理解しようとした文に衝撃を受けたね。
部分部分だけでは理解出来るところがあった。
小説の中では人がいとも簡単に、
それもえげつない状況に陥れられるんだ。
俺は、気持ち悪くなりつつも快感に似たものを感じた。
気持ち悪くなっている間だけは
それ以外の嫌なことを忘れられるんだ。
自分の仲間が見つかったみたいにも思ってたのかもな。
ああ、まあそれで書き始めたんだ。小説を。
はじめの頃は今思い返しても恥ずかしいもの
ばっかり書いてたよ。でも夢中だった。
極端にグロテスクなもの、
極端に怖いもの、
極端に気持ちの悪いもの。
話の構成なんかどうでも良くって、
自分の中の負を吐き出すことばかり考えてたんだ。
それで小学校もそのまま卒業して、
中学に入ってもすぐはやること同じだったな。
そのまま卒業ってのはあんまりその進学に変化を
感じなかったからだな。だってやること
同じなんだから。
ただこの頃から少し構成も拘りだしたし、
想像力なんかにも幅がききだしたんだ。
保健体育とかの授業もあったし、
ここでも俺に友達なんか居なかったけど
周りのゴシップなんかにだけは敏感だったな。
そういえば恥ずかしい話だけど、
俺は中学時代に自分の書いた小説で精通してるんだ。
気持ち悪いだろ?
でもなんだかその時は俺はこれだけの技量がって
自信に思ったね。
それから高校に進学。それもさっきと同じく
「そのまま卒業」してって感じだ。
成績も悪くはなかったし、
特に教員も特段俺に注意払うことも無かったから
受験だからって何だってことも無かった。
まあここでは流石に周りの鬱陶しい連中が
居なくなったってのが唯一変わったことか。
今思えばすげえよなあ、あいつら。
親が1人だけってきっかけだけで中学まで
標的作りのネタに出来てたんだぜ。笑えるよ。
ま、それで高校でもやることは同じ。
ただ親父がスマホを持たせてくれてさ、
そこで初めて公募ってのを知ったんだ。
公募って分かるか?ああ、そうか知ってるか。
じゃあ賞金出るのもあるってのは知ってるな?
俺はそれも目標にしだしたんだな。
それで運良く3回かな。3年の間で賞金取れてさ。
こんな下らないきっかけで続けてきたことでも
実を結ぶんだなってちょっと泣いたこともあったな。
まあ実際賞金取れたことってよりも、
俺の金で親父に焼肉奢れたことが嬉しかったんだ。
あんま話には出して無いけど、
出さなくていいくらい良い親父だったんだよな。
1回殴られはしてるけど、それだけだったし。
まあそれで3年の時かな、就職か進学か、
俺は迷わず就職を選んで親父に楽させてやろうって
思ってたんだけどさ、
大卒との給料は全然違うぞ!って言われて、
親父さえ良ければって大学に進学したんだ。
倫理か政経かなんかで丁度やってたんだよな、そん時。
大学生の期間はモラトリアム期間だ、みたいなこと。
この時間で小説家になってやろうっても本気であって。
それで〇〇大学の文学部に行ったんだけど、
これが面白いくらいにどこの出版社に持ち込んでも
ネットで送っても鳴かず飛ばず。
ゼミに入っても友達も出来ないまま4年の
就活の時期に入ってしまったんだな。
そしてもう俺も叶わない夢なんか諦めて
って思った時だ。親父が逝っちまったんだ。
俺はもうなんか、
自分の空虚さが本当に辛くなってさ。
原稿とか文章データとか見ても訳わかんなくなったよ。
俺の小説の根幹は結局小学校の頃から変わらない、
周りへの怨恨だけで出来てるから、
それに人とも関わっていないから浅いものしか
書けなかったんだな。
思い返せば誰だって思いつくんだあんなもの。
それで俺はそこで何をしたと思う?
マッチングアプリに手を出したんだよ。唐突だろ?
童貞を捨てる経験を得れば何かが変わると思ったんだ。
親父のことできっと気が動転してたんだな。
と、思いたいだけかもだけどな。
だけどな、長々聞いてもらった訳がここにあるんだよ。
俺は今話そうとしてもほら、手が震えてるだろう?
冷や汗もかいてるのがわかるかな。
ちょっと待ってくれな。
よし。
…よし。
それでだ、俺が小説に大学まで賭けてきたことは
今言った通りなんだ。小説が好きとかじゃない、
全てだったんだ。じゃあ何故読まなくなったか?
俺はマッチングした女と
ファミレスで待ち合わせをしていたんだ。
小説のネタなんかもいつも通り考えていた。
溶ける顔。穴だらけの腕。眼球にまち針。指に溶岩。
人間焼肉屋。胎児焼却炉。ドア前に必ず殺し屋。
脳髄かき混ぜ。人皮ソーセージ。
ろくな事は浮かばないが、この時間はやはり
世界を隔絶しているようで好きだったんだ。
…今思えばこれが最後のネタ出しだったかな。
時間5分前になると正直見るからに頭の悪そうな
女が来たんだ。
黒のキャスケットに肩を出した薄緑のブラウス、
黒のスキニーに底の厚いブーツを履いてさ。
それに俺でもわかるような高いカバンを、
俺よりも年下…ってのは一応アプリで知ってたし、
見て確信したんだけど、そんな奴が持っててさ。
ああ確実に俺は今日この女と寝るんだなって思ったよ。
ごめんなさい遅れちゃって〜、と
俺が頼んでおいたコーヒーの置いてある席に、
対面する形で座ると、途端にその女が言ったんだ。
お兄さんって小説家なんですか〜?
そういえばそんな情報書いてたかもしれない、って、
さっきも言った通り気が動転した中で書いてたから
他人事みたいなんだけど。
ええ、そうですよ。って言うと、
なんだか少し理性が戻ったというか、
その女が性欲の対象じゃなく人間として見えたんだな。
私も実はちょっとだけ書いていて〜。
私、どんなの書いてるか気になります〜。
って続け様に言うもんだからもう気が良くなったよ。
君みたいな子には少しハードかもしれないけどって
饒舌に語り始めた。
まあもちろん女の人となんか話したことも無かったから
えっそのー、とか、あっえとっ、とか
あんまり上手くは話せなかったんだけどな。
でもまあそれで話し始めると
その女案外食い付きがいい。
耐性があるんだな。俺は少し嬉しくなったんだ。
ところがだ。話を続けていくと
段々とつまらなそうな顔になっていく。
こりゃまずいと思って話を切り上げると、
シーンとした時間になったよ。
実際の時間なんかもちろん意識してない訳だけど、
体感でいえば10分位はそのままだった。
コーヒーの湯気も消えてたはず。
そんなもんなんですね。
口火を切ったのはその女だった。
俺ははじめその空気感からの解放にほっとしただけで
意味を理解するのは少し時間がかかった。
SONNNAMONN。ソンナモン。そんなもん。
漸く頭で消化出来ると俺はもう腹の底が熱くなってね。
なんでこんな股のゆるそうな
人生楽勝みたいなクソ女に
そんなこと言われなきゃならないのか。
じゃあお前は何かもっとあるのかよ。
そう言ったんだ。でかい声で。
周りの客と店員が一斉に不安そうに
こっちを見たもんで直ぐに冷静になったんだけどね。
もちろんその女もキョトンとしてしまった。
ああなんで俺はこんなことをと思ったよ。
でも…でもそこからだったんだ。
ごめん、ちょっと待ってくれ。もう1回時間をくれ。
見てくれよ、足がふらついてる。
肩肘も張っているのが見てわかるだろう?
…すぅー…。
…ふうー…。
…よし。じゃあ続きだ。
その女は、キョトンとしたのは本当に一瞬で、
直ぐに笑ったんだ。アレは笑顔だった。確かに。
ただ…俺はあんなに人の笑顔を怖いと思ったのは
初めてだった。
決して失敗した人を慰めるようなものでも
でかい声を出した男を嘲笑うようなものでもなかった。
獲物を前にして確実に仕留められると分かった時の
動物…いや、とにかく悪意ある何かのような
表情だった。
そして今の俺みたいに強ばったところを
耳元に囁くように手を置いて、言ったんだ。
…何を言ったかっていうのは…言えない…
と言うよりも覚えていない。
普通、女性にそんな囁くようにされたら
ドキドキするとかがあるんだろう。
だがそんなものじゃなかった。
あまりにも内容が…凄惨だったんだ。
いや、凄惨というのもあまりに軽い。
俺はそれまでに小説を書いていたこともあって、
辞書とは唯一の友達だって言えるくらいだったよ。
それでもだ。
あんな内容のものを表す言葉なんかこの世に無い。
断言する。それほどまでにその女は言葉だけで
俺を圧倒し、言葉だけで脳に映像を送り込んだ。
何より恐ろしかったのはその内容を、
おそらくその女は全て経験していたということだ。
でなければ有り得ない。あんなに酷い…リアルな…。
さっきも言った通り、その女は俺よりも年が下だった。
正直言ってそれほどまでの経験をしたというのは
有り得ない話だ。
だけど、現に俺はそれを言葉で見せられてしまった。
恥ずかしい話だけど、俺はその場で吐いてしまったよ。
胃液の臭いだけは覚えているんだ。
大丈夫?とその女は言ってくれたが、
例の笑顔だった。
俺は大袈裟に言っているんじゃなく
本能で恐怖を感じているんだなと
自分で分かるくらいだったが、
それと同時に小説家を辞める決意が固まったんだ。
何故このタイミングでか?言わずもがな、
彼女の言葉に魅せられたんだよ。
小さい頃なんかは大人になってみると
大したことでもないのに一喜一憂するだろう?
ちょっとした事でも悪いことしたって
何か満足気に思ったり。
俺は正にそれだって思わされたんだよ。
その女の呪詛のような言葉に比べれば
俺の発想の何と陳腐なことか。
それでまあ、一応は話は終わりだ。
周りの本が全部つまらなくなってしまったんだよ。
だからと言って俺が書けるなんてことは絶対に無い。
俺がこれだけの話を終えたと言うのに
志生野だかの反応は薄い。
これだから想像力の無い奴は。
「それで、えっと、
その後はどんな生活だったんですか?」
これでもまたつまらない質問をするのか。
「まあ、その後はそのまま…」
そのまま?
「どうなんですか、先輩。」
「いや、」
何だ?そのまま?
そういえばその後俺は何をどうしたんだったか。
ホテルに行った?違う。俺は…?
「先輩」
「いや、俺は…」
俺は、何をその後したんだ?
自分の人生が思い出せない?
いやそんなことあるはずがない。ならどういうことだ?
「…ダメね。到着してしまったわ。」
「到着?そういえばランチ…」
ここはあの時のレストラン。
「収穫無しね。一旦帰ってらっしゃい。」
「君は…そうか、俺は
ICUの照明のような、ほの明るさのある個室。
俺は久しぶりに椅子から降りた。
「すいません。俺また…
「良いのよ。E-36君。君はまだ2回目。
これからまだまだチャンスはあるもの。」
黒のキャスケットを被り直しながら、その女が言う。
「それで、小説の方は順調ですか?」
「んー、君が何かいい経験を取ってきてくれるって
思ったんだけど、私と会ったところから特に
何も無かったみたいだからな〜。」
悪戯っぽく微笑む笑顔はやはり怖いが、
俺の小説家としての生涯を託した人の、
小説と向き合う顔と思えば喜びがある。
「すいません。
俺、じゃあ今からもう1回行ってきますよ。
今度はいいネタのある人生送ってきます。」
「投薬はそんなポンポン出来るもんじゃないぞ〜?
下手すると君の本当のオリジナルの記憶にまで
ヒビが入る可能性もある。やめたほうがいいよ。」
「…っ。」
本来送るはずの幾パターンかの人生のうち1つを
実際の時間では1時間程で脳が描いて体験するのは、
確かに酷いダメージを脳に与えるというのは分かる。
ただ。ただ。
「俺はそれも受け入れたから…
俺には小説しかないから、あの時
協力させてくれと頼んだんです。」
吐きながらも、小説家になれないと思いながらも、
心では小説を捨てきれなかった俺のその女への頼み。
「…しょうがないねぇ〜。
まあまだ大丈夫だとは思うけど。」
良い小説の、せめて一欠片になれたなら。
「じゃあ、注射するから椅子に座ってねぇ〜。」
今度こそは一生分の体験を、記憶して持ち帰る。
覚悟を決めて俺は椅子へと座った。
創作の原動力になります。 何か私の作品に心動かされるものがございましたら、宜しくお願いします。
