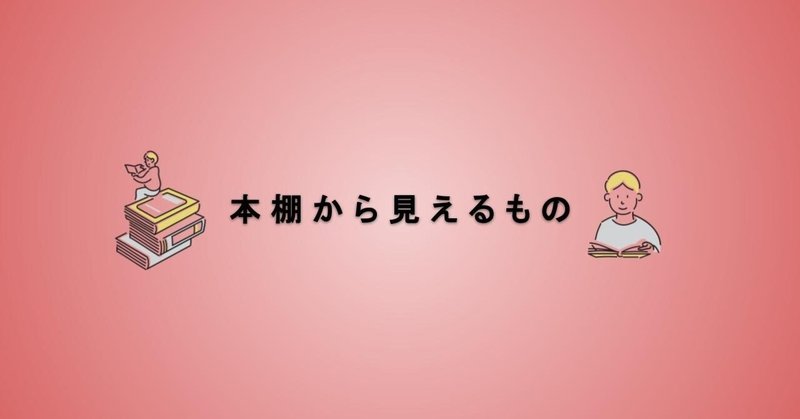
オススメ本#2~工藤 勇一 著『学校の「当たり前」をやめた。』
「目的思考」の在り方を考え、「当たり前」を見直すきっかけに
第二弾は、教育関連で是非ご紹介したいものです。
私が職員として、子どもたちに指導をしているときに、
「教科書を疑え」
ということを伝えていました。勿論、書いてあることが全部嘘だから信じるなということではなく、そこに「なぜそういうことになっているのか?」という”考える”スタンスを常に持ってほしいという想いです。
※
子どもたちに伝えるには、端的にわかりやすく、多少の”毒”をいれると興味関心を引きやすいという持論があります。
大事なのは、『”そもそも”何のために…?』という姿勢。
つまり『目的を考える』ことです。
この本の中には「当たり前」となっている「手段」を、そもそも何のためにやっているのかという「目的」から考え直すというビジネスのフレームワークとしても応用できる内容が沢山あります。
教育の現場だけでなく、企業・組織改革を進めていくうえでも非常に参考になる名著です。これをどう自身の直面する場面に応用させるかを考えながら読み進めることで学びにつながります。
それでは早速、こちらについて私のおすすめポイントも含め、ご紹介します!
秀逸な「はじめに」
正直、このおよそ10~12頁の「はじめに」を深く読み込むことをオススメします。「基本的な考え」それに伴う具体的な過程と実践、そして想いとメッセージが込められています。
ここに出てくる言葉を、どれだけ深く考えながら読めるかで、この後の具体的内容の解像度がよりあがることと思います。
個人的には「民間人校長ですか」と言われることに対する工藤さんの
『私にとって決してうれしい言葉ではありません』
というコメントに、相当なプロフェショナルさを感じました。
私は、民間の教育機関の人間なので、公教育機関の方や、他の業種の方とお会いすると、こうした声をいただくことが多いです。いただいた言葉は「誉め言葉」と解釈し、ある程度先進的なことや、人材育成も行えてきたのかなと思うことにしています。
しかし工藤さんは、『うれしい言葉ではない』と言います。
ずっと教育の現場で生きてこられた方だからこそ、かつての教育の現場を想い、「嬉しくない」と述べています。
100年も時計を戻す必要はありませんが、かつての学校は、時代の最先端にあり、教員もまた、社会の変化に最も敏感な人たちであったと思うのです。
いわゆる「民間」の経験を持った人でないと、先進的なことは行えないだろうという認識になっている現状に、「嬉しくない」と述べられているのだと感じました。
つまり視座は、”教育界”全般にあり、
”学校が変われば、社会が変わる”を実践しようとされています。
ここに共感し、私の立場では、公教育外から教育を変えることはできないかを考えた”はじめに”だったのです。
目的と手段の観点からスクラップ(見直し)する
この内容は具体例を通して「目的」と「手段」を見直すパートです。
宿題の必要性?定期考査の必要性?などなど。
全てのポイントは
”何のために、それをやるのか?”
なのですよね。
教育の現場だけでなく、職場にも応用することが出来ると思います。
私も実践した内容では、朝礼の在り方、会議の在り方…
※
現在進行形ですが、近日「朝礼」はなくそうと思っています。
より深く考察する「手段の目的化」
この言葉は、普段から私も使っている言葉です。
何を実践するにしても、それはあくまで手段であって目的ではないということを、忘れがちな人が多いのです。
教育に携わる身としては、この問いに対する正解を追い続けなければなりません。
「学校は何のためにあるのか」
学校に通うことは、目的ではありません。手段です。
それは「何のための”手段”」なのでしょうか?
そしてその手段は大きく
①何を教えて(カリキュラム)
②どう教えるか(教え方)
であるという観点から、江戸時代の寺子屋の話に展開しています。
温故知新とはよく言ったもので、私は
「近年の海外の教育手法が素晴らしい!」
「日本の教育は遅れている!」
という論調があまり好きではないのです。
良いものは良い、悪いものは悪い。
ただその前に日本人というアイデンティティや、独自の文化・風土を省みずに海外の実践をそのまま入れていくというのは、少し「?」なのです。
と少し話がずれました。
こうした「何のための”手段”」をまたいくつもの事例を通して、考えさせてくれる内容となっています。
これからの学校教育の新しいカタチ
この本の第3章以降は、実践された教育のカタチや、これからの学校教育のカタチを描いてくれています。
特に私が共感しているのが
「クエストエデュケーション」
「模擬裁判」
「麹中アフタースクール」
です。是非この内容をご覧ください。他にも素晴らしい取り組みがたくさんあります。
そして一番取り上げたい内容は、それに関連した
「未来の教室」(P.137)
です。これをどう形として作りあげられるか。私のやりたいことが詰まっている構想なのです。
こうした理想をくみ上げていくには、仲間が必要ですし、工藤さんはその風土を作り上げていくために『「当たり前」を徹底的に見直す学校づくり』をされてきました。
そのプロセスや実践方法に、組織改革や教育を志す人、そして教育に関わる人は、学びを得ることが出来るのではないかと思っています。
やはり最後には、「夢」「理想」を語る
人が物事を実行するときに、一番の原動力になるものは何か?
「好奇心」
と私は思っています。
”~をしたいという想い”は、好奇心からくるものです。
工藤さんの想いは第5章に詰まっています。
私は
『「早く大人になりたい」子どもを育てたい』
『教育の本質を取り戻す』
ここにポイントがあると思っています。この言葉だけでもワクワクしませんか?ここに私の”好奇心”はくすぐられています。
昨日、「普通教育ってなんだろう?」という記事を書きました。
この記事をかけたのは、この本のおかげかもしれません。
もっと言うと、工藤さんのおかげかもしれません。
この本に出会えたことに感謝です。
是非、教育に携わる人だけでなく、一つのビジネス書、または人生の考え方として参考になる本だと思いますので、ご覧ください!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
