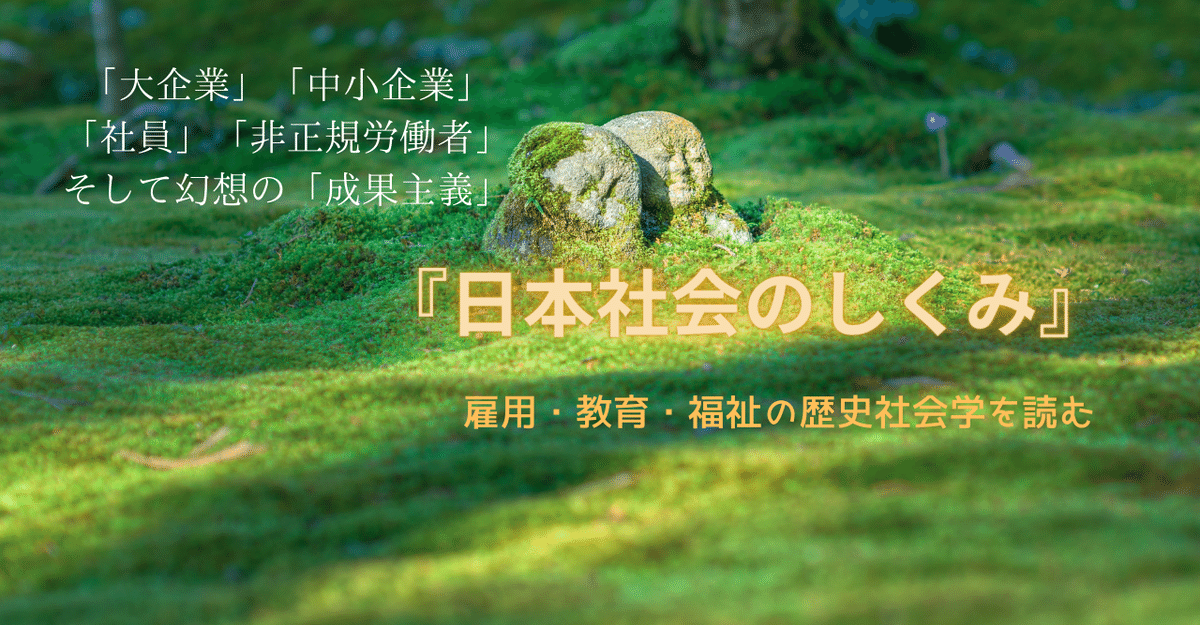
社会の二重構造と幻の成果主義『日本社会のしくみ』を読む(最終回)
小熊英二『日本社会のしくみ』を読んでいます。
日本社会で生きていくには3つの生き方がある(①はコチラ)、と筆者は語り、世界の働き方と日本のそれがどのように違うのか(②はコチラ)日本型雇用の戦前の歴史(③はコチラ)戦後の流れ(④はコチラ)を見てくることで雇用のシステムが変わり、今までは高卒や中卒の一般職員や工員がしていた仕事を大卒にさせるようになりました。これを「学歴代替」と呼びます。世界でこの流れはあり、アメリカではそのためにさらなる高学歴化が進みました。
①軍隊型の資格制度と人事異動と女性定年制
各企業は職能資格制度を導入しました。資格(主事とか参事)=基本給のことで、与えられた任務で結果を出せば資格は上がって給与も上がりました。一方で職能は「職務遂行能力」の略で主に人物や人格を評価したものになりました。どんな職務についても適応できる潜在能力、といった意味になり、当時の財界は「人中心の階層的秩序」と呼ぶことを好みました。こうした資格制度は各社ばらばらに導入されて互換性がないので、もしその企業を辞めてしまったら、それまで上げてきた等級も無に帰するものでした。
さらに定期人事異動制度が広まりました。これは大卒社員を販売や生産現場に配属することになった企業ですが、そのままでは士気が低下してしまうため、数年のうちに社員をローテーションさせるという制度になります。
戦前、定期人事異動とそれに伴う昇給があったのは大企業の上級職員に限りました。職工などは随時採用、長期雇用の保証ももなかったことを考えれば全社的定期人事異動は「社員の平等」の完成を示すものでした。
そしてこの制度を裏から支えたのが女性社員(高卒、短大卒)でした。女性の賃金が上昇する前に内規によって解雇するシステムは1960年度ころに達成されました。これは定期昇給が企業の重荷になったからです。女性の年齢別労働力率がM字カーブを描くようになったのはこのころからです。
この職能資格制度の普及は急激でした。戦後出来上がった「生活給」(年齢、家族構成、勤続年数)制度だと企業はコントロールできませんが、「能力」の査定ならば経営の裁量できめられるからです。また、この職能資格制度はあくまでも社内資格であり、企業横断的なものではありませんでした。
②新たな二重構造の出現
1970年代半ばまでに雇用の量的拡大は終わり、一定数の「社員」の採用(そうしないと昇進させた中高年に部下がいなくなるので)が行われ、景気動向のバッファーは準社員と期間工によってなされました。
また、高校進学率は1974年に90%を超え、大学進学率は横ばいとなりました。すると、少ない大企業への就職というパイを奪い合うために受験戦争は過熱しました。一流企業への就職ランキングから、一流大学への入学ランキングまで「横の学歴」に対する需要はとどまることがなく、「タテの学歴(大学院、博士号)」への関心はより一層薄くなりました。
受験戦争は大学のタイプに合わせた高校の履修選択につながりました。「国公立文系・理系」「私立文系・理系」と別れるこのコース選択基準は主に「数学の得手不得手」によって決まることが多く、どの教科もまんべんなくできるものが「国公立」へ。その残余が「私立理系」さらにあまったものが「私立文系」になるという消去法選択態度にありました。というのも日本企業の特にホワイトカラーに対する要請は
「特定の技能や仕事に固執せず、フレキシブルな働き方ができ、多科目に成績で評価された偏差値の高い、性格的にも適応性のすぐれた人材」
という一元的能力主義だったので、こういった選択こそ大企業の正社員にふさわしいものではありました。けれども「大学に進学できなかった」高校生、特に普通科の高校生は就職市場において職業科よりもさらに不利でした。そのため専門、各種学校が半失業青年たちのプールとなりました。
こうして社会は大企業正社員とその残余に分極しました。
地方の町内社会の支え手たちは自分の子どもたちを同じ自営業者にしようとは思いませんでした。自分にはかなわなかった高い学歴を子どもに与えようとし、そのことが地域社会の空洞化を招きました。
③人事考課の強化
いままでのことを続けていれば必然的に日本の大企業は労働力が高学歴化し、高齢化していきます。この人件費は企業にとり非常に重荷となりました。1977年日本鋼管では一般男子における係長以上の管理職比率は41%に増大していました。こうした管理職の増加は「資格制度」で選抜していけば抑制できるはずでした。ところが企業は「どの職務でもうまくやっていく潜在能力」の測定ができない、という理由で結局バロメーターが学歴しか存在しなくなっていきました。そこで企業は人件費抑制のために「人事考課」を使うことを考えました。一元的能力主義の人事考課は、結果的に採用にあたって企業が参考にする内申書と大変似通ることとなりました。(成績の記録、行動の記録とその評価)教育社会学者の刈谷剛彦は内申書調査でクラスの上位に付くものが大企業に就職しているという相関性の高さを確認しています。
④非正規労働者の増加
人件費の抑制に動く日本企業は人事考課のほかに「社員」の外部を作ることにしました。それが出向、非正規雇用、そして女性です。
まず、中高年社員のポスト不足への解消として「系列会社への出向」が行われました。これは官公庁が公社や公団を天下りに活用していたことと類似の対応です。
次に非正規雇用への依存が始まりました。非正規従業員という言葉が初めて雑誌に登場したのは1981年で、1984年10月「中間労働市場」を経済同友会が提案し、労働者派遣法が施行されてからです。
そして、女性の「活用」でした。高度成長期から性別定年制が導入され、これに対する訴訟と企業側敗訴によってあからさまな男女別定年制はなくなりましたが、慣習としては残りました。そのひとつが男女雇用機会均等法以降の「一般職」「地域限定社員」などの導入でした。
「大企業」と「中小企業」のあいだにあった賃金格差は高度成長期にいったん改善されましたが、それ以降はまた広がりました。1985年経済企画庁は「同年齢で同学歴だと同じくらいだ」といいましたが、そもそも中小企業には「中高年女性か高齢者、もしくは学歴が大企業ほど高くない」という非正規労働者が多かったのです。この頃から「大企業」「中小企業」に加え「正社員」と「非正規雇用」という新たな二重構造が出来上がりました。
⑤「日本型経営」は変わらなかった
もし日本が製造業の部品を自社生産していたら、もしくは下請企業も産業別労働組合に入っていたら、情況は異なっていたかもしれません。
1990年代に入り、「団塊ジュニア」世代により、大学進学率が再び上昇に転じました。これらの大量の人材を正規従業員として吸収することはもう企業にはできませんでした。特に成績下位の普通科高校卒業生は就職の紹介もなく、進学するほかはありませんでした。けれどたとえ進学をしても、派遣労働者などの「フロー型労働市場」(中高年女性や低学歴者を含む非正規労働者)へとリクルートされていきました。社会は彼らを吸収できる状態にはなかったのです。
日本型雇用慣行はそう簡単には変わらずに、厳選主義による年功賃金抑制がいっそう強まりました。2000年代、日経連は「雇用柔軟型」の導入を歌いました。」この報告書は日本型雇用の改革をとなえず、総額人件費の抑制を唱えました。つまり、従来型の社員はさらに少数精鋭に、3年程度の派遣による高度専門能力活用型の導入です。
またたびたび「成果主義」や「目標管理制度」も喧伝されましたが、一連の学歴主義と年功による賃金カーブを変えないまま「成果主義」を導入することは困難でした。日本の人事労務管理は職務ベースで行われず成果主義は幻想である、といったのは労働研究者の濱口圭一郎でした。日本社会のジレンマは、各社の内部で職務の価値づけを行っても、それが一社内の序列でしかなく、横断的な労働市場ができない限り成果主義は労働者の士気低下をまねくだけになることでした。しかし、企業はバブル期に大量入社した中堅層の賃金抑制を目的として成果主義を導入しました。そして、部下を評価する中高年管理職は発想の転換ができずに「努力と根性」を評価項目にしてしまうのでした。
こうした試行錯誤のなか、企業は余裕を失い、2015年の企業の教育訓練費は1991年の約六分の一にまでなりました。昇給や昇格はますます狭き門になり、社員は厳選されていきました。受験戦争は過熱し、一部の上位大学卒業者が何を勉強してきたかは問われず「コミュニケーション能力」「協調性」「誠実性」を求められて大企業に採用されています。明治時代から続く日本企業の慣習の束は当面変わりそうにありません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
