
interview Mark Guiliana:自分なりの“サイレンス”を見つけた先にあった音
マーク・ジュリアナの新作『The sound of listening』はクリス・モリッシー、ジェイソン・リグビー、シャイ・マエストロとのカルテット。「お!いつものアコースティックのジャズかー」と思っていたら、はっきり言って、これまでのマーク・ジュリアナのジャズ・アルバムとは全く違う。アルバムにはシンセが入っていて、自分でビートをプログラミングした曲もある。ただ、その違いはそこではない。アコースティックのセッション曲でも曲の構造からムードまでまるっきり違うのだ。
これまではどちらかというと高度なコンテンポラリー・ジャズ。マークが共演してきたダニー・マッキャスリンやアヴィシャイ・コーエン、ブラッド・メルドーらのサウンドとも通じるサウンドを、マークなりの美学で演奏しているといった印象だった。
しかし、新作は全然違う。そのコンテンポラリー・ジャズ的な複雑さや徹底的に構築されたクールな手触りなどが感じられず、実に人間らしく、どこか内省的でありながら、それがなんならスピリチュアル、もしくは瞑想的にも聴こえるサウンドだった。「あれ、マークってこんな人だっけ?」と思って、『Jersey』や『Family First』を何度も聴き直した。
それで資料を見ると、『The sound of listening』のタイトルとアイデアはベトナムの禅僧・詩人ティク・ナット・ハンの著書『Silence』からインスパイアーされたものとある。
そこで思い出したのが、グレッチェン・パーラトの『Flor』。このインタビューでグレッチェンはティク・ナット・ハンの話をしていたし、『Flor』は種が芽を出し、茎を伸ばし、葉を付け、花が咲き、種を落とし、枯れていき、その種が芽を出し、というような輪廻を思わせるような流れをアルバムに感じさせ、どこか瞑想的でもあった。グレッチェンとマークの夫婦はティク・ナット・ハンの考えを共有し、それが制作へのインスピレーションにもなっているのではないかと思った。
グレッチェン・パーラト「今を大事に、今を生きるってことを花に喩えている話で私が好きな言葉があるんです。それはティック・ナット・ハンというベトナムの僧侶が言っていた「No Mud、No Lotus」って言葉。「蓮の花は泥の中に埋まっていて、その泥から栄養を得て美しい花を咲かせる」って意味。その泥に当たるものが努力であったり、困難や苦しみであったり、とすると、そういうものがあってこそ美しい花が咲くと。その両方があってこそ、人間の存在だってことを伝えているんだけど、今回の私のアルバムで伝えたかったことはまさにそういうことだってこのインタビューで気が付きました」
ティク・ナット・ハンの本を読んでみると、彼は
「ある国に仏教がもたらされれば、そこには必ず新しい形態の仏教が起きる」
「仏教が仏教であるためには、その社会と文化に合った適切なものでなければならない」
と言っている。つまり、彼はベトナム出身ではあるが、ベトナムやアジアの仏教そのまま持ち込むのではなく、アメリカ人のためのアメリカ人にふさわしい仏教の在り方や言葉を考えていた人だ。そう考えれば、『The sound of listening』は決して、仏教的でもアジア的でもないが、そこにはティク・ナット・ハンからのインスピレーションをマークなりに自身の文化や音楽性にふさわしい解釈をしながら、取り入れているのかもしれないと僕は考えた。
というわけで、今回は音楽の構造や制作のプロセスというよりは、もっと内面的な哲学や考え方について話を聞いてみることにした。
最後に一つ、マークのことをシェアしておこう。2014年にマークにインタビューした際、彼は
マーク・ジュリアナ「ミニマルに最小限のパターンを延々と繰り返す曲ではベースドラムは心臓の鼓動と同じだ。そのパターンを延々とやるには自分を一端置いて、自分の存在すら忘れる必要がある。それは瞑想に似ているんだ」
と語っていた。この頃から僕はマーク・ジュリアナが東洋思想のような考え方で音楽をやっているのかもしれないと考えていた。その意味では僕が聞きたかったことをようやく聴けるチャンスがやってきた、とも言える取材だった。
【新規公演決定】マーク・ジュリアナ(2.1 wed., 2.2 thu., 2.3 fri.)→https://t.co/BmJvv3LwB8 pic.twitter.com/dwHV9AuB5I
— ブルーノート東京 (@BlueNoteTokyo) November 17, 2022
取材・編集:柳樂光隆 | 通訳:染谷和美 | 協力:コアポート
◉みんな知らなかったサマソニ2022出演
――ハロー。マーク。
ハロー。みんな元気?あ、後ろにコルトレーンの『Interstellar Space』が置いてあるね。そのレコード高くなかった?コルトレーンを集めていて、そのレコードがずっと欲しくて、最近ようやく見つけてレコードを買ったんだけど、けっこういい値段だったんだよ。
――ははは。答えはノーです。日本はヴァイナル天国なので、コルトレーンの国内盤を入手するのは難しくないと思いますよ。
そっか、日本はそうだよね。いいなぁ。日本でレコード買いたいなぁ。あ、そうそう、来週、日本に行くんだよ。サマーソニック。観に来てよ。
――え?!サマーソニックって名前無いですけども。
セイント・ヴィンセントのバンドのメンバーとして行くんだ。みんな知らないんだ。じゃ、よろしく伝えといて。
――マジすか…。チケット手に入るかなぁ。とりあえず、あなたのファンのためにツイッターで告知しておきますね(笑)
よろしく。
◉『The sound of listening』とパンデミック
――雑談はこのくらいにして、そろそろ始めましょうか。アルバム『The sound of listening』の資料を見ました。このアルバムのタイトルはベトナムの禅僧・詩人ティク・ナット・ハンの著書『Silence』からインスパイアされたものだそうですね。実は以前、あなたの妻のグレッチェン・パーラトにインタビューした際にもティク・ナット・ハンの名前が出たこともあって、気になるので買って読んでみました。なので、今日はそのことも含めて話を聞かせてください。というわけで、まずはこのアルバム『The sound of listening』のコンセプトから聞かせてください。
このコンセプトは最後の方に思い付いたんだ。当初、このアルバムは2021年の1月に録音する予定だった。2021年の1月12~17日にNYのヴィレッジヴァンガードで1週間演奏する予定だったので、ライブで新曲をやって、こなれてきたところですぐにスタジオに入って録音しようと思っていたんだけど、パンデミックの影響で2022年に延期になってしまったりしてね。
――それは大変でしたね…
パンデミックの間はみんなそうだったと思うけど、自分のことを振り返る時間になったんじゃないかなって思うんだ。僕も不安があったし、先行きに対して恐怖を覚えていたんだけど、“せっかくだからこれを機に自分のことを振り返ってみて、自分の内面を見つめるようなことをしてみよう”と思うことにしたんだ。そんな時に作曲をしていたから、何か意図があったわけじゃなかったんだけど、自ずと今回収録されているような曲が出来上がっていった。2年くらいかけて少しずつ書いてきた曲をまとめて、それをバンドにプレゼンしたときにみんなから「内省的な曲が多いね」って言われたんだ。そこでようやくアルバムのコンセプトが見えてきたって流れだね。
◉ティク・ナット・ハン『Silence』からのインスピレーション
――そこでティク・ナット・ハンの著書『Silence』が出てきて、このアルバムのインスピレーションになっていると。まずこの本のどんなところに惹かれたのか聞かせてください。
僕はグレッチェンから10年以上前に教えてもらっていたんだ。グレッチェンはティク・ナット・ハンの教えにかなりハマっていたので、彼女に影響されて、僕も本を読むようになった。彼はたくさんの著書がある人だから色々読んだよ。だから、なんというか、直接的なインスピレーションというよりはジェントルな形で自分たちの日常の中に、生活の中にこっそり入り込んでいたもの、みたいに考えてる。つまり、改めて今回直接的に影響を受けたってことではないんだよ。これまでの自分の音楽の中にも自ずと入り込んでいたんだろうし、子育てをしている中にも入り込んでいたと思うんだ。彼の教えは仏教ではあるんだけど、厳格な宗教ではなくて、押しつけがましくなくて、すごくオープン。オーガニックに受け入れてくれるようなものなんだ。『Silence』はたまたま僕が直近に読んだ本。その本はアルバム制作のプロセスの終わりの方に入ってきたものなんだけど、僕が作っていた音楽にも響きあうテーマだなと思ったんだ。
さっき言ったようにこの2年間で自分を振り返っていたから、僕は自分なりの“サイレンス”を探しながら生きてきたようなところはある。例えば、“聴く”って作業のことを考えると、他人を客観的に見ようとすること、もしくは誰かのためにいる自分を意識することかなって思ったんだ。そういったあり方って音を立てない静かなものだから、これも“サイレンス”かもしれないって思った。即興演奏で最も重要なことは相手の音を“聴く”ことだよね。だから、即興演奏で作ってる自分たちの音って“客観的な自分たちがいる静かな場所から生まれてくる音”なんだろうなって考えたりね。
――面白いです。“サイレンス”の概念をいろんなところに応用していたと。ちなみにティク・ナット・ハンはそのサイレンスを“人間にとっての空気のように不可欠なもの”と言っています。そのサイレンスのあなたなりの解釈をもう少し聞かせてもらえますか?考え方をあなたは『The sound of listening』の音楽にどう取り入れていますか?
直接的な意味でのサイレンスを音楽に取り入れるのはすごく難しい。リスナーからの期待感っていうのもあって、たぶんサイレンスを許容できる限界っていうのが聴き手の中にあると思うからね。音源だったら、音が止まった状態に耐えられるのは3秒とかなんじゃないかな。3秒を超えたら、この曲は終わったんだなって判断されるしね。ライブなら視覚情報もあるから“もしかしたらまた演奏が再開するかも”って思ってもらえるから違うんだけど、とはいえ“金払って見に来たのに半分くらいは音を出してないじゃん!”みたいなことになるかもしれないし。だからサイレンスはビジネス的には非現実的だよね(笑)
ーーははは、たしかに。
僕がティク・ナット・ハンから学んだサイレンスは必ずしも音が全く鳴っていない状態のことを指すわけじゃない。つまり物理的な意味だけじゃないってことだね。自分の内面が穏やかで静かであれば、それがサイレンスだってこと。サイレンスって言葉を聞いたときに人々が思い浮かべるものってあると思うんだけど、こうやって君たちと対話しているときにはそれぞれが順番に話をしているよね。そして、自分が話していないときは何もしなくていいわけではなくて“質問をちゃんと聞いているよ”、“日本語に訳しているところも聞いてるよ”って感じで、みんなが存在としての自分を表現している。つまり、僕らはみんな黙り込んでいるだけではないんだよ。だけど(人の話を)聞いている間、音は出していない。そういう感じで、様々なサイレンスがあると思うんだ。
――なるほど。それはさっき語ってた即興演奏において大事なことは聴くことって話の理解の解像度が上がりました。
このアルバムに関しては、僕は聴き手に対して「それぞれの聴き手が自分の中にサイレンスを見つけてほしい」って招待状を送ったんだ。音楽は作っただけでは完成していなくて、リスナーが聴いてくれて、それに対してリアクションを返してくれて、初めて完成するものだと僕は考えている。誰かの手に渡って、それを自分なりに消化してもらえたら、初めて成り立つものってこと。だからこのタイトルをきっかけに聴いたみんなが自分の中にある内なるサイレンスを見つけてくれたらいいなってところに止めたいから、この辺にしておこうかな。それぞれに与えられてるはずの解釈のオプションを閉ざしたくはないからね。
――わかりました。でも、もうひとつ聞いていいですか?ティク・ナット・ハンの本を読むと、彼は「Suffering」(苦しみ)についてよく語っています。しかも、彼はSufferingを重要なもので、自分と対話して、自分の中にあるSufferingを認識して受け入れることを学ぶべきものだとも語っています。さっきの自分を見つめる時間だったって話も含めると、このSufferingの考え方は『The sound of listening』にも通じている気がするのですが、いかがですか?
仏教の教えって、必ず悪いニュースから始まるんだ。仏陀も苦悩を説くところから始まる。それってすごくパワフルで、美しいものをパンパンパンって並べて、それを愛でるってことじゃなくて、辛いところから始めたうえに、辛いことをひとつひとつ上げ連ねて一通り眺めて、それから“じゃ、始めるか”って感じでそれから脱するにはどうしたらいいかを説いていく。モダン・カルチャー的には良い方に目を向けがちで、それはそれで楽観主義的でいいのかもしれないけど、いいことばっかり見ようとすると忍耐は無くなっちゃうよなと思うよね。目の前にある辛いことから逃げようとするか、飛び越して向こうへ行こうとするか。でも、実際には苦境から脱する方法はそこを突き抜けるしかなかったりもするので、それは辛いことだったり、苦しいことだったり、いやな思いもする可能性もある。でも、一旦そこを突き抜ければ、そこの道は永久に残ることになる。そこを避けて、本当に立ち直る術はないんじゃないかと。そういうことが彼の教えの核の部分にあるんじゃないかな。僕はそういう本を読んできたから、自ずとそういう影響は受けていると思うし、それが音楽にも出ているんじゃないかと思うよ。それは大きな画として僕らの世界にあるのであって、具体的にそこから影響を受けて作った音楽ってことではないけどね。
――わかりました。以前、僕はあなたに東洋思想っぽい考え方がいろんなところにありますねって話したこともあるので、興味があったんですよ。では、ここからは個別の曲のはなしを。「a way of looking」はとてもシンプルでミニマムな曲ですが、薄くシンセが鳴っていたり、ちょっと変わっていますね。
このアルバムって、2枚のアルバムを1枚にしたような感じなんだよ。4曲から5曲はバンドでスタジオに入って一緒に演奏して一発録りして“今のでよかった?じゃこれで完成だね”って感じのやり方。『Jersey』や『Family First』に近い感覚だよね。それはサウンドのフォトグラフ的なものと言えると思う。
――なるほど。
「the way of looking」「the courage to be free」「the sound of listening」「practiong silence」は僕がミニチュア・ソングと呼んでいるもの。自分の時間が沢山あった時期に自分の家で書き溜めていたものを実際にきちんと形にしたものだね。だから、インプロヴィゼーションじゃなく、コンポジション的な曲ってことになる。家にあるシンセをいじってみたり、木管が聴こえてきたらバスクラやフルートを足したいなって考えたりしながら作ったんだ。しかも、ドラムがほぼ入っていない。これは僕にとってはとても重要なことで、ドラムががんがん鳴っていないことで聴いている人の耳をコンポジションに持って行きたいと考えたんだ。僕はたまたまドラマーだけど、ドラム・ファーストの人間ではないからね。ドラムは僕の表現手段の中のひとつにすぎないんだ。
その意味では『BEAT MUSIC! BEAT MUSIC! BEAT MUSIC!』を作った経験は自分にとって良かったと思う。沢山素材を録って、オーバーダブもいっぱいやって、スタジオでもポストプロダクションでも作り込んで、必ずしもライブ・パフォーマンスだけではない作品を一度作っているので、プロダクションで音を作り込む経験が自分の中に蓄積されている。それにこのバンドにエレクトロを持ち込むのは初めてで、シャイがメロトロンやジュノを弾いていて、クリスが弓を使ったり、シンセも使ったり、ある意味では飛躍しているんだけど、このバンドらしさからはそうかけ離れてはいない。自分たちの核はそのままに新しいサウンドを加えたアルバムになったと思うよ。
◉音を足さないこと、大きくしないこと
――もう一つ変化があるとすれば、これまでのアルバムよりは引き算的で、曲のテイストがかなり違いますよね?
そこはかなり意識していたところなんだ。このバンドでは3枚目のアルバムでもあって、バンドの自然な本能や誘惑に従えば、音を足していく方に行きがちだと思う。人は発展や進化を考えると増えていくことを考えがちだよね。つまり進化とは増加だと。例えばそれをもう少し身近なところで考えていくと、楽器がうまくなることに関しても、どんどん音数が増えて、音量が大きくなるってことが上達だと思いがち。人生も同様で、何でもできることが進化だってなりがちだしね。僕は今回、そこから離れたかったんだ。人間が自然と行ってしまう習慣やハマってしまいがちな癖や本能から離れるには意識的にやらないと難しい。ここでは意識して離れることがその他諸々ある音楽作りのオプションに負けないくらい意味があることだし、重要だし、美しいことだと僕は考えたんだ。意識しなかったらもっとやりやすくて、簡単な方法が沢山あったと思うけどね。でも、今回はその罠にはまらないようにしたんだ。
――それってマークひとりが思って、そんな演奏していてもダメで、その意図をグループ全員で共有しなきゃいけないですよね。
このアルバムのレコーディングの前に2022年の2月8~13日にヴィレッジ・ヴァンガードでライブをやって、その直後にスタジオに入ったんだけど、それはほぼほぼ恵みだったんだけど、実は悪い面もあった。ライブでやっている時って自然なノリで考えているんだ。同じヴェニューで何度も演奏して、曲に馴染むと、頭で考えなくても心のままに弾けるようになる。それは良かったんだけど、曲の尺を考えていないって問題がおきる(笑)ライブの時はその場で思うままに弾いて、その場のノリでやってる。そうやって演奏していた曲をアルバムの尺に収めるのはけっこうなチャレンジなんだよ。あんなにオープンに自由にやっていた曲をひとつの型に収めるっていうのはなかなか難しいんだ。「a path of bliss」はライブでは18分になったこともあった。そんな曲を10曲まとめてアルバムにして、ヴァイナルにも収めますってのは大変な試みなんだ。だから尺に関しては話し合ったよ。ソロの長さに関しては細かくは言わなかったけど、全体の尺に関して伝えれば自ずとやるべきことは見えてくる。実は他にも録音した素材がたくさんあって、すでにもう一枚分の音源がある。これは来年出そうかなって思ってるんだ。だから、やりたいことはやりつつも尺に収めるってことは頭に入れておいてもらったというのはある。

――なるほど。
もうひとつよく話していた大事なポイントがある。自分たちのやりたいことを全部やって、納得しましたって音源が録れたとするよね。そしたら僕の方から「OK。じゃ、これを5分でやろう」って言うんだ。そうするとスタジオ内にちょっとした悲しみ(Small Sadness)が漂うんだ(笑)。それは「それじゃやりたいことできないじゃん」「こんなにできることがあるのにそれを入れられないじゃん」って悲しみだよね。曲の長さと、その人が出したいエモーションを考えると、短くするとテンションも下がっちゃうみたいなところはある。でも、僕が一生懸命お願いしたのは長いバージョンで発揮していたスピリットやエモーション、その曲に対する入れ込みみたいなものと同じだけのものを短い時間につぎ込んでほしいってこと。曲の熱量と曲の尺を分けて考えることが重要なんだってことをかなり言ったよね。彼らにはそれができるから。
◉敢えて反応しない”アンチ・ジャズ”な曲のこと
――「everything changed after you left」(あなたが去ってからすべてが変わった)はどこか瞑想的なサウンドです。前半は全員ピアニッシモで演奏していて、サックスのジェイソン・リグビーのソロにいたってはかすれたような音色ですよね。
曲は3パートで構成されている。イントロはジェントルでリズムもほぼ入ってきていない。そこにクリスのベースが入ってくるんだけど、それはとてもシンプルで、しかも変化しなくて、同じことをずっと繰り返している。それは僕も同じで、僕の演奏もずっと同じことを繰り返している。その上で、シャイとジェイソンがちょっとした会話をしているんだけど、僕とクリスはそれを無視していて、絶対に反応しないんだ。これは時間が動かないような曲になっている。ここでいろいろやりたくなるんだけど、そこでやってしまうのはイージー・チョイス。僕が若かったら、あっという間にそっちに行っていたと思う。若い頃って、自分のボキャブラリーを増やして何でもやりたいと思っているから、そこで自分を抑えてやらずに耐えるってことはとても難しい。でも、今の僕にとってはこういうやり方もできるようになったし、そっちの方が選びやすかったりもするんだ。
――なるほど。
即興の時は好きなことをやっていいし、何をやってもいいんだけど、この曲は“リアクションしたくない”ってでの考え方、つまりアンチ・ジャズな姿勢だよね。ジャズの世界では誰かが何かをやったらすごくリアクションをするっていうのがある意味、ノーマルになってしまっている。だからこそ、逆にそこで反応しないことの方がインパクトがあるんじゃないかって思ったんだ。相手の音を聴いていないってことではなくて、むしろ相手の音をしっかり聴いているからこそきちんと無視することもできるっていうかね。そういう具体的な制約を敢えて課したんだ。それはエレクトロニック・ミュージックから学んだことでもある。変化を続ける場合よりも反復してずっと同じところに留まることのほうがテンションをより高められることもあるって考え方。この曲はそれを持ち込んでいるとも言えるよね。
――“敢えてやらないで留まるってことの成熟”みたいなことは今のマークにとって必要なテーマだったのかもしれませんね。
それも時には大事だよね。それが正しいチョイスになることもある。自然だと感じることに敢えて抗うことが面白いチョイスになることもあるから。
――以前、シャイ・マエストロが僕に「静寂の中で、オーディエンスは何が起こるんだろうって耳を澄ましてるんだけど、何も起こらずに終わるってある意味、成熟したコンサート」「演奏者もそこに行こうと思えば行けるのに行かない状態=潜在力があるっていうこと」って話をしていたことがありました。あなたとシャイがいろんな部分でかなり通じ合っているのもこのアルバムの成功の理由のひとつかもしれませんね。
そうなんだけど、実はこっちからシャイに手を差し伸べないといけないこともあったんだよ(笑)。シャイの問題はやることなすことがアメイジングなことだよ。だから、アメイジングなのにそれを縮めてくれって言わなきゃいけないことに僕は罪の意識を覚えるんだ(笑)。でも、このアルバムでは明確にやりたいことがあるから、今回は止めてくれって言わなきゃいけなかった。ま、ぜいたくな悩みではあるよね。
◉カルテットとビートミュージックの共存
――たしかに(笑) では、次はタイトル曲の「the sound of listening」です。ここではドラムをプログラムし、シンセも使っていて、タイトルの曲なのに異質ですよね。
この曲はカルテットの自然なサウンドから最もかけ離れている曲だと思う。僕はかつて“カルテットはサックス、ピアノ、ベース、ドラムでかちっとしたもの”を考えていて、“ビート・ミュージックではエレクトロニックで、インプロ的な要素はほぼないもの”を考えていたんだ。もともと僕は少し離れたところにその二つの木を植えた。その二つの木はずいぶん育ってきていて、今の僕はその二つの木の間を行き来することに抵抗が無くなってきた。そして、行き来することに居心地の良さを感じるようにもなってきた。頭の中では脳内でのビートミュージック的な部分、つまりエレクトロニックなテクスチャーのことを考えていて、一方で目のレンズはカルテットのものを使っているって感覚だね。この曲に関してはその姿勢が正しいと感じられたんだ。
これをタイトルトラックに持ってきたのは、自分の音楽の世界においてはこの曲の感じは離れ小島みたいな部分だから、これを押し出したら面白いかなって思ったから。僕の音楽の世界があるとしたら、そこからボートに乗って少し離れた島に行く感覚だね。自分の中ではすべて同じ音楽だから、出てくるものがビートミュージックでもカルテットでも同じところから発信しているので、表現としては自分の中では同じ意識。でも、ソニックの部分では違いがあるって捉え方だね。この曲でもかけ離れているとは言いつつも、片足はカルテットに突っ込んでいるんだよ、一応。
――これ聞いてもしょうがないと思うんですけど、インスピレーションになったアルバムとかありますか?
ないなぁ。結局、ジョン・コルトレーンやボブ・マーリーばかり聴いちゃってるからね、僕は。
◉コルトレーンのレコード集めの話
――ですよねぇ。ただ、このアルバムにはメディテーションな感じがあるので、冒頭であなたが触れてたコルトレーンの『Interstellar Space』あたりは関係なくはないかもですね。
さっき「Past」がライブで18分になっちゃった話をしたけど、コルトレーンが日本でやったライブだと26分とかぶっ続けで演奏しているんだよね。あれだけの時間、リスナーを惹きつけられるってすごいよね。最近、『Coltrane In Japan』のヴァイナルを買ったんだ。ちょっと待ってね、持ってくる。これもさ、高かったんだよ。日本版のライナーノーツがついてて、これを誰かに翻訳してもらって、そのうち読まなきゃなって思ってるんだよね。日本盤だけボックスセットになっていて、3枚組のヴァイナルだって知ってね。コルトレーンを集めている僕としては見つけて買わなきゃなって思ったんだよね。
――マジで日本に来たらレコードショップにお連れしますよ(笑)
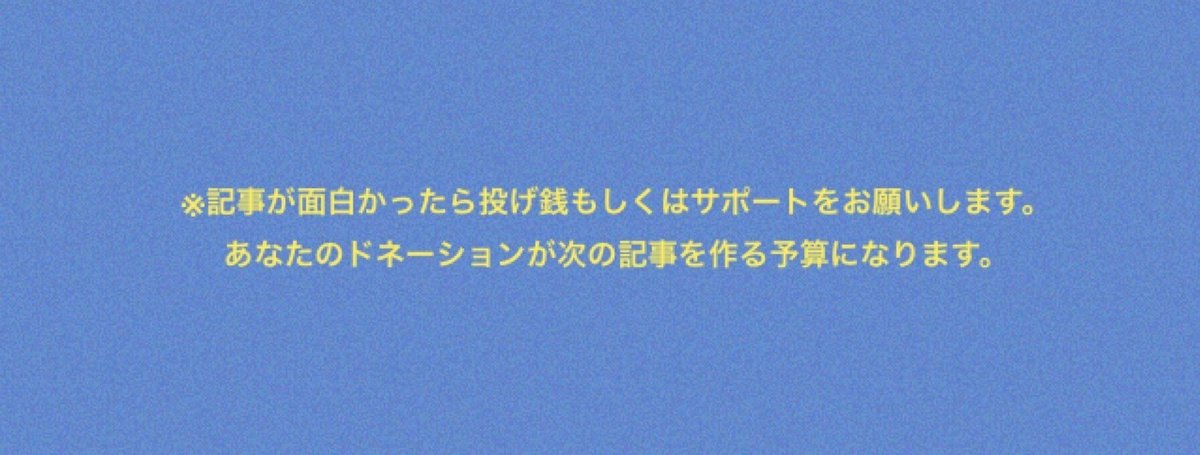
ここから先は
¥ 250
面白かったら投げ銭をいただけるとうれしいです。
