
Interview Kit Downes - Vermillion:僕らが選んだのではなく、録音した環境が演奏を決定していた
キット・ダウンズはUKのジャズ・シーンでずっと注目されていた人だった。
1986年生まれのこのピアニストはパーセル・スクール・オブ・ミュージックとロイヤル・アカデミー・オブ・ミュージックで音楽を学び、ミュージシャンになり、2009年にリリースしたアコースティックなピアノトリオ・フォーマットのグループのキット・ダウンズ・トリオでのデビュー作『Golden』を発表。この『Golden』はいきなりマーキュリー・プライズにノミネートされる。The XXやマムフォード&サンズなどと並んでアコースティックのピアノ・トリオ・ジャズがノミネートされたことのインパクトは大きかった。まだUKのジャズが話題に上るようになるかなり前のことだ。ブラッド・メルドーやアーロン・パークス、ヨーロッパで言えばエスビョルン・スヴェンソンやフローネシスあたりとも通じるようなコンテンポラリー・ジャズとハイブリッドなセンスが同居しているセンスが彼の出発点だったことがわかる。
その後、ジャズ・ロック的なプロジェクトのTroykaや、クラブジャズ系のノスタルジア77やアンビエント・ジャズ・アンサンブルに参加したり、現代音楽やフォーキーなプロジェクトなど、大量の録音に参加し、常に面白い場所に顔を出していたのがキット・ダウンズだった。
近年では北欧シーンの気鋭のベーシストのペッター・エルドとの『Enemy』『Projekt Drums Vol. 1』などで高い評価を得ている。
そのキットの近年大きなトピックはECMとの契約だろう。しかも、いきなりリリースしたのはチャーチ・オルガンのソロ・アルバム『Obsidian』。それに続き、またもやパイプ・オルガンのアルバム『Dreamlife Of Debris』を発表。両作ともパイプ・オルガンのイメージを裏切ってくれる面白いサウンドだった。
そこから満を持してリリースしたのがピアノトリオでの『Vermillion』。今やECMの新たなチャレンジの象徴のひとりとなっているキットがペッター・エルド、ジェイムス・マッドレンとのトリオでECMのピアノトリオに新たな一ページを付け加えた。
ここではキット・ダウンズにここ数年のECMでの作品について語ってもらった。
取材・執筆・編集:柳樂光隆 通訳:丸山京子 協力:ユニバーサル・ミュージック

◉2015 Thomas Strønen『Time Is A Blind Guide』
――2015年にトーマス・ストローネン『Time Is A Blind Guide』に参加しています。これがあなたのECMへの最初のレコーディングだと思います。この作品に参加した経緯を聞かせてください。
友達のイアン・バラミーからの紹介だね。イアンはトーマスとフードってプロジェクトをやっていたから。トーマスがノルウェーとUKのミュージシャンを組み合わせたプロジェクトをやりたいって話になった時に僕に声をかけてくれたんだ。それでバンドを作ってギグを何度かやって、その音源をマンフレートに送ったら気に入ってくれて、リリースにも繋がった。その時に後に僕の作品を手掛けることになるプロデューサーのスン・チョンとも知り合って、それが僕のECMとの契約にも繋がっていった。
――『Time Is A Blind Guide』がどんなコンセプトで、あなたはどんな演奏をしたのか、聞かせてください。
あれはトーマスのバンドで彼が作ったものに僕が後から参加したもの。これはライブバンドで、そういうバンドは常に進化していくもので、変わること自体がコンセプトって感じだと思う。その一方で僕のアルバムみたいにコンセプトが決まっているものもあるんだけどね。トーマスのバンドのようなレコーディングでは僕はできるだけその時のベストを尽くすって感じで演奏するよね。
――トーマス・ストローネン『Time Is A Blind Guide』にはチェロ奏者のLucy Railtonが参加しています。彼女は現代音楽や電子音楽にも精通している音楽家で、彼女の作品にはまさにエレクトロニカやアンビエント・ミュージックも通じる部分もあります。あなたと彼女は『Subaerial』など共演作も多いですが、彼女とコラボレーションのきっかけは?
ドラマーのジェイムス・マッドレンと同じでロイヤル・アカデミー・オブ・ロンドンの同窓だね。ただ、大学時代には交流はなくて、卒業後に親しくなった。彼女とはピアノとチェロのデュオでライブをずっとやっていて、2013年の『Light From Old Stars』に彼女が参加してくれたりもしたよ。その後、アイスランドでレジデンシーをやった時に、オルガンとチェロのデュオを20時間ぶっ続けでやったんだけど、それが『Subaerial』に繋がったんだよね。
◉2018 Kit Downes『Obsidian』
――2018年にはECMからの最初のアルバム『Obsidian』をリリースします。これはオルガンによるソロですが、どんなコンセプトだったのか教えてください。
子供の頃、当時住んでいたUK東部の田舎町でいろんな教会に行ってはそこにあるチャーチ・オルガン(パイプ・オルガン)を弾いていた。その経験をアルバムでもやってみようと思ったんだ。いろんなところに行ってオルガンを弾いてみると、大きなオルガン、小さなオルガン、その中間のものとサイズだけでも様々なオルガンがあって、それぞれに音が違う。そのオルガンにふさわしいアイデアや構造、即興演奏のやり方を自分なりにやってみるというのがこのアルバムのコンセプトだね。
――ずいぶん変わったプロジェクトだと思いますけど、よくレコーディングのOKが出ましたね。
2015年にサックス奏者のトム・チャレンジャーと一緒に『Vyamanikal』という似たコンセプトのアルバムを作ったことがすでにあったんだ。それに比べると『Obsidian』のほうがコンセプトもよりフォーカスされているから問題なかったよ。
――『Vyamanikal』はどんなコンセプトだったんですか?
実は同じコンセプトでいろんなところに行って、そこにあるオルガンを弾くってコンセプトなんだけど、ひとつ違いがあって、それは壊れている楽器を敢えて使ったところ。壊れた楽器だからこそ引き出されるいびつさみたいなものをドキュメントしたアルバムだね。
――では、『Obsidian』はどこにフォーカスしたものですか?(Obsidian=黒曜石)
いわゆる即興のメタファーとして、火山性(Volcanicity)をイメージしたんだ。火山って一気に爆発するっていうよりは徐々に徐々に溜まっていってから爆発するようなもの。古いオルガンを使っていて、少し不具合があったりする楽器もあったからというのもあるんだけどその遅さも含めた火山性にフォーカスしているよ。
◉2019 Kit Downes『Dreamlife Of Debris』
――2019年にはECMからの2作目として『Dreamlife Of Debris』を発表します。このアルバムもオルガンを演奏していますが、ソロではなくて、ミュージシャンとの共演で、『Obsidian』を発展、拡張させたもののように感じました。
『Dreamlife of Debris』は『Obsidian』の対の一方。『Obsidian』が ”火山活動”というか”火”がテーマだったのに対し、『Dreamlife』のテーマは”水”。なのでアルバム全体を水中のようなサウンドにしたかった。普段オルガンと一緒に演奏しない楽器と組み合わせで、より広いコンテクストの中にオルガンを置くと言うのがメインのアイディア。それを可能にするには、(巨大な)オルガンが他の楽器と同じサイズになるような人工的な音響空間を作るしかない。多くの編集やマニピュレーションを伴うことでね。なぜならオルガンをチェロと同じ空間で弾くと、両者の間の距離とサイズの違いが大きすぎるので、ハイファイ的に、なじまないんだ。そういう意味で、ずっと人工的に作られたアルバムだったよ。
――なるほど。ちなみに『Obsidian』『Dreamlife Of Debris』はSun Chungのプロデュースです。彼が出したアイデアや、彼の貢献について聞かせてください。
もちろん貢献している。彼は最初から常にいたし、ミーティングにも常に参加していた。『Dreamlife Of Debris』はかなり時間をかけて作られていて、いろんな場所で録音されているんだけど、それも彼のアイデア。選曲に関しても彼は出過ぎない程度にはかなり貢献していると思うよ。
――『Dreamlife Of Debris』はかなり特殊な環境にオルガンを置いたって話をされてましたが、そういう環境ではオルガンに弾き方もかなり変わるのかなと思うんですが、どうですか?
もちろんそうなるよね。それに『Dreamlife Of Debris』はソロじゃないから、たくさんあるサウンドの中ひとつって考えた方になる。演奏に関してもかなり特殊なことができたと思う。沢山重なっているレイヤーのうちのひとつを奏でるわけだからね。
――その2作では教会にあるパイプオルガンを演奏しているわけですが、誰か参照した演奏者はいますか?
ECMから出ているものならChristopher Bowers-Broadbent、Keith Jarrett『Hymns Spheres』。他にはJurgen Essl、Kali Malone、Giulio Tostiとか、オルガンで面白いことをやっている人はけっこういるんだよね。
――『Obsidian』『Dreamlife Of Debris』を聴いたときに、演奏だけでなく、楽器そのものの響きやテクスチャー、録音などのコンビネーションにより、エレクトロニカやアンビエント・ミュージックと同じ感覚で聴けるなと個人的には思いました。エレクトロニカやアンビエント・ミュージックなどを通過した人が行う即興音楽だなとも思いました。そう言った意識はありますか?
僕自身はWilliam Basinskiとかは好きで聴くんだけど、ここでは敢えてそういうことをやろうと思ってはいないかな。オルガン自体は音が大きくて、ゆっくりした音が鳴る楽器。でも、そんな楽器を使って、ディテールを弾こうとしたんだ。ディテールを弾いていって、それを積み重ねていくと、最終的にオーケストラのようになる。それをミックス次第では音響的なものにもすることができるということだと思う。ここではディテールにこだわって、オルガンが本来持っているものとは違うことを注意深く弾きながら、それを積み重ねていったんだ。最終的にはそこに20台のオルガンがあるように聴こえるものを作ったりもしたよ。
――オルガンっていうのは音も大きくて、ゆっくりと音が出る楽器ってこともあるので、基本的にはディテールを弾くのが難しい楽器でもあるんでしょうか?
というよりは、歴史的にオルガンって楽器は教会において、ソロもしくは聖歌隊のバックで弾かれるもので、レコーディングを前提にしていないものだよね。それもあって、ディテールにまでこだわるものじゃないってことがあると思う。だから、それを敢えてレコーディングするってことになると、必然的に伝統的なオルガンとは違う意味合いを持ってしまうんじゃないかな。
◉2022 Kit Downes Trio『Vermillion』
――では、次は2022年のKit Downes Trio『Vermillion』を制作するようになった経緯を聞かせてください。
このトリオは7年くらいやっていて、2018年には『ENEMY』ってアルバムもリリースしている。実はこのアルバムを作る前にスン・チョンがECMから離れてしまったので、プロデュースをマンフレート・アイヒャーが引き継いでくれたんだ。自分たちとしては、これまで以上にアンサンブルのダイナミクスや色彩がある作品を作りたいって話をしていたところだったから、ECMとやるのはちょうどいいなって感じだったね。
――『Vermillion』のベーシストのPatter Eldhはスウェーデン出身でドイツが拠点だと思います。どういう経緯で知り合って、どういう経緯で何度も共演を重ねるようになったのでしょうか。
ペッター・エルドがジャンゴ・ベイツとやっていたのを見たのがきっかけだ。僕はジャンゴ・ベイツのファンだからね。これだけ複雑なリズムを自然に、しかも自由にできるところに魅了されたんだ。それで僕もペッターと一緒に演奏したいって気持ちで曲を書いたんだ。その時に実際にやるんだったらドラムはジェイムス・マッドレンだなって思っていた。ジェイムスとは大学時代からの友人で、一緒に学んだ仲なんだ。
――ジャンゴ・ベイツやルース・チューブス由来の複雑なリズムを扱う感覚ってのはあなたの音楽とも共通していますよね。あなたたちが共演する理由がわかりました。あなたとPatter Eldh は『Enemy』や2021年の『Projekt Drums Vol. 1』で共演しています。ここにはジェイムス・マッドレンも参加していました。この2つのアルバムについてどんなコンセプトだったのか、聞かせてもらえますか?
『Projekt Drums Vol. 1』はペッターのお気に入りのドラマーを集めて録音するってコンセプトで、ロックダウン時のプロジェクトだね。『Enemy』はライブを4年くらいやっていた自分たちのバンドをスタジオでドキュメントしたものだね。曲はそれぞれが半々で書いてる。ECMでやっていることとの正反対って感じで、生々しくて、荒々しいサウンドにしようと思ったものだね。自分たちは相反するものが好きだし、しかも、両極端にあるものが好きなんだ。
――『Vermillion』は『Enemy』のトリオと同メンバーによるアコースティックのピアノトリオです。『Enemy』はエレクトリックなサウンドなので、『Vermillion』とは一見全く別物ですが、そこには共通している部分もあるように思えます。敢えて、その共通点をあげるとすればどんなところだと思いますか?
プレイのやり方は同じ。ただ、そこにある美的センスみたいなものが違うと言ってもいいかもしれない。曲の書かれ方も違う。でも、アプローチは一緒だね。自由であること、役割がどんどん入れ替わっていくこと、その中での演奏者同士のコミュニケーションの速さ、そして、リスクをとること、そこは同じ。
――『Vermillion』はジャズともクラシック=室内楽とも言えないような抑制的で静かなのに動きもあるサウンドで、しいて言うなら“ECMの即興音楽”とでも呼ぶのがふさわしいサウンドだと思います。シンプルでメロディアスな中に独特の複雑も潜んでいる。そして、ECM=マンフレート・アイヒャーはこれまで多くのピアニストにこのような方法での録音を課してきたと思いますし、そこではその演奏者の個性やその演奏者の音楽の核になっている部分が浮かび上がってきていたとも思います。ECMでのピアノトリオの録音について聞かせてください。
ECMでのピアノトリオの録音は初めてだったけど、すごく自然だったし、楽しかったよ。このアルバムに関しては、多くのことに関して、どんな環境で録音したのかってことが決定していたんだと思う。それは僕らが選んだことではなかった。このアルバムは大きな劇場のようなところで録音したんだ。ヘッドフォンもなく、モニターもない、みんなで同じ場所で一緒に演奏して仕切りもなかった。それに編集もできない。そうなれば必然的にドラマーは大きな音は出せない。静かに叩くしかないよね。そういう選択は僕らではなく、環境が決めたこと。マンフレートがやったのはその環境を決めたことや、僕らが沢山演奏した中からベストなものを選ぶってことだったね。

――つまり、今回録音したスイスのルガーノのスタジオ Auditorio Stelio Molo, Lugano はこのアルバムのサウンドに関してはすごく大きな条件になっていたってことですか?
そうだね。録音したルガーノの会場はスタジオっていうよりは劇場なんだよね。いわゆるスタジオとは環境が全く違うんだ。だから、演奏の中にできるだけスペースを持たせることを余儀なくされた。でも、スペースを持たせることでよりダイナミクス、強弱、タッチなどのディテールにかなりこだわることができたし、そのディテールが前面に出てこられるような音楽にもなった。そして、僕自身はピアニスティックな演奏をすることができた、と言えるかもしれない。ディテールにこだわりたいっていうのはもともと僕ら3人がずっと持っていたアイデアなんだけど、ルガーノの環境がその部分により強くフォーカスさせてくれたってこともあると思う。それはこのアルバムのすごく大きな要素だね。そして、“マンフレート・アイヒャーという人がそこにいたこと”もそういった方向性に加担していたことを付け加えていいと思う。
それにレコーディングとギグは違うものだから。レコーディングっていうのはどこかにフォーカスして、よりディテールを引き出すものでもある。その弾き出されたディテールの周りに何を作り上げていくのかってことだと思う。そして、どんな中心を作るのかってことだと思うし。だから、今回の条件はすごく大きな影響があったと思う。
――それは面白いですね。今後、ルガーノ録音の作品の聴き方が変わりそうです。ECMであなたが特によく聴いたアルバムがあったら、教えてください。
キース・ジャレット『The Köln Concert』、『Facing You』、『Standards』、『Whisper Not』、『Tokyo ‘96』、アルヴォ・ペルト『Tabula Rasa』。他にはボボ・ステンソン、ヤン・ガルバレク、ジョン・テイラーなど、たくさん聴いてきたからあげたらきりがないね。
――イギリス人のピアニストのジョン・テイラーってどんなところが好きなんですか?
一時期、彼に師事していたことがある。彼はもちろん世界的なプレイヤーだけど、イングランドのシーンにとってはとても重要な人。音楽の中にエキサイティングな瞬間を作り出すような、遊び心みたいなことがあるし、彼はいつもリスクを負っていた。そういうセンスがあった人だね。必ずしもうまくいかないこともあったと思うけど、それでもチャレンジするんだよね。
――ジョン・テイラーは予想のつかない即興演奏をする人で、彼の音楽を聴いているとなんでそっちに行ったの?って思うような瞬間があるのが面白いんですけど、そこはあなたにも共通しているんじゃないかなと思いますが、どうですか?
僕は彼のそんな部分を受け継いでいられたらいいなって思ってるよ。
――最後に、あなたやJames Maddren、Christian Lillinger、Petter Eldh、Kaja Draksler、Otis Sandsjö、Anton Egerなど、イギリス、ドイツ、フィンランド、スウェーデン、スロベニアなどヨーロッパの様々なミュージシャンが繋がって、面白い音楽を生み出しています。今、挙げたミュージシャンたちのネットワークについて、僕は今、とても関心があるのですが、あなたがどんな感じで交流しているのか、聞かせてもらえますか?
僕もカヤ・ドレクスラーの音楽は大好きだよ!僕も彼らからすごくインスピレーションを受けている。共通点があるとすれば、ほぼ同世代で、多くはベルリンを拠点にしている。デンマークのコペンハーゲンにあるRhythmic Music Conservatoryの出身者が多いってのもあるね。近いアプローチをシェアしていると思う。自由で、ジャンルを超えた表現で、強度(インテンシティー)を持っている、そんなところが近いのかなって思う。
ーーそんな虎の穴が… しかも、ジャンゴ・ベイツが教鞭をとっている。謎が解けました…
(了)
※記事が面白かったら投げ銭もしくはサポートをお願いします。
あなたの購入が次の記事を作る予算になります。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
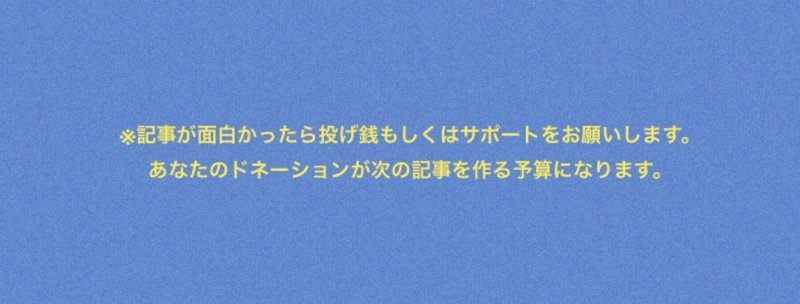
◉考察:キット・ダウンズとECM
ここから先は
¥ 150
面白かったら投げ銭をいただけるとうれしいです。
