
interview BRIAN BENDER:ホセ・ジェイムズの右腕エンジニアと『Merry Christmas from Jose James』
ホセ・ジェイムズはUKでデビューし、ジャイルス・ピーターソンのレーベルBrownswoodから2枚のアルバムを発表。ヨーロッパや日本で人気を獲得してから、ヴァーヴで1枚出したのち、ブルーノートと契約し、2012年に傑作『No Beginning No End』をリリースし、その評価を一気に高めた逆輸入のアーティストだった。
そこからブルーノートから5枚をリリースしたのち、現在は自身のレーベルRainbow Blondeへと活動拠点を移し、2020年以降、すでに3枚のアルバムをリリースしている。
ホセは作品ごとに音楽性を変化させているアーティストで、そのすべてがホセ自身のディレクションによるもの。実はそのほとんどの作品に関与している人物がいる。それがエンジニアで、プロデューサーのブライアン・ベンダーだ。
ディアンジェロ『Voodoo』などで知られるNYのエレクトリック・レディ・スタジオでアシスタントをやっていたブライアンは『Voodoo』に関与したエンジニアのラッセル・エレヴァードの下で働き、彼の手法を学んでいた。
ホセはエレクトリック・レディ・スタジオで知り合ったブライアン・ベンダーに『No Beginning No End』の録音やミックスの多くを委ね、それ以外にも(ピノ・パラディーノと共に)プロデューサーとしての役割も任せた。そこでの成功で生まれた二人の信頼は現在まで続いている。
その後も二人はともに歩んできた。エンジニアのブライアンとの強い結びつきがあるホセの作品はどれも録音やミックスへのこだわりが見えるものだった。改めて『No Beginning No End』や『While You were Sleeping』を聴くとディアンジェロ系譜のネオソウル的なサウンドを参照しつつ、そこに新たなチャレンジを加えているのがわかる。また、Rainbow Blonde以降の『No Beginning No End 2』や『José James: New York 2020』を聴くとよりオーガニックでナチュラルな響きを追求しているのがわかるし、その流れは『Lean On Me』あたりから見えていたこともわかる。ブライアンと組んで以降のホセの作品では録音やミックスへのこだわりが強く鳴っていて、それがブライアンのサポートで実現されていることもわかる。そして、その二人の作品にはずっと貫かれているものも確実にある。
2021年、ホセ・ジェイムズはRainbow Blondeから突如クリスマス・アルバム『Merry Christmas from Jose James』を発表した。
スタイル的にはオールド・スクールな古き良きアメリカを思わせる50年代ごろのクリスマス・アルバムそのものだ。ピアノトリオをバックにホセが朗々と歌う。その中にはもちろんコンテンポラリー・ジャズ的な演奏の欠片も入っているし、ネオソウルを経由した要素も聴こえる曲もある。歌と演奏、作編曲のクオリティは非常に高い。ただ、僕が気になったのはそれらよりもその録音やミックスの部分だった。
ウッドストックにある古い木造の教会だった建物をベースにレコーディング・スタジオに改装したというDreamland Recording Studioはナショナル、パーケイ・コーツ、カート・ヴァイル、フリート・フォクシーズ、ジャズ周辺だとボカンテやビル・ローレンスなども使用している知る人ぞ知るスタジオだ。
ここで録音した『Merry Christmas from Jose James』は音の分離ははっきりしていないが、どの楽器も生々しく鳴っている。そのリアルさは楽器の音色を高い解像度で録ったというよりは、その場の空気感も含めて克明に捉えていると言ったほうがいいだろう。そして、少し音量を上げて再生すると”サーー”というテープ録音特有のノイズがはっきりと聴き取れる。まるで50年代のレコードのようなノスタルジックなサウンドが聴こえてくる。ホセの声も各楽器の音色もどれもがうっとりするほど美しい。
古臭いのでも、過去のテクノロジーでもなく、今のホセをとんでもなく魅力的に捉えるためにふさわしいやり方だと僕は思った。なぜならここでは敏腕たちの演奏の繊細さが聴こえてくるからだ。アナログな録音方法だからこそ、音量をコントロールし、生音でのアンサンブルを成立させる匠の技が鳴っているのを感じることができる。
そして、本作はこれまでにホセとブライアンのコンビで手掛けてきた音源の中でも最も尖ったサウンドの作品かもしれないとも思う。
あまりに興味深いのでエンジニアでプロデューサーのブライアン・ベンダーに話を聞いてみることにした。
取材・執筆・編集:柳樂光隆 通訳:染谷和美
協力:ユニバーサル・ミュージック・ジャパン

◉『Merry Christmas from Jose James』のこと
――ホセ・ジェイムズ『Merry Christmas from Jose James』について聞かせてもらえますか?
パンデミック中の作業だったので、果たしてみんなで一緒に作業ができるのだろうかって話していたんだけど、結局(LAに住んでいる)僕はNYに行くことはできなかった。だから、僕を除いたホセのチームがアップステートにあるドリームランド・レコーディング・スタジオを使ってレコーディングしたんだ。木造のすごく素敵な建物で、ルディ・ヴァン・ゲルダーのスタジオみたいな感じを想像してもらうといいかもしれない。そこでバンドのメンバーが全員一緒に演奏したのをテープに録音している。これは『No Beginning No End』の時に僕のブルックリンのスタジオでやったのと同じ感じだね。
そこにあったレコーディング機材はOtari MTR90 MKII 2” 16-track。2インチのテープで16チャンネルしかないってことで、24チャンネルですらなかった。その状態で録ったものをテープからプロトゥールスに変換した状態で僕のスタジオに送られてきた。それを僕がまたテープに落としてアナログに変換してからミックスの作業をしたんだ。
みんなアナログ時代の巻き戻しってプロセスを忘れているよね?僕のスタジオの少し離れたあそこにテープのプレイヤーがあるってことは、少し再生したら、いちいち席を立って歩いていって、また巻き戻して、再生したら席に戻って、またもう一度聴くには席を立って歩いて行って巻き戻さなければならない笑 このプロセスがあるから、椅子に座ったまま機材を触ってカチャカチャやる作業とは全然違うものになるんだ。これは変な答えで良い答えではないかもしれないけど。ロマンチックな答えではあるよね。
ーーこのアルバムを再生するとテープのヒスノイズがいい感じで(かなり大きめに)聴こえます。
そうそう。そこがいいいんだよね。
ーーですよね。全体的にもナチュラルではありながらも最近ではあまり聴いたことがないような質感だったりします。ドリームランドの特徴や、そこで行われたレコーディングの特徴はどんなものだと分析しますか?
このアルバムに関しては実際にテープに入っていた音だけで出来ていて、僕が後からアンビエンスを足したりはほとんどしていない。今の人たちはその辺を誤魔化すことが上手くなっているんだけど、基本的には“このレコーディングをしたこの音が気に入りました。だから、これでいいでしょ?”ってのがこのアルバム。例えば、ドラムの音が大きくて、ホセの声が小さく聴こえてしまう箇所もあるとすれば、実際にマイクとミュージシャンの距離感がそうだったってこと。つまり現場における状態がそのまま反映されている。アンビエンス的な響きはお互いのマイクの中に入り込んでいる音が生み出している。つまり、ヴォーカルを録るためのマイクにドラムの音やピアノの音が入ってしまっているから生まれている。そのおかげでバンド全体の風景みたいなものが見えてくるような音になっているんだよね。
――ああいうレコーディング方法をすることのメリットってどういうことだと思いますか?
僕がさっき自分の仕事にはテンプレートを持たないって言ったけど、こういうレコーディング方法は型がないものになる。だからこそ面白みがあるんだ。そして、同時に複雑にもなる。一番に言えるのはホセのバンドみたいな優秀なバンドだったらこういうやり方は最高だってこと。“いい曲があって、演奏がうまくて、はい、演奏しました、録音しました、最高だね”ってそういうことができるからね。ただ、それは腕が伴わないとできない。その場で全てを決めないといけない。たまたまその日にいい音が録れなかったり、ドラムの音がうまく決まらなかったりしたら、それでダメになっちゃうことだってあるから、諸刃の剣だよね。
――なにかしらのリファレンスがホセからのリクエストがあったとか、ブライアンからホセに提案したとかはありますか?
このレコードに関してはホセから具体的なリファレンスがあった。まずはフランク・シナトラのクラシックなクリスマス・アルバム。それにレコードだけじゃなくて、シナトラがテレビに出ていた時のあの感じみたいなもっと具体的なものもあって、そこは面白いなって思ってた。他にはナット・キング・コールのレコード。あとはオリヴァー・ネルソン『ブルースの真実』。これはテクノロジーが進んでからの時代(1961年)のもので、割とハイファイで、クリーンなサウンドに関する参照元としてあがっていた。でも、全体的にはクラシックな50年代の感じで、ハードバップのレコードとかそういうものの感じだったね。
◉ブライアン・ベンダーの拠点Mother Brain Studio
――なるほど、ここからはあなたの話を聞きたいです。あなたの活動拠点でもあるマザー・ブレイン・スタジオ(NYからLAに移転)ってどんなスタジオなのか、紹介してもらえますか?
名前に関しては任天堂のゲームの『メトロイド』のトリビュートだね。究極の悪役に向かっていくアナログな騎士の存在ってところが惹かれるものがあった。このスタジオもそういうところがある。
とりあえず、見てもらおう。(カメラでスタジオを映し、Zoom画面で機器を見せながら)まず、60年代のゲルマニウム・トランジスタ(※ヴィンテージのNEVEのコンソールなどには使われていた)の機材(コンソール)があって、
その横にはモダンなデジタルのミキサーがいくつも入っている。ロジック、プロトゥールスなどのDAWコントロールなどなど
その横にはヴィンテージのボード。ヴィンテージのシンセサイザーがいくつも並んでて、その上にはモジュラー・シンセサイザーを置いてる
コンプレッサーもあらゆる種類が揃えてある。
そして、もちろんテープ・レコーダーもある。アンペックスのものだね。僕のスタジオはこういった機材で構成されている。
ーーヴィンテージの機材もたくさんありますが、特徴としてはアナログとデジタルのハイブリッドなんですね。
そうだね。僕は(ディアンジェロ『Voodoo』などを手掛けた名エンジニアの)ラッセル・エレヴァードからこの仕事を学んだこともあって60年代のヴィンテージのアナログ機材もたくさん集めている。一方でモダンなデジタルの機材も使っている。
アナログな機材でしか作れないテクスチャーはあるからそれらは外せないんだ。でも、デジタルでないと実現できないサウンドもあって、それはスピーディーにやらないと実現できない新しいサウンドだったりする。デジタルの魅力ってサウンドデザインが迅速にできちゃうところだからね。デジタルのもうひとつの魅力はリピートが可能だってこと。再現性だね。ホセのドラム・サウンドはここにあるゲート・コンプレッサーで作っているんだけど、シグナル(信号)っていうのはすごく複雑かつ繊細なもの。だから、アナログの機材は全く同じものを作ろうとしても不可能なんだ。それは他人にも不可能だけど、自分でも全く同じものを作るのは不可能。でも、デジタルだったら、全く同じものを再現することが可能なんだ。だから、そういう部分でデジタルの機材は僕のスタジオにとって必要なものなんだよね。
(※黒田卓也さんに『Rising Son』の時について質問したら”あの時はテープは使ったなかったですね。もしかしたら録音したものをテープに流す作業を経てたかもしれませんが”とのことなので、デジタルとアナログを様々な形で組み合わせているみたいです。)
――なるほど。ラッセル・エレヴァードから学んだ部分もありつつ、彼とは違ってデジタルの特性を活かして取り入れているところにあなたらしさがあると。ミックスに関してあなたの特徴はどんなところだと思いますか?
僕はメソッドを持たないミキサーなんだ。最近はミックスをコンピューターでやる人が増えている。となるとある程度テンプレートがあって、そこに放り込んで出来たものに対して、そこからどう変えていくかそういうプロセスになってきている。でも、僕は全てゼロからスタートするんだ。それがいいことなのか悪いことなのはわからないんだけど、自分がやってきた中で”こういうやり方は使える”とか、”こういうトリックは効果的だ”とかそういうのを繰り返し使うことも当然あるんだけど、いわゆる“これが僕の処方箋”ってやり方は持っていない。僕は最終的に仕上がったものとの感情的な繋がりを大事にしているんだ。テクニックと感情は別だと思う人もいるし、すごく大変だったから思い入れがあるって感じる人もいるかもしれないけど、そういう意味では感動できるからいいってものではない。でも、いいミックスって最終的には何か感情的に訴えかけてきて、何か感じさせてくれるものだと思うから、僕は最終的に何を感じさせてくれるかを重視しているんだよね。
あと、これもラッセルから学んだことなんだけど、どんなミックスをやるにあたってもまずはその音をとにかくじっくり聴くんだ。ミックスとか機材関係の人にこの話をすると驚かれる。音が届いたらどうやっていじるかってところでなんかやらなきゃって感じになると思われがちなんだけど、そうじゃなくてまずは音源に隠されているイディオム(※複数の要素から構成され、全体で1つの意味になるもの)とか、どんな人がどんなことをやっているのかを頭と心で思い描きながらとにかく聴くってことを僕はまずやってるよね。
◉ホセの代表作『No Beginning No End』のこと
――では、ここからはホセ・ジェイムズの話も。ホセとの関係はいつからなんですか?
ホセがブルーノートから最初にリリースした2012年の『No Beginning No End』から始まった関係だね。その後、引き続き2014年の『While You Are Sleeping』も一緒にやってて、その時の僕はプロデューサー兼エンジニアという役割だった。コラボレーションに関しては境界線があいまいでプロデューサーとかエンジニアとか言いながらも実は歌詞も手伝っているし、コーラス・アレンジもやったりもしている。『No Beginning No End』ではギターも弾いているしね。ホセは寛容な人なので、細かいことを言わずに何でもやらせてくれているんだ。
――まずは『No Beginning No End』のときはどんなことをしたのか教えてください。この時はエンジニアであなたの師匠のラッセル・エレヴァードも関わっていたと思いますが、あなたはどの部分を担当していたのでしょうか?
僕が知り合った段階ではすでにホセはピノ・パラディーノと一緒に曲を作り始めていた。「Trouble」「Sword + Gun」がそうで、他にも「It’s All Over Your Body」「Vanguard」に関してはピノ・パラディーノ、クリス・デイヴ、ロバート・グラスパーたちと共にラッセル・エレヴァードがすでに録音していたんだ。
僕はその頃のホセのパートナーとクリエイティブな仕事で繋がっていたので、ホセとは直接顔を合わせてはなかったけど、すでに知らない間柄ではなかった。幸運なことにホセと知り合う前にエレクトリック・レディ・スタジオでラッセル・エレヴァードの下で一年くらいアシスタントしていて、そこで色々学んでいたからアナログ機材の使い方やサウンドの捉え方など、色んな事を身につけることができていた。だから、『No Beginning No End』のための技術的な準備ができていたのは良かったよね。
ホセと知り合ってから、すでにラッセルたちの手で出来上がっていた4曲の音楽性を前提にする方向で僕もエンジニアとして参加することになった。僕が所有していたブルックリンのスタジオで録音したり、ミックスをしたってことだね。これは全てブルーノートとの契約前の話。アルバムがすべて完成した後で、その音源をブルーノートに持って行ってライセンスしてもらう形になった。ブルーノートの社長はローリング・ストーンズとかアーロン・ネヴィルとかを手掛けていたプロデューサーのドン・ウォズ。彼に聴かせたら頭の3曲くらいの段階で「これはまだミックスの段階だと思うけど、マスタリングは誰にやらせるの?とりあえず、誰にも渡さないでくれ!(※最終的にマスタリングは名匠トム・コインが手掛けた)」ってドンが言ったのを僕は忘れられない。ミックスまでやった人間としてはドンがそこまで言ってくれたことは光栄だったから。
――ラッセル・エレヴァードの下でトレーニングしていたとのことですが、彼はヴィンテージのアナログ機材やテープ録音で知られるかなり特殊なエンジニアです。エレクトリック・レディ・スタジオでどんなことをやっていたのでしょうか?
アシスタントだね。ラッセルはあらゆる部屋を行き来していたんだけど、僕は一番上の階のスタジオCでのアシスタント業務が僕の担当だった。その時に出入りしていたのはキザイア・ジョーンズ、ブルーノートと契約していた時期のアル・グリーン、ロイ・ハーグローヴ、ウィル・カルホーン、ピノ・パラディーノ、もちろんディアンジェロ。
ディアンジェロには曲作りにも関わらせてもらうことができて、すごくいい経験になった。基本的にはどこで誰が何をやっていたかの記録をとっておいたりもしていたし、タコスの注文もしていたよ(笑)
(※キザイア・ジョーンズの2008年作『Nigerian Wood』と2003年作『Black Orpheus』がラッセル・エレヴァドが録音。アル・グリーンの2008年作『Lay It Down』もラッセルが手掛けていて、クエストラヴがプロデュースしている。)
――『No Beginning No End』に関してあなたはエンジニアとしてどんなことをしていたのでしょうか?
ミュージシャンの腕が良ければ良いほど、僕の仕事は楽になる。この時、僕はマイクの準備と確認だけをきちんとすればいいくらいの感じだった。僕のスタジオでレコーディングしたんだけど、そこはかなり広くて250平米くらいあった。だから、バンド全員が入れるし、アイソレーション(隔離)もできた。(ハービー・マンの)クラシックス『Memphis Underground』(のジャケットの写真)みたいな雰囲気で、ごく自然な録音ができたと思う。バンドはみんな同じ部屋にいて、アイコンタクトを取りながら演奏したし、ランチもそこで一緒にとった。アナログなレコーディング方法をオーガニックにやることができたと思うよ。録音したのは確か7曲だったと思うけど、あっという間だった記憶があるね。
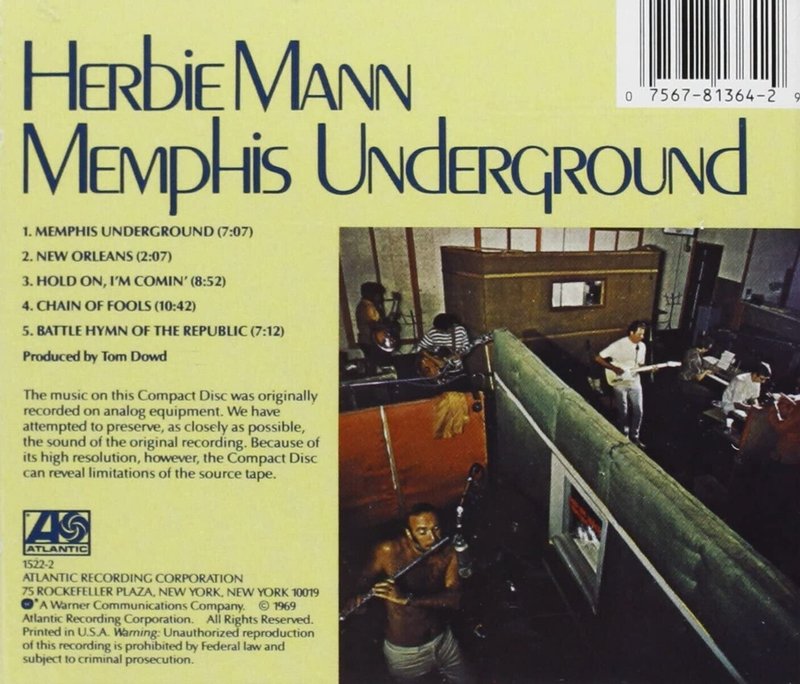
その頃、ピノはディアンジェロ(『Black Messiah』)のリハの合間を縫って僕らのレコーディングにも来ていたから、どこか現実離れした感覚があった。あんな仕事をしている人がこっちにも来てくれているって感覚があったからね。ただ、ディアンジェロの仕事があるから、こっちに来れる時間は限られていたっていう部分もあったんだけどね。こっちの仕事を終えると“じゃ、またディアンジェロのところに戻るね”って感じだったよ。
◉ホセの異色作『While You were Sleeping』のこと
――その次の『While You were Sleeping』はかなり変わったアルバムです。そこではあなたがかなり深く関わっていると思いますが、ここでどんなことをやりましたか?
僕がかなり手掛けたって言ってくれたのはうれしいね。あれはみんなで作ったアルバムで、みんなのエネルギーが集結している。ホセってプリンスが大好きなんだけど、同じくらいニルヴァーナも好きな人。みんなが同じ目的をもって音楽に向かっていくそのエネルギーみたいなものを形にしたがっていた。もちろんシンセサイザーを使った部分がかなりたくさんあったから、そのサウンドをそのままテープに落とすことは僕の役割だった。でも、それ以外のみんなのエネルギーを音としてまとめるみたいな部分こそが僕の仕事ではあったので、その意味では実際のプロセスはなかなか難しいレコードではあったと思う。
“こういうのにしてください”って具体的なメモを渡されてその通りにすればいいのなら簡単なんだけど、“なんかこんな感じで”もしくは“こんな感じのサウンドになる方法を探してほしい”って感じだったから。でも、結果的にあのアルバムに参加した全員があのアルバムの仕事からパブリッシングの契約を取ることができた。だから、あのアルバムは参加したミュージシャンにとっては全員が実力を発揮できた作品だったと思うよ。
――なるほど。
チャレンジって意味では前提となる比較の対象がない中で広大なところを彷徨っている感覚があった。『No Beginning No End』でさえも、曲によっては『Voodoo』や『Mama’s Gun』のようなネオソウル的なリファレンスはあるにはあるんだけど、全部の曲がそうじゃないからね。
僕にとってホセ・ジェイムズって人はルー・ロウルズの後継みたいな人なんじゃないかと思うんだよ。常に新しいことをやって、常に変わっていくことを目指すって言うね。その時々でホセがやっているジャズっていうのは、ジャズっぽくなくなることもあって、そういうのって“よくわからない”って言われちゃったりもするんだけど、でも、それこそがホセがやりたかったことなんだと思う。常に新しいものを探して、どんどん新しい影響を自分の中に注入していって変わっていくってこと。『While You were Sleeping』ではその前とは全然違うものになったから、混乱を招いたよね。僕が思うに彼がスタジオでやっている作業というのは、自分でどう問いかけていいかわからないような問いに対する答えを探しているような状況だったと思う。
『While You were Sleeping』での面白いエピソードをシェアしよう。「EveryLittleThing」の時にホセが自分の歌入れをしていたんだけど、それは他のメンバーと聴いている音源が違っていたんだ。だから、ホセが別の音源に乗せて歌っていたからズレちゃっていた。みんななぜかズレちゃうなって思っていた。しかも、ホセはそこに付けた詞に対してアクセントをつけていくので、その部分も含めて、他のメンバーがやっているリズムに対して歌がズレていて、ホセの歌が遅れて聴こえていたんだ。でも僕らはそれを聴いた後、“これで行こう。このままにしよう。そのほうがいいよね。”ってことになったんだ。ファニーでしょ?普通に考えたらリズムの捉え方は間違っていたんだよね。でも、出来上がった音楽としてその選択は間違っていなかった。僕らがやっていたのはそういうこと。そして、ホセってそういう人なんだよね。
◉Rainbow Blonde設立と『No Beginning No End 2』
――その後、ホセはRainbow Blondeと言うレーベルというか、コレクティブのようなものを作ります。そこでもあなたは重要な役割を果たしています。まずそこから2020年に出した『No Beginning No End 2』について聞かせてください。
あのアルバムは僕とホセとターリの3人でやったものだね。音楽的には少し前からホセの頭の中にあったものだと聞いている。ホセは自分にとってオーセンティックというか、ある種の正統だと思えることしかできない人なんだよね。傍から見ると、前作の成功を受けてその続編をとか、またネオソウルをとか言われていたけど、そういうのをやりたい気分ではなくて、彼はあの時点で自分の気持ちに素直に嘘のないものを心を込めて作ったんじゃないかな。そう思える曲のひとつが「Saint James」だったと僕は思っている。僕から言わせると彼の作品の中で最もパーソナルで素直に曲作りをしているアルバムだと思うし、これが彼にとってのオーセンティックなんだろうなって思う。
――エンジニアとしてはどんなことをしたんですか?
プロデューサーの仕事では心理面とテクニカルな面があって、その両方ができなくてはならない。優れたプロデューサーはその両方ができなくてはならない。両方が重要だからね。僕としては彼に対して、君の言うことは重要で、何をトライしてもいいし、君は間違えることはないんだって空気を作ることが仕事だった。
エンジニアとしてのテクニカルな部分では僕らが一緒にやったものはすでに7枚くらいあって、僕がミックスだけ手掛けたものを含めるともっとある。だから、僕らの間には何も言わずとも通じ合うランゲージがあるから、どのように彼の声を響かせればいいかというのは言われなくてもわかっていたんだ。なぜならホセ・ジェイムスのサウンドは僕が作ってきたものだからね。
ーーちなみにホセは以前の『No Beginning No End 2』に関するインタビューでは”70年代にはLAでジャズ・ミュージシャンを起用できる環境があって、そこでロックやポップスやシンガー・ソングライター(以下SSW)のアルバムが作られていた。それらは温かくて、アナログなサウンドなんだ。そういったスペースから生まれたサウンドを意識したと思う”って話をしていました。
具体的にマーヴィン・ゲイの72年のあの音とかって言われたわけじゃないんだよね。ホセが78年生まれで、僕が81年生まれだから、音楽の志向が共通していて、言わなくてもこれがかっこいいんだってことがお互いの間で合意できるんだ。ドラムの音でも、カーティス・メイフィールドとか、オハイヨ・プレイヤーズとか、プリンスとか、って名前を出せば”あぁ、あの感じの音ね”ってお互いに通じ合える。具体性って言うよりは幅広い共有するものみたいなところで言葉を交わさなくても音を作ることができていたレコーディングだったと思うよ。
――最後にブライアン自身のエンジニアとしての目標にしているようなレコードがあったら教えてもらえますか?
もちろんたくさんある。音楽の仕事で食っている人が疲れたとか、飽きたとかってなる時は自分の中にあるファンの部分を大事にしてあげてないからだって僕は思ってる。そもそも音楽が好きで楽しくてってところから始まっているはずなので、ファンである自分を大事にしてあげないとエキサイトメントみたいなものが失われて行くと思う。そういう意味でも自分が好きなレコードを振り返ってみることは大事なことだ思うよ。
まずはディアンジェロ『Voodoo』とエリカ・バドゥ『Mama‘sGun』。音楽的にも最高なんだけど、僕はこれを聴いて、NYに行こうって思うようになったきっかけになったレコードだから自分にとってすごく重要。最近ジェイムス・ポイザーと会って話す機会があったんだけど、「あなたが参加してるあのレコードを聴いて僕はNYに出て来たんだよ!!」って本人に言ったんだよね。
あとはカーティス・メイフィールド『No Place Like America Today』。そもそもカーティス・メイフィールドのレコード・レーベルのカートム・レコードのアルバムって、ダイレクトでクリーンで温かい音がするんだ。それらは全て僕にとって大切な作品だ。
◉ブライアン・ベンダーのプロジェクトBright &Guilty
※ちなみにブライアン・ベンダーはBright &Guiltyというプロジェクトをやっている。これが音楽としても素晴らしいし、エンジニアだけあって音の良さがすさまじい。イヤフォンでもすごいですし、スピーカーから出すと更にすごいです。なので、オーディオ好きの方もぜひに。
※記事が面白かったら投げ銭もしくはサポートをお願いします。
あなたの支援が原稿料や通訳費になります。
⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩
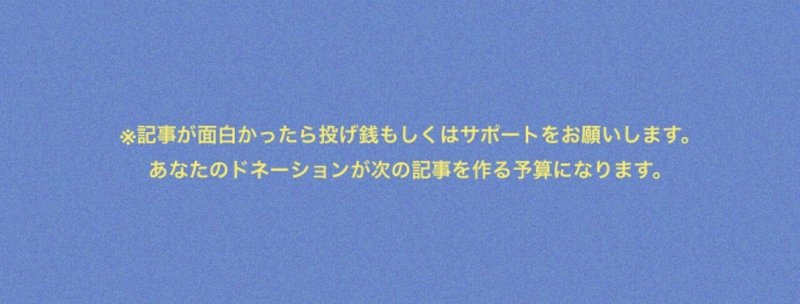
オマケです。
◉いくつかのアナログなレコーディング作品についての考察
ここから先は
¥ 150
面白かったら投げ銭をいただけるとうれしいです。
