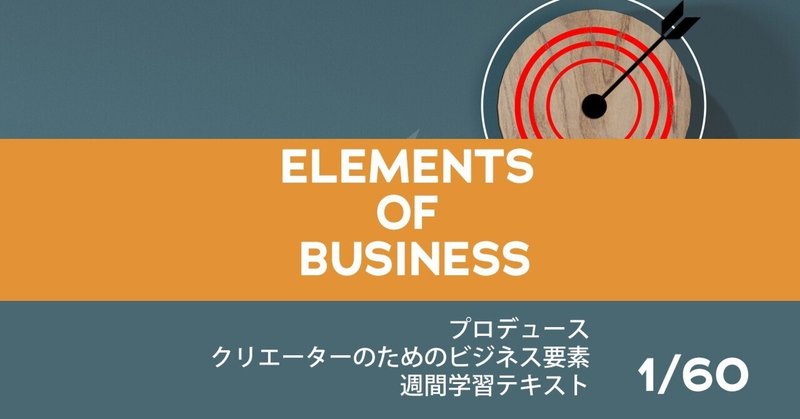
no.1 はじめに
現代の経済成長には、生活者の変化を予知した新しいビジネスの創造(起業)が大きく貢献している。そして、その原動力は人、特に最近においてはクリエーターだ。
また、現代の成熟した経済社会では、一部の生活者自身が自己実現を目指して自分の創造性を衣食住遊などの原点におく傾向、またクリエーターとしてそれを自身のキャリアの糧にしたいという願望も顕著になってきている。
このテキストで私は”クリエーター“という言葉をデザイナー、アーティスト、作家、音楽家といった狭義ではなく、発明家、エンジニア、科学者、あるいはその他さまざまな技術を駆使し”創造する者“という意味に使っていくのだが、このテキストでは、そういったビジネス創造の可能性を秘めたクリエーター、特に今までフォーマルなビジネスについての教育を受けていなかった人たちに、ビジネスを作り出し運営するうえで必要になる考え方を明らかにしたいと思う。
これが将来的に成功する会社を築く方法だ。本稿では「ビジネスの全体像」を、私が重要と考える要素を説明しながら紹介したい。
もちろんこの内容は全管理職にとっても有用である。なぜなら企業内でも起業家を育成することは、現代の企業存続の課題だからだ。
米国の大企業においては、現在、MBA(経営学修士)プログラム卒業生を幹部候補生として採用しようとする傾向とともに、MFA(Master of Fine Art)プログラム卒業生を求める動きが出て来ている。ビジネスウイークにも次のような内容の文章が載っていた。
“P&G Changes its Game (Design Thinking) July 28, 2008 BusinessWeek”において、P&Gはデザイン発想を会社の文化を変えることとして使っています。過去にP&Gはデザインを、商品を市場に出す最後のプロセス、つまり商品の飾り付けのための機能と考えていました。しかしこの考え方を新しいステージに変化させようと考えています。デザイン発想法を、問題を根本的に発想しなおすために使う、ということです。』
P&Gの代表者だった、A.G.ラフリー氏は次のように語った。
『ビジネススクールにおいては、直接的に入手可能な客観的データに基づく帰納法と、過去の歴史の中で証明された論理をベースにした演繹法、この二つに焦点をあてて発想が行われます。一方デザインスクールにおいては何が可能かということを考えるアプローチが評価されています。この新しい考え方は、我々が過去から持っている既成概念を超え、新しい考え方を否定するのではなく、歓迎するのだというカルチャーを作ります。』
現在、成長企業の優秀な経営者ほど、このような考えを持っている。クリエイティブな人材獲得が急務だと考えているのだ。
その理由はほかでもなく、「本物」、「良いもの」、「美しいもの」、そんな商品やサービスしか売れなくなってきたからだ。そういった商品やサービスの開発には、人間性、感性の豊かなクリエーターが必要。しかし、クリエーターとビジネスマンの一般的価値観は水と油のようにも違うので、企業ではまだ少数派のクリエーターたちが圧倒的多数のビジネスピープルにその準備不足を指摘され、圧し潰される傾向も存在する。一つの問題は、多くのクリエイティブ分野を専攻してきた学生には、利益追求型の組織やビジネスの仕組みを理解するための機会が少ないということ。そのためクリエーターは自分の持っている能力を企業の中でまだ活かしきれていないのだ。
このテキストは経営者がクリエーターをビジネス環境において有益に活用するための教材にもなる。
ここで自己紹介もかねて、少し私のことに触れておきたい。
1967年の私の高校の卒業時には私自身アーティストになりたいと思っていた。また私がP&G Wella Japan Divisionの責任者を退職し、ビジネスマンとしてのキャリアを終えたときにも、わたしはビジネスエグゼクティブというよりもデザイナーに近かった、とのメッセージが同僚からの寄せ書きにあった。
この性格はビジネス組織を率いて管理する私の長所であり短所でもあった。私自身がクリエーター的だったのだ。
わたしはカリフォルニア大学バークレー校で経済学やビジネスとは無縁の美術を専攻し、20代前半はアメリカ西海岸のリベラルな雰囲気を楽しんでいた。
しかしその後、家庭の事情でビジネスに関わるようになった。父の、事業を継がせたい、という意思を尊重する必要があったのだが、やがてそれに興味を持つようになる。
幸いなことに80年代初頭、米国の会社と共同で開発した「セロフェイン(ヘアマニキュア)」が日本の美容市場でブームになり、父の会社は大きな利益を上げた。
40代のときには営業に興味を持ち、わたしは日本の営業手法に、より効率的で透明性のあるアプローチを取り入れたいと考えるようになり、米国ネバダ州リノにあるミラー・ハイマン社の教育者育成プログラムに参加した。これらのプログラムで説明された概念は、のちにサロン業界向けの教育ビデオを作製するのにも役立った。
50歳の時に父の会社を離れ、アメリカのセバスティアン本社に入社し、その後ウエラジャパンの取締役として事業を行っていた。またProcter & GambleがWellaを買収したのちは、P&Gの下で日本のプロの美容師のための美容事業をウエラジャパンの社長として率いてきた。
このビジネスキャリアの中で数々の「プロデュース」も行った。手痛い失敗も経験した。その原因分析と反省は、P&Gのビジネス手法を理解することでより深まり、わたしにとって有益な勉強になった。
またP&Gでさまざまな研修を通じて組織のリーダーになることを学べたのは幸運だった。特に企業の使命、個々の組織メンバーにとっての目的の重要性を実感した。
わたしは60歳でビジネス界を引退し、さまざまな大学や専門学校で教鞭をとった。60代から70代までの10年間、マクロな視点でビジネスを学ぶことができた。またこの間、アカデミックな分野における教授たちとの出会いも実り多く、「戦略マップ」と「バランススコアカード」をビジネスに活かす方法を彼らから学んだ。
同志社女子大学の必修科目「経営研究」を担当した時、最初にこのようなテキストの必要性を感じ、この原稿はまず、そのために作成された。
同志社女子大学では、メディアクリエーション学科に在籍する20歳前後の女性を対象に、「マネジメント」について15回の講義を行うことになったのだが、彼女らはビジネスをまったく理解していなかった。また「経営研究」はこれらの学生にとって卒業のための必須科目でもあり、彼女らの好き嫌いに関係なく、学校からの指示で、全員この講義を受けることが強制された。そのため授業が嫌いな学生が多く、苦労した。
その際、「クリエーターを志望する人に、ビジネスの全貌を短時間で理解してもらうことはできないのか……」「できるだけシンプルに、でもビジネスで発生するさまざまな要素をカバーしたい。あまり細かいところまで踏み込まず、概要を網羅してみよう。」と真剣に考えるようになった。
そんな思いと、その時に始めた準備がこのテキストのバックボーンになった。
残念ながら結果として、シンプルなものにするという意図は達成できなかったと思う。また、これらはわたしの経験からの知識を紹介する講義ノートのようなものになってしまったのだが、わたしが学んだすべてのビジネス要素を「プロデュース」の観点からここに有機的に関連させた。
ちょうどそのころ、同志社大学の<プロデュース技術研究所>でわたしのプロデュースの経験を発表する機会を与えられたこともきっかけとなったのだ。
このテキストの内容は社内起業家、事業主、これから経営者になりたい人、ビジネスを勉強したい人、特にクリエーターのために活用できる構成になっている。
前置きが長くなったが、言いたいのはクリエーター的な私は最初ビジネスがわからなかった、ということ。そしてプロデュースという切り口が私にとってはビジネスの全体を理解するうえで役立ったということだ。
このテキストでは「プロデュース」という用語を強調したいと思う。もっとも「プロデュース」という言葉は、これまで事業のメインテーマとして語られることはなかったのだが。
もうひとつここで述べたいのが、このテキストの構成とその使い方である。
私自身振り返って思うのだが、若いころはとかく毎日、毎月、毎年のスケジュールを慌ただしく作り、ムダと思われる時間は嫌だったのだが、今になれば20代、30代の2年や3年は決して長い年月とは言えない。
大学院でのMBAやMFAは2年のプログラムになっているが、一定の考え方や技術を身に着け、それを自身の能力とするにはその程度の期間がかかるのだ。
「経営研究」の15回の講座はビジネスをマスターするにはあまりにも短すぎたので、ここでは15回の講義を4クール、つまり約60回のレッスンとエクササイズにした。もし大学だとすると、約2年分のクラス設定になるだろう。
またレクチャーでは細部にわたって説明もできるし質問にも答えられるが、文章ではどうしても言葉足らずになってしまった。
英文が多いところは辞書を片手に、抽象的表現のところはぜひ時間をとって自身で考え、自分なりに会得してほしい。
また1冊ノートを用意してメモをとる、アイディアを書き留める、という習慣とともに読むべきだ。
1週間分のレクチャーやエクササイズは比較的短時間で読んだりトライしたりできると思うが、焦って先へ進まず、一週分を繰り返し、時間をかけて自分のものにしてもらいたい。ゆっくり着実にやることでクリエーターの人たちにもビジネスの思考が身につくはずである。
