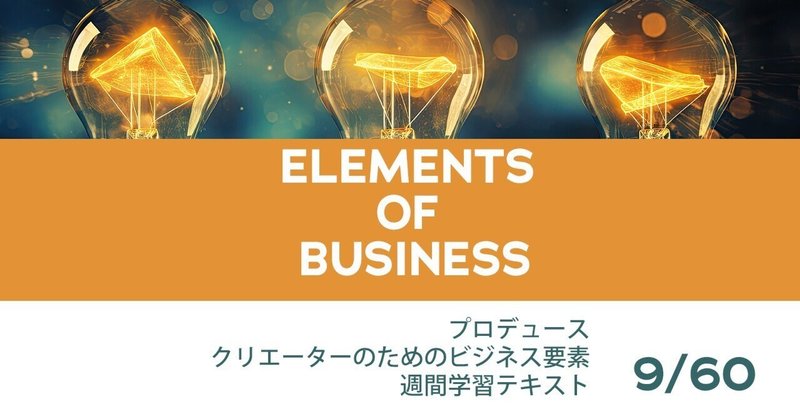
no.9 着想 ― コントリビュート(貢献)

着想ステージの次の段階である「貢献」は、JP ギルフォードの心理学では「発散」段階と呼ばれている。ここでは、知性と感性によってテーマを入念に吟味する。
プロデューサーとしての自分のためではなく、テーマにとって (またはその顧客/消費者にとって)、その実現のための具体的方法を見つけることが特に重要なのだ。
テーマ実現の障壁となっている問題を解決する手段を考えよう。 「自分がやりたいこと」に集中して、利己的な考えにとらわれてはいけない。利己的な見方から離れて、「私に何ができるか」を考えよう。 「どうすれば貢献できるか? 」、利他的な視点を保つ必要がある。難しいが、それがこの段階を「貢献」と呼ぶ理由なのだ。
どこで戦うかを決めるプロセス、テーマの認識についてはコネクトで説明した。
このコントリビュート/貢献の段階で、我々は勝つための方法を探す。
テーマ、ターゲット市場、ターゲット市場のニーズとウォンツを理解した後、それらを満たすための具体的な方法を見つけようとするのだ。あなたには何ができるか? 些細なことでも、大きな計画の一部でも、何でも、思いついたことをリストアップしてみてほしい。もう一度強調しておくが、純粋な科学や芸術におけるイノベーションとは異なり、ビジネスにおけるイノベーションは、特定の顧客/消費者とその特定のニーズ・ウォンツをターゲットにすることから生まれる。
それらに貢献するためのアイデアを探る。ほとんどの人は自分が「楽しい」と思えるアイデアやテーマからプロデュースを開始することを好むが、しかし「貢献」では、さらに一歩先を行く努力をする必要があるのだ。
近年、創造や貢献といった挑戦よりも、社会全体が消費や娯楽に走る傾向にある。多くの若者はまた、仕事に魅力を感じようと「楽しい仕事」を求めている。
しかし、ものづくりの本質は、楽しさを求めることではなく、人や社会に貢献することであり、その結果として求められるのは「満たすことによる喜び」である。
貢献のアイデアを探る
効果の高いアイデアをできるだけ発散的に考えることが重要だ。着想の重要性は、アーティスト村上隆のコメントからも理解できる。
日本の美術教育は精妙に絵を描くことに執着している。そして、現代日本美術の学生は絵が得意です。つまり、日本の資産は技術に頼る傾向にあるのに対し、欧米の資産はアイデアに頼る傾向にあります。 「赤ひげ」のカメラワークがどんなにすばらしいとしても、技術的には後世追いつかれる。しかし黒澤監督の人柄と魅力は、技術が追いつかないところにあります。そして、アートも技術よりもアイデア<個人的、個性的思考>を重視すべきだと思います。 (⑫)
つまり、必要な技術の議論に入る前に、自分がどのように貢献できるかを多く発想し、かつ明確にすることが重要なのである。ここでは、何人かのアーティストの、いくつかの貢献の姿勢に関する事例を紹介したいと思う。
共感していただければ幸いである。
クリエーターが、自身のテーマへの貢献を実践するためには、そのフィールドでの過去のクリエーションを研究するのも有効だ。
「どうだった? オイストラフはどれくらい速かったかしら。もう一度聞いてみましょう。」 ……いずれにせよ、気が付いた生徒たちは、オイストラフだけでなく、他の演奏者のテンポをも比較します。優秀な学生は、できるだけ多くのパフォーマンスをチェックしていきます。比較と予習により、彼は同じ音楽でも異なる解釈があることを知るでしょう。10人の話を聞きましょう、 10人の演奏者の音楽を聞いて、リストを作りましょう。 聴き比べてみると、テンポだけではないことに気が付きます。セツは、このセッションを、「一人にならないで 先人たちの演奏に謙虚に耳を傾けて」とディレイ先生が暗黙のうちに言ったものと解釈しました。 (⑬)
唐招提寺の襖絵では、東山魁夷が表現手段やテキスチャー、使用する道具の選定に力を注いでいた。さまざまな手段を検討するとき、彼は常に貢献の想いを貫いていた。
この揚州をテーマにした襖絵は、御影堂が一般公開される毎年恒例の開山法要の際にも拝殿が部屋の前に置かれているため、参拝者の目に触れることはありません。特に手前の柳の古木は厨子の陰に隠れています。私はそれを知っていて、絵を構成しました。それは、これらの障壁画は和尚に捧げられているからです。 (⑭)
唐招提寺では、襖絵は鑑真和尚に捧げられたアートということになるのだが、ほとんどの場合のアートはその鑑賞者に捧げられるということになる。
私は眉をひそめた。 「そうではありません。マティスの目標は、表面的な清楚さではなく、常に本質的なものです。マティスは単に人を楽しませるためだけに仕事をしているわけではない……そんなことを考えるのは馬鹿げています。
マティスの作品は装飾的ではない、もしたとえ見る人に苦痛ではなく喜びを与えたいと思っていたとしても、それは彼が危機に瀕している人間の内面の調和を再現するのに、役立つと信じているからです.
彼は、芸術がストレスによって危険にさらされることがある人間の心に影響を与えると信じています。
「マティスとピカソ」フランソワーズ・ジロー(⑮)
貢献すること/貢献は、顧客にお世辞を言うことではない。貢献は真の善を追求するものでなければならないからである。 その真髄は、スターバックス CEO ハワード・シュルツの言葉からも感じられる。
第二に、顧客の要求するものを提供するだけでは十分ではありません。お客さまが知らないものや、最高のものを提供することには、お客さまの味覚が洗練されるまでに時間がかかる場合があります。しかし、それは顧客に発見の喜びと興奮を与え、ロイヤルティを確立することにつながります。良い商品を提供すれば、たとえ時間がかかっても、お客様は必ずそれを選んでくれます。大衆市場をふらつく必要はありません。 (⑯)
ビジネスにおいて、貢献の精神が組織に浸透すると、チーム活動は一体となる。会社の業績が社会の中で明確に見えるようになり、評価されるようになる。イケアの例では、以下のような成果を上げている。
カンプラード氏は、世界中の人々の住宅生活を改善する業界の貢献者として自分自身を認識しており、その方向に進み続けなければならないと考えています。彼はエバンジェリストであり、ほとんどの従業員が同じ考えを持っていると確信しています。 「社内調査によると、イケアの従業員はより良い社会に貢献したいと考えており、イケアで働くことに満足しています」と彼は言います。 (⑰)
社会に貢献するイケアのような企業はどのように生み出されるのか? それは、着想の初期段階から、「貢献する」という概念がアイデアを発散するための原動力として位置付けられていたからである。
イケアは私を満足させるために、発展するだけでなく、多くのお客様の家に明るい未来を提供する―という目標を達成したときの充実感を私にもたらすのです。企業がこれらの目標を持っている場合、それはその企業で働くスタッフにも影響を与えます。 (⑰)
「インキュベーション」。この言葉は起業家精神についてよく使われる。親鳥が卵を抱き、温め、貢献するためにできることは何でもしようとすることを意味する。そんな形で、彼らは世話をし、愛するものを大切に育てていく。ましてや、他人を喜ばせることで幸福を得ることのできる動物は人間だけなのだ。
人は貢献する。周りの環境を明るくするために、人は生き続けてきた。
独自性に固執する必要はない。人類の性質上、全く同じ人間はなく、人にはそれぞれに、その人固有のものがある。それが個性だ。そしてこの個性は、テーマが定義され、その人が本気でそれに貢献しようとするとき、完全かつ効果的に表現される。貢献することで、一人ひとりの個性が光る。
私たちは皆、他人の仕事によって食べ物と家を与えられています。だからあなたはその代償を支払わなければなりません。自分の内なる満足のために選んだ仕事をするだけでなく、人々に奉仕する仕事をすることによって。そうでないと、それがどんなに質素な欲望であったとしても、寄生者と呼ばれてしまうでしょう。 --- アルバート・アインシュタイン (⑱)
ビジネスにおける発散の方法には、特定のルールと形式もある。 制約を設け、決められたルールに従って貢献を考えることは、アイデアを発展させるのに効果的な場合があるのだ。
導入部で述べたように、個人ではなくチームとして作業する必要がある場合、特定の形式がないと、アイデア発散のプロセスは混乱し、的外れになる可能性もある。
次に、貢献するアイデアを生み出すのに役立つ具体的なフォーマットについて説明したいと思う。
具体的なアイディエーションのプロセスの実例はあまり多くはない。なぜなら、「貢献」の段階と次の「創造」の段階は、プロデューサーの心の中で起こる個人的で、繊細で複雑なプロセスだからである。場合によっては、最終的に着想プロセスが完了した後、実際のプロデューサー自身がこれらのプロセスを忘れてしまっていることさえある。
そういうわけで、これから私が例としてあげるのは、わたしの想像によるプロデュースプロセスである。特定のプロデューサーが使用した実際のプロセスとは異なる可能性もある。しかし、本質的にこれらのプロセスが現実に近いと私は思う。そして、次のセクションに記したフレームワークは特にビジネスプロデュースにおいて実用可能でかつ有用であると確信している。
シャネル、スターバックスのシュルツ、イケアのカンプラードが使用したと仮定したフォーマットを次に示そう。
参考文献:
⑫ 「芸術起業論」 村上 隆著((株)幻冬舎)
⑬ 「五嶋節物語 母と神童」 奥田昭則著(小学館)
⑭ 「唐招提寺全障壁画 東山魁夷小画集」 東山魁夷著((株)新潮社)
⑮ 「マティスとピカソ 芸術家の友情」 フランソワーズ・ジロー著(河出書房新社)
⑯ 「スターバックス成功物語」 ハワード・シュルツ、ドリー・ジョーンズ・ヤング著(日経BP社)
⑰ 「IKEA 超巨大小売業 成功の秘訣」 リュディガー・ユングブルート著(日本経済新聞出版)
⑱ 「アインシュタイン150の言葉」 ジュリー・メイヤー&ジョン・P・ホームズ編
((株)ディスカバー・トゥエンティワン)
