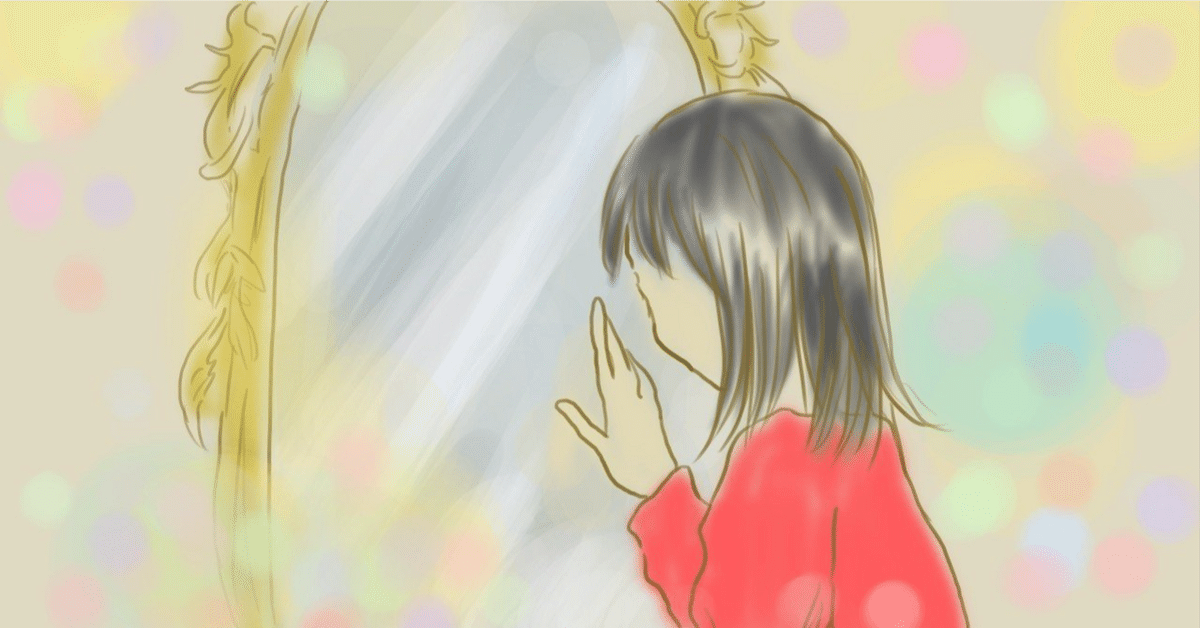
大学のゼミは教員自身を映す鏡
私が勤務する大学では、各研究室に配属された卒論生のテーマやゼミ内容は完全に教員に任されています。同じ学科であっても、研究室によって「ゼミ」の中身は千差万別なのです。
私が主催する研究室では週に一度の「ゼミ」は完全に論文講読です。といっても最初から論文を読むわけではなく、4月は研究テーマに沿ったキーワードを渡してそれを調べてもらって基礎知識を身につけます(ついているかは不明)。
実際に論文を読み始めるのは5月から。なるべくシンプルなストラテジーで分量も多くないもの、さらに日本語で書かれているものを読んでもらいます。
少しずつレベルアップして、秋くらいから英語の論文に移行します(その辺は学生のレベルにもよりますが)。
これまでnoteでさんざん書き散らかしている文章を棚に上げていうと、私は割と言葉にうるさいんですよ。なので、論文の中身が理解できているかだけでなく、説明やレジメにも大いにツッコんでいます。
そうするとどうなるかというと、「レジメを作りこむ」ようになるんですね。
これって必ずしも悪いことではないのですが、文章をみっちり入れたレジメを作ってきてそれを「読み上げる」方向に傾いていくのです。最初は様子を見ていたのですが、ひとりがやり始めたら「右へ倣え」になってしまい、先週のゼミは完全に「書かれたものを読み上げている」だけ。
学生が論文を読みこんで、内容を理解して(難しいだろうけど)、その内容を他人に理解してもらえるように工夫しながら説明する、というのが私のゼミの目標です。みんなの反応を見ながらみんなの理解度に合わせて説明するためには、「書かれたものを読み上げる」というのはありがたくないスタイル。
ウチの学生は創意工夫するのは苦手な反面、とても素直なんですよ。なので「自分で考えて作り直して」と指示してもうまくいかないのですが「次回からはこういうふうにレジメを作ってほしい」というフォーマットを渡すと頑張ってやってくれます。
というわけで、今週はフォーマットをしこしこと作りこんでいました。
さて来週からどうなるでしょうねえ。結局のところ、学生は私の意見とか考えとか好みに敏感だから、発表は如実にそれを反映しているのでしょう。つまりゼミは学生から見る私を映す鏡なんでしょうね。私が思うようなゼミになるためには、私が理想とすることをきちんと学生に伝えないとダメなんだなあ(責任重大)。
