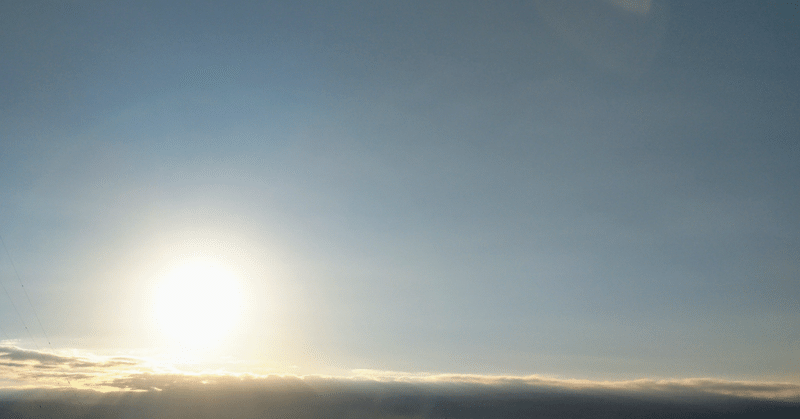
エネルギーベストミックス
エネルギーベストミックス
エネルギーベストミックスとは経済産業省が、一次エネルギーの転換・加工等によって電力について、経済性や環境性、そして安定供給できることを踏まえた電源構成で安全性を担保した上で最適化を目指している言葉です。
これを私は住宅設計の中でも取り入れて、家族構成等踏まえたライフスタイルに応じて、省エネ設備機器等を選択するべきと提唱しています。
例えば、①若いご夫婦で共働き、お子様は二子の男女、ペット(犬か猫)も飼われている世帯。②高齢者夫婦で、揃って年金暮らしの世帯。③二世帯が住まう世帯。
さて、給湯器含めた設備機器等を、どのように選択すべきか。ここには温熱環境等を含めた提案が必要になると思われます。
まずは、今世紀最強と言われるべきヒートポンプ技術の革新でしょうか。エアコンのヒートポンプ技術を活かした「エコキュート」と言われる給湯器は、電気温水器(最悪の電力爆食機器)と打って変わって、同じ電力系統の熱源機であってもヒートポンプ技術によって、給湯器の省エネ化では最強と言われる設備機器でしょう。しかも深夜電力を利用することができるので、省エネ度に関しては他の設備機器とは一線を画す機器と言っても良いでしょう。
同様にガス機器も進化を遂げており、排熱利用を上手く利用した「エコジョーズ」、そして、お湯を使うごとのガス消費によって燃料電池を搭載し発電する「エネファーム」。
中でもエコキュートは発売開始時期(約2000年)から2020年度まで約700万台を突破する勢いで、オール電化と合わせてIHヒーター等も普及しています。太陽光発電等と上手く組み合わせれば、電気代やガス代が相殺(実質0円)されることもあって、新築だけでなくリフォーム需要でも普及しています。
しかしながら、これらの機器含め先に例題として紹介している①〜③の家族構成等にマッチングする設備機器はどのような考え方をすべきか。また、断熱性能についても検討をしたいものです。青天井のようにコストを掛けるのではなく、メリット/デメリットを活かした適材適所ということを考察して見ましょう。
まずはエコキュート。300リットルとか500リットルという「お湯」をポットのように常時抱えていることから、大きな貯湯タンクがあることは否めません。つまり、「設置面積」はかなり大きな条件に当てはまります。また、冬場では外気温にさらされることになるので、「保温能力」や「凍結等」にも配慮が必要です。
このエコキュートの設置面積に続き、「凍結」、又は「低温化」(設定温度よりも低くなり昼間の高い電気代を使用するなど)が大きな悩みどころです。基本的には一般製品でマイナス10℃までは対応、寒冷地仕様ではマイナス20℃対応となっていますが、メーカーや機種、そして地域性を十分に考慮する必要があります。給湯器の設置は一般的に屋外で、機器に近い設置場所(捨て水等を考慮)を選択するのですが、南東面に設置することも選択肢の1つです。また、豪雪地帯では無くても冬場の雪を考慮した設置場所(いくらヒーター付きタンクでも雪に埋もれていては冷たくなるのは必至です)、又は「防雪オプション」を購入して十分に配慮するケースもあるでしょう。また、敷地等に余裕があれば「屋内設置」も検討すべきです。ちなみにD社の寒冷地仕様のエコキュートは、日本で最も寒い地域と言われる(マイナス20℃以上)北海道は旭川市をモデルとして作成されています。他にも、M社製やP社製など、寒冷地に強い機種があるので、単に「エコキュート」だからという選択ではなく、十分に検討して見て下さい。大半の機種は省エネ性能に優れていますが、「エコキュート」はあくまでも名称なので、各メーカーや機種などで得意分野があるということです。
さて、ライフスタイル別に見た場合はどうでしょうか。
①の例題では男女の子供達がいます。10年も経てば思春期を迎えるでしょうし、男の子は体育系の部活で洗濯機の使用量も多くなるでしょう。(女の子だって考えられますね)また、受験をすることで不規則な入浴や食事、お湯の使用時間・使用量というのは、格段に変わって来るでしょう。また、ペットを飼っていることで、意外とシャンプーやドライヤーなどを使用するケースも多くあり、ペットフードの食費だけでなく、多くの光熱費の負担はかかるものです。ここでエコジョーズを使用してしまうと、使用量の増加等で「缶体」に負担がかかり過ぎるので耐用年数が短くなることでしょう。「エコキュート」が選択されることが好ましいです。(ここで言う使用量と言うのは、例えばお湯を良く使用するうどん屋さんやお蕎麦屋さんなどは、沸騰するお湯を減らさないように、少量のお湯(又は水)を利用したり、食器を洗うケースも多くあります。つまり、給湯器にも一般家庭用と業務用があるのです)
②のケースの場合は、高齢者ご夫婦です。若い人でも寒くなると入浴においては躊躇します。高齢者では温熱環境への反応が鈍くなるし、汗を余りかかなければ2日~3日に一度の入浴かも知れません。また、少しでも暖かい昼間にゆっくり入浴するケースとして、近所にあれば温泉施設なども多く利用するでしょう。また、食が細いことからも少量で済ますので、煮炊きするケースも少なくなり、スーパーのお惣菜などを多く利用することも考えられます。そうなると、お湯の使用量というのが各段に減少することから、貯湯タンクを背負うよりも「必要な時だけ必要な量を効率良く」という観点からは「エコジョーズ」が最適になります。
③のケースはどうでしょう。二世帯という世帯構成から、入浴やキッチンなどは別々とする計画もあるかも知れませんが、①のライフスタイルの変化という経過ではなく、最初から膨大なお湯を使用する(二世帯分)ことが想定されます。そうなると、設置可能であれば太陽光発電と発電量する機器をセッティングして、何とか負担の少ない効率化を考察することで「エネファーム」、おひさまエコキュート、又はそもそも大容量のエコキュートも考えられます。
(太陽光発電は豪雪地帯では設置が難しい事とリフォーム等の改修でも難しいですね。あくまでも条件に適合できるか、災害等を考慮した搭載が好ましいでしょう)
つまり住宅設計における「エネルギーベストミックス」の考え方は、自社のスケールメリットを活かした機器(アップセリング、クロスセリング)を選択するものでなく、お客様を中心とした家族構成やライフスタイルに応じたメーカーや機器の特性を考慮して選択することが好ましいという考え方です。
ちなみに「凍結深度」という建築用語がありますが、自分の地域の凍結深度を調べるのはインターネット含め各自治体が決めているので、問い合わせることをお勧めします。(温暖化地域である九州と沖縄は設定されていません。一般的に45㎝~100㎝程度)ただ、大半の人(建築士含め)は、基礎が凍って寒くなるとか、地面が凍ったり配管が凍って破裂することをイメージされていると思いますが、一番重要なことは地面の水分が凍る過程で、基礎を押し上げてしまって家屋が持ち上げられるということです。浮き上がるという表現でも良いと思います。そもそも、水が氷に変わるときに約9%前後も体積が膨張するということです。この膨張する時の力というものは、配管を破裂させるだけでなく家屋を持ち上げることも理論上では可能であり、コンクリートを粉砕(ひび割れ等も)する力を持っていることで、これらの専門技術もあることで有名です。よって、凍結深度を考慮した基礎設計が必要だということです。
では、配管等については一応基準値としては敷地内は0.3m以上の埋設とあるので、30㎝は埋設する深さですが、排水管については勾配が必要になるので場合によっては0.5m以上になるケースもあるでしょう。最近では長期優良住宅の設計、又は凍結防止策と維持管理メンテナンスの設計上、屋内配管(ヘッダー配管等)を使用するケースが多く、基礎断熱を行っている住宅では、屋内配管することで余り心配しなくても良いと思います。また、凍結防止を兼ねた水道メーター含め配管等も保温材(寒冷地用など)の種類も多く対応しており、地元の有力な配管設備業者であれば対応可能でしょう。
私の知っている企業では関東地域でも地域によっては、冬場の北西からの「吹きさらし」や「吹き溜まり」になることがわかっているエリアをチェック(履歴)しており、これらの対応を行っています。
そして温熱環境における断熱性能についてですが、基本的には最新の省エネ基準に適合すること。また、2025年より義務化されることが発表されているので、従来よりも各段に断熱性能が向上することは間違いないでしょう。しかしながら、断熱性能も高度な知識と施工技術を要することなので、業者選択としてはある程度施主になるお客様自身も最低限の知識を必要とすることが好ましいと思われます。
表題がエネルギーベストミックスということなので、ここでは詳細を控えますが、断熱性能については、「HEAT20」の概念である「G2」以上の基準や、事業者しかできない「C値」である「気密施工」(0.5以上)、熱交換含め換気効率(約90%を推奨)を最大限に活かした空気環境など、単にUA値だけでない総合的な温熱環境の特性を熟知している業者を選択することが好ましいでしょう。土地から購入を検討しているのであれば、災害対策(ハザードマップ)や日射効率を活かしたパッシブ性能を十分に考慮できます。また、空調機器も部屋の数だけとか局所的ではなく、ヒートショックや健康維持という観点から、玄関から廊下、階段、水廻りなどのサニタリースペース、そして寝室を含めた、屋内全体が快適な空気環境を維持できる「全館空調」も選択の1つです。一見、電気代が高くなるのでは?と考えますが、エネルギーベストミックスを最大限に活かした設計では、イニシャルコストよりも返ってランニングコストを考慮した省エネ化と快適性に繋がるのです。
今のこの時期、三省合同(国交省、経産省、環境省)の莫大な補助金が利用できます。場合によっては、半額以上の補助、光熱費や医療負担を考慮すると実質「0」円になるとも言われています。温熱環境は個人差があるので、まずは体験(体感)できる施設(実験設備、展示場等)や完成見学会(お客様の家)などを利用して見ましょう。
