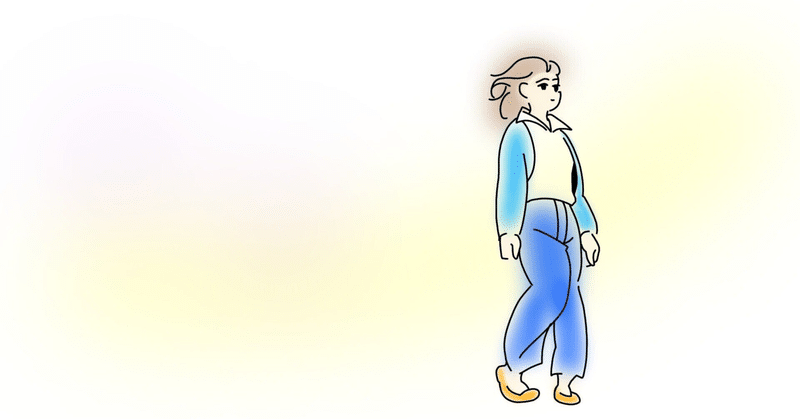
業務に前のめりで喰らいつく、活きのいい人材になるには
異動や転職で新しい仕事に向き合う時、人は予備知識がゼロの状態からスタートする。
ここで良いパフォーマンスを発揮できるどうかかは、「自らで発見・解消した疑問の数」に左右される。
ところが、現実にはこのアクションがとれずに身体が固まってしまう人が多い。「何が分からないのか分からない」状態で、行動に移せない人が多いのである。
この記事では私が実体験を通じて考えた「分からないことの発見法」について書いてみたい。
前提の確認
まず大前提だが、質問や疑問が生まれるのは「自分の予想と現実の間にギャップがあった」時である。
今まで500円で買えていたものが、ある日を境に550円払わないと買えなくなった時、「なぜ?」と疑問が生まれる。
これは「今日も変わらず500円で買える」という予想を裏切られたからである。
それで店員さんに質問して「理由は原材料費の高騰によるもの」という回答を受け、ここではじめて物価に対する理解が深まる。
自分の中に何の仮説もない状態では、そもそも質問が生まれないのだ。
何の疑問も持たない人間にはやるべきタスクが見えてこないので、すごく暇になる。そのまま一定時間が過ぎると、いつの間にか無能の烙印を押されるのである。
ビジネスマンとしてはもっとも恐ろしく、不幸な結末である。
ここから先は、このような悲劇を回避するためのより具体的な方法について考えてみよう。
自分が疑問を発見しなくてはいけない立場の時
予想をたくさん立てるアプローチ
初級編:丸投げ質問
仮説を立てる知識すらない場合、まずはここから始めなくてはいけない。
「〇〇って用語はどんな意味ですか?」という感じで、全く自分の考えを込めない丸投げの質問をする。
ここで重要なのは回答してもらう際に調べ方もあわせて習得し、自力で仮説を立てられる範囲を広げてゆくことである。
中級編:身の回りのものに仮説を立てる
知識が増えてきたら、今の自分が接しているものに対して仮説を立て始める。
取り組む仕事の5W1Hを全て挙げたり、手順の全体図を書き起こしてみたり、いろんな角度から「足りてない要素はないか?」を掘り起こす。
例えば、自分が本を出版するとしよう。
「書く内容を何にするか?」は誰でも考える。じゃあ、その他にやるべきことは?
・出版の手段をどうするか(紙か電子か?出版社を通じてやる?イベントで手売り?書店に並べてもらう?)
・集客をどうするか?(SNS、動画サイト、現地でビラ配り、ポストに投函、イベント参加、書店に挨拶回り)
・紙の本で出版をするなら、紙の手配は?印刷は?販売予定日から逆算するといつまでに原稿上げる?
・人手が足りないならどうやって人を集めるか(知り合いの紹介?バイト代払って手伝ってもらう?雇用契約の条件は?直接スカウトしに行く?所属コミュニティから仲間を探す?)
世の中の多くの人は、一番楽しい書く内容だけ考えて、後の雑務は外注している。
周辺のプロセスまで考えて仮説検証を繰り返している人間からは、こう見える筈だ。
外注すると料金がかかるので、その分たくさん売らないと採算が取れなくなり、「販売ノルマ」が増えてゆく。
本当に「たくさん売る覚悟」をした上で決断したの?
外注先は商売だから止めたりしてくれないよ。
上級編:遠くにあるものへの仮説を立てる
身の回りのものに仮説を立てられるようになったら、徐々に射程範囲を伸ばしてゆく必要がある。
「これまでは直近1週間のことに対して仮説を立てているが、プロジェクトが2ヶ月後にどうなっているかの仮説も立ててみよう」
「自分の部署と関わりのある他部署の業務は実はこうなっているんじゃないか?」
考えた仮説を使わずに終わる場合もあるかもしれないが、積み上げた思考は「将来に備えた素振り」になる。
類似の事例にぶち当たった時に、「考えなくても身体が動く」という、最も効率の良い状態になれるのだ。
仮説と検証は車の両輪
仮説ばかり立てて現実との答え合わせをしない人間は、仮説を修正する機会がないので成長できない。
逆に、仮説を持たずに現実と向き合っても、読み取れるものがなくて学びに繋がらない。
両者は車の両輪であり、どちらか一方に偏ってはいけないのだ。
ということで、ここからは現実との答え合わせの方法についてである。
現実との答え合わせをたくさんするアプローチ
有識者とミーティングを開いて指摘をもらう
問題点を炙り出しやすいが、人の時間をもっとも拘束する方法である。仕事ができる人は本当に価値の高い時にしかこのようなミーティングをしない。
実物を触ってみる
自分で実物をいじくり倒し、立てた仮説が正しいかを確かめる。ミーティングを開くよりスピーディに結果を確かめられる方法だ。
全体図や起こりうるケースを書き出す
意識の外にある考慮漏れを炙り出す方法だ。
起こりうるケースを全て書き出したり、全体図を書いたりして、空白地帯がないかを確かめてゆく。
私の経験上、節目節目でやっておかないと大体痛い目にあう。
雑談混じりの会話
雑談チックに仕事で抱える課題をゆるく共有する。ミーティングのような改まった場では得られないアイディアを得られることがある。
他人に働きかけをして疑問を発見させなくてはいけない時
最後に、他人に働きかけをして、この仮説と検証を行わせるケースについて考察してみよう。
私が現在試しているのは「壁打ち役になる」ということだ。
例えば、とある業務を外注(業務委託)しようとしている後輩がいたとする。
私「そもそもだけど、業務委託にあたって必要な要素って何だろう?」
後輩「え?・・・業務範囲を示すことでしょうか?」
私「そうだね。業務仕様書の提示は必要だ。他には?」
後輩「・・・お金ですかね」
私「そうだね。今回はお金周りは〇〇さんが既に手配してくれてるからそこなら任せておけばいい。他には?」
後輩「・・・すいません、思いつきません」
私「あとは契約書を結ぶ必要があるね。ところで、契約書を結ぶ時に気をつけなくちゃいけないことには何があるだろう?」
後輩「うちの会社が不利な条件を呑まされないようにすることです」
私「その通り。そのためには『会社として絶対譲れないライン』を抑えておかないといけない。でも、私も君も契約書を作った経験はない筈だ。では、どうしたらいい?」
後輩「契約管理担当に質問します」私「具体的にはどこの部署?」
後輩「総務部」
私「そうだね。他には?」
後輩「うーん」私「契約書は法律文書だから・・・」
後輩「あっ、法務部か」
私「その通り。ただ、契約書のあらゆる質問を受け付けていたら法務部も総務部もパンクする。
なので質問すべきときと自分達で判断してよい場合をルール化してる筈だ。ここにマニュアルが載ってるから参照してみて」
後輩「ありがとうございます。読んでみます」
私「まとめると、委託にあたって必要なのは、仕様書、お金、契約書だね。そのうち、今回我々が決めなきゃいけないのは業務仕様書と契約書だ。この2つを推し進めるように動いてみて」
こちらから問いかけをして考える時間を与え、出した結論に対して私の考えをぶつける。仮説と検証のサイクルを意図的に作り出して、後輩に考える癖を植え付けてゆこう、という作戦である。
まだ始めたばかりなので上手くいくか分からないが、地道にやってゆこうと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
