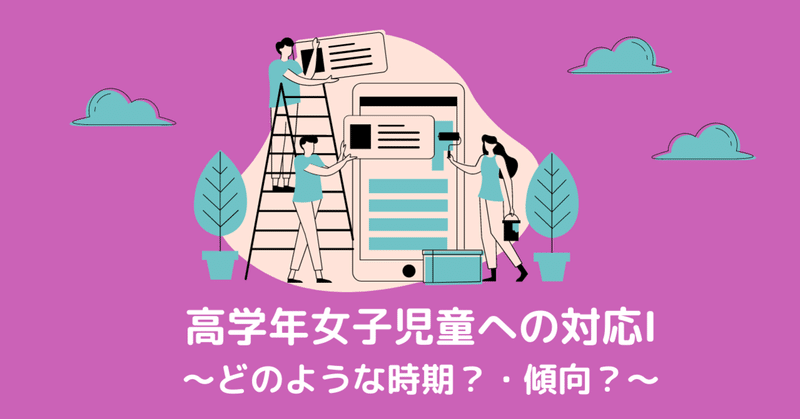
高学年女子児童への対応Ⅰ ~高学年ってどのような時期なの?・どのような傾向があるの?~
「女子児童への対応が難しい。どうすれば、よりよい関係をつくることができるか。どのように指導したらよいか。」という悩みをもつ高学年担任は意外に多い。経験則でしかないが、特に男性の先生に多いようである。
私も学級担任時、同じような悩みをもっていたことがある。 教職経験3年目になり、「学級経営も授業もある程度できる」と勘違いしていた時期である。
叱れば叱るほど、ぶつかればぶつかるほど、正論で攻めれば攻めるほど、女子児童グルーブと関係が悪化していく。そして、それが日常化していき、その関係は修復されることもなく、三学期の終業式を迎えることになってしまった。今となっては、苦い思い出であると同時に、子どもたちに申し訳ないという思いが強い。
高学年女子児童に限らず、高学年の子どもたちは、思春期に入ると同時に、大人の言動の一貫性・整合性、また、「何」を言うかより「誰」が言うか、「どのように言うか」ということに目が向くようになる。特に高学年女子児童においては、グループに居場所を求める傾向があると考える。
以上のことは、私の経験則である。
赤坂真二氏は、次のように言われる。
小学校高学年女子児童がとのよりよい関係づくりが難しい要因は、彼女たちが形成する私的グループの存在を挙げている。グループの1人を叱るなどして関係が悪くなると、グループ全員との関係が悪くなる。男子児童にとってグループとは、共通の取組をするための手段であるが、女子にとっては居場所そのものである。
男子は、暴力等「オモテの攻撃」が多いのに対して、女子はどちらかというと「無視」「手紙回し」「陰口」「ネットいじめ」など「ウラの攻撃」が横行しがちであり、今日問題とにっている「自己肯定感の低下」「個人攻撃しやすい密室性のあるメディア」「他者への共感性の未発達」がその傾向を増幅させている。赤坂真二氏は、高学年女子児童の傾向をアドラー心理学の視点から「(居場所への)承認欲求」の表れととらえている。
私の経験則と一致するところが多々ある。
今は「性で分けない」指導が言われているが、赤坂氏が分析されている「高学年女子児童」のおおよその傾向をつかんでおくことは必要になるだろう。
以上の実態や傾向を把握したうえで、対応を考えていくことが大切である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
