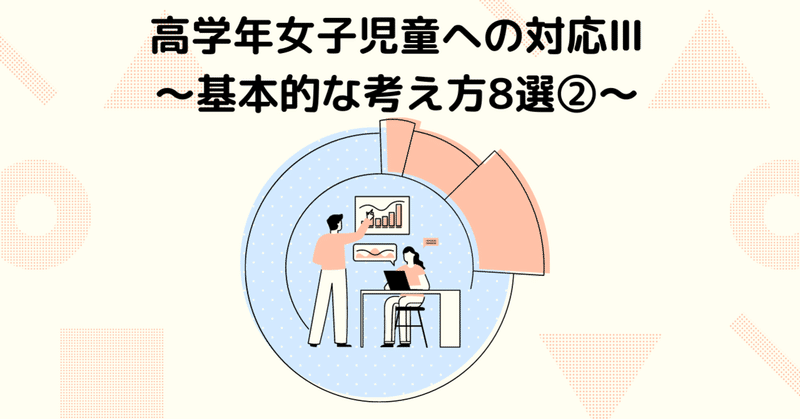
高学年女子児童への対応Ⅲ ~基本的な考え方8選➁~
④よさを認め、労をねぎらっているか その子どものよさや、がんばったことをしっかり認めたり、教師が依頼して行ってくれたことなどに対して「ねぎらいの言葉」をかけたりしているかということである。 「ねぎらいの言葉」と言っても特別なものではない。 「ありがとう。」「先生は、とても助かったよ。」「先生は、うれしかった。」「〇〇さんのこの行動は、先生はなかなか真似できないなあ」などの短いIメッセージでも充分である。 子どもとのよりよい人間関係を築いている先生方は、子どもへ言葉かけ等の優先順位がとても高い傾向がある。
➄建前だけを押し付けていないか 教師という職業上、建前を話さなければならないことは多いだろう。 しかし、思春期の子どもたちは、建前だけでは生きていけない、うまくいかないことも十分に承知している。 例えば「学級全員、みんなが仲良くすることがいい」というのは、建前でああろう。しかし、実際は簡単にできるものではない。 「みんな仲良く」ということばかり前面に押し出すと、息苦しくなる子どもたちもいるのである。 「仲良くできない、気の合わない友達もいるかもしれないけど、みんなが安心した学校生活を送るために、それぞれを理解しながら付き合っていくことが大切だよね。そのためには、どうしたらいいと思う?」などと子どもたちに投げかけることも必要になってくる。
⑥一人前の大人として扱う 過度に子ども扱いしないということである。 高学年は、一人の人間として丁寧に扱われたいという承認欲求が高くなってくる時期である。 「Aさんは委員会活動で忙しいと分かっているけど、〇〇を頼んでいい?」などと、相手の状況を踏まえて頼み事をする。 たまには「教師から相談」するものよい。 「先生の両親が喜ぶようなプレゼントを探しているのだけど、〇〇さん、何をあげたらいいと思う?」と他愛もない会話の中でちょっとした相談をしてみるのである。あまり学級に関することではない相談がいい。 子どもでも頼られるとうれしいので、様々なアイディアを出してくれる。相談事を解決することが目的ではなく、その子どもとコミニケションを取ることが目的である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
