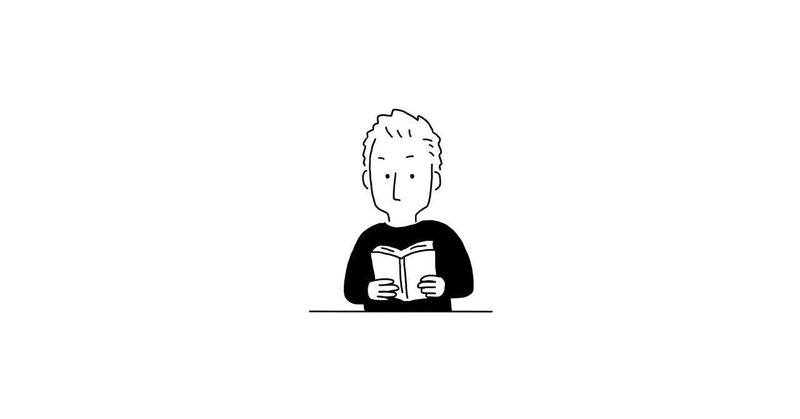
密度をあげる、もっと、もっとだ
週末、中央図書館に赴いた。先週の講座で、「新人賞にはどれくらいの長さのものが好まれるのか」という話題になったからで、先生は「たとえばすばるは、それで本を出すと決めているから、長い作品でないと受賞しにくいというのはある」と仰っていた。参加者の一人が、「皆さん、仕上がってから文字数の合いそうな賞に出す、なんて感じだろうけど」と言っていた。
私は賞に出す時、各賞の受賞作の傾向をしっかり調べた上で、自分ならこの賞だなと決めていたから、そんな適当なと軽く反発を覚えながら、そういえば文學界新人賞についてはちゃんと調べていなかったと思い当たった。うまくまとめるには難しい絶妙な指定字数という評判があるし、手持ちの作品の到達しそうな分量とは合わないので候補から外していたのだ。中央図書館は昭和以前からのバックナンバーが揃っているので、過去数年の受賞作を調べてみようという気になったのだった。
しかし、毎回二千通以上の応募を勝ち抜いて賞を獲得した彼らのうち、「ああ名前を聞いたことあるな」という人の少ないこと。私がもっと文芸誌を読んでいたらそう思わないのだろうか。あるいは、文學界新人賞が最近振るわないというだけのことなのだろうか。文學界新人賞が夏冬の二期から一期に変わったのが案外最近で、出版業界の受ける吹雪の加速度を思った。いずれにせよ、新人賞を獲ることは通過であって、その先、ずっと緻密で濃密ながらも、緩急をつけたあり方でいないといけない世界なのだと思う。
一年前の選評を読んで、キーワードをメモする。作品を読む時間がなかったので選評を先に読んだのだけれど、本当はこういう読み方は良くない。選者の言葉を思い出してしまって、したり顔の読み方しかできないから。結局借りて帰ってきたから、読むのを我慢すれば良かった。でも選評は面白い。落選した作品がどういう言われ方をしているのかを知るのは、まだ絶対に癒えていない瘡蓋を無理やり外すような行為だけれど。私はマゾなのか。
その中に、「エッセイで求められる濃さと小説の濃さは違う」というような表現があった。その通りだと思う。
このところ、私の脳がまるで緻密ではない。こんなに緻密でなくて、どうしていいものが書けるのだろうかと思う。力を抜くのは削ればいいのだから幾らでもできる。滑らかな文章であるべきだが、読みやすい文章ではいけないと思う。読者に、卑屈に寄り添わない。
他方、noteをふらふら飛んでいて読んだ文章に、「普通の人の日常なんて詰まらないものである」「詰まらないものでも面白いと思うものがもしあるとするなら、それはその人の文章が上手いからだ」という言葉があった。どきっとした。
noteで、薄い文章を上手く書けるようになる。それはそれで一つの成果ではあるけれど、私はそれを誇りに思えるだろうか。noteで創作を出す心理的抵抗はかなりあるが、緻密に考えて、それを苦もなくできるようにしたい。全集中の呼吸である。
という訳で、エッセイを創作の密度で書くという試みをしてみたいと思う。密度を上げるので、毎日投稿は無理だろう。それでもさすがに週一回はアップできるだろうから、連続X週投稿は果たせるだろう。狙うなら、毎日投稿のバッジより、ニッチな分野で何かを突き詰めるようなやり方だ。
本当はこういうのを宣言しないでぬるっと始めたいのだけれど、文學界新人賞の話も書きたかったのでこのまま投稿する。試みがうまくいくといいなあ。
サポートいただけたら飛んで喜びます。本を買ったり講習に参加したりするのに使わせて頂きます。
