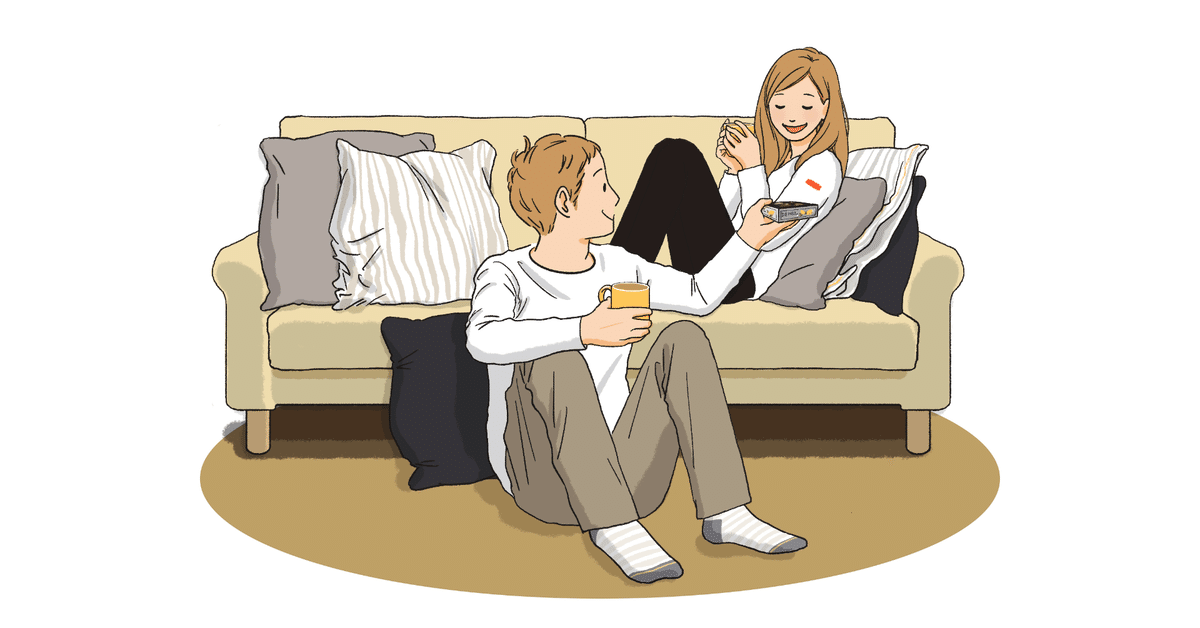
小説 自転と公転の同期
待ち合わせ場所として指定された表参道のカフェに着くと、広い店内の一番奥、窓際の明るいソファ席に座っていた妻が軽く手をあげた。離婚が成立して数年経つが、彼女に顔を合わせる瞬間はいつも、元妻、でなく、妻、と思ってしまう。私の表情に気付いて、妻が少しばつの悪そうな顔をした。
「悠太、近くにはいるんだけど……せっかく表参道に来たんだし、ちょっと店に寄りたいって。生意気に、『父さんに会っても何かもらえるわけじゃないし』なんて言うのよ」
「ははっ、言うねえ。まあ、もう親と遊園地って年でもないしな」
自分もそういう時期があったから、さほど不快感はなかった。もし子供が娘であったなら、もう少し違っただろうか。私は彼があどけなかった頃さえ、息子を愛せていたとは思えなかった。原因は息子にはなく、私達のひどい結婚生活、そして私自身の業というべきものにあったが、理由が分かっていたからといって、ごく一般の親のように愛情を与えられるわけではなかった。
正式に籍を分けてからも定期的に面会を続けていたが、元妻とは子供を引き渡す行き帰りに少し顔を合わせるくらいで、こんな風に同じテーブルで相対するのは久し振りだった。
「……元気?」
「まあ、なんとか」
「ちゃんとしたもの食べてる?」と彼女は言ってから、「ごめん、私のこういう心配が、あなたには負担だったんだもんね」と軽く顔を俯けた。
「まあ男の一人暮らしだから、大したものは食べてないよね。中年太り防止に走ってはいるけど」
店員がオーダーを取りに来たのでコーヒーを頼むと、元妻が怪訝な顔をした。
「コーヒーは酔うから飲まないんじゃなかったっけ」
世間一般から見て多分美しい部類に入る、彼女の整った眉がきゅっと寄せられる。シャドウを塗ったまぶたにもしわが寄ったのは、彼女も私と同じだけ年を取った証だった。
「ああ……えーと、そんなに長居しないだろうと思って、適当に頼んじゃっただけで」
彼女は眉根の緊張をすぐに解いたが、私は軽い息苦しさを感じていた。この顔。私をこわばらせ、そのこわばりが彼女をますます苛立たせた、顔。
「そんな顔しないで。ただ、飲めるようになったんだと思っただけだから」
会話の途切れた私たちのテーブルに、隣の席からスマホのシャッター音が届く。パンケーキを切るカチャカチャというナイフやフォークの音も、そこここから聞こえてくる。私は気まずい沈黙を破る、悠太からの連絡がはやく来ないかそわそわしはじめたが、彼女の方はというと、正面に向き直り、何かを眩しがっているような、あるいは多くを諦めたかのような、弱い微笑みをたたえて私を見ていた。
「これは、今日言うべきか迷ったんだけど……でも悠太はこれからもきっとこんな調子だと思うし、今後二人で話すこともあまりないだろうから、言うね」
「何?」
「私のドイツ赴任が決まったの」
「ああ……おめでとう」
「それと、秋に再婚することになった」
「そっ……か。いやおめでとう。え、ドイツへはその人と一緒に?」
元妻への未練などさらさらないくせに、喉のあたりが締め付けられたようになった。驚いたせいで、普段なら詮索だと思って遠慮するような言葉が、私の口をついて出た。
「うーん。どうするかはまだ決めてないんだ。私の赴任が決まってから、色々あってそういうことになったから。向こうにも仕事があるしね。まあ、次失敗したらバツ三になっちゃうし、とも思ったんだけど」
その時、彼女のスマホが震えた。
「うん。用は終わった? そうそう、そのカフェにいるから」
少し声をひそめ、顔を横にそむけて悠太と会話する元妻を、私は見るともなく見た。今は軽くパーマをかけているらしい、つややかな黒髪が縁取っている横顔は、私の妻だった人の顔でも、上場企業の事業部長の顔でもなく、窓からの光を受けてふんわりと柔らかかった。はじめて会ったときですら、こんなに心惹かれる表情はしていなかった気がする。
もしかしたら、息子がもっとずっと幼かった頃、彼女は息子にはこんな顔を向けていたのかもしれない。私も注意さえしていれば、こういう顔を見ることが出来たのかもしれない。私が選択的に見ていたのは、眉間にしわが寄った、あるいは、本来は形の良い唇が斜め左に歪んだ、顔だったけれど。
私の頭にふと、月と地球の関係が思い浮かんだ。月は重力の関係で、いつも同じ面を地球に向けて回っている。今は月だけがそのような状態だが、地球の自転も段々遅くなっていて、遠い将来、地球も月に対していつも同じ面を向けて回るようになるという。距離が近いほど、また両者の質量差が少ないほど、そうなるのではなかったか。
私達は徹底的に合わなかったと思っていたが、逆だったのではないだろうか。彼女が後ろ側に秘めている私の知らない顔を、彼女が出せるだけの余白がもしあったら、どうだったんだろうか。あるいは、私が少しでも、全てのことを深刻に捉えないでいたら……。
いや、私達は三人暮らしには広すぎるあの部屋で、お互いの重力に絡めとられていて、そんな余裕はなかった。それに、もうたらればを言うような時期はとっくにすぎている。
しかし私は、自分も近いうちに再婚するかもしれないことを彼女には言えなかった。別居している間に交際していた女性とは、結局うまくいかなかった。だから後ろめたさを感じる必要はないし、実際感じてもいなかったが、二人がほぼ同時に再婚することになりそうなのは、あの重力のなせる業のように思って、それに半分納得しながらも、ぜひ抗いたいような気持ちになったのだった。
「再婚しても、養育費は払うからね」
「ああ、そんなこと……そういうつもりで話したわけじゃないから」
「うん、でもそうしたいんだ」
「……ありがとう」
これから私と彼女達の軌道はどんどん調和を乱し、そのうち、お互いどんな顔をしていたかさえ分からなくなってしまうだろう。養育費の送金の細い線は、おそらく重力の代わりにはならない。でも何年か後に再会したら、お互いこれまで見ることがなかった、新しい二つの顔で笑えるかもしれない、という甘っちょろいことを思う。
カフェの扉が開く音がして、歩幅の広い足音が近付いて来た。正面の彼女の顔はもう、ほころびの無い美しさを取り戻している。
〈了〉
サポートいただけたら飛んで喜びます。本を買ったり講習に参加したりするのに使わせて頂きます。
