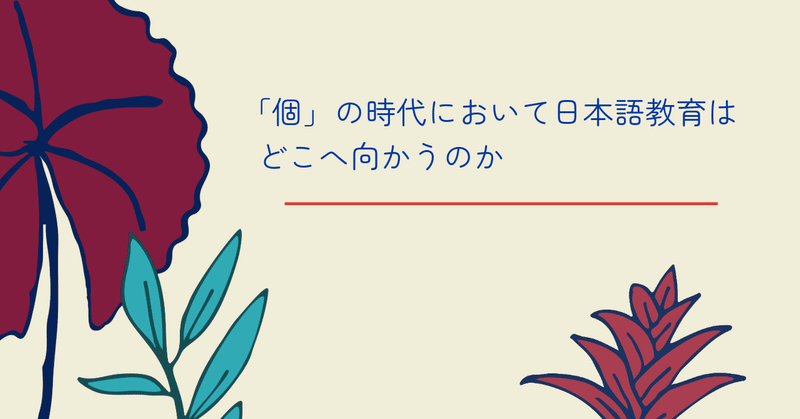
「個」の時代において日本語教育はどこへ向かうのか
今回は、未来に向けて日本語教育はどこを目指せばいいのかについて書いてみたいと思います。
未来について考えるきっかけになったのは、木下斉さんの以下のnoteです。
このnoteでは、「組織」から「個」の時代へとシフトが起こっており、それを踏まえて私たちが今やるべきことについて書かれています。
私自身、組織で働くことに限界を感じ、2020年に個人開業しています。これまで組織でやってきたことを、事業としてどう成立させるかをひたすら試しているような状態ですので、内容に深く共感しました。
一方で、私が関わっている「技能実習生」や「特定技能」に対する日本語教育は、組織に属する人を育成し、供給しているような状況で、何か自己矛盾も感じます。「日本語教育」という側面から、何か突破口を作れないかと試行錯誤しているのですが、なかなか思うようにいきません。
上記のnoteでは、3冊の本が紹介されています。どれも20年から10年前に書かれたもので、その時点から未来を予想しています。3冊とも読んでみましたが、今読んでも、全く古さを感じません。むしろ、予想されたとおりのパラダイムシフトが起こり、現実のものになっているのではないかと思いました。
奇しくも、これらの本では、未来の教育についても深く洞察されています。そこで、今回は、これらの著書をもとに、未来の教育、特に日本語教育はどこを目指すのかについて考えてみたいと思います。
産業革命後の教育
まず、岡田斗司夫さんの『評価経済社会』です。
この本では、アルビン・トフラーの『第三の波』(1980)を引用しつつ、現在、起こっている第三のパラダイムシフト、「モノ不足・情報余り」の状態がもたらす社会の変化を分析しています。
同著では、これまでに起こった「農業革命」と「産業革命」により、社会における価値観が大きく変化したことについても考察されていますが、「産業革命」後の教育について、トフラーの興味深い指摘が引用されていました。
工場での労働を想定して、公共教育は基礎的な読み書き算数と歴史を少しずつ教えた。だがこれは、いわば『表のカリキュラム』である。その裏には、はるかに大切な裏のカリキュラムが隠されている。
その内容は三つ。今でも産業主導の国では守られている。
時間を守ること
命令に従順なこと
反復作業を嫌がらないこと
この三つが、流れ作業を前提とした工場労働者に求められている資質だ。
「裏カリキュラム」として挙げられた三つ。おそらく学校教育の中で、私たちも体験しているのではないでしょうか。私は、命令の意図がすんなり理解できない上に、集中力がないため反復作業が続かず、さらに時間通りに行動できない子どもでした。存在自体がトラブルメーカーだったのは、言うまでもありません。
今更ながら、このような「裏カリキュラム」のもとでは、上手くいかなかったのは当然だと思うわけです。
翻って、現在の日本語教育についても考えてみます。
日本語学校では、働くために必要な基礎的な読み書きである「日本語」を教えています。テキストに示された「正しい日本語」を覚えるために、何回も反復練習をし、指示通りのやりとりができるように練習する。さらに、法務省の告示にしたがって、授業開始時には、出欠を確認し、厳しく在籍管理をするということをしています。
まさに、「産業革命」後に必要とされた労働者を愚直に育成していることになります。トフラーのようなシンプルな言葉で説明されると、私自身もやってきた日本語教育とイメージが重なり、ハッとします。
「フリーエージェント社会」における教育
次に、ダニエル・ピンクの『フリーエージェント社会の到来』から教育について考えてみます。
同著では「フリーエージェント」を以下のように定義しています。
インターネットを使って、自宅でひとりで働き、組織の庇護を受けることなく自分の知恵だけを頼りに、独立していると同時に社会とつながっているビジネスを築き上げた人々のこと
日本では、ようやく複業が一般化しつつあり、組織に縛られない「フリーエージェント」的な働き方が増えていますが、この本の原著は2001年に書かれているのが驚きです。
そして、同著の第15章は、まるまる教育について書かれています。
ここでは、アメリカの義務教育を「均質化装置」であるとし、組織で働く人を養成するのに理想的なシステムだったと指摘します。そして、フリーエージェントと同じような「在宅教育」の可能性についても書かれています。
さらには、フリーエージェント社会においては、「脱学校化」が進み、生涯において学ぶ必要があること、ティーンエージャー起業家の増加、学歴の価値の低下、勉強のためのイベントやグループの増加などなど、興味深い指摘がされています。
「教育」のあり方一つとってみても、確実に「フリーエージェント社会」へと、価値観が変化していることが実感できます。
このように大きく変化しようとしている社会において、日本語教育業界に起こっている流れを振り返ってみます。
以下のnoteにも書いていますが、
2024年4月1日から「日本語教育機関認定法」が施行され、日本語教師が「認定日本語教育機関」で働くためには、「登録日本語教員」として、文科省に登録することが義務付けられます。つまり、「登録日本語教員」と「認定日本語教育機関」が、紐づけられることになります。
これから訪れる「フリーエージェント社会」に、逆行しているような気がしてなりません。
これからの日本語教育のあり方
政府の教育未来創造会議では、2033年までに外国人留学生を40万人受け入れるという方針が示されました。
未来を創造する若者の留学促進イニシアティブ(第二次提言)概要
(2023年4月27日)
ここで受け入れようとしている外国人留学生は、大学等卒業後「高度人材」として日本の産業を支えるべき人材となっていきます。
このような留学生の最初の受け入れ機関である「日本語教育機関」が、「産業革命後」に構築された均質的な教育であっていいはずがありません。
2024年4月1日に施行される「日本語教育機関認定法」では、新たに、文科省の基準に沿った「教育課程」を編成する必要があります。このとき、本当に、これからの社会で活躍できる人材を育成できるようなプログラムになっているのか、しっかり考える必要があると思っています。私たち日本語教師の仕事は、ただ「日本語を教える」だけではないと思うのです。
日本語教育というと、どう教えるか、どんなテキストを使うかばかりに議論が集中しますが、ときには、一歩引いて社会全体や未来の社会を俯瞰する必要があると思っています。
もう2年前になりますが、以下のnoteを書きました。
私はやはり、それぞれが持つ思考や可能性を束縛するものから解放できるような「ことばの教育」をしていきたいと思っています。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました!
共感していただけてうれしいです。未来の言語教育のために、何ができるかを考え、行動していきたいと思います。ありがとうございます!
