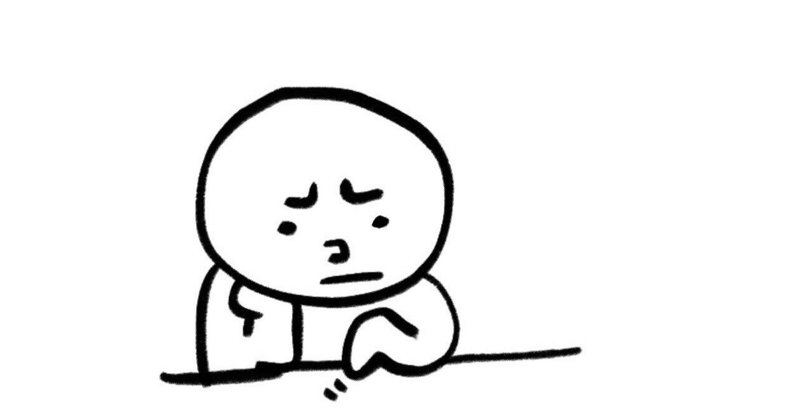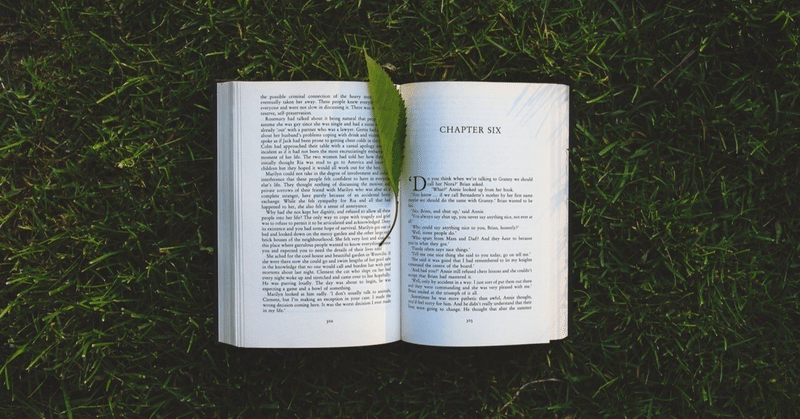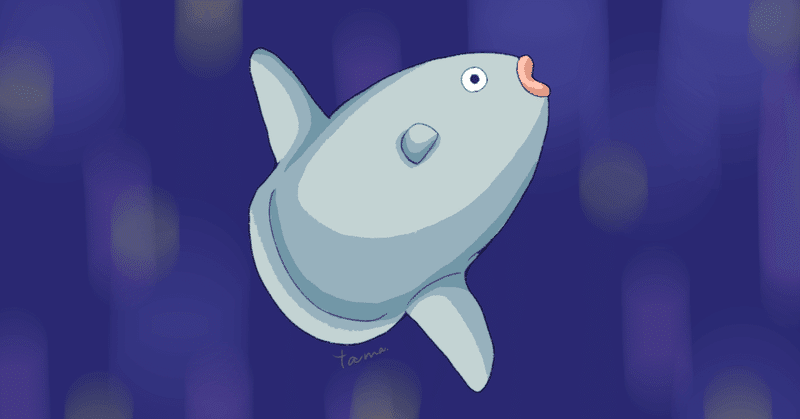#読書感想

「問い」の奥深さを感じる1冊。【読書記録#21】【『問いのデザイン 創造的対話のファシリテーション』安斎勇樹・塩瀬隆之】
皆さんは「ファシリテーション」という言葉をご存じだろうか? 個人的にはあまり聞き馴染みのない言葉かなと。 「ファシリテーション(facilitation)」は「促進する」「容易にする」といった意味を持つ英語「ファシリテート(facilitate)」を名詞化したもの。 主に企業や学校、地域などでの問題解決を容易にするための働きかけといった文脈となる。 問題解決の場として会議形式だけでなく、ワークショップという体験型の知識創造の場を設ける場合がちらほら出てきている。筆者も10年