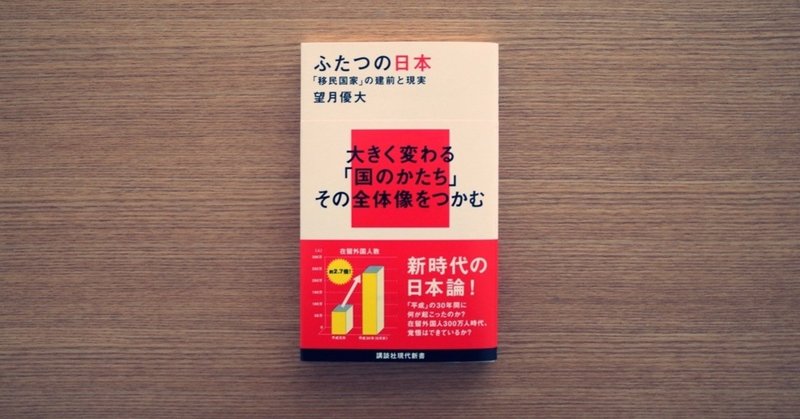
本を読んで「わたしたちを広げていこう」と考えた(2019年4月)
「ふたつの日本」(望月優大さん)は、日本で「いないことにされている」移民を真正面から取り上げてくれました。副題の通り、日本は「移民国家」なのだけれども、「建前」で移民はいないと言っている。統計を分析すれば、既に移民となった外国にルーツを持つ方が多数いることが「現実」だと分かる。
「いないことにする」にはどうしたらいいか。それは「言葉を剥奪する」ことだと、望月さんは明らかにしている。政府は移民ではなく「外国人材」と呼ぶ。それは、外国から来た方を「単身で、健康で、いつか帰る外国人労働者」に単純化する、「漂白」する試みで、悔しいかな、成功している。でも望月さんは「移民の否認は人間の否認だ」と叫ぶ。叫ぶことをやめない。移民も「わたしたち」であると。
「移民」 を否認する国は、「人間」を否認する国である。人間を否認する国とは、社会の中でしか生きられない私たちから社会的な支えを剥奪する国である。社会統合の対象は外国人だけではない。この国に生きるすべての人々が対象だ。
今、目の前にふたつの道があるーー。撤退ではなく関与の方へ、周縁化ではなく包摂の方へ、そして排除ではなく連帯の方へ。これは「彼ら」の話ではない。これは「私たち」の問題である。(p217)
ナオミ・オルダーマンさんの「パワー」は、「わたしたち」の問題を違った、ユニークな形で問うてくれる。パワーの世界ではある日、女性だけが手のひらから高圧電流を放てるようになる。男性が女性を抑圧する世界が逆転する。
示唆的なのが、逆転した世界でも抑圧がなくならなかったことだ。それは男性の女性に対する抑圧ではない。パワーを獲得した女性から弱い男性への「新たなる抑圧」だった。新しい世界でトゥンデという登場人物が語る。
路上で女たちの集団ーー笑ったり冗談を言ったり、空に向かってアークを飛ばしたりしているーーのそばを歩いたとき、トゥンデは胸のうちでこうつぶやいた。ぼくはここにいない、ぼくは何者でもない、だから目を留めないでくれ、ぼくを見ないでくれ、こっちを見てもなんにも見るものはないから。
女たちはまずルーマニア語で、それから英語で声をかけてきた。彼は歩道の敷石を見つめて歩いた。背中に女たちが言葉を投げつけてくる。淫らで差別的な言葉。だが、彼はそのまま歩きつづけた。
日記にこう書いた。「今日初めて、路上でこわいと思った」インクが乾いたとき、その文字を指でなぞった。真実は、その場にいない者のほうが耐えやすい。(p331)
パワーを読むと、フェミニズムは「女性による問題提起」ではないと感じるようになる。それは男性が保有する「パワー」への抗議であって、男性にとっても、自己に内在する権力性や暴力性を点検する必要性を浮き彫りにする。フェミニズムはきっと「わたしたち」の問題だ。フェミニズムを否定する世界は、抑圧を肯定する世界であって、それは男性の自分にとっても生きづらい。
「わたしたち」を拡張し、問題に立ち向かっていくためのツールはたくさんある。「幸せな選択、不幸な選択」(ポール・ドーランさん)は、そのうち行動経済学とポジティブ心理学の方法論を示す。「生き残る判断、生き残れない行動」(アマンダ・リプリーさん)は、「動物的本能は今日的災害において不利に働くけれど、人間は新たなる本能をインストールして危機を回避できる」ということを教えてくれる。
わたしたちは広げていける。問題は一つ一つクリアにしていける。本が授けてくれるのはいろんな形の希望だと感じます。
万が一いただけたサポートは、本や本屋さんの収益に回るように活用したいと思います。
