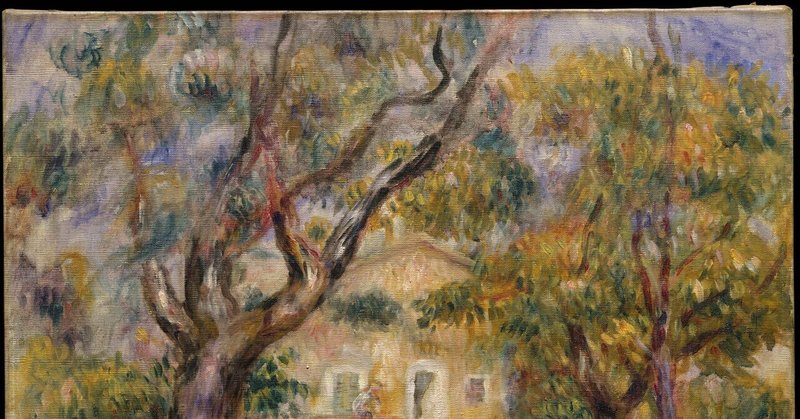
見えなくなった歴史を見るーミニ読書感想「日本人はなぜキツネにだまされなくなったのか」(内山節さん)
哲学者内山節さんの「日本人はなぜキツネにだまされなくなったのか」(講談社現代新書)が面白かった。秀逸なタイトルの通り。小さな村で暮らし、他の小さな村を訪ね歩く著者は、1965年を境に日本人はキツネにだまされなくなったとの仮説に行き着く。1965年に何があったのか?誰も語らず、見ることのない歴史に目を凝らす良作。
山の上、水神、田の神、……、村の世界はさまざまな神々の世界であり、それとどこかが結びつくさまざまな生命の世界であった。自分の生きている世界には、「次元の裂け目」のようなものがところどころにあって、その「裂け目」の先には異次元の世界がひろごっていると考える人々も多かった。(中略)
可視的な、不可視的なさまざまな生命の存在する世界、それがかつて村人が感じていた村の世界である。とすれば、天狗やカラス天狗といった生命が山の世界のなかに感じとられていたとしても、それはそのまま受け取っておけばよい、現在の私たちの世界では架空の生き物であったとしても、その頃の村の人たちの生命世界のなかでは感じとられていたものなのである。
著者は実際に現代を生きる村人との会話の中から、「経済の発展」「科学の発展」など、さまざまな近代化の波が1965年前後に押し寄せてきたのだと解説する。そうして人々は、「キツネにだまされる」体験や、その体験を得るための感覚を失った。
とりわけ自分は、引用した「裂け目」に関する記述が胸に響いた。経済が肥大化する中で、暮らしの中の神や怪異を感じ取れなくなった。世界は合理的になり、裂け目のない完全な空間になってしまったことを思い知らされた。
自分の周りを見渡してみても、自然的なもの、霊的なものとつながれる空間はとても限定的だ。たとえば、近所の神社の鳥居や境内くらいか。その空間も、温情といっていいくらい機械的な都市の中にぽつんと残されている程度。この暮らしの中で、新しい怪談や、伝承が生まれるとはとても思えない。
かつて人々は、裂け目を見ることができていた。こちらから裂け目へ、裂け目からこちらへ。出入りする「何か」もはっきり感じ取れていた。世界が複層的だったのだ。
本書は、人間の生き方が現代のような経済一色の単一的なもの「だけではない」ことを教えてくれる。もちろん、そんなことを知っても資本主義から抜け出せるわけではない。今日の日銭がなければ明日の生活もままならない。しかし、知っていることだけでも呼吸を楽にしてくれる。
1965年にキツネにだまされなくなったと、学校の歴史で習うことは少ないだろう。グローバルヒストリーの中では、あまりに小さな一コマだ。だけれど、この問いの立て方は近代化の代償の本質に迫っている。実に秀逸な問いの立て方を学べる本でもある。
つながる本
歴史は問いの立て方によって見え方が変わる、ということを深く学ぶには岩波新書の「シリーズ歴史総合を学ぶ」がおススメです。一作目「世界史の考え方」、二作目の「歴史像を伝える」、どちらも平易な書き方で歴史の複層的な見方を伝えてくれています。
それぞれ感想はこちらです。
自然とのつながり方、つながる豊かさについてもっと考えてみたい方には、ジェイムズ・リーバンクスさんの「羊飼いの暮らし」(ハヤカワ文庫)を。英国で大学を出た後に伝統的な羊飼いの仕事を引き継いだ方のエッセイです。
万が一いただけたサポートは、本や本屋さんの収益に回るように活用したいと思います。
