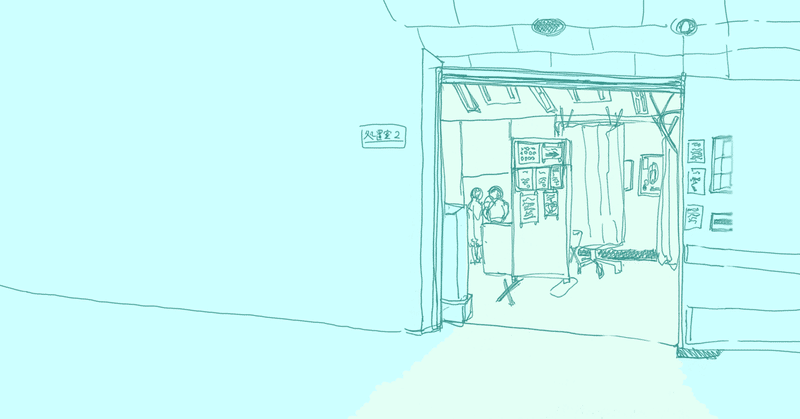
ノンフィクション作家が「無名」の父を描き切るーミニ読書感想「無名」(沢木耕太郎さん)
沢木耕太郎さんの「無名」(幻冬舎文庫)が胸に沁みました。「敗れざる者たち」で非業のスポーツ選手、「テロルの決算」でテロリストの姿を描くなど、人物ノンフィクションの名作を残してきた沢木さん。本書では、世間的には名を知られていない父の最期を、正面から描き切っていました。
ポイントは、無名の父を「有名な存在として」描くことはしないこと。著者はそうした欺瞞には逃げません。無名であり、ある種、無名であることに徹した父の人生を、等身大のものとして見つめます。そこに美化したり、知られざる発見を無理やり求めたりする姿勢はない。
1990年代、その父の体調が崩れ、入院するところから話は始まります。看病のため、病院に泊まり込む時間が増えた著者。父と真正面から語り合う機会がなく、なんとなくは知っていた父の半生をようやく紐解けると期待します。
小説であれば、そこから父の激動の日々を振り返る展開になるわけですが、これはノンフィクション。当然ながら、体調の思わしくない父からそんなに都合良く話は聞けない。作品を作るために父に向き合っているわけでもなく、病床の父との会話は、もっと生活感のあるものとなります。
結局著者は、父とはどんな人間だったか、どんな人生を歩んだかを、そうした断片的な会話と、そこから連想される思い出の中から辿っていくことになる。まるで水たまりの周りをぐるぐる回るようなこの歩みが、なんだか胸に沁みたのです。
大切な存在を前にした時、私たちは、大切な話こそしにくい。そのもどかしさを、著者もまた抱き、そして「それでも書いた」ことに本書の価値を感じます。
大切な人と別れるとき、「あの時こうしていれば」「もっと語り合っていれば」と思い返す後悔。でももしかしたら、大切なことを単刀直入に話せないからこそ、その人との関係は大切なのかもしれない。そして、「他愛無いこと」を通じて、それこそをもって、大切な人に近付く方法があるのかもしれない。本書はそんな希望を抱かせてくれます。
本書は新刊ではありません。文庫版ですら2006年の刊行のようです。しかしある書店で、棚の一画に表紙を表にして推し出してくれていた(いわゆる面陳という掲示方法かと)。その書店の書店員さんもおそらく、この静謐な感動をより多くの読者につなぎたいと考えてくださったのでしょう。感謝したい。
家族の見取りに直面している方。あるいは、家族との距離感に悩まれている方。心がほんのりと温かくなると思います。
万が一いただけたサポートは、本や本屋さんの収益に回るように活用したいと思います。
