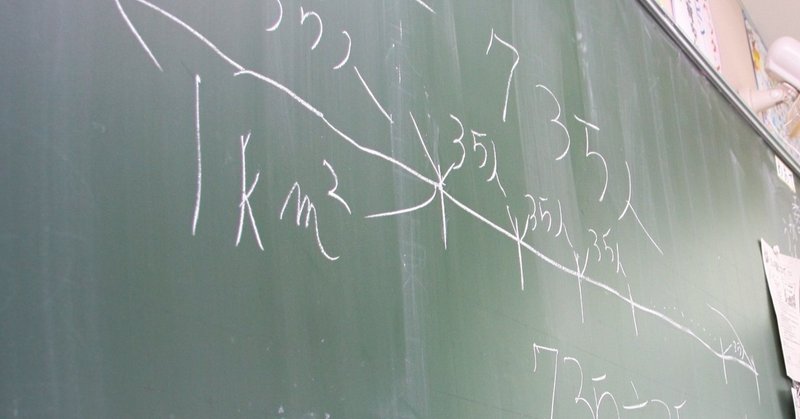
反学校文化の力ー読書感想#14「ハマータウンの野郎ども」
イギリスの「不良学生」が将来、肉体労働に従事するケースが多いのはなぜなのか?ーこの疑問を、自ら不良学生の輪に入り、人類学的手法で考察したポール・ウィリスさんの「ハマータウンの野郎ども」が知的好奇心をそそられました。本書で解き明かされるのは、不良が「反学校文化」と言えるカルチャーを構築し、それが「労働者文化」に接続していること。頭と心を両方使いながら、文化の中に入って考察していくウィリスさんの姿勢がとても勉強になります。
不良は文化である
ウィリスさんの指摘で一番爽やかさったのは、不良を文化として捉えたことです。不良は単に条件反射で反抗しているわけではない。学力が低いから反抗に走るのではない。そういう上から目線のステレオタイプを排していく。
不良文化とは、インフォーマルな文化である。そこではフォーマル=学校の要求を拒み、時には軽やかに身をかわす。不良たちは、授業の無視、教師のちゃかし、真面目な生徒の蔑視を通じて、インフォーマルな文化を楽しむ。
文化を構築するには、集団を作らなければいけない。だから徒党が組まれる。不良が学校という規律を否定しつつ、自らグループを構成することは、何ら矛盾していない。
ある生徒が〈野郎ども〉の一員であるということの要点は、彼が集団とともにあるということだ。たったひとりでなにがしかの文化をかたちづくることはできない。たったひとりで楽しみや独特の雰囲気や社会的なアイデンティティを生み出すことはできない。反学校に与するとは、集団に所属することであり、その文化を生きるとは、集団とともに行動することなのである。(p62-63)
不良をインフォーマルな文化を支持する集団と見ると、裏返しに真面目な生徒はフォーマルな文化を崇拝していると言える。ということは、「どっちつかず」の生徒も生まれてくる。
たとえば、中産階級の学校に通いつつ、不良に憧れている生徒だ。ウィリスさんは、この生徒がインフォーマルな文化に飛び込めば将来は「多難」になり、放棄してフォーマルな文化に順応すれば「有望」だと指摘して、こう語る。
社会的な階層移動の現実を知るためには、個人的資質としての「学力」なる観念を機械的に適用するよりも、文化的な帰属関係を、とくに異なる文化形態のあいだで揺れ動く帰属意識をとらえるほうが、はるかに有効なのである。(p149)
不良/優等生を、学力の有無という単純なファクターで見るのではなく、異なる文化間の綱引きと見る。この方が現象を動的に解釈できるし、「揺れ動き」も見えてくる。ウィリスさんの思考枠組みは、別の場面でも適用出来そうな気がします。
「洞察」と「防壁」
そしてウィリスさんは「反学校文化」が「労働者文化」に接続していると指摘します。この展開も刺激的だし、明晰です。
イギリスの労働者階級=頭脳労働よりも肉体労働に従事するワーカーの集団は、不良集団と驚くほど似ている。授業をサボりつつも卒業は果たす不良のように、労働者は出世にあくせくはしないものの、給料はちゃんともらうべく働く。仲間内でのふざけあいや、ルールの逸脱を楽しむ。
ウィリスさんはここに「洞察」を見出す。不良や労働者がある意味で真面目に働かないのは、学校=職場=権威の欺瞞を見抜いているからである。学校は勉強すればみんなが自己実現できるように語るけれど、実際は競争社会で落ちぶれた者への保証なんて何もない。あるいは、教師の権力は確保しつつ、生徒を抑圧する全体主義的な機構を備えている。だからこそ、フォーマル側の要求を鵜呑みにしない。
労働者の場合、ここで労働を「防壁化」している。
つまり、ここで意識されている「労働力」とは、社会の需要にこころの底から応じようとする労働ではなくて、社会の要請から自我を守る一種の防壁にほかならないのである。労働過程から全幅の満足を引き出そうとは、ここでは最初から考えられていない。満足を得る前提としての労働に対する自我の全的投入が、そもそも拒絶されるのである。自我の内奥は、あたかもおのれ自身の労働から隔離されて、より切実な意味を労働の周辺に求める方向に働く。(p251-252)
エリート層が労働と一体化し、自我を全投入する働き方をとることと一線を画す。労働者は自我と労働を隔離し、それによって労働の「周辺」=仲間との交流や遊びを楽しむ態勢を構築する。
防壁としての労働力の活用は、日本で働く上でもヒントになると思いました。いまやあらゆる労働がサービス化し、顧客への全投入を望まれてはいないか。その中で「生き延びる」ために、労働者的な、不良的な「かわし方」があってもいいんじゃないか。
「否認者」が階級社会を支える
ウィリスさんの視点はさらに展開する。そこで見出したのは、「階級社会を否認する人がいる労働者がいるからこそ、階級社会が存続する」というパラドキシカルな現象です。
ここまで述べたように、不良はインフォーマルな文化を支持する文化集団であり、その文化は労働者文化に接続する。言い換えれば、労働者は自らが従事する肉体労働とそれに付随する文化を「いやいや」ではなく「望んで」引き受けている。
労働者は、自らがエリートよりも劣っているとは考えていない。もちろん得られる所得や社会的地位は明らかに低いのだけれど、「人間の根本」として下位にあるとは思っていない。これが、鍵となる。
実は、下層階級の根幹部分は、能力の低下とともに社会的地位も低下するという能力主義の虚構を認めてはいないのである。そして、これこそが、資本制社会が安定を保つ、意想外な要因のひとつなのである。公認の能力主義に与するのではなくて、社会的地位を測る精神労働・肉体労働のものさしを逆転させてしまう人びとが存在するのだ。(中略)こうして、みずから劣位の部署を選びとる人びとがいるおかげで、他の人びとは、精神的労働を価値とする支配的イデオロギーのものさしを安んじて受け入れ、その程度はまちまちだとしても、比較的に優位の部署を獲得でき、それに応じた優越感にひたることもできる。(p347-348)
「能力が高ければ精神・頭脳労働に従事でき、社会的地位も高まる」という「ものさし」を否認する労働者がいるからこそ、ものさしが強固になる。もしも全員が同じものさしで考えれば、肉体労働に進んで従事する人がいなくなり、社会が崩壊するからだ。この考察は頷けるし、衝撃的なまでに皮肉です。
この構図は非常に悩ましい。見抜いてしまえば、誰もが労働者を脱したくなるかもしれないが、そうすると社会はもたない。そこまで考えると、この「制約」に安住する方が賢いかもしれないという「洞察」が首をもたげる。なんとも悩ましいものの、少なくともこの考え方を手に入れたことで、転がす度に思考が刺激される。
本書は「見ようとする人にしか見えない」というシンプルな事実を突きつけてくれる。これはきっと、イギリスにだけではなく自分の身の回りにもありそうです。(ちくま学芸文庫、1996年9月10日初版。熊沢誠さん、山田潤さん訳)
次におすすめの本は
ジャレド・ダイアモンドさん「昨日までの世界」(日経ビジネス人文庫)です。ウィリスさんの対象は不良でしたが、ダイアモンドさんは「昨日まであった社会」、部族文化に目を向けて、そこに「現代でも分のある」考え方を見つけ出します。未開と思いがちな文化に英知を見出す姿勢が、ウィリスさんと共通して刺激的です。
万が一いただけたサポートは、本や本屋さんの収益に回るように活用したいと思います。
