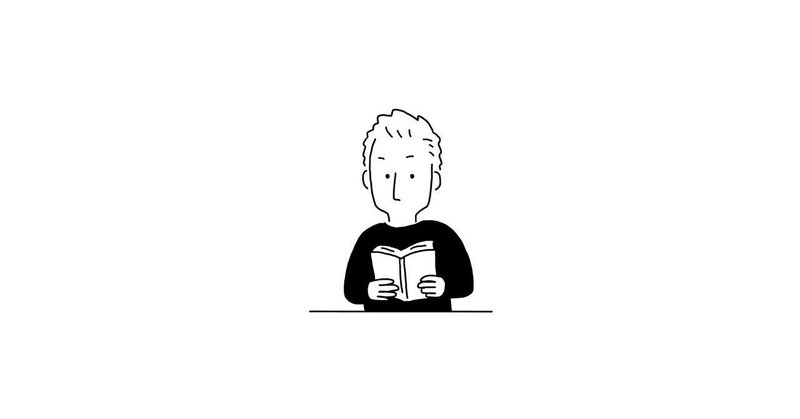
「勉強の哲学」を大学入学前の自分に読ませたい(本の感想4)
千葉雅也さんの「勉強の哲学」は素晴らしくて、過去に戻れるなら、大学入学前の自分に読ませたい。一番シビれたのは「勉強は中断するものである」ということ。中断し、再開し続けることこそ、勉強である。
中断と決断は違う
中断の反対は「決断」で、千葉さんは決断を危険とすらみなします。なぜなら、決断は「絶対的」な根拠を求めてしまうから。でも、勉強の広がりは「無限」であり、たどり着けない絶対的根拠の代わりに「無根拠」に陥ってしまうから。
絶対的根拠を求めると無根拠になる
このことを説明するには「ユーモア」と「アイロニー」という概念が要ります。ユーモアは「ボケ」、アイロニーは「ツッコミ」に相当する。
たとえば「Aさん、不倫してるって。嫌だね」という友達との会話がある。このとき、「恋って音楽みたいだね」と言い出したら、それはユーモアになる。ちんぷんかんぷんな発言でも、「たしかに音が合わないと不協和音だね」と話をつなげることも可能である。すると不倫の話はいつの間にか音楽の話に転換する。この「視点の変更」こそユーモアです。
対してアイロニーは「てか不倫って本当に悪いことか?」と言うこと。会話の前提である「不倫は悪」という共通認識にツッコミを入れる。ポイントは、アイロニーには終わりがない。このアイロニーに答えても、「そもそも悪って何よ?」と更なるアイロニーが可能である。アイロニーは「深追い」の怖さがある。
いつまでも終わらないアイロニー。アイロニーは前提を転覆させ、より強固な根拠を求めますが、そこには一向に到達しない。するとどこかで「ダメと言ったらダメなんだ」と思ってしまう。絶対的な根拠を追い求めた先に、無根拠による決断という皮肉な結果が待っている。
仮固定から仮固定へ
だから千葉さんは、アイロニーを「半端に止めておく」ことが大切だと言う。中断です。でも中断は、諦めることではない。ここで「仮固定」という言葉が出てきます。
ある結論を仮固定しても、比較を続けよ。つまり具体的には、日々、調べ物を続けなければならない。別の可能性につながる多くの情報を検討し、蓄積し続ける。
すなわちこれは、「勉強を継続すること」です。(p141)
仮固定し、比較し、更なる可能性を見つける。仮固定から仮固定へ移っていく。それが「無限」の海、「絶対的根拠」という島のない海を泳ぐ「勉強」である。この考えが、大学入学前には有効だと思うのです。
自分は大学に入った最初の講義で、「高校までの勉強は答えのある世界だったわけだが、これから君たちがやる学問は、答えのない世界だ」と言われました。これはたしかにそう。でも、「じゃあ答えのある世界から答えのない世界へ、どう橋渡ししていくの?」という課題が残ります。
この橋渡しこそ中断の思想、「仮固定から仮固定へ」という考え方じゃないかと思います。たしかに、大学で学ぶ「社会学」や「物理学」に答えはない。答えを見つけようとすると、アイロニーの罠にはまる。でも、仮固定はできる。高校の勉強で培ったように、学びを重ねて、「一応の回答」は出せる。そこを足場にできる。
実は「勉強の哲学」そのものが、千葉さんのたしかな思想、言葉がレゴのように積み重なって、ホップステップで進んでいける設計です。仮固定すること、アイロニーに加えてユーモアを働かせることを実体験できる。本書を読めば、感覚として中断の思想を学べると思います。(2020年3月10日初版、文春文庫)
次におすすめの本は
見田宗介さんの「現代社会の理論」です。これを読んだら大学の勉強に役立つんじゃないかなというつながり。見田さんの言葉に乗れば、高い視座に連れて行かれる。社会の構造が違った形で見えるようになると思います。新書で、ページ数も多くないので、読みやすいです。(1996年10月21日初版、岩波新書)
万が一いただけたサポートは、本や本屋さんの収益に回るように活用したいと思います。
