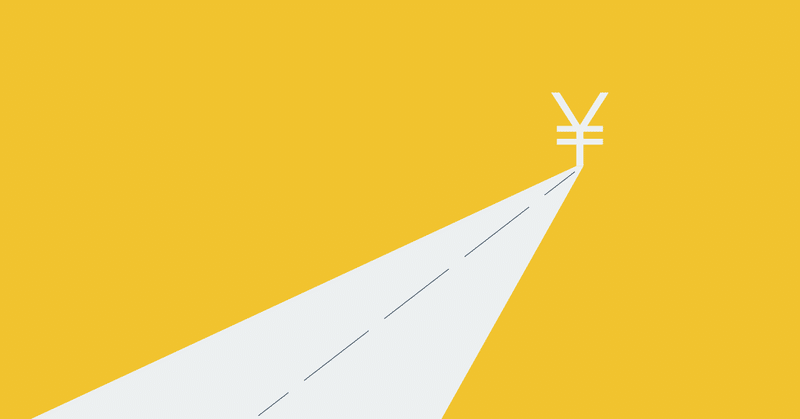
「それをお金で買いますか」は戒め
マイケル・サンデルさん著「それをお金で買いますか」には大事な戒めが書かれていました。それは「お金は腐らないが、お金が腐らせるものがある。それは道徳だ」ということ。「市場原理の腐食作用」を色んな例で学べます。
罰金を科すと遅刻が増えた
イスラエルの保育園のケースが分かりやすい(173pあたり)。保育園では遅刻した親から罰金を取ることにした。すると、遅刻が減るどころか、かえって増えてしまった。なぜか。
それまで後ろめたかった遅刻という行為が、罰金の導入によって後ろめたくなくなったからだとサンデルさんは言います。親にとって遅刻が「追加料金を払えば、定刻を過ぎても預かってくれるサービス」になったから。
同じイスラエルでこんな例もあるそう。イスラエルの高校生は毎年、「寄付の日」に住宅を訪問して回って寄付を集める。この時、「無報酬」「歩合1%の報酬」「歩合10%の報酬」の3つのグループに分けた。一番寄付を多く集めたのは、なんと「無報酬」組だった。「10%」組は「1%」組よりも集めたけれど、「無報酬」には敵わなかったそう。
いずれも、「遅刻してはいけない」「寄付を集めよう」という規範意識が、市場原理の導入によって損なわれたことを示している。お金が道徳を腐らせたわけです。
腐敗した道徳は戻らない
大切だと思ったのは「市場原理の導入で腐敗した道徳は、市場原理を除いても戻らない」ということ。遅刻に罰金を課した保育園では、罰金を無くしても増加した遅刻が減らなかったそうです。「後ろめたくない」経験をした後に、もう一度遅刻を「ダメなこと」と思うことは難しい。
何が「美徳」か考える
本書の教訓は「市場原理は道徳を損なうからやめた方がいい」という話ではない。そうじゃなくて「市場原理による効率化と、道徳の腐食作用と、両方を頭に入れて判断した方がいい」ということ。サンデルさんはこんな風に言う。
市場や商業は触れた善の性質を変えてしまうことをひとたび理解すれば、われわれは、市場がふさわしい場所はどこで、ふさわしくない場所はどこかを問わざるをえない。そして、この問いに答えるには、善の意味と目的について、それらを支配すべき価値観についての熟議が欠かせない(p290)
つまり「使いどころ」。市場原理がプラスに作用する場面はたしかにあるし、一方で全部に導入すると大切なものが朽ちてしまう。
たとえばキャンプファイアーさん。このサービスのおかげで、それまで知らなかったNPOやスタートアップの活動を支援できています。キャンプファイアーは寄付を「市場化」してると思うけれど、「慈善」という道徳を毀損しているようには思えない。むしろ、それまでチャレンジできなかった人の背中を押すようなサービスになっているのではないかと思います。
あるいは、noteの深津さんは「noteはアフィリエイトはやらない」と言っていた記憶があります。お金を払ってnoteのPR記事を書いてもらうことは、表現の扉を多くの人に開く、クリエイターを支えるというnoteの価値の根幹を脅かす。これはまさに「市場原理の腐食作用」を念頭に置いたアクションだと思います。
万が一いただけたサポートは、本や本屋さんの収益に回るように活用したいと思います。
