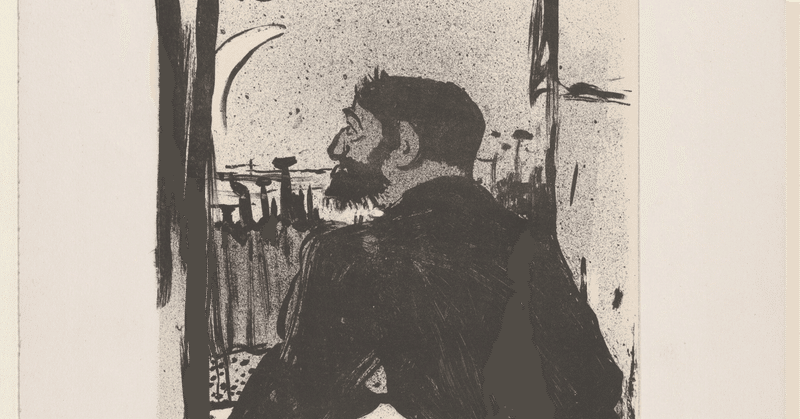
「愛するということ」を補強するーミニ読書感想「エーリッヒ・フロム」(岸見一郎さん、講談社現代新書100)
岸見一郎さんの「エーリッヒ・フロム」(講談社現代新書)が勉強になりました。100ページ程度の短い分量でまとめた「一気読みできる教養新書」を銘打つ「現代新書100(ハンドレッド)」シリーズの一冊。フロム氏の名著「愛するということ」のファンでしたが、その内容を補強できるコンパクトな内容になっていました。
「一気読みできる教養新書」と聞くと昨今話題の(問題視する声もある)「ファスト教養」の一種だと見ることも可能かと思います。たしかに、フロム氏の哲学を「一気読み」することは出来るわけありませんし、出来ると思うことも誤りかと思います。そういう警戒感を持って読みましたが、「面白い」と感じました。
それは、本シリーズが三つのテーマに絞る制約を課しているからかと思います。①その人物の思想の概論②その思想が生まれた背景③なぜ今その思考が読まれるべきなのか、その現代的意義ーーです。
本書に当てはめて言えば、フロム氏の思想の根幹は「ヒューマニズム」だということが理解できました。つまり、人類の普遍性への接続をもって、現代社会の孤独を乗り越えていく考え方です。
その思想は、フロム氏がユダヤ教のラビの家庭に生まれ育ったこと、そして2度の対戦を経験しドイツ国外に亡命したことが下敷きとなっている。
現代的な意義は、もちろん孤独の深まりが言えるでしょう。スマホによる常時接続社会において、なぜ私たちは孤独を克服できないのか?それはフロム氏の指摘する「権威主義的倫理」に頼り切りになっているからだと考えられます。
印象に残った一文としては、孤独とヒューマニズムの関係に関するこの記述です。
「自分自身に耳を傾けるのが難しいのは、この[両親の声を聞く]技術が現代人にはほとんどないもう一つの能力、すなわち、自分一人でいる能力を必要とするからである」(前掲書)
人は自分が所属する狭い集団内部での孤立を恐れる。しかし、人はそのような共同体の一員であるだけではなく、人類の一員でもあるのだ。たとえ自分が所属する共同体の中では孤独でも、人類としては孤独ではないーー人類との本当の「連帯」を感じることができる時、社会か人類かという葛藤は、もはや、ない。
共同体内での孤独を超えて、人類との連帯を感じる。「孤立」を恐れず「孤独(連隊のために一人である)」を、とも言い換えられます。
名著「愛するということ」では、「愛される」ことよりも「愛する」ことの方が本質的で、そして愛するためにはある種の「技術(art)」が必要だという論でした。この時の「愛する」というのが、まさに共同的存在ではなく、人類と連帯する個人としては「愛する」ということなのだと、本書を読むことで感じられました。
つまり、孤立を恐れる存在である中での愛とは、孤立を「紛らわす」ためにしかなりえないのではないか。だから、相手を支配したり、相手からどれだけ愛されているかを重視したりしてしまう。いわゆるトロフィーワイフ的な発想は、共同体の中で自分を誇示する考えから生まれるのではないか。
一方で、人類普遍のヒューマニズムにやって立とうとする個人は、同じく「孤独を選んだ個人」と紐帯することができる。この時はじめて、相手に心底愛を注げ、かつ見返りを求めないという態度が可能なのではないでしょうか。
繰り返しになりますが、本書は「補助教材」あるいは「その人の思考を読み進める取っ掛かり」としては非常に意味が大きいと思います(本書を読んだだけで「フロム哲学を理解できた」とはならない)。私は本書を読めて良かったと思います。
万が一いただけたサポートは、本や本屋さんの収益に回るように活用したいと思います。
