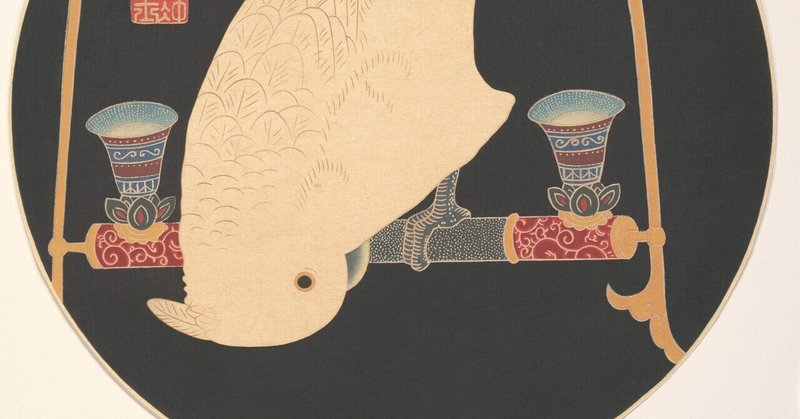
惑うための技術ーミニ読書感想『ネガティヴ・ケイパビリティで生きる』(谷川嘉浩さんら)
哲学者・谷川嘉浩さん、同じく哲学者・朱喜哲さん、公共政策学者・杉谷和哉さんの3人の座談を収録した『ネガティヴ・ケイパビリティで生きる 答えを急がず立ち止まる力』(さくら舎、2023年2月10日初版発行)が面白かったです。ネガティヴ・ケイパビリティとは、日本語にすると「不安を受け止める力」。不確実で、曖昧で、答えの出ない状況に「それでも」立ち止まる力です。本書は、そのネガティヴ・ケイパビリティを発揮する、あるいは培うために必要な考え方を探求する。
現代は、最短距離で最速の答えが求められる時代。加速の時代とも形容できましょう。その中で、あえて立ち止まる力を取り上げる本書。私たちは迷うために、あるいは惑うために、一種の「技術」が必要なのだと教えてくれます。
本書は、ネガティヴ・ケイパビリティの「身につけ方」が分かるわけではありません。何かをすればネガティヴ・ケイパビリティが身につくという発想自体、非常に現代的、即効的、「一問一答的」と言えましょう。そうではなくて、「ネガティヴ・ケイパビリティとは何なのか?」をあれこれ考え、その中で浮かんでくる「泡」を掴むような内容です。
だから技術に近い。たとえばサッカーで、シュート、トラップ、ドリブルなど一連の技術は、勝利のために必要な要素です。それを磨く必要はある。しかし、どれか一つの技術が確実に勝利を約束してくれるものではない。それぞれのプレーヤーが、そのプレーヤーに最適な技術を高め、チームに貢献する必要がある。ネガティヴ・ケイパビリティと本書で取り上げられる思考的技術の関係もまさにそうです。
だから、本書の楽しみは3人の対談の中で登場する概念や、思考の組み立て方を味わうことにある。「つまみ食い」が醍醐味といえます。
たとえば、最初の方では「陰謀論」が取り上げられるのですが、その中で「愚かさの批判」というキーワードが登場します。
谷川 ですね。「愚かさの批判」というのは、誰かを批判するとき、その人が「愚かだ」「浅ましい」「馬鹿だ」というところに帰着させながら語ることを指す言葉です。(中略)そうすると、「こいつは愚かだからこれ以上話すことはない」というメッセージを暗に発することになりますよね。そうなると、もうまともに話ができないし、自分の側に愚かさがないだろうかと自問する道も開かれない。このタイプの批判の仕方をどうやって離れようか、という話をしたことがあるんです。
陰謀論に取り憑かれた人を「愚かだ」と切り捨てると、自然と自分を「賢い」側に絶対化し、対話が閉ざされる。このやり方は実は陰謀論を唱える側の論理そのもので(世の中は真実に気付いていない)、ある意味、答えを希求する思考法。反・ネガティヴ・ケイパビリティとも言えます。
この谷川さんの発言に、朱さんがこう被せる。
朱 対人論証(人格攻撃)と呼ばれるものですね。古代ローマの辺りから弁論術では避けられるべきとされている。
この応答から、「愚かさの批判」は「対人論証」とも言うんだ、しかも古代ローマの時代から禁じ手だったのかと理解が広がる。技術の広がりが、対談の中から感じられるのです。
これが対談の醍醐味。呼応し、時には脱線する。すると当然すっきりした答えからは遠ざかるのだけれど、その「回り道」が脳を刺激する。
本書は、そんな道草的キーワードに溢れている。本書を読んだからといってネガティヴ・ケイパビリティは身につかないけれど、「ネガティヴ・ケイパビリティって結局何なんだろうな」という問いは、頭に残り続けます。
万が一いただけたサポートは、本や本屋さんの収益に回るように活用したいと思います。
