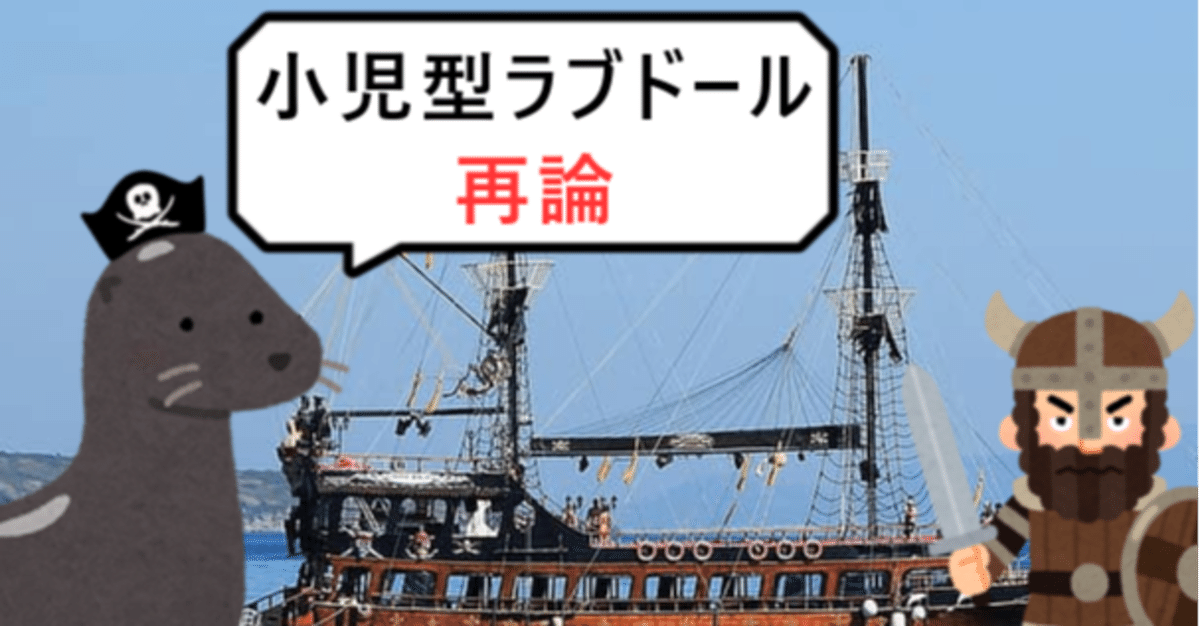
論点整理:「明日海賊にはなれないが、小学生を襲うことはできる」について
小児性愛(ペドフィリア)に関する議論が終わらない。
児童型ラブドールについて、私は次のようなnoteを書いて整理したが、児童型ラブドールを題材にしたレビュー漫画がバズッたことをきっかけに、議論が再燃している。
※既出の論点の復習までに、拙稿のリンクを。
さて、今回は、いま絶賛バズり中の「漫画批判側」のnote記事について、論評したい。
多数の論点が乱雑に提起されているため、主要な論点に一つ一つコメントしていきたいと思うが、結論から言えば、私の立場はどの論点についても「半分賛成・半分反対」ぐらいのものである。
というのも、普遍的な法や正義や倫理について語っているような部分と、個人の感情や処世術としての小児性愛(さらにはオタク趣味)一般への向き合い方の問題とが、混然一体となって記述されているからだ。
本稿では、「法や正義の問題として見たときにどうか」と、個人としての感情や共感の問題としての小児性愛という問題の二方向から照射しながら、簡単にコメントしていきたいと思う。
今回の論争の「論点整理」に少しでも貢献できれば幸いである。
前提:なぜ「小児性愛」を熱心に擁護するのか
まずはここを押さえておきたい。
表現の自由に関する議論について、日の浅いみなさんからすると、
「なんでよりにもよってキモい児童型ラブドールを擁護するの?」
「児童型ラブドールをむきになって擁護する小児性愛者がたくさんいる! 怖い!」
などと思われるかもしれない。
これは分からなくても当然で、実は歴史的な背景がある。
今から遡ること十年余、2008年頃、保守系の婦人団体やリベラル系のフェミニスト団体が手を組み、反児童ポルノキャンペーンを展開したことがある。
実在の児童の人権侵害ともなる児童ポルノが取り締まられることそれ自体は多くの人が賛成することだろう。ところが、このムーブメントを利用して、「架空の児童の性行為が描かれた漫画・アニメ・ゲーム」まで法規制をせよとの動きが広がった。

(写真:準児童ポルノ規制の寸前まで進んだ第169回通常国会の委員会審議の模様(国会中継よりスクリーンショットで抜粋))
正確に全ての経緯を記述しようとすれば、それこそnote記事1本費やしても全く足りないほどなので、詳しく知りたい方はwiki記事などを参照していただきたい。
表現の自由を巡る長きにわたる「オタク」と「規制派」の戦いはすべてここから始まったと言っていい。
「非実在児童」に小児性犯罪の理由を求める意見に必死になって反論したり、ことさら「フィクションに危険性はない」ということを言い立てたりするのは、この「児童ポルノ法改正反対運動」の頃の論調が通底音になっていると言っていいだろう。
もちろん、それが行き過ぎて「フィクションには何の影響もない」とでも言うような論調がいまだに見られるのは問題だが、それぐらい当時から「オタク」をやっていた人々にとってはトラウマになっている話題だと言っていい。
本当に、表現の自由が根底から失われる寸前だったのだ。
そして、小児性愛に対する規制や、反発する大衆感情が、表現の自由への規制の「橋頭保」になる……という危惧は、現在でも十分現実味のあるシナリオだ。
小児性愛表現を一生懸命擁護している人々は、そのような我が国の運動史の文脈の上で述べているのだ、ということは、論争の前提としてどちらも踏まえておく必要がある。
論点① 「小児性愛は嗜好自体が加害性を持っている」のか
ハッキリと言えば、小児性愛者は「自身の性的嗜好の、子どもへの加害性」を自覚し、社会的責任感を持って慎重に振舞う必要がある。「自身の性的嗜好そのものが、加害性を伴っている」という自覚である。内面に持つ嗜好そのものを、責めることはできないから。しないから。まず自覚をしてほしい。
自らの子どもを愛することは、人間として自然な感情であり、すべての児童が大切にはぐくまれ、健やかに育つよう願うことは、現代社会に生きる私たちにとって当然のことだ。
それゆえ、児童性犯罪、チャイルドマレスターによる性加害は、他の犯罪にも増して私たちの怒りと嫌悪をかき立てるのであり、その感情そのものを否定するべきではない。
したがって、子どもを持つ親や、社会に住む他の人々のことを考えれば、「私は子どもでしか欲情できない」などということをわざわざ大勢の人の前で口にするべきではない。それはある種のマナーであると言ってもいいだろう。
しかしそれは、小児性愛者である人々が、「加害性」を持っているということとイコールではない。
小児性愛者の中には、チャイルドマレスターもいるだろうし、そうでない人々もたくさんいる。それは、小児性愛以外の人々に、犯罪者もいればそうでない人々もいるのと全く同じことだ。
「小児性愛」と聞いて、私たちが、「私たちの子どもを犯すのではないか」と「連想」してしまうことは、人間の想像力や思考の働きとして、非合理だけれどもやむを得ない感情だ。
そして、多くの人が当然に抱いているであろう感情に対して、社会に生きるならばちゃんと配慮しなければならないだろうというのも当然のことだ。
(※私たちは、公道で意味もなくナイフを取り出したりしてはいけないし、式典の最中におならを我慢すべきなのと同じことである。他者をあえて不快にしたり、恐怖をあたえたりしてはいけない。それが社会性というものである。)
とはいえ、繰り返すが、ラブドール使用者も含めて、他者を危害せずに生きている人間に「加害性を自覚せよ」というのは全く筋の違った、差別的な主張だ。
加害性は他者を加害するときにはじめて発揮されるのであって、ある属性が加害行為を実際にしてもなければ、現実にする見込みもないのに、「○○であること」自体において加害性を持つという発想は、受け入れられない。
それは、しばしば、正義の名の下でマイノリティを迫害し、抑圧してきた論理それ自体にほかならないからだ。
論点② 「同性愛とは違う」について
論点①は、「同性愛」に置き換えるとわかりやすいので、しばしば思考実験の事例として用いられる。例えばこのようなものだ。
小児性愛者であると公言されて、「私の子どもが性加害される」と思い込むのは、ゲイと告白されて「俺の尻はやめてくれ」というのと同じじゃ。
— ながし (@Pnagashi) September 1, 2020
こうした主張に対する予防線として、四谷三丁目氏は次のように述べている。
小児性愛は「性的嗜好」である。性的行動の対象にその人固有の特徴がある、という意味で、簡単に言えば「好みやこだわり」に分類される。ジェンダー間での、性的魅力を感じるパターンや性的なアイデンティティを指す「性的指向」とは全く異なる。
例えば、同性愛という「性的指向」をもつ人が現実で同性と結ばれても何ら問題はないが、同性愛という「性的指向」かつ・小児性愛という「性的嗜好」を持つ成人が、現実で同性の児童と結ばれたらそれは犯罪である。(そもそものツイートも成人男性から男児への性的欲求でしたね)
これもしばしば出される反論で、それ自体は筋が通っている。
確かに、同性愛者は対等なパートナーシップを実現しうる可能性があるのに対して、小児性愛者はどのような場合であっても、実在の人間とパートナーシップを結びえない。
しかし、それがなんだというのだろうか。
その点は同性愛者と大きな違いであるが、それは「小児性愛は加害性を持つ」というレッテルを当然化しない。
私たちにとって、性愛は実在の人間とのパートナーシップだけが実現の方法ではないし、理想であるわけでもない。
もし、ある人が、決して報われない一方的な片思いで誰かを好きになったとしよう。その恋は加害性を持つだろうか?
少し思考実験をしてみればいい。ある島に同性愛者が流された。その島には同性愛者が一人もないということが分かっている。さて、彼の欲望は加害性だろうか。それとも、悲劇だろうか?
決して報われない思い、社会制度の上で実現の可能性が限りなく低い欲望などいくらでもある。
欲望はそれ自体として否定されるべきではない。他者を加害せずに折り合いがつけられるのならば、その欲望には何の加害性も存在しない。
もちろん、小児性愛者と同性愛者との実際的な違いはいくらでも挙げられるし、同性愛が他の性的嗜好と切り離して「性的志向」と区分されたことには、相応の意味があるのだろう。
けれども、だから小児性愛者だけを切り捨てて事足れりとするやり方は、結局、理解できない他者を切り捨てても良いという社会規範に繋がるのではないか。
それは、かつて同性愛者を切り捨ててきた社会のやり方の再生産になってはいないだろうか。
論点③ 小児型ラブドールは犯罪を助長するか

小児型ラブドールによって児童への性的加害が助長される可能性があるのだ。あくまで可能性だ。もちろん100%じゃない。でも“ある”んだ。実際に、あのレポート漫画の描き手は、児童のイラスト(2次元)では満足できなくなってラブドール(3次元)に手を出している。そこで発散できているともとれるし、欲求がエスカレートしているとも取れる。その先がどうなるのか、断言できることは何もない、ということをまず解ってほしい。
本稿で最も重要な論点がこの点であると思われる。
ミクロなレベルで「助長」することがあるかと言えば、可能性はゼロではないとしか言えない。
なぜなら、どんなことでも可能性はゼロではないからである。
実際、ラブドールではないが、ミクロレベルの実験では、ポルノグラフィの視聴は性犯罪に対する罪悪感が低減させるのではないか、という研究も存在する。
とはいえ、現在のところ、マクロレベルで確実に犯罪率を引き上げるのかと言われれば、そのような研究結果はほぼほぼ存在しないというほかない。
引き下げるのではないかとする研究もあるにはあるようだが、それも引き上げるとする研究結果と同様に、確実にそうだと言えるほどの確度でもない。
確実に言えるのは、ポルノグラフィやラブドールといった様々な性的娯楽が充実するのと並行して、性犯罪率は低減してきたという歴史的な事実のみである。
(参考)性犯罪に関する総合的研究(法務省)
http://www.moj.go.jp/content/001178520.pdf
これはもう、ケースバイケース!!!としか言いようがないだろう。ラブドールで発散することで、実在児童への性的加害欲求が抑えられる人もいれば、ラブドール使用によって実在児童への性的加害欲求が助長されてしまう人もいる。異論はあるか?ないだろ?AVを見て加害欲求を発散できる人もいれば、「AVを見てやりたくなった」という性犯罪も実在するのである。同じことだ。正直、ここの異論は認めない。
「ケースバイケース!!!」でいいのであれば、なんだって言えてしまう。それはそうだろう。石にけつまずいたのが動機で犯罪を起こす人だって世界のどこかにはいるかもしれない。
「AVを見てやりたくなった」というのは、有名な「引き金効果」の話だ。本人が主観的にAVが動機と認識していても、AVが無かったら性犯罪が起こっていないかと言えば、世の中そんなに単純なものじゃない。AVがない時代には、別の何かを動機として、人類は性犯罪をしてきたのだから。
アルベール・カミュの『異邦人』の有名な一節で、「太陽が眩しかったから殺した」というものがあるが、もしもその日の天気が雨ならば、ムルソーは犯罪を犯さずに一生を終えただろうか。
ここまでの話は正直、十年前のポルノ規制論の際にやりつくした話だが、しかしもうそろそろ前進しよう。
ポルノは犯罪に関係がない。少なくとも、犯罪に関係があるとする積極的な証拠はない。したがって、法規制せよとか、取り締まれという意見に賛成することはできない。これは現時点での結論だ。
とはいえ、である。
子どもを題材にしたポルノやラブドールを、たとえ架空のものとはいえ、「なんとなく危なそう」「犯罪に関係するっぽい気がする」という漠然とした嫌悪感や危機感まで否定できるだろうか。
子を持つ親や、子どもが大切にされる社会であってほしいという普通の人々の思いや願いは、ほとんど誰にでも想像できる話のはずだ。
我が子の隣に「私は子ども型のラブドールでオナニーするのが趣味でして」などと言う人がいたら、まあ普通は我が子を遠ざけるだろう(そんな人はまずいないと思うが)。
もちろん、児童型ラブドールやエロ漫画を悪者にする論調は、客観的・科学的に考えればおかしい話だ。しかし、感情までもわからないとしてしまうと、対立はどこまでも深まってしまう。
四谷三丁目氏は「社会的責任」という言葉を使われているが、マナーの問題として、あえて殊更にそうしたものを公然と展示しないぐらいの気遣いはあっていい。
例えば、塩瓶が倒れれば不吉なことが起こると信じるイギリス人の前で、あえて塩をぶちまけないとか、仏滅に結婚式をすると不幸が生じると信じる御年配の親戚に配慮して、挙式の日を考えるとか、そういう話である。
あとはその「配慮」をどう社会的にアジャストするのかの話だけである。小学校で過激なポルノ雑誌を読んだり、病院の待合室でラブドールを使用すべきでない、という完璧に当然の話から、どこまでをマナーや慣習の問題として受け入れ可能かということを、私たちは議論を通して合意形成していく必要がある。
そのぐらいまで「表現の自由戦士」も歩み寄っていいのではないか……と思うのである。
論点④ フィクションはどのように影響を与えるか
マジのマジレスするけど、現代日本で生活を捨てて船を買って海賊になるのと、その辺を歩いている小学生を暴行するのがなぜ比較になると思うんだ。考えてみてくれ。私は多分一生かかっても海賊にはなれないが、小学生を襲うなら明日にでもできる。実行に至るまでに必要なハードルが全然違う。皆さんの目の前にいるでしょう、小学生。手を伸ばせば届くところに。
これは残念ながら例えが良くなく、失当と言うほかない。
「小学生が手の届くところにいる」から、フィクションが犯罪を引き起こすような影響を与えるというのであれば、海賊のような極端な例を挙げずとも、殺人や窃盗を描いた作品はいくらでもあるし、それらは法の問題を無視し、やろうと思えば明日にでも実行することはできる。
彼らの安全は、私たちが「その気」になるか否かの、ただその一線で守られている。私がもし「その気」になれば、その後捕まろうがなんだろうが児童の心に一生消えない傷を残すことが可能だ。明日にでも。何かが、「その気」を助長するんじゃないか。
私たちがフィクションに窃盗や強姦や殺人が溢れているにもかかわらず、「その気」にならないかといえば、「やってはいけないこと」だとわかっているからである。
なぜ「やってはいけないこと」だとわかっているかといえば、学校や家庭における教育の過程において、そうだと教わるからである。
「やってはいけないこと」だと分かったうえでフィクションを読めば、読者は「やってはいけないこと」をやるのは倒されるべき「悪いやつ」だとみなすか、もしくは、「やってはいけないこと」が許されている世界におけるカタルシスとして、社会において許されざる欲望を消化する媒体となる。
もしも、フィクションの行為を「やってはいけないこと」と考えず、やってしまった人がいるとすれば、それは悪を悪と学ばずに実行したその人の責任に他ならない。
フィクションから何を血肉として学び、どう取り入れるかは私たち自身が負うべきことだ。
物語をどうとらえ、どう活用するのか。ルフィを見て、友情の大切さを学んだり、航海士になろうと志すのか、それとも、ゴムゴムの実を探したり、感情的に他者をぶん殴っていいと考えるのかは、フィクションを読む私たちが決めるべきことだ。
そして、私たちが「どのように生きるか」という選択肢は多様であればあるほどよい。であるならば、フィクションもまた、自由で、多様で、善にも悪にも、正義にも不正義にも、開かれていなければならない。
キャプテン翼を読んでサッカー選手になった人が、「キャプテン翼のおかげだ」と言うのは、その「選択肢」を教えてくれたことに対する感謝であろう。選択肢をつかみとり、血のにじむ努力を重ね、艱難辛苦を乗り越えて大成したのは、その人自身にほかならない。(逆に、サッカー選手になろうとして失敗した人が、キャプテン翼を恨むとしたら、それは全く馬鹿げた話だとなるだろう)
フィクションが示してくれるのは、「選択肢」にほかならない。
「悪」が描かれた表現物を見て、「だから悪をなそう」と考えるのか、それとも、「これは許されざる悪だ」と考えるのか、それも「選択」だ。
そして、選択肢を示すフィクション作家は、選択肢を示すことはできても、読者が何を選び、どう生きるかまでコントロールすることはできない。
フィクションはそのような万能ではないのである。
自由な社会においては、選択肢に真剣に取り組み、ひとつひとつ選んでいくのは、私たち自身にほかならない。そして、幼き日の私たち自身に選択肢の選び方や、物語の活用の仕方を教えてくれるのはなにか。
それこそが「教育」の役割に他ならない。
「やってはいけないこと」をそうだと知らずやってしまったことを怒られるのも、フィクションに感化されて努力した結果をほめて伸ばすのも。
すべては「教育」であり、教育を受けた私たち自身の働きだ。
したがって私は、次の主張については全面的に却下せざるをえない。
そうならないために作品にレーティングをかけるのは製品元の社会的責任だし、「殺人は絶対に許されるものではない」というメッセージを込めるのはクリエイターの社会的責任である。そして、そこから漏れた表現があった場合はそれを指摘するのが、コンテンツ嗜好者の社会的責任であると思う。
フィクションに描かれた殺人を見て、自分たちの生にどう反映させるかは私たち自身の責任なのであり、それが自由な社会の在り方であるはずだ。
こう言うと、次のように反論する人がいるかもしれない。
「最初から悪を選ぶような選択肢をすべて排除すればいいではないか」
と。
もちろん、そのような社会もありうる。
教会が選んだ「正しい書物」だけが許された社会もかつてはあった。
悪として解釈されうるすべての娯楽を禁止し、無菌室のような場所で子どもを育てるべきだという考えもなくはない。
しかし、一方で、善にも悪にも等しく触れる可能性がある場所で、教育者が善を善と教え、悪を悪と諭し、自らで善悪理非を弁別する力を身につけさせるほうが、はるかに健全な社会になると言えよう。
少なくとも、歴史を見る限りにおいて、様々な悪徳の表現に溢れる自由な現代社会のほうが、かつてのあらゆる不自由な社会よりも、はるかに犯罪も不正義も減少している。これは一つの事実だ。
したがって、私たちの社会的責任というのは、「ジャンプのページにびっしりと注釈をつけること」だとか、クリエイターに道徳の教科書のような作品を求めることではない。
自由な表現が許された、多様な表現物が闊達に流通する、今の私たちの社会をしっかりと守りぬくことである。
結論 オタクの社会的責任とは――もしくは「ヤマアラシのジレンマ」に対する一般的解法

しつこいけども、我々オタクも「オタクコンテンツの嗜好者」である前に、社会構成員だし、成人なら社会的責任を負っている。ケースバイケースの「悪い影響」を危惧する声が上がるのは、社会において必然である。それについて我々が社会的責任感を伴う客観的な視点を持てないなら、大喜利大会を開いて茶化し続けるなら、その果てにあるものは、社会的信用の失墜からの一律の法的規制である。
ここまで述べてきたことを踏まえてもなお、私はこの四谷三丁目氏の結論を否定する気にはなれない。
「悪い影響」を危惧する声が上がること自体を防止することはできないからだ。それは全く科学的な根拠を欠くけれども、社会は科学や客観的根拠だけで動いているわけではない。
したがって、こうした声に対して適切に説明や反論を加えたり、政治的な場で活動してくれる、オタク文化に理解のある政治家を支援しつつも、社会的な妥協や適応は常に必要となる。
私たちが最も考えなければならないのは、「欲望」の表現だ。
人間は、自分自身に欲望を向けられることを恐れ、嫌悪する。飢えた狼が私たちの肉体に歯を立て、かみ砕き、胃袋に収めたいと思いながら、ギラギラと見つめてきたとしたら、恐怖の感情から免れ得ないだろう。
同様にして、むき出しの性的欲望を、それと望んでいない他者や、その家族や、ましてやかけがえのない子どもたちに向けられたとき、防衛本能から強力な嫌悪と忌避の感情を持つのは当然だ。
その当然の感情を無視して、「オタク差別だ」とか「小児性愛者の人権が」と言い募っても、理解を得られることはあるまい。
したがって、小児性愛のようなセンシティブな欲望を、他者に公然と示す場合には、どうしても一定の社会的配慮が必要である。
件の「ショタコン」漫画の作者の作品を見る限り、冒頭に注意書きをするなどの一定の配慮は見られたものの、「手を出す前にドールを」などの発言は、確かに配慮に欠けたところがあると言わざるをえない。
他方、私たちは、「嫌悪」を向けられることによっても、社会的な疎外や傷つきを受ける。それは、同性愛嫌悪(ゲイフォビア)が歴史的にどのように少数者を抑圧してきたかを想像すればわかりやすいだろう。小児性愛者も、嫌悪を直接向けられれば当然に傷つくことは想像に難くない。
重要なのは、欲望と嫌悪のバランスだ。
私たちの社会では、欲望を示さなければ欲望を充足できないという構造にあるし、逆に、不快な欲望を照射された対象は、嫌悪を口にしなければ、いつまでも自分の傷つきを他者にわかってもらうことができない。
だから、欲望と嫌悪のやり取りを繰り返しながら、「ヤマアラシのジレンマ」のように、一番お互いが傷つかない心地よい距離を探るしかない。
今風に言えば、「ソーシャル・ディスタンス」とでも言うべきだろうか。
私たちはしっかりと異論者や異質な他者とコミュニケーションをとりながら、社会のあるべき姿を探求する必要がある。その誠実で地道な言葉と言葉の積み重ねこそが、私たちの「社会的責任」の内実にほかならない。
少なくとも。
「お前は加害性を持っているのだ、自覚しろ」と小児性愛者にむき出しの嫌悪感情をぶつけることは、社会的責任を果たすことでも何でもない。
マジョリティと一緒に差別をしているだけであり、オタクがいじめに加わることで社会的多数者からのお目こぼしをもらおうという話なのであれば、そのしっぺ返しは必ずオタクたち自身の身に降りかかってくるだろう。
少数者を攻撃する社会が、別の少数者に優しいという保証など、どこにもないのだ。
特に四谷三丁目氏の言いぶりで引っかかったのは、次の一節だ。
小児性愛という嗜好を社会へ受け入れてほしいならば、当事者たちが「そんじょそこらの大人より児童の人権に配慮する」姿勢が必要ではないか。
社会的なマイノリティに対して、マジョリティの高みから「受け入れてほしくばもっと善良であれ」と言ってのけているのである。
私には耐えがたい、醜悪な差別主義だと感じた。
別のマイノリティに対してここまで酷薄でなければ、マイノリティが受け入れられない社会なのであるとすれば、それこそ変えられるべき構造であるように、私は思う。
もし、オタクたちが今のような自由な表現ができる社会を維持したいならば、できること、なすべきことは、ほかにある。
それは、しっかりと地域に根を下ろして、多様な表現物があることを当たり前に受け止める、次の世代を育てることである。
自由な社会を維持し、守り続ける政治家や活動家の方々をはっきりと支持し、不断の意思で下支えすることである。
そして、コンテンツを消費する良き市民として、社会に参画し続けることである。
それがオタクが「社会的信用」を生み出す唯一の、遠回りだが確かな道なのである。
以上
青識亜論
