
SaaS起業家限定配信「SaaS部 2020 Autumn」レポート
みなさん、こんにちは。今回は、遡ること2020年10月末に開催したイベント「SaaS部 2020 Autumn」のレポート記事をお届けします。弊社の投資先およびSaaS領域で起業した起業家を対象にDNXが主催となって開催しているイベントですが、今回もコロナを忘れてしまうほど、経営者たちの集中と熱量溢れる学びの詰まった会でした。
今回は、SaaS/クラウド領域で数多くの投資実績をもつManaging Partnerの倉林陽とJunior Associateのチェ・ミンジュンのふたりが解説する「BtoB SaaS企業のIPO後の株価形成と IPO時の公開価格について」を前段に、SaaSビジネスで非常に頭を悩ませるプライシングについて、プライシングのスペシャリストであるボストン コンサルティング グループの服部奨さんをお招きしました!
聞き手は、弊社の投資先アルプ株式会社の代表取締役 伊藤浩樹さん。SaaS起業家向けに徹底的にプライシングついてたっぷりお話を伺いました。今回は、そのなかから一部をご紹介します。
会場の熱量と学びがみなさんに届き、みなさんの会社のプライシングのヒントになりますように。
ちなみに、すでにアルプ代表の伊藤さんが、本SaaS部をスマートにまとめてくださっていますので、こちらの記事も合わせてご覧ください!(ちなみに、アルプが提供するScalebaseは、商品設計やプライシングにおけるPDCAを回せる仕組みを提供しています。本記事でプライシングを見直したい!と考えた方は合わせてぜひチェックください)

はじめに
様々な業界の様々な企業のプライシングに長らく携わらせていただいて思うのは、プライシングは競争戦略そのものだということです。顧客のセグメンテーションや提供価値、競合などあらゆることを考えないと、本当の意味でのプライシングの答えは出ない。プライシングを考えることは、会社の事業戦略を考えることとほとんど同じではないかと思います。
このことを深く踏み込んでいらっしゃるのが稲盛さんです。多くの本を出版されいますが、印象に残っているのが「値決めは経営」という言葉です。顧客が納得して喜んで買ってくれる最も高い値段、そのギリギリの一点で値決めをしなくてはいけない、その見極めがすごく大変ということが語られています。それは経営者の器の問題であり、心の問題であり、さらに読み進めると、戦略をシャープにしてプライシングを見極めることだけでなく、提供価値とその価格がわかるほど顧客のことが本当に理解できているか、もしくはそれだけプロダクトやサービスを磨いてきた自信があるのかを問われる、と。私も様々なプロジェクトに関わらせていただく中で、「経営そのもの」と仰られる意味がわかったような気がしました。

まずは普遍的な枠組みで考えてみる
そうは言っても値段を決め、プライシングモデルを考えなくてはいけません。そこで、BCGではいろんな業界の普遍的な枠組みを設けて考えるようにしています。平たくいうと、①プライシング戦略、②プライシングの実行、③組織能力・経営基盤の三階層。「プライシングを通じて実現する戦略とはなにか、目的はなにか」というのが一つ、「その上でそれを具体的にどうやって実行するか」、そして「それを実行するための経営基盤、つまり組織と運営をどうやって作っていくか」の3段階で考えます。
競争環境で考えてみる
このようなプライシングを考えるための枠組みはありますが、プライシングはいくつもの切り口で考える必要があります。SaaSスタートアップの切り口で考えると、業界構造や競合との相対的なポジションを考えるべきだと思います。
競争環境を考える時には、トップシェアかそうではないかという自社のポジションの軸と、競争環境の厳しさという二つの軸によってプラシングの考え方は変わります。自分たちがマーケットを握っている(つまり自分たちが価格を下げると類似企業も下げなくてはいけない状況)のか、そこまでいかなくとも一緒にマーケットを作りながら自分達の収益源を確保していく状況か、市場が混み合っていて自分達のポジションも限定的でニッチな戦略をとるのか、など。
プライシングは競争戦略そのもの。プライシングが顧客行動に繋がるかが重要
私がお付き合いしてきた大企業とは業界もステージも違いますが、SaaS企業も本質的には共通することがあるのではないかと思います。

出所:ボストン コンサルティング グループ
ひとつは、プライシングは競争戦略のど真ん中であること。プライシングってSaaSの経営のど真ん中にあって、お客様にどういう価値をつけられようとしているのか、それはセグメントの付け方によって違うのか、競争環境や優位性によって何を変えなくていけないのか。
2点目は、そのプライシングの設計や実現方法などのHowとWhatも大事ですが、何を目的関数にするかというWhyの部分が本当は重要です。それの一つが、顧客行動です。顧客の行動が望ましい方向に変わるかが大事かなと思います。
3点目は、競争環境が変わればプライシングも変わるというところ。競争環境がずっと一緒ということは絶対にありません。競争環境に合わせてプライシングを変えていくことが非常に重要です。ということは、相当なPDCAを回すということであり、そのPDCAについてこれる「プロセスやチーム」も重要になります。
最後は、価値を提供していることを自信を持って言い切れるかどうか。顧客への価値創造がきちんとできているかどうかと、価値提供のためにプロダクトやサービスの磨き込みをしているか。顧客もここを見ているのではないかなと思います。
---
BCG服部奨さん:ここからはSaaSのプライシングについて、対談形式でSaaS起業家がどのようにプライシングを考え進化させてきたのかについて深く切り込んでいきたいと思います。
❶アンドパッド「顧客の売り上げ成長を軸に価格訴求」
アンドパッド代表 稲田武夫さん:アンドパッド稲田です。弊社の場合、複数のサービスがある中で一番大切にしていることは、顧客である建築会社の経営者に基本プライシングの話をしないこと。建築業界の中でIT化に成功し売上を伸ばしている先行企業の「売上対IT投資比率」を伝えます。多くが売上対IT投資比率が0.1%程度なので、少ない予算を他のSaaSやITサービスと奪い合うのは非効率であるということ、そしてIT投資を引き上げるために売上を伸ばすことが大事であり、そのためにアンドパッドを導入しましょうと話します。
服部さん:大変参考になりました。「そもそも売上を上げましょう」と言うところが、顧客が御社のサービスを導入するときのバリューの源泉ということですね。
Sansan寺田「実現したい世界からの逆算と、事業が伸びるドライバーを意識した設計」
Sansan代表 寺田親弘さん:初めまして、Sansan寺田です。まず、プライシングはとても重要だと思っています。最近まで全部僕がやるくらい、プライシングに関わってきました。一時期全社で使ってもらうサービスのプライシングに悩んだ時期がありました。Sansanは名刺管理サービスを提供しているので、我々としては全社でインフラ的に使って欲しいという思いがあります。一方、コンセプトは理解されてもID単位で提供する限りはどう頑張っても思うような使い方をしてもらえませんでした。そこで編み出したのが、名刺の枚数ベースで月額をあらかじめ見積もって、かつ全社員にIDを付与しなければならないものにする、という真逆の考え方を取りました。「ただ使って!」ではなく、約款に全員にIDを付与しなければならないと書きました。これが実現したい世界観に対してようやくプライスが開発されたモーメントだったと思います。
スタディスト 鈴木さん「初期は収益性度外視でユーザー数拡大に注力。そこから基準とするValue Metricも変化し、単価も拡大」
スタディスト代表 鈴木さん:皆さんこんばんは、スタディストの鈴木と申します。当社はTeachme bizというサービスを提供していますが、このサービスは、業種も用途も様々であるため、業界と使われ方によって効果が異なり、バリューに基づいた価格設定が非常に難しいプロダクトでした。
今まで6回の価格変更と課金方法の見直しをしてきました。現状は一社あたりのベースの月額料金は10万円ですが、サービスローンチした2013年は2500円でした。初めは、社数を増やすために価格を低く設定し、SMBでお客様を増やしていくことに注力していました。収益性は度外視ですよね。一定期間経ってから値上げしていきました。
基本的に小売店様や飲食店様のお客様が多いため1店舗に1IDで使われることが多く、「このままだと成長が見込めないからビジネスモデルを変えるべき」と、人材育成や能力管理機能を追加することで、個人がアカウントを持つ必要性が生まれるよう機能強化をしていきました。
DIGGLE代表 山本さん:思い切った価格変更をされたなと感じたのですが、既存のお客様にも改定後の新しいプライスを適応されていたのでしょうか?
鈴木さん:これは企業のポリシーだと思います。我々は既存のお客様の料金は上げておりません。初期のお客様は創業期から支えてくださったファンですので、そのままの料金でご使用いただいてます。そこにはお客様がお客様を連れてきてくださるという観点で回収すればいいのではないかと。まだまだ数千社の規模ですが、先には数万社の可能性があるわけですので、未来を見ようということで、腹を括っているというのが今ですね。
DNX Ventures 倉林:服部さん、伊藤さん、そしてコメントをくださったみなさん、ありがとうございました。非常に勉強になりました。多くの経営者の方々と話している中で、VC的な観点で感じたことは、グロースが止まっている時にプライシングの話になる傾向にあること。一方で、すごく成長しているときにあまりその議論にならないんです。「値決めが経営」なので、調子が良い時にもプライシングについての議論をしてみるといいなと思いました。経営者のみなさんはPMFして採用してお金集めてと、日々ものすごく多くのことを考えなければいけない中で、果たしてどれだけの時間をプライシングについて考える時間に費やせるのか、というのは非常に大変だと思います。ただ、優先順位を上げるべきという認識は皆さん持っていただけたかと思いますので、今回教わったフレームワークで皆様が考えやすくなれば良いなと思います。
本日のまとめ、そしてプライシングのPDCAをクイックに回していくために
服部さん:ありがとうございました。最後に、今日皆さんと議論していく中で感じたことをラップアップ的におさらいして終わりたいと思います。思ったことは3つありました。
①バリュークリエイションが重要
一つ目はプライシングの大前提のところのバリュークリエイションがどれだけ骨太かがすごく大事だなと思いました。先程のアンドパッド稲田さんの売上をどのように上げていくか、そしてそこにどう貢献していけるかですね。バリュークリエイションが先にあって、その後にバリュープライシングがあるというのは非常に重要なポイントだと思いました。
②自信と徹底の仕方
二点目は、ここに対する自信や徹底の仕方です。Sansan寺田さんが約款に入れてしまうのは凄いですが、自分たちのプロダクトへの自信があって、それが最終的にお客様のためであるという揺るがないものがあると迫力が違うなと思いました。どの商売でも大事なことですよね、私自身も非常に参考になりました。
③見直し進化させることが重要
三点目は、皆さん共通しておっしゃられていたことですが、どんどん進化していくということです。つまりPDCAを回すこと。しっかりとデータを供給しクイックに回していくには、色々なツールや組織や人材がついてなど、仕組みによるところが大きいのかなと思いました。ここで最後にそうした仕組みを提供されている伊藤さんにパスしたいと思います。
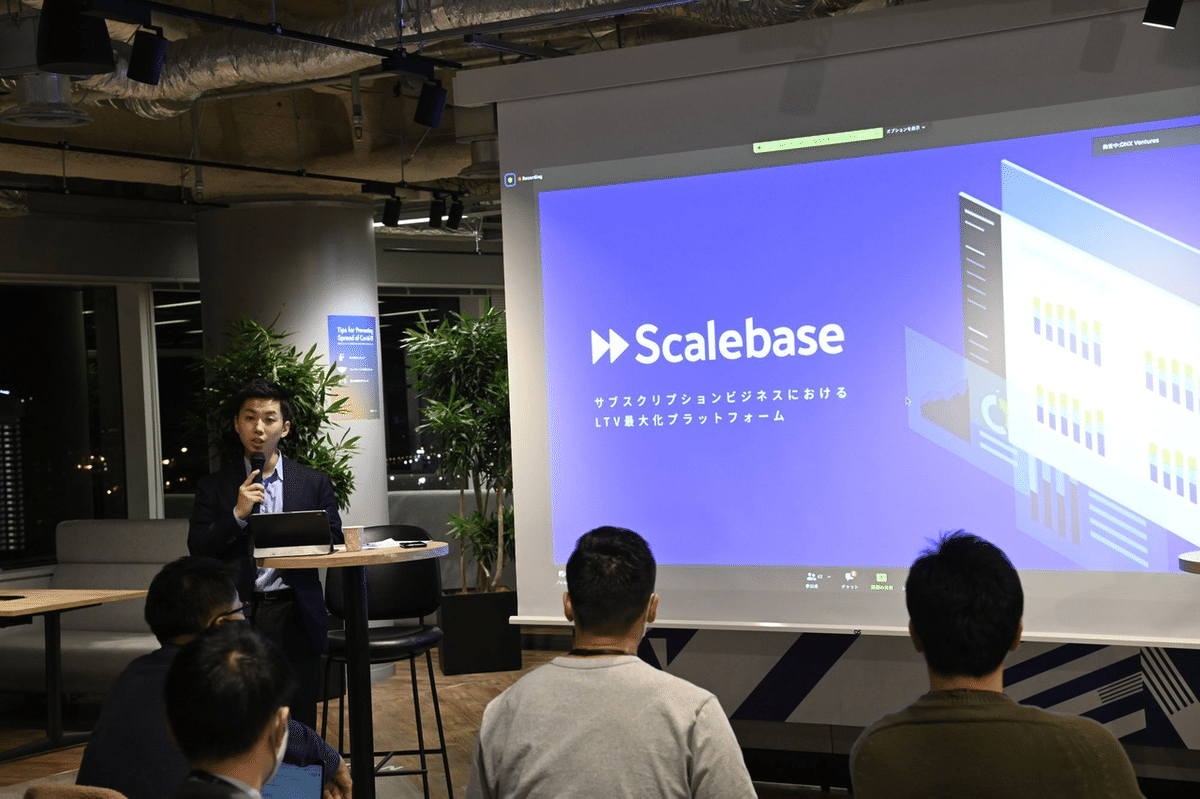
伊藤さん:改めまして、Alpの伊藤と申します。Scalebaseというプロダクトを扱っており、商品設計やプライシングにおけるチューニングとフィードバックサイクルを回せる仕組みを提供しています。SaaS企業様のプライシングや契約の管理、セールスの管理、運用の仕組みについてSaaS自体の販売をしていくのはもちろん、プライシングとかのフェーズからご一緒していきたいなと考えています。
本日も常にプライシングの見直しが重要であることが語られましたが、グローバルのSaaSでも毎年5%〜7%くらいのプライシングの調整は入るべきで、逆に1年2年プライシングを変えていないというのは取れるお金をとっていないというメッセージにとれます。プライシングについて考える時には様々な論点があります。顧客ごとに請求・決済などにおいて独自のルールがあったり、トライアルが発生したり、同じプロダクトを使っていても導入したタイミングによって価格が違うなど、これらの管理に課題を感じているSaaS企業さんが多いのではないかと思います。Scalebaseは、プライシングのパッケージの進化・PDCAを持続的に運用できるサービスで、プランを作成したり、料金モデルを提示、それを販売・契約提供まで実行する一連の流れを簡単に管理できます。さらに、検証するためにテストしたプランをダッシュボード上で管理することができます。ということで、本日テーマに上がったプライシングのチューニングを理論的にできるプロダクトだと思っています。
セールスフォースやマネーフォワード、クラウドサインなど皆さんが使われているであろう会計プロダクトとは連携しておりますので、契約とか商品のデータ、SFAの分析やマスタ属性などを見て、そこで正しい契約請求管理を行うことで、正しい会計データや請求書発行を行うことができます。さらに、契約・請求・商品のマスタデータを元に、リアルタイムでMRRやチャーンレートを可視化することもできます。正しい契約請求管理を実現し、また日本独自の商習慣にも柔軟に対応した形で提供可能ですので、ぜひご興味ある方がいらっしゃいましたらお声がけくださいませ。また、プロダクトだけでなく、プライシングそのものについてのディスカッションや、私がこれまでBCGなどで調べてきたことなども共有できるので、少しでも貢献できることがありましたらお気軽にご連絡ください。
倉林:伊藤さんありがとうございました。皆さんぜひAlpのScalebaseにご興味持たれた方がいらっしゃいましたら、伊藤さんにご連絡ください。服部さんもお忙しい中、本当に勉強になる素敵なプレゼンテーションをありがとうございました!
(文:上野 なつみ / 制作協力:辻良太朗、塩野清雅)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
