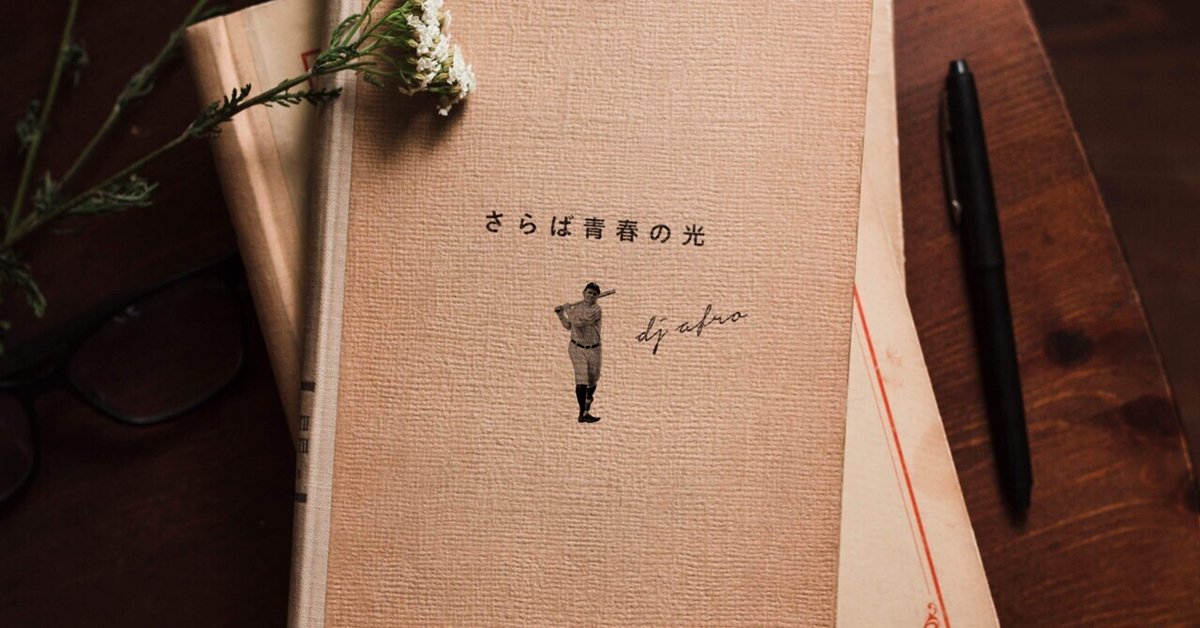
さらば青春の光
ヤンキーの巣窟として悪名高い、地元の荒れた高校に通っていた。煙草の吸殻がそこらに転がり、窓ガラスは破壊され、廊下にはゴミが散乱。廃墟のような殺伐とした校舎に、入学初日から絶望した。
少しでも目立つ新入生はすぐに先輩ヤンキーの標的となり、理不尽な制裁をくらうか、あるいは一大勢力と盃を交わし、傘下となることでパシリとなった。
そんな横暴が日常的に繰り返されているのだ。新年度を迎える度に1クラス単位で退学者、音信不通者が続出し、卒業の頃には3クラスあった学年が1クラスにまで減少していた。
その頃の自分はロックに傾倒しており、ビートルズやキンクス、ザ・フー、スモール・フェイセスなどをよく聴いた。音楽に限らずファッションにも魅了され、特にモッズカルチャーには強い影響を受けていた。
マッシュルームカットにモッズコート、レコード屋の袋を持ち歩く自分の姿は、異質に映っていたようだ。先輩の存在は恐怖でしかなかったが、一度も絡まれたことがない。
通っていた高校は独特のスクールカーストで構築されており、頂点から底辺まで、ほぼ武闘派のヤンキーで塗りつぶされていた。「その他」の未分類に、ヤンキーもどき、普通の人、異常に暗い人がこそっと紛れ、カースト外にモッズ(これが僕)がひとりいるのだ。おそらくこれまでに、「ヤンキー×モッズ」という局面はなかったと思われる。彼らにとって僕は領域外の人種で、妙に触れにくい空気をにじませていたのかしれない。
同級生は次々とヤンキーの餌食(部活に強制入部)となり捕えられていたが、僕には無関係であった。しかし、入学して数週間が経過した頃、安住の地は崩壊する。
野球部の先輩が暴力をちらつかせ、新入生を部活に勧誘しはじめたのだ。どこから情報を掴んだのか、野球経験者はすでに先輩たちに包囲されていた。それでも部員は足らず、次第に入部の条件は緩和される。少年野球の経験だけでも即戦力と見なされ、なんならスポーツ経験者であれば競技を問わずクリア。最終的にはそれらの経験が一切なくても、経験者の友達ならもうそれでよしっ。となる。
それもそのはず。野球部員は2名しか在籍していなかった。そもそも、新入生の数自体も少ない。条件をぐずぐずに緩めないと、部員を確保できないのだ。
野球未経験の自分は強制入部から逃れられたと呑気に浮かれていたが、条件は日増しに緩み続けた。そしてついに、自分にも勧誘が迫る。気がつくと、友達のひとりが放課後になると消えていた。グラウンドを見渡すと、友達が先輩から地獄のノックを浴びせられながら、雄叫びを上げていた。
僕は、“経験者の友達”枠に当てはまってしまったのだ。
退っ引きならない事情を偽り、どうにか先輩を避けていたのだが、すぐに虚偽はつきる。薄暗い野球部の部室に監禁され、先輩とふたりきりになった。
「いますぐ俺に殴られるか、野球部に入るかどちらか選べ」
このように脅されて、友達は巻き込まれていったのか。凄まじい圧力と、殺意だ。確かに、これは断れない。
心臓がばくばくで破裂しそうだったが、この時、僕の脳裏に浮かんだのは、「モッズって野球するの?」であった。貧相な知識しかないモッズ気取りの自分は、まずそこで悩んだ。
細身のスーツに、モッズコート。イギリスと……あと、ライトがいっぱい付いたベスパ。
モッズに関する知識は、それで全てだった。苦悩した挙句、最後は感覚で判断し、“モッズはきっと野球はしない”に辿り着く。
ロック精神を貫いて、「どちらも嫌です」と返答したのだが、そんなものが通じる相手ではないし、「見た目よりは強肩」というデマが流れていた。僕のポジションはすでに確定しており、自分の意思とは関係なく外野手になっていた。過去に、中継プレーを目撃された憶えはない。勝手な噂を流されて怒りが込み上げてきたが、同級生も必死なのだ。無下に入部を断れば、彼らが痛めつけられることになるだろう。
野球用具を揃えに行くという名目で先輩から帰宅の許可をもらい、その日はなんとか解放された。
翌日の放課後、グローブを装着して部室へ向うと、先輩は僕の姿を見るなり、唖然とした。
「それ、キャッチャーミットや! 俺のポジションじゃい!」
先輩は地面にボールを叩きつけ、怒鳴り散らした。僕は先輩の怒りを鎮めようと思い、なぜかキャッチャーミットをそっと差し出した。
「腐るほど持っとるわ! もうええわい! 帰れ!」
どうやら僕は、戦力外通告を受けたようだ。
僕は先輩に、ちぃーすっと軽く挨拶をして、逃げるように部室をあとにした。
数ヶ月後、先輩にとって最後の試合が行われた。
ヤンキーに混じって、真面目そうな人間がひとりぽつねんと佇んでいた。数年前に話題になった物語を連想させる、個性の集団。しかし、現実はドラマのような展開にはならない。ヤンキーチームは1点も奪うことができず、コールド負けで試合は終了。
先輩は部活動以外でも常に野球帽を被っていた。不器用で強引なひとだったが、純粋に野球がしたかっただけなのだと思う。
ゲームセットになった瞬間の先輩の表情が、忘れられない。先輩は悔しさをまぎらわせるように帽子を目深に被り、空を見上げた。灰色の空はどんよりと曇っていたが、雨にはならず、蒸し暑い熱気だけがじわじわと漂った。
振り返ってみると、自分にはそういう青春がなかった。
感情が昂ぶり、漠然とした衝動に駆られる。どんな豪速球でも打ち返せる気がした。
側にあった硬貨を乱暴に握りしめ、バッティングセンターへ向かう。
打席に立つと、身体中の血が騒ぎ、力が漲るのを感じた。ピッチングマシンから豪速球が放たれ、フルスイングでホームランを狙う。
魂を込めた打撃は虚しく空を切り、初球からチップで自打球。心が折れた。
いずれにせよ、僕が入部したところで何の役にも立たなかったと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
