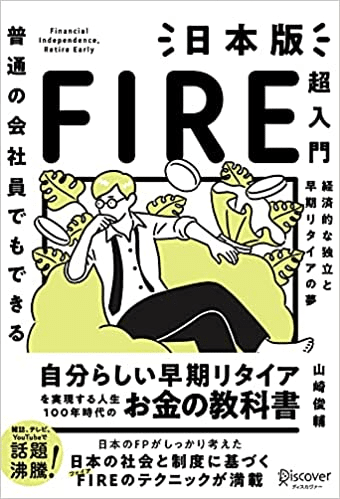「子ども大人も夢中に!」科学実験図鑑や「2022年の世界情勢」まで分かる占い! 7月のブックバースデーレポ➂
ディスカヴァー・トゥエンティワンでは、新刊の発売日当日に著者さんをお招きし、書籍に発売をお祝いするイベント「ブックバースデー」を開催しています。7月16日(金)に開催したイベントの様子をお届けします。
本記事では、7月に発売した書籍のうち、
『なぜ・どうしてがよく分かる わくわく科学実験図鑑』(クリスタル・チャタトン・著/岩田佳代子・訳)
『図解 コンサル一年目が学ぶこと』(大石哲之・著)
『で、結局何が言いたいの?と言わせない ロジカルな文章の書き方超入門』(別所栄吾・著)
『令和四年高島易断シリーズ』(高島易断協同組合・著)
『夢を叶えるイメージマップの作り方』(角谷建耀知・著)
の5冊他について、担当編集者を交えながらお祝いしている様子をお届けします。
司会は、オンラインセールス担当の滝口と、ストアセールス担当の川本です。
夏休みに一冊欲しい! 弊社社員も夢中の「お手軽実験図鑑」とは?
司会 滝口:続いては『なぜ・どうしてがよく分かる わくわく科学実験図鑑』です。
こちら個人的に大注目の一冊なんですけれども、社内でも小学生のお子さんを持つ社員から「これで夏休みの自由研究も工作も、両方楽しく取り組めそう」というコメントを頂いています。
谷口:この時期に並べたい夏にぴったりなワクワクするような装丁ですよね!見た目はすごくライトな感じなんですけど、STEAM教育が上手く取り入れられていて、それが色味で分かるように工夫されているオシャレな一冊です。是非お子さんがいらっしゃる親御さんに手に取って頂きたいですね。

司会 川本:中身も可愛くてワクワクするような感じですよね。
本日はこちらの翻訳を担当された岩田さんからコメントを頂いております。元木さん、こちら読んで頂けますでしょうか?
編集 元木:こんばんは、編集部の元木です。翻訳者の岩田さんからコメントを頂いておりますので、拝読させて頂きます。
Q 翻訳する中で一番工夫した点はなんですか?
「1セント硬貨など、アメリカでは身近にあるものを使った実験が数多くあるのですが、それらを、実験の趣旨を違えることなく、日本で簡単に入手できるものにどう変えていくかということは特に考えました。
また子ども向けの本ですが、解説などは大人の方が読んでも十分に楽しめる本格的な内容になっていますので、それをどの程度までかみ砕いて訳すか、そのバランスには気を付けたつもりです。」
Q どんな読者に届けたいですか?
「科学が好きなお子さんはもちろんですが、科学があまり好きではないお子さん、そしてかつてあまり好きではなかった大人の方にも読んで頂きたいです。本格的な内容がコンパクトにまとまっていて、学生時代、理数系が大の苦手だった私でも楽しく読むことができました。」
編集 元木:こんなメッセージをいただきました。
私も理数系が大の苦手なので(笑)、このコメントにはすごく共感できます!
Q この本に対する想いを伝えてください
「遅まきながら、この本のおかげで科学の楽しさ、面白さを知ることができました。楽しんでほしいという作者の想いが溢れた作品で、その想いを多少ともお伝えすることができていれば幸いです。
どの実験も身近にあるものでできるので、ついやってみたくなり、実際にやってみた実験もいくつかありました。そんなふうに、読む人を魅了していくれる素晴らしい作品だと思います。STEAM教育の一助となれば幸いですし、なにより多くのお子さんに楽しんで頂ければ、こんなに嬉しいことはありません。このように素敵な作品を翻訳する機会を下さった皆様に、この場をお借りしてお礼を申し上げます。」

司会 川本:ありがとうございます。残念ながらお会いすることが出来なかったんですけれど、お言葉を頂くことが出来て嬉しいです!
編集 三谷:STEAM教育というのは世界で注目されている教育でして、これから日本でもはやろうとしているところなんですけれど、日本での第一人者である中島さち子先生にもご推薦を頂けました。
中島先生がおっしゃるのは、「勉強ではなくて、ワクワク楽しむことが一番大事だ」ということで、まさにそれを体現した新刊だと思います。本当に見ているだけで楽しい一冊ができたと思いますので、ぜひお手に取ってご覧頂ければと思います。
司会 川本:いよいよ来週から夏休みに入る学校も多いと聞きましたので、ぜひ多くの方に手に取って頂きたいですね。
司会 滝口:大人の方でも楽しんで頂けるというコメントがありましたが、三つに二つくらいは自分でやりたい実験がありました。これは本当に親子で楽しめるものだと思います。
司会 川本:私も明日、一個やってみます(笑)
ベストセラー『コンサル一年目が学ぶこと』の図解版が登場!
司会 滝口:続いて『図解 コンサル一年目が学ぶこと』担当編集の志摩さんにご登壇頂きたいと思います。
こちらはロングセラー『コンサル一年目が学ぶこと』の図解版ですね!
編集 志摩:元々この本は2014年に発売され、おかげ様で10万部を超えている書籍になっています。タイトルに “コンサル一年目” という言葉が使われているんですけれど、コンサルタントの方以外にも役立つスキルが詰まった内容になっています。
なぜコンサルという言葉がこんなに大きく書かれているのかということなんですが、コンサルティング業界出身の方々には、業界や職種を問わず色んなところで活躍されている方が多いですよね。どうやらコンサルの仕事・技術には、いろんなところに通用する秘密や秘訣が詰まっているというところで、コンサルタントの方々が新人の頃に学ぶ仕事術をぎゅっと凝縮しているのが今回の一冊になっています。
今回図解にすることで、ぐっと読みやすさがアップしました。内容は変わっていないのですが、30項目あった項目が50項目に細分化されて、より一層サクサク読めるようになっています。私も新人の頃にこれを読んでいれば、上司を困らせることはもっと減っただろうな(笑)と、学びの多い一冊でした。
幅広い方々に読んで頂ける内容かと思うので、お勉強用、復習用など、ぜひ様々な使い方をして頂きたいです。
司会 滝口:弊社で『コンサル一年目が学ぶこと』は新入社員向けの定番書になっているのですが、来年からは図解版が定番になるのかな?なんて思っております。この本もこれからたくさんの方に届けていきたいと思います。
電話口で喋る感覚でメールを書くのはNG! シンプルでロジカルな文章を書くには?
司会 川本:それでは続いて、『で、結局何が言いたいの?と言わせない ロジカルな文章の書き方超入門』で、担当編集は安達さんです。
ディスカヴァーでもそうなんですが、リモートワークになってから相手と文章でやり取りする機会はぐっと増えました。その中で活かせるノウハウが盛りだくさんの書籍ですよね。
この中で「すぐに実践してほしい!」といったオススメのポイントはありますか?
編集 安達:昔は電話でコミュニケーションを取っていたところ、いまではメールやLINE、Slackなど、メインの連絡ツールがほとんど「書くこと」になりました。
そして、僕も同じなんですけど、電話のなごりか、どうしても口でしゃべるのと同じ手順で文章を打ち込んでしまうことがあるんですね。それをそのまま発信してしまうと、実は相手の方にとっては理解しづらい文章になっている場合が多くあります。
本書は、ベーシックな文章をロジカルに書く練習をしながら、33個あるテクニックを学んでいける本になっています。
その中で自分が学んで実践しているのが「箇条書き」のテクニックです。長い文章を書くと、どうしてもポイントが散漫になって、一番重要視すべきポイントがわかりにくくなりやすい。そうすると相手の人が要点を読み取れませんし、読み取ってもらえたとしても、あまりよくありませんよね。ここで活きるのが「できるだけ優先順位を付けて箇条書きする」テクニック。こうした取り組みやすいテクニックは、おそらく一読いただければすぐに身につけることができると思います。
このような簡単なものに加えて、他にもロジカルに書くためのテクニックがびっしり詰まっていますので、文章を書くのが苦手という方がいましたら、この本をさらっと読んで頂いて、まずは書くことに自信をつけて頂ければと思います。
司会 川本:自分もSlackでやりとりするときに、あるいはメールで外部の方とやり取りするときに、「文章としては正しいけれど……伝わっているかな、読み取れるかな?」と考えて書き直すことがよくあります。箇条書きをはじめ、他のメソッドを盛り込みながら、月曜日から実践してみたいと思います!
司会 滝口:パラパラめくって取り入れられそうなところから取り入れられるというのもすごくいいところですよね。
編集 安達:基本的には見開き完結になっていますので、どこから読み進めて頂いても大丈夫だと思います。ぜひお手に取って、ご覧いただけますと幸いです。
2022年の世界の動きまで分かる?! 『高島易断シリーズ』が見逃せない!
司会 滝口:続いて発売されることになりました『令和四年 高島易断シリーズ』のご紹介です。
担当編集は、今年初めて本シリーズを編集した元木さんです。
編集 元木:実は私、去年ディスカヴァーに入社したんです。それまで書店で高島易断の本を見かけたことはあったんですけど、実は宗教系の本か何かかなと勘違いしておりまして(笑)そもそも高島易断ってなんなんだ!というところから入って、占いなんだ!100年も歴史があるんだ!と、そんなところからスタートしました。
占いというと、自分のことだけ占う本が多いかと思います。しかし本書は、日本や欧州、世界の情勢まで書かれていて、「2022年が世界的にどんな年になるかを知ることができるスゴイ本なんだ!」と。
あと新たに学ぶこともありました。皆さん吉日を示す「六曜」はよくご存じだと思うんですけど、この本はそれ以外にも「十二直」が掲載されています。実は平安時代~昭和初期までは「六曜」よりこちらのほうが主流だったそうで……そんなことまで載っていて。他にも姓名判断についてですとか、知らなかったことをたくさん知ることができました。
で、ついつい自分の生まれ年のところだけは校正しながら熟読してしまうという……そして姓名判断を読んでいたら、私の名前は凶だということに気づいてショックを受けて……(笑)
一同:(笑)
編集 元木:そんなことをしながら、楽しく仕事をしたのが、『高島易断』でした。一日一日どういう日だとか、そこまで細かく出ている占いって他にはなかなかないと思います。すべてを網羅した占いというのがこの世の中に存在するんだ!と感じ入った一冊です。来年2022年がどうなるのか、気になる方は是非お手に取って頂ければと思います!
「夢の叶え方」を伝えるのに選ばれた舞台が “カレー同好会” だった理由とは?
司会 川本:ラストに紹介するのは『夢を叶えるイメージマップの創り方』です。カレー同好会の奮闘を通して、チャレンジをする、チーム一丸となって取り組むことで開かれる可能性が描かれています。著者の角谷さんは「わかさ生活」の代表取締役の方なんですね?!
編集 村尾:そうなんですよ。この「わかさ生活」という会社の代表取締役の角谷さんはいろんな活動をされているので、是非ご紹介させてください。
ブルーベリーアイのCMでおなじみの「わかさ生活」という会社ですけれども、この会社は社長である角谷さんの号令で、盲導犬の支援や震災支援など、本業以外の様々な活動をされています。その中で、角谷さんご自身やわかさ生活のメッセージを書籍で伝えたいという想いから、今は出版活動にも力を入れています。
角谷さんはご自身でシナリオを学ぶためにシナリオスクールに通われて、会社の経営をやりながら一からシナリオを学ばれたほどなんです。
司会 川本:すごくバイタリティにあふれる方なんですね。
司会 滝口:いまコメントで「なぜカレーだったんでしょう」という質問が(笑)。
編集 村尾:以前刊行した書籍では、ストーリーの中で「夢の見つけ方」を伝えています。今回は「夢の叶え方」を伝えたいと考え、「高校生たちのひと夏の挑戦」というストーリーを通じて分かりやすく正面からストレートに伝えようという想いからうまれたそうです。
ご自身もカレーがもともと好きということもありますし、とっつきやすいテーマを決め、ストーリーを立てることで、メッセージを効果的に伝える、ということを目的として今回はこのようなつくりの書籍となりました。
司会 川本:印度カリー子さんというカレー業界のカリスマの方がいるんですけど、推薦文も頂いていて。カレーファンの界隈もざわつかせたいですね!
あっという間にエンディング! ゲストのお二人と弊社社長からのメッセージ
司会 滝口:楽しい時間もあっという間に過ぎてしまいました。またまだお伺いしたいことがあったんですが。最後にゲストの『「がんばり過ぎて疲れてしまう」がラクになる本』『普通の会社員でもできる 日本版FIRE超入門』の著者のお二方と谷口さんからコメントを頂きたいと思います!
松浦真澄さん:私たちって様々な事情がある中でがんばっているんだと思います。しかし「がんばるのをやめましょうよ」というわけにもいきませんので……どんな風にがんばりと付き合うかを考えるきっかけになる本になればいいなと思います。
山崎俊輔さん:「FIRE」っていう流行りのキーワードを使ってはいるんですが、やはり真面目に働いている普通の人が、お金の問題で心配せずに幸せになってほしいですし、そのための助けになる情報提供をしたいなと。
昔は自分自身、全然貯金できていなくて。それを反省して30歳でFPの資格を取ったところがそもそものはじまりでした。20代や30代の方に何らかのきっかけで手に取って頂き、お金の問題からできるだけ早く脱出してもらって、楽しく仕事できるようになって頂ければなと思います。
谷口:今日は本当にお二方の制作秘話や想いをお伺いできて、本当に嬉しい時間でした。たくさんの新刊が、読者の皆さんの行動が変わるきっかけになってくれたら嬉しいなと思います。本日は本当にありがとうございました。
一同:ありがとうございました!
~~~
▼次回のブックバースデー情報▼
9月のブックバースデーの詳細は、ディスカヴァー公式サイトのイベントページにてお知らせいたします。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?