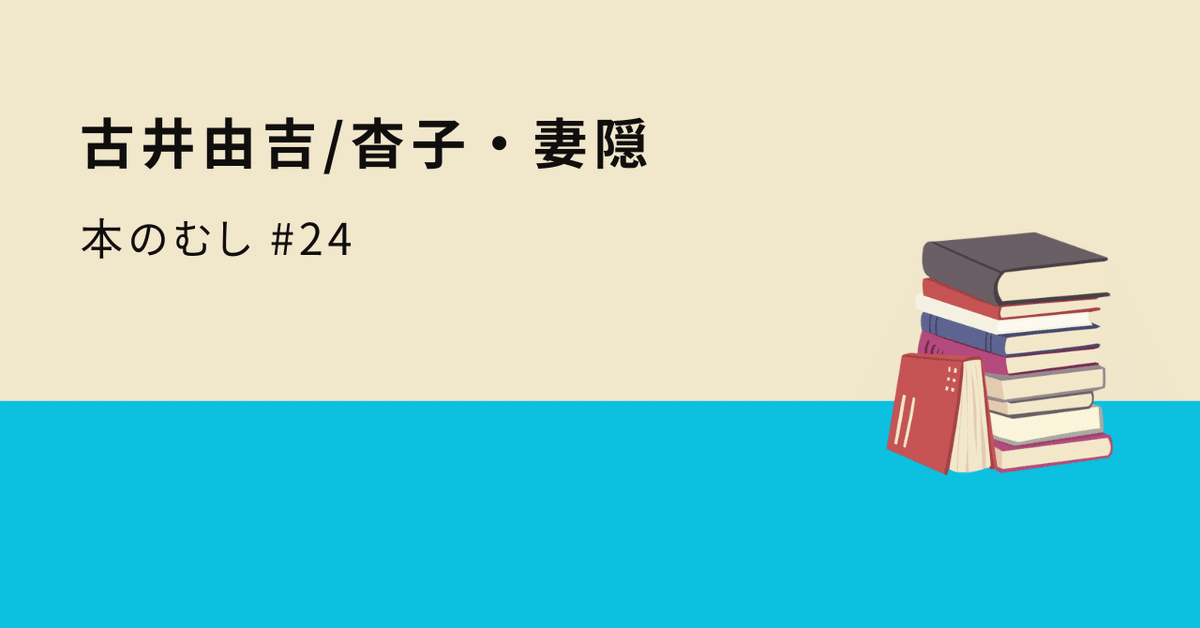
【おすすめ本】「わからない」をしりたくて(古井由吉/杳子・妻隠)
今週もこんにちは。関東は今週大雪だったみたいですね。みなさん元気でお過ごしでしょうか。
今回取り上げるのは古井由吉「杳子・妻隠」。古井さんは「杳子」で1971年に芥川賞を受賞しています。新潮文庫のオビには、ピース又吉さんが「脳が揺れ比喩ではなく実際にめまいを感じました」という応援文を寄せています。
「杳子」は精神を病む杳子と男子大学生の壊れやすい恋を描いた作品。「妻隠」も男女間の機微がテーマですが、こちらは夫婦間で、二人の心の奥深くにあるズレが日常の中で炙り出されていきます。
▼▼今回の本▼▼
又吉さんの言う「めまい」は分かるような気がします。例えば、次の文章。
夏には誰も踏みこまない繁みの中から白い姿が浮び上がり、夏草に着物の裾を絡め取られてか、立ち止まって足もとに目を落した。軀を軽くよじって裾のうしろを眺める姿の、襟元からのぞいた肌がやさしかった。それから、片手で裾をからげ、もう片手で草を押し分け、すこし及び腰で出てくるのを見ると、老婆だった。
ぼうっと白い姿が見えてきて、下を向く。上品な肌が見える。近づいてくる。それが「老婆だった」で色鮮やかになります。遠くをぼんやり眺めていたのに、急に現実へ引きずり出された感じ。この落差がめまいを生んでいる気がします。
一個のものをじっと見るうちに、別のものに見えてくる。知っているものが知らないものになり、知らないものが知っているものになる。映像が万華鏡のように変わりゆくさまが、作品の色気にもなっています。
ある夜、杳子のために気を張りつめているうちに、周囲の何でもないいとなみが、ひとつひとついかにも困難な業として目に映ってきた。
とにかく男から目が離せなくて、礼子はカーテンの蔭から長いこと見つめていた。それから、段々に、夫かもしれないと思いはじめた。(…)ところが、シーツに頬を埋めて眠っている横顔をじっと見つめているうちに、段々にまた勘がおかしくなって、ふだん夫が目の前のこの顔に比べてどんな顔をしてるのか、感じ分けがつかないような、そんな空恐ろしい気持になって歩みを止めた。
杳子が振り返った。顔つきが変わっていた。
こわい。ゾクゾクする。古井さんの文章は「わかる」と「わからない」のあいだを自由に往来しているようにも見えます。僕らがわかった気になっている世界は、見えかたによっていかようにも変化するのだと教えてくれる一冊です。
▼▼前回の本▼▼
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
