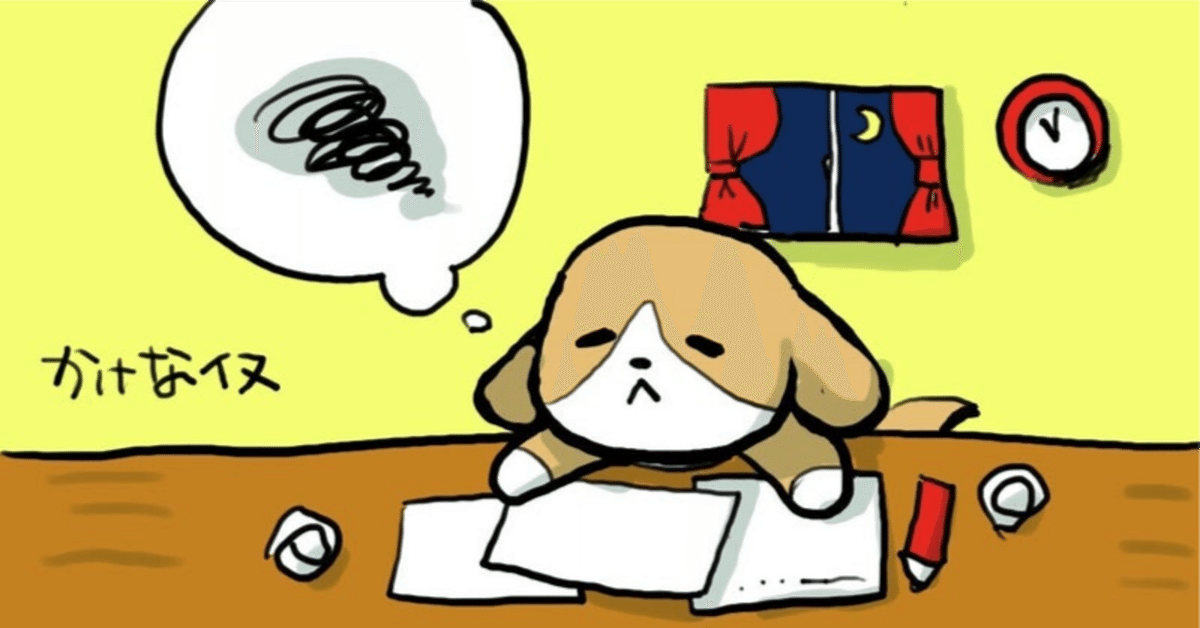
書けない人にどうアドバイスをしようか
友人がnoteを始めた。自分はnoteが(もっと言うと書くことが)大好きなので、共通の趣味を持ってくれたのが凄く嬉しかった。
しかし、その友人はnoteの更新を辞めてしまった。実生活の忙しさとかもあったのだろうが、大きな理由としては、「書けない」ことのようだった。
この辞めた理由が、「面白くない」とか「忙しい」とかだったら納得できる。娯楽にあふれる現代で、キーボードをカタカタ打って金にもならない文章を書くことを楽しむ自分みたいな人間のほうが特殊だ。
でも、理由が「書けない」ということが凄く悔しかった。つまるところ、少しは「書きたいな、書けたら楽しいだろうな」と思ってくれているはずだから。書くことに対して、マイナスな感情は抱いていないはずなのだ。
「頭がこんがらがる」「何を書きたいのか分からなくなる」そう話す友人に対して自分は適切なアドバイスをできなかった。ことばが好きで、普段長文ばっか書いているんだから、こういう時に気の利いた言葉を返せれば良いののに。何も言葉は出てこなかった。
やはり、「話す」ではなダメだ。頭の回転が遅い自分にとっては、会話の中で適切なアドバイスは難しすぎる。「書く」ことで考えてみようと思う。「書けない」という人へのアドバイスを。
プロの意見を聞いてみる
と言っても、自分1人の力で、ズバリな解決策を出せるとは思えない。今回はプロのライターさんの力も借りようと思う。
古賀史健さんが書いた『さみしい夜にはペンを持て』という本からいくつか引用したい。
この本は、ライターである古賀史健さんが、中学生(10代)に向けて書いた本。ライターを志向する人のような、本格的に「書くこと」に向き合った人に対して書かれた過去作『取材・執筆・推敲』とは違い、今作品はそもそも「書くこと」をやったことがない人に向けて書かれた本だ。
著者が発売に際して書いたnoteの記事にこのような記載がある。
これは作文やレポート、読書感想文を上手に書くための本ではありません。書くことを通じて自分と対話し、自分を受け入れ、みずからの生を肯定していく本です。
様々な自分の悩みを、「書くこと」で救っていこうという、そういう話だ。
この本はジャンルとしては小説となっている。海の生物たちをキャラクター化したファンタジー世界を舞台にした作品。
上手く喋れず、緊張するとゆでタコのように真っ赤になってしまうことがコンプレックスの主人公、「タコジロー」。そんな彼が、ある日公園で「ヤドカリのおじさん」と出会い、自分の悩みを打ち明けていく。ヤドカリおじさんは「日記を書いてみよう」とタコジローにアドバイスする。
タコジローは、ヤドカリおじさんと一緒に少しずつ日記を書くことで、自分を救っていく。コンプレックスを解消していく。これが本作のおおまかなストーリーだ。
書けないなら、まずなにをするか
と言っても、タコジローは最初から日記を楽しく書けたわけではない。おじさんと出会ったその日、タコジローは日記を書いてみる。その後、おじさんと再び会うのだが、その際にタコジローが、書くことの難しさを愚痴る場面がある。
「なんていうか、最初の1行で手が止まっちゃうんだよね。なにをどう書いたらいいかわからないっていうか」
そう愚痴をこぼすタコジローに、おじさんは優しく問いかける。どう感じたのかと。タコジローは答える。
「たのしかったし、くやしい」
「くやしい?」
「だってさ、きっとおじさんに言わせると、ぼくが書けなかったのも『考え』が足りないからなんでしょ?そこに納得がいかないっていうか、なんだかバカにされている気がする。ぼくだってそれなりに考えているのに。」
このやり取りを見て、友人を思い出してしまった。
彼も書けない自分を卑下してしまっていた。かく言う自分も、自分の考えがうまくまとめきれずに筆が止まったとき、タコジローと同じような気分になることも多々ある。この時の気持ちは同じく「悔しい」だ。
心のスケッチをしてみよう
それに対して、ヤドカリおじさんはアドバイスをする。「心のスケッチをすればよい」と。
今日のできごと、と言っても1日は長い。さまざまな事件があったりなかったり。そんな長い時間を振り返りながら、「今」の自分がなにを「思っている」のか、というのを書くのは難しい。
でも、美味しいお昼ごはんを食べた時のきもち。友達から話かけられたきもち。今日のできごとの、一瞬のできごとでもよい。「昔」のその瞬間の自分がなにを「思っていた」のかを書いてみよう、とアドバイスをする。道ばたの景色をスケッチするように、できごとのその瞬間の心の景色をスケッチすれば良いと。
要するに、テーマを決めてそこに集中して書きなさい、という話だ。最初は短くても良い。どういうふうに感じたのかを、ひたすらに掘り下げれば良い。そこには、論理的な構成力や、頭の良さは関係ない。
その時感じた気持ちを順にたどっていけば、まるで物語のようにきれいな流れになる。ちょっとした飛躍があってもよい。その飛躍も、自分の個性なのだから。その個性は、自分も他人も読んでおもしろいものになるはず。
思えば、noteを今まで続けてこれたのは、自分は作品の感想を書いていこう、という明確な意志があったのが良かったかもしれない。日記や漠然としたエッセイを書こう、という目標だと、なにを書けばいいか分からず、続かなかっただろう。
作品に触れたときに自分が思ったことをひたすらに書く。そうしていくうちに、書くことに慣れてきた。1つのできごとから感じた様々な感情を書いていけば良いのだとわかってきた。
いまだからこそ雑多に色々と書けるが、それは狭いテーマで何度も書いてきたからだろうなと思う。
読者がいるということ
上記は書くための実践的なアドバイス。ただ書くだけではなく、noteを続けていくと確実に存在するメリットについてもこの本は書いている。もちろん、noteというサービスの話をしているわけではない。
どちらかと言うと、この本は自分のためだけの日記を書くことを推奨している。「他人に見せる文章は絶対に偽りが入る。だから、まずは自分しか読まない日記を書いて、自分と向き合おう」とヤドカリおじさんは言う。
これは正しい。日記ほど自分の心に向き合う瞬間はないし、他人に見せる、となるとハードルが上がってそこで尻込みして書くことを辞めてしまう人もいるだろう。
でも、他人に見せる文章を書くことのメリットも確かに存在するとは思う。それは、本書も否定していない。
ヤドカリおじさんはタコジローに対してこう語る。
「でもさ、仮に『読者がひとりもいない日記』なんてものがあったら、どうなると思う?つまり、自分も読まないし、ほかのだれかも読まない。ただ書かれて、ただ捨てられていくだけ、っていう日記があったとしたら」
「うーん。ほとんどの日記はそれに近いような気もするけど……」
「そうするとね、『わかってもらおう』としなくなるんだ」
これはすごく本質的なことばだと思う。人間というのは怠惰な生き物だ。特に、自分のような意志が弱い人間は、「誰かに見せる」ことを意識しないと、すぐに適当な文章を書いて満足してしまうだろう。
本書では、「将来の自分」を読者として想定して、「わかってもらう」ように努力をしようという話になるが、なかなかにこれもハードルが高い。だって、将来の自分は書き上げた直後に反応はくれないし、何より実感しづらい。
だからこそ、自分はnoteのようなサービスで自分の文章を何かしら公にすることは大切だと思っている。すごく大きなモチベになるはずだ。
この考え、思いを伝えたい。自分という存在を「わかってもらいたい」。その一心で考えぬいて書き上げた文章に、「イイね」がつくと、最高に嬉しい。だから自分に向き合い、とことん文章を考える。そうすると、さらに良い文章が書けて、評価がされて…
そんな良いサイクルも、外に向けて発信することでまわりはじめると思うのだ。
…(中略)ぼくたちは、わかってもらおうとするから、自分の感情を整理する。わかってもらおうとするから、ことばのペン先を補足してことばの色彩を豊かにする。すべては、読者にわかってもらうためなんだ」
シンプルにまとめると
本書は、冒頭に書いた通り、技術的なことをまとめた本ではない。タコジローのような自分のことが好きになれない人たちにとって、書くことがどれだけ救いになるか、ということを書いた本である。
その中でも、「実際に書こうとして書けない人へのアドバイス」を選んで抜き出した。本書のことばを借りながら、自分なりに考えると
テーマを絞って、それに対して感じたことを深掘りして書く
それによって自分を「わかってもらう」ために、ということを意識して書く
この2つだと思う。論理的な構成だとか、表現力だとか、そんなものは後回しで良い。この2つがしっかりと守れていれば、誰かには刺さる文章なはずだ。少なくとも、自分自身には。
本当はもっとこの本には素敵な文書がたくさんあった。それらを全部紹介したかった。話すことばと書くことばの違いだったり、表現力の話だったり、考えることの勇気だったり。
でも、自分がこの本を読んで一番感じたのは、書くことを続けたい、という思いだ。この本は「書くことをはじめてほしい」という目的で書かれているのかもしれないが、一番辛いのは書くことを「つづける」ことだと思う。
書けなくなったとき、それでも書き続けるためにはどうすればよいか。それも凄く重要なことなのだ。書き出しは友人の話を出したが、将来の自分にも向けてこの記事は書いている。何かに詰まったときに、ここに帰れるように。
最後にヤドカリおじさんの素敵なセリフで締めようと思う。
「そう。半年後、1年後、3年後、もしかしたら10年後や20年後、きっとタコジローくんはその日記を読み返す。真剣に生きていた『あのときの自分』と向き合うことになる。
これはね、書き続けた者にだけ与えられる、最高のプレゼントなんだ」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
