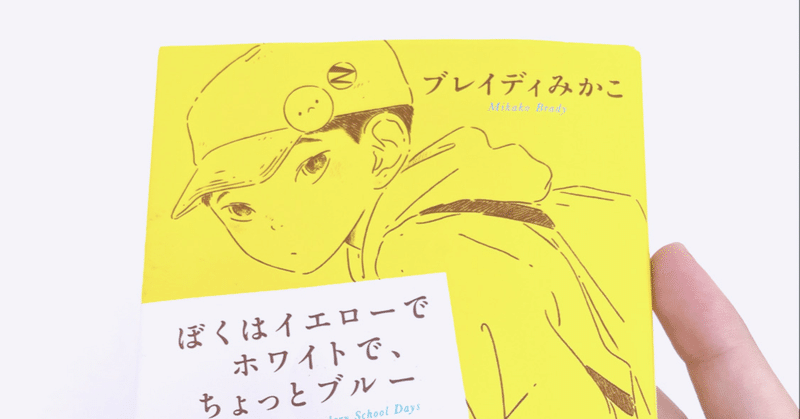
No.14 『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』今旬の本。
『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』は、ブレイディみかこが描いたエッセイである。
何を隠そうこのエッセイ、実は今とても旬な、いわゆるバズっている本なのだ。
気が付けばアマゾンのレビューは3000件を超え、瞬く間に文庫化までされた。さらには最近、『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー2』まで発売された。めちゃくちゃにノリに乗っている。ついでにその波にちゃっかり私も乗っているのだが。
そんな本作がなぜこんなにもバズり、人々の心をつかんでいるのだろうか。
今回はこの本の魅力や、書いてある内容について自分の意見を述べていきたい。
初めてエッセイのレビューをするということで、話の方向性がかなりずれているのはご了承いただきたい。
え?元からおめぇの文章は一貫性がないだって?だまらっしゃい。
私が想像していた英国との乖離
始めに皆さんは、英国についての具体的なイメージや印象はなんですか、と聞かれたらどのように話すだろうか。
正直なところ、私が想像していた英国のイメージは
「優雅」 「貴族」 「ご飯が美味しくない」(最後は大失礼)
のように、古めかしいステレオタイプに囚われていたと思う。実際に行ったことはないので、もちろん一部の地域にはこれらのイメージが当てはまる場合もあると思うが。
このエッセイは、
・東洋人(オリエンタル)の著者
・白人の配偶者
・その息子
という家族構成をしており、この息子の成長やそこでのエピソードを語ったものである。
当時小学6年生だった息子は配偶者が圧倒的なカトリックだからという理由で、国内有数のカトリック校に通っていた。
特に心身に異常もなくすくすくと育っていた息子は、そのままならエレベーター方式によってカトリックの中学へと進学するはずだった。
しかし彼の友達の一人が元底辺中学校に行くと言い出し、学校見学へいったのち、息子は当初行くはずだったカトリック校をやめ、元底辺中学校に入学することになる。
ここで語られていくものは、どちらかというと英国のリアルな政治・経済情勢であったり、英国だからこその人種問題などである。
日本は移民の受け入れにあまり寛容ではないこともあり、学校に白人や黒人の子供がいるという状況はあまりないように思う一方でいろんな人種が存在している息子たちの中学校では、レイシズムの問題が当たり前のように存在している。
例を挙げると、「チャヴ」という白人労働階級への蔑称や(オックスフォード英英辞典には、「チャヴとは無礼で粗野な振る舞いに象徴される下級階層の若者」と定義されてるらしい。マジ???)「イエローモンキー」、日本人などの黄色人種への差別的発言等々がある。普段このようなワードさえ耳にしない私たちにとってこれらの描写は結構新鮮で、刺さる。奥深くへと。
ティム(息子の友達)のリュックの底が破れてノートが飛び出しているのを見たダニエル(友達)が「貧乏人」と笑ったので、ティムが「ファッキン・ハンキ―」(中欧・東欧出身者への蔑称)と言い返し、逆上したダニエルがティムにとびかかって取っ組み合いの喧嘩になったのである。
このシーンはとても印象的だった。日本でもいじめや悪口はあるが、少なくとも人種がほぼ統一されている私たちが被害者に対して人種の問題上で見つけることの出来る差異はほぼないと言ってもいいだろう。上の喧嘩は、どちらも人種が異なる英国だからこそ起きた問題の一つであると言える。
それに加えて家庭ごとの経済状況に応じて生じる貧困問題なども絡んでくる。ほとんどの男女がともに迎える第二成長期に応じて買い替えなければならない制服や女子生徒の生理に使用するナプキンなど。
2016年~2017年度の英国では、2010年に政権を奪還した保守党政権の大規模な緊縮財政によって、当時約230万人であった貧困層の子供の数はかなり増えてしまったと言われている。
厳密には、平均収入の60%以下の所得の家庭で暮らす子供の数が410万人に達していた。これは英国の子供の総人口の約3分の1にものぼる数である。
英国の財政状況を調べる機会もそんなにないので、ただただほえーって感じだった。
日本も近年、富裕層と貧困層の所得、生活格差がいろんなところで囁かれているが、この一文について考えてみると(詳しく調べてないので、正確な情報かは定かではない)、どうやら英国の格差問題も深刻であるらしいことが分かってもらえるだろう。
このエッセイを読んでいると、いかに自分が世界のニュースについて浅い知見しか持ち合わせていないかということがはっきりと分かる。これがリアルな英国なのだ。
アイデンティティ
しかし、リアルな英国も悪いところばかりではない。いやむしろ、良いところも驚くほど多い。
私が読んでいて特に英国の良さを感じたのは、「アイデンティティ」である。これを辞書に照らし合わせると、
「自分は何者なのか」「自己同一性」
などが出てくる。他にも「自分らしさ」、みたいな意味合いで使われるようになってきたこの言葉であるが、彼らが生きている英国では、このアイデンティティがとてもはっきりとしている。
アイデンティティが著しく乏しい私たち日本人と比較すると分かりやすいと思う。英国にいる彼らは、時にはそれを歌にしたり、ポエムやラップ、ジェスチャーなど、ありとあらゆる方法で自分たちの想いを表現するし、デモにも積極的に参加する。
そしてここが一番なのだが、彼らはそれらの発言したことに対して、真摯に向き合う。同じ人間として。
良く言えばおしとやか、慎ましい日本人であるが、どうしても私たちの間には「壁」のようなものが介在しているのではないか、と思う時がある。それは電車に乗っているときや横断歩道を待っている時、学校や会社など、日常的に生じている。その「壁」は、少しだけ、でも確実に私たちの精神的距離を離れさせている。それは飲食店に置いてあるパーテーションのようでもあり、マスクで本当の表情が見えない私たちのようでもあるけれど。私はこの本を読み進めて、時には彼らのような情熱を持って生きること、「壁」をなくして一人の人間として発言していくことも大切なのではないかと感じたりもした。
息子の話
この息子はハーフということもあってか、英国でも日本でも偏見に満ちた目にさらされることが多い。(「ハーフ」の言葉そのものが失礼な場合もあるらしい。ちなみに息子は「ハーフ・アンド・ハーフ」だと主張していた)
その体験のためか、この息子は一人の子を放っておけない、とても思慮深く優しい子に育っており、本作の中でもそれはリアルな英国で、またはリアルな日本において物語の優しさを感じさせるスパイスのような役割を果たしている。
「エンパシーとは、他人の靴を履いてみることだ。」
他人の靴を履いてみる努力を人間にさせるもの。そのひと踏ん張りをさせる原動力。それこそが善意、いや善意に近い何かではないのかなと考えている。
この一文は私がかなり好きなもののひとつであり、息子の優しさが存分に感じられるシーンだ。
エンパシーとは、シンパシーと似て非なるワードの一つで、シンパシーは「身分、経済などの様々な要因において貧困である人に対して同情、共感を寄せる」ことであるのに対し、エンパシーは
「自分とは異なる人種、性格、価値観の人を理解しようとする力、知的作業のこと」と書かれている。というよりかは自分はそのように解釈させてもらった。
エンパシーはまだ日本には浸透していないが私はこのシーンを読んで、かわいそうな子に自然と共感や同情を誘うという意味合いで使用されるシンパシーではなく、自分とは異なる立場や環境にいるひとりひとりの人間に対して想像する力であり、知的作業であるエンパシーを自分も身に着けていきたいし、実際に使っていきたいなと思った。
「己の欲せざる所、人に施す勿れ」といったのは孔子だが、彼が学校の宿題で書いた、「他人の靴を履いてみる」という言葉。これは人間の真理なのではないだろうか。
そこに中学生の段階で気付くことが出来ている息子はとても賢いし、優しいんだろうなと思う。そしてその優しさは、次に私が紹介するであろう『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー2』にも表れている。
おわりに
正直、この作品の中にはとてつもなく多くのテーマや意思が存在していて、それをひとつひとつ抽出して考えていくだけで物を書くことが出来そうだ。
それほどまでに様々な考え方が描かれている本作、その中から学べることや感じることはここまで読んでくださったあなたの中にもきっとあるはずだ。
これを読んで実際に手に取ってみようと思って下さったのなら、私もこれを書いた甲斐があるというものだ。
結構色々語ってしまったので、今回はこの辺にしておこうと思う。次回は彼女の最新作であるシリーズの続編について語っていこうと思うので、その時にお会いしよう。それでは、良い一日を。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
