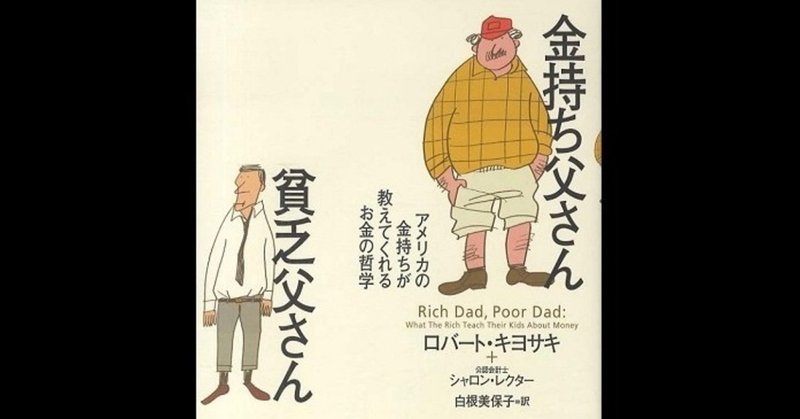
「金持ち父さん貧乏父さん」を読んで。Vol.1
ども。超ひよっこブロガーのでぽろんです('ω')ノ
みなみなさまの手で立派な鶏に育て上げてください。
さて、今回はタイトルの通り読書感想文です。感想文て。
読書備忘録にしよう。うん。思い出したい時にまた同じ本読むのもメンドくさいので、ここでアウトプットしながらのインプットして、忘れたらここに読みに来るっていう場所にします。好きに使わせてつかあさい。
最近、お金の勉強をし始めて、何冊か読了していってるんですが、その中でもこの「金持ち父さん貧乏父さん」は秀逸でした。
なんて言うんでしょうか、著作物に見られるようなキラーワードとかそういうのが一切ないんです。「お金持ちになるためのマニュアル」みたいなイメージがあります。しかも、おそらくは(やれるならば)正しいと思われる。
かといってまったく堅苦しくなく、ちょくちょく対話形式や図解が出てくることもあって、ビジネス書の中で最もワクワクしながら読めた本でした。
著者であるロバート・キヨサキ氏は二人の父親がいます。
と言っても、一人は実父と、もう一人は友達のお父さんで、血縁関係にはないのですが。
高い教育を受けた実父と、ハイスクールも出ていないもう一人の父親。
そしてこの本のタイトルにもある「金持ち父さん」のほうがハイスクールも出ていない友達の父さんで、「貧乏父さん」のほうが3つの大学をはしごして、すべて奨学金でまかなうほど成績優秀だったほうの実の父さんです。
キヨサキ氏は子供の頃から大人になるまで、二人の父親に学び続けます。(貧乏父さんの方は反面教師として)
彼は二人の父親の言うことがあまりに違うので戸惑います。
一方の父がよく「金への執着は悪の根源だ」と言っていたのに対し、もう一方の父は「金がないことこそが悪の根源だ」と言います。
二人の父親がどちらも大好きだった少年は、いつも二人がまったく違う事を言ってくるので懸命に考え、自分で判断を下してきました。しかし、そのおかげで、ひとつの考えを簡単に受け入れたりするよりも、自分で選択することのほうがずっと価値あることだと知るのです。
他にも印象に残った二人の父親の比較を列挙してみます。
父のうち一方は「それを買うためのお金はない」と言うのに対し、もう一方の父は「どうやったらそれを買うためのお金を作り出せるか?」と言うべきだと諭した。
一方は「金持ちはお金に困っている人を助けるためにもっと税金を支払うべきだ」と言うのに対し、もう一方は「税金は生産する者を罰し、生産しない者に褒美をやるものだ」と言った。
一方は「懸命に学べ、そうすればいい会社に入れる」と言うのに対し、もう一方は「懸命に学べ、そうすればいい会社を買える」と励ました。
一方は「私にお金がないのは子供がいるせいだ」と言うのに対し、もう一方は「私が金持ちなのは子供がいるおかげだ」と言った。
一方は「食事中に金の話などするな」と言うのに対し、もう一方はお金やビジネスの話を食卓でするのを大いに奨励していた。
一方は「この家は私たちにとって最大の投資であり、最大の資産だ」と言うのに対し、もう一方は「この家は負債だ。持ち家が自分にとって最大の資産だという人は大いに問題がある」と言った。
一方の父は、会社や政府が自分たちの面倒を見てくれると信じて疑わなかった。もう一方は、経済的に100%「自分に依存する」ことが大事だと考えていた。
一方の父は、いい仕事につくための上手な履歴書の書き方を教えてくれた。もう一方は、自分で仕事を生みだすためのビジネスプラン、投資プランの書き方を教えてくれた。
一方は「私は絶対金持ちになれない」と言ってはお金に困ってばかりいたのに対し、もう一方は金持ちになる前から「私は金持ちだ。金持ちはそんなことはしない」と言い切っていた。
ごく個人的な印象ですが、なんとなく後者の父さんのほうが魅力的な大人に映ります。真面目一辺倒だけではないというか。
最後のなんて引き寄せ的発想で僕は大好きですね。以前「僕のメンターシリーズ2『鴨頭嘉人』」で紹介した鴨頭さんも同じことを言ってました。43歳にしてマクドナルドを辞めて、講演家になることを決めた収入も仲間も顧客も講演回数もゼロの時に、日本一の講演家だったらこうするだろうと徹底的に考え、その状態を先にもうやっていた、と。
はっ! 開いた本のページをよくよく見てみたら、まだ10分の1も進んでないではありませんか。このままのペースでは2万文字を超えてしまいます。ここからは特に個人的に忘れたくない備忘録として記しておきます。
ファイナンシャル・リテラシー
この本の中で最も重要な基礎がこれです。何度も何度も出て来ます。ファイナンシャル・リテラシーは日本語訳で「お金に関する識字率」ですが、例えばあるものが「資産」なのか「負債」なのか、高い教育を受けた大人でも中々見抜けるものではないのが、この言葉の浅からぬところです。
たとえば、ある高級外車を負債だと捉える人もいれば、3時間で腐ってしまう魚を大量に強制的に購入させられても(どんな状況)それを資産だと見なせる人もいるわけで、その人の知識や行動力や立場など万別の状況があるために、一概にどれが「資産」でどれが「負債」と言えないところがあるんでしょう。「その人にとって」という前置きがつくということでしょうか。
で、具体的にこの識字率を上げるのには、次の4つの能力が重要であるとキヨサキ氏は言います。
1.会計力
細かいところに気を配る能力。
具体的には、貸借対照表や損益計算書といった財務諸表を読んで理解できる力を示す。これが高ければ、いかなる類のビジネスにおいても、その強みと弱みを見極めることができる。左脳の働きを要する。
2.投資力
「お金がお金を作る科学」を知る能力。
投資には戦略と方式が必要とされる。この技能には右脳の働き、つまり想像的な力が求められる。
3.市場の理解力
「需要と供給の科学」を知る能力。
市場を理解するには、その「人為的」側面を知る必要がある。つまり「人の感情を読む」側面である。
1996年のクリスマス、「エルモ人形」が爆発的ヒットを記録した。これは人気のテレビ番組「セサミストリート」のキャラクターをもとにした人形で、子供たちはみんなこれを欲しがり、クリスマスにほしいプレゼントリストの1番上に持って来た。
あちこちの店舗を走り回った親たちの中には、メーカーが子供の所有欲をそそるために、クリスマスを狙って広告を出す一方で、商品の出荷をわざと遅らせているのではないかと疑う人もいた。需要が増え続けても在庫はなく、途方に暮れた親たち相手にひと儲けしようと、高値で転売する者まで現れる。
運悪く人形を買えなかった親たちは、他のおもちゃを買うしかなかった。エルモ人形のこの想像を絶する人気は、需要と供給の経済論をよく物語っている。株、債券、不動産、ベースボールカードなどの市場も同じで、4つの能力のうち最もセンスを問われるのがこの力である。
4.法律力
会計、投資、市場に関する専門知識を現実に即する能力。
たとえば「会社」という殻で包むことで、資産を大幅に増やすのに役立つ。
会社を持つことで得られる税の優遇措置や、保護といったことに関する知識を有する人間は、そうでない多くの人に比べて速く金持ちになれる。その違いは歩くのと飛ぶのとほどの開きがある。長期的に見た場合、その差は非常に大きい。
はっ! すいません、またやってしまいました。全然書き足りないので2回に分けます。3000文字以上書くと体調が優れなくなるので。
次回は実践編のようなもので、「乗り越えるべき5つの障害」と「スタートを切るための10のステップ」をお送りいたします。
ではまた('ω')ノ
サポート大歓迎です! そりゃそうか!😆 頂いた暁には、自分の音楽か『しもぶくりん』への「やる気スポンサー」としてなるべく(なるべく?)覚えておきます✋ 具体的には嫁のさらなるぜい肉に変わります。
