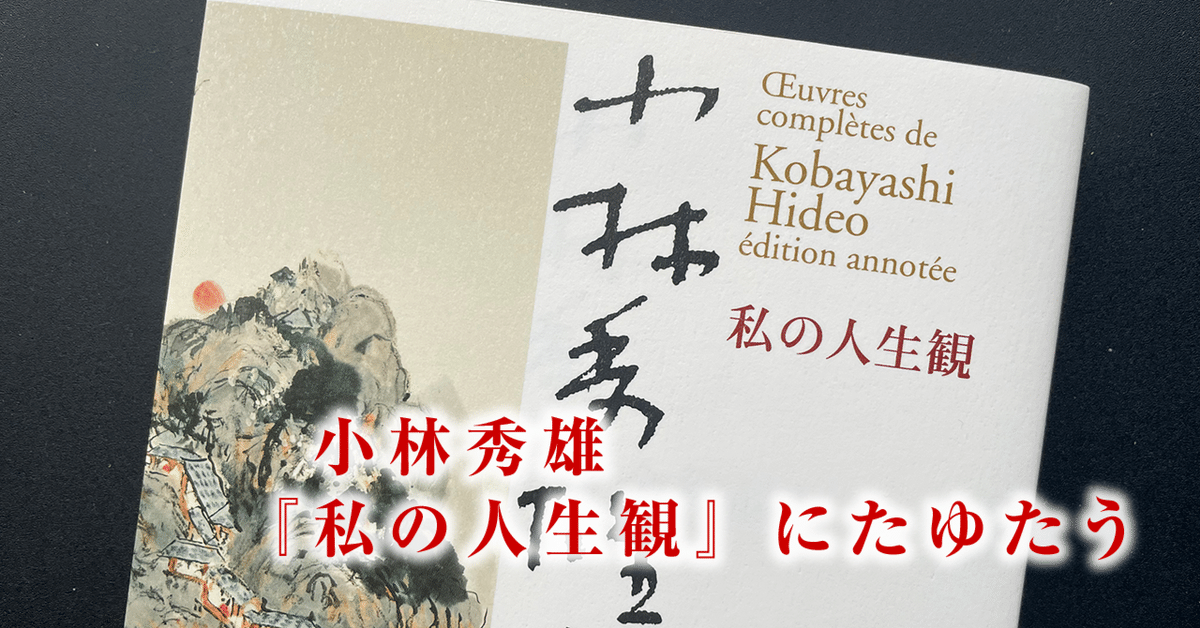
小林秀雄からベルクソンの森へ分け入る
我が国の知識人の政治的関心というものはまことに心細い、という事がしきりに言われている。(中略)だが、この問題には、世人が注意したがらぬもう一つの側面がある様だ。(中略)ベルグソンが、晩年の或る著述の中で、これからの世にも大芸術家、大科学者が生まれるかも知れないが、大政治家というものは、もう生れまい、と言っております。
Henri Bergson。19世紀半ばから20世紀半ばまで活躍したフランスの哲学者で、1927年にはノーベル文学賞も受賞している。近年では原語の発音に近い「アンリ・ベルクソン」と表記することが多いが、小林秀雄は常に「ベルグソン」と表記する。
小林秀雄が若い頃から晩年まで、熟読玩味したのがベルクソンの著作である。小林秀雄の亡き後の1992(平成4)年、蔵書の一部は遺族によって成城大学の成城学園教育研究所に寄贈された。そこにはベルクソン全集はもちろん、主張著書すべての原書が含まれていたという。
実際、作品中にもベルクソンの言葉を数多く引用している。「小林秀雄全作品」においては、1958(昭和33)年から56回にわたって雑誌「新潮」に連載したものの、未完となったベルグソン論『感想』が別巻1と別巻2に収録されている。そのほかにも、小林秀雄の処女小説である『蛸の自殺』からはじまり、講演文学として名高い『信ずることと知ること』、初対面の数学者・岡潔と意気投合し半日かけて語り合った『対談/人間の建設 岡潔・小林秀雄』や講演CDにも収録されている『現代思想について』など、30以上の作品で言及している。
この『私の人生観』においては、大きく分ければ3ヶ所にベルクソンが登場する。最初がp170で政治について。次がp177から知覚・visionについて。さらにp185から哲学者の言葉について論じている。いずれもベルクソンの思想を知らなくても読める内容ではある。だが、これをきっかけに「小林秀雄の一読者」という視点で、ベルクソンの著作にも触れてみようと思う。ベルクソンという深い森に分け入るのは、ちょっと恐ろしいが、楽しみでもある。
(つづく)
まずはご遠慮なくコメントをお寄せください。「手紙」も、手書きでなくても大丈夫。あなたの声を聞かせてください。
