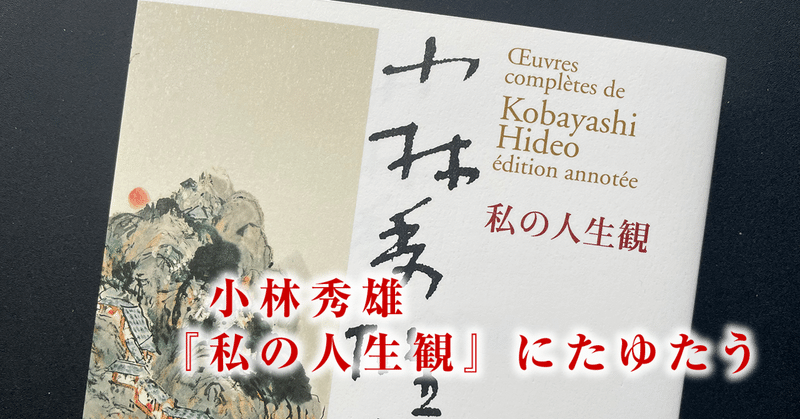
「器用」を極めたから、師匠はいない
宮本武蔵が著わした『五輪書』の「地の巻」にある、兵法の道を学ぶ心がけ九箇条のなかで、小林秀雄がまず触れたのは、第三条と第四条だ。
第三に、諸芸にさはる所、
第四に、諸識の道を知る事、
(第三に、広く諸芸にも触れる所、
第四に、諸々の職業の道を知ること)
兵法を極めたければ、逆に兵法のほかの道にも通じていなければならないし、また他の職業など、広く社会にも通じていなければならないという。ここを小林秀雄は「『道の器用』は剣術に限らない。諸職の道にそれぞれ独特の器用がある」と解釈する。
第七に、目に見えぬ所をさとつてしる事、
(第七に、目に見えないところを覚って知ること)
これは、『私の人生観』で滔々と述べてきた「心眼」のことである。小林秀雄は「器用という観念の拡りは目で見えるが、この観念の深さ、様々な異質の器用の其処に隠れた関聯は、諸芸にさわる事によって悟らねばならぬ」というように、第三条と結びつけて考える。
宮本武蔵はこの九箇条の前に、「兵法の利にまかせて諸芸諸能の道となせば、万事におゐて我に師匠なし」と述べている。兵法の道を極めたのと同じ「器用」の深め方をもって、他のさまざまな芸能に取り組んでいるので、自分には師匠というものがいないというのだ。「諸芸諸能」は水墨画、茶の湯、連歌などである。

小林秀雄は「今日残っている彼の画が、彼のさわった諸芸の一端を証しているのは言う迄もないが、これは本格の一流の絵であって、達人の余技という様な性質のものではない」と褒めている。
このような言葉や絵をもって、小林秀雄は宮本武蔵について、思想も諸職諸芸の一つであり、その「器用」を追究していると考える。思想とは一つの行為であり、勝つ行為である。そして一人に勝つということは、千人万人に勝つということであり、つまりは己に勝つことだという。
この「器用」の極め方は、どこか既視感がある。経験を重んじる、小林秀雄の批評の極め方である。
(つづく)
まずはご遠慮なくコメントをお寄せください。「手紙」も、手書きでなくても大丈夫。あなたの声を聞かせてください。
