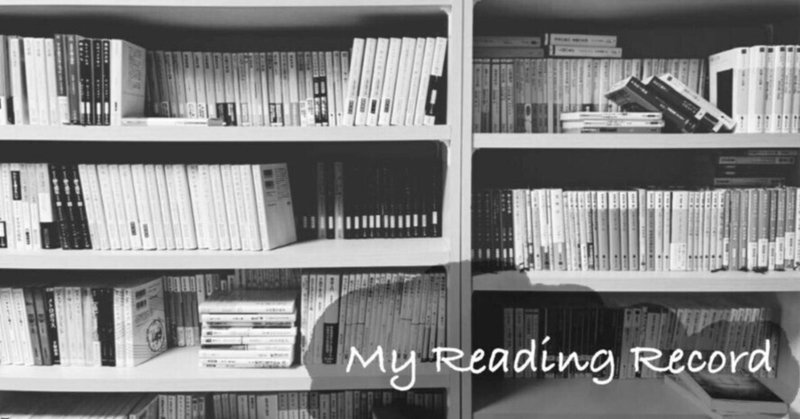
デレラの読書録:熊野純彦『西洋哲学史 近代から現代へ』

熊野純彦,2006年,岩波新書
同一性の根拠を求めて、西洋人たちは思考を展開する。
昨日のわたしと今日のわたしと明日のわたしの同一性を担保するものは何なのか。
デカルトは神を要請し、ロックは身体を白紙に見立てた。
あるいはルソーやコンディヤックは認識の起源、言葉の起源を掘り起こす。
丸を見たことがないひとに、丸の概念を教えてから、初めて丸を見たとき、丸を認識できるだろうか。
そもそも認識ってどうなっているのか。
カントは、空間と時間を人間の感性の主観的な条件に設定して、人間が認識する現象と、物自体を分割した。
そうして、認識は世界から切り離され、わたしたちは孤独になる。
フィヒテは自我をトートロジーで救い出し、ヘーゲルは矛盾律さえ精神の運動に取り込んだ。
フォイエルバッハが神の本質は人間の本質の別名だと暴露したとき、マルクスは人間の本質は現実的な人間の別名だとブーメランを投げ返す。
市民社会では大衆は疎外され、人間が人間として扱われなくなる。
人間とは何か、改めて問われるころ、人間は死と無の不安に怯えながら、現在の現(=そこ)へと投げ込まれていて、それを決意せよとハイデガーは促す。
その決意はやはり、不安との裏腹であり、ウィトゲンシュタインは人間とは何かを問うことはしなかったが、言語の限界へと向かうハイデガーの衝動に共感する。
言語の限界、語りえぬもの。
カントの言う通り、我々はその深淵に耐えられない。
その行く末が、存在と存在者の存在論的差異に帰着すれば、ひとはまた決断主義に陥るかもしれない。
そうしてレヴィナスは、理解から無限に溢れ出るような、決断には決して回収されないような、存在とは別のしかたを渇望する。
西洋哲学史の道のりは難解であり、当然、この歴史を「一つの物語」では汲み尽くすことはできない。
むしろ、汲み尽くされることから逃れるようにして歩んできた。
物語の快楽と、そこから引かれる逃走線に驚きながら、西洋の哲学史を楽しむことができる本書、きっと読み返すごとに新たな発見があるだろう。
おわり
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
