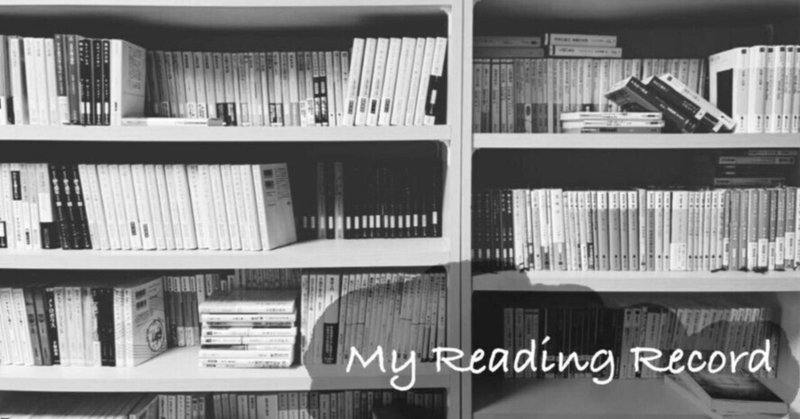
デレラの読書録:千葉雅也『センスの哲学』

千葉雅也,2024年,文藝春秋
読後感が気持ちがいい。
生活する自分の部屋から始まり、言葉に導かれ外に出て散歩をして、街並み、高架や河川、公園や街路樹、ビルや商店街などの風景の見方を教えてもらい、また自分の部屋に帰ってきたようだった。
解放感と閉塞感を同時に感じている。わたしは散歩が好きだ。
高低差のある土地で高いところから街を一望する気持ちよさ、住宅街の人間の生活が密集した感じ、商店街の店構えや文字、建物や道路の形、煙突などの突起物、公園や森林などの自然物が出てきたときの色の混ざり。
こういう楽しみ方をセンスという言葉で肯定してもらえた気がする。
本書は何か物を見るときの見方を教えてくれる。
一体どういう見方か。
それは「意味を追うのではなく、形の移り変わりを追う」というものだ。
形には、色や音も含まれている。
形の並びには、ビートとうねりというリズムがある。
ビートとうねりの説明箇所を読んで、わたしは高速道路を思い出した。
あるとき、友人たちと無意味に深夜の首都高をドライブしたことがある。
高速道路にある長いトンネルの、天井に設置された照明が、規則正しく流れる感じ。
社内の会話やBGM、多少の眠気と車の振動、車内に広がるお菓子の匂い。
たしかに世界にはビートとうねりがある。
わたしたちはリズムに囲まれている。
同様に、美術作品、映画、音楽作品、マンガなどの「意味を第一に扱っていると思われている表現物」にも当てはめてみる。
作品の持つ意味をいったんキャンセリングして、作品の持つ形=リズムだけを見てみようと。
これまで見てきた作品について、別の見方ができるかもしれないという期待感が膨らむ。
また本書は、期待感と同時にもう一つのことを教えてくれる。
それは、いったん作品としてその形を作らざるをえなかった作家がそこにはいる、ということだ。
形を見るという鑑賞方法は、意味からの解放であり、かつ同時に、その形にたどり着いた作家と出会う方法でもある。
自分の家で本書を読み終えたあと、わたしが一番最初に出会ったのは、眼の前にあるわたしの部屋の形であり、この生活を形作っているわたし自身だった。
街に出て、この生活を、わたしの部屋の形を変化させるために何かを買い足したい、と今は考えている。
植物だろうか、あるいは壁に絵を飾るのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
