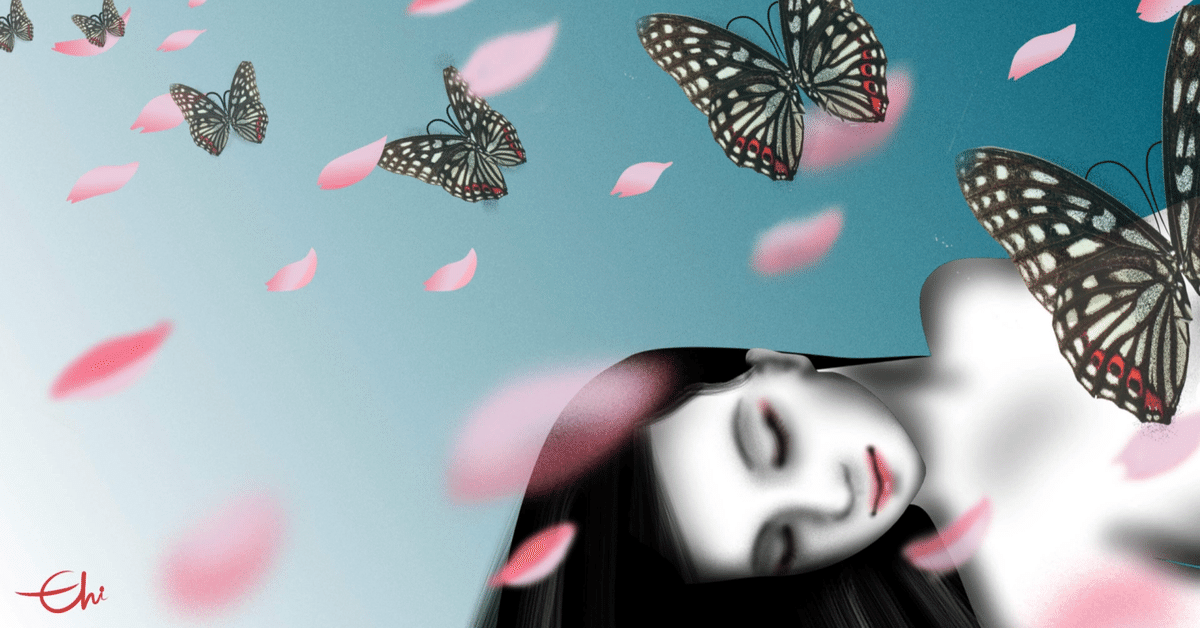
求められることに食い尽くされていく。映画『ヘルタースケルター』考察
今回は蜷川実花監督の映画『ヘルタースケルター』の話。
あまり評価の高くない作品らしいが、私はこういう悪趣味的な世界観が好きなので、サブスクで繰り返し観ている。
原作を読んでいないので、以下は全て映画版の話と思って読んでいただきたい。
ネタバレありの感想です。
この物語は二層構造になっていると思う。
表面にある第一のテーマは、「求められたいという心理」である。
この映画の画面はとにかく赤い。毒々しい。うるさくて色と光が強くて禍々しくて、頭痛と吐き気がしてくるような映画。
でも、それも本作の狙いだったのだろう。
極彩色の多用された毒々しい画面は、消費者女性たちによって口癖のように意味なく連発される「カワイイ〜」という言葉や、美しさを求めるという行為のグロテスクな側面を捉えた表現なのだと、個人的には解釈している。
女性の内側には、無自覚な暴力性が備わっている。美の追求や承認欲求、セックスもまた、破壊であり自傷行為である。
それらは「求められたいという欲求」と「求められないことへの不安」に集約される。それはカリスマにとっても消費者にとっても同じことだ。
その大きすぎる欲求に、カリスマ的存在であるりりこ(沢尻エリカ)は、身も心も食い尽くされていく。これが作品でもっとも目立つテーマとなっている。多用される赤い色は、すなわち欲望だ。
かつてカリスマと呼ばれた浜崎あゆみの栄枯衰退、安室奈美恵の引退と神格化をリアルタイムで見てきた世代だからか、物語の展開には、ある種の既視感や現実感、納得感がある。
ただ引っかかる点はあって、それは、「カリスマを消費する一般女性」の象徴として登場するギャルや女子高生たちの感性と、レディーガガ風のアーティスティックなカリスマ性を打ち出したりりこのギャップである。
ギャルが好む女性像というのは、「一見派手だけど、内面にピュアさや可愛らしさ、寂しさを抱えた女性」だと思う。
そのイメージとりりこには微妙にズレがある。要は売り方がスタイリッシュすぎる。出立ちが海外セレブ風で、可愛さや愛嬌、共感の面が薄い。
水原希子演じる新たなカリスマ・こずえにも同じことを感じた。日本はもっと「カワイイ文化」だ。
特殊漫画家・根本敬は「日本人の9割はヤンキーとファンシーでできている」と言っていたそうだ。たしかに、日本のカリスマは、皆どこかにその要素を持ち合わせている。
だが、りりこの描かれ方にはその要素を感じない。もっと強くて奇抜なイメージだ。
スクランブル交差点やバラエティショップのカットなどを見ると、なんとなく「海外から見た日本」を意識した作品になっている気がするので、日本人が感じるリアリティよりも、わかりやすさを優先し、「カリスマ=セレブ」的な描かれ方になっているのかもしれない。
それでも、沢尻エリカの演技自体はとても良かったと思う。
それこそ先ほど挙げた、「ギャルが好む女性像」を滲ませる説得力と存在感があった。「強気に振舞っているけど、根は悪人じゃないんだろうな」と思わせる演技力。
体つきは小柄で素朴だけど、顔はお人形みたいという所も、映画の中では良い方に作用していた。
沢尻エリカは歌に芝居に多方面の活動をしているし、「この台詞はりりこが発しているのか?それとも沢尻エリカが発しているのか?」と思えるほど境遇も近く、いい配役だった。
今となっては、彼女の不機嫌騒動や離婚スキャンダル後にこの映画を撮ってくれたことも、奇跡と思えるほどベストタイミングだったと思う。
二層目にあるのは、「欲望の消費」というテーマである。
りりこはカリスマ芸能人である。芸能人は、消費されるために存在している。
消費するのは大衆、一般の消費者である。映画の中での、りりこに羨望のまなざしを向ける多くの女性たち。
しかし、こずえの台詞にあるように、はっきり言ってカリスマは、別に誰でも良い。
綺麗で可愛くて夢中になれる存在であれば、りりこであってもこずえであっても、全く別の誰かでも構わない。大衆は得てして薄情である。
それを知りながら、求められることをアイデンティティとし、求められるままに自身を「消費させる」りりこ。
しかし彼女の限界、いわば「消費期限」はじわじわと迫っている。
ある事件に関連して彼女を追う検事・麻田(大森南朋)は、誰かを喜ばせるために自らの羽を撒き散らして傷だらけになる蝶に、その様を例えている。
麻田が見据えているのは、りりこに全身整形を施した違法クリニックから連なる巨悪である。
「この件の行き着く先は、この国のブルジョワジーだ」という台詞からわかるとおり、作中で(直接的でないやり方で)描かれているのは、りりこという一女性の欲望ではなく、「上流階級層の欲望」だ。
りりこ含む女性たちの欲望から成り立っている、美容整形クリニック。悪事の巣窟と化しているものの、政治家の後ろ盾があり、おいそれとは切り込めない。
切り札として、りりこの証言を得たい麻田。
整形の後遺症でボロボロになりながらも最後の記者会見に臨むりりことメイクさん・錦ちゃん(新井浩文)の、悲壮感漂う会話。
りりこ「あたしほとんど特殊メイクの世界だよね」
錦ちゃん「あら。じゃあアタシ、マイケル・ジャクソンの専属メイクになれたわね」
りりこ「・・・・もう死んじゃった」
錦ちゃん「アンタは生きてるじゃない」
マイケル・ジャクソン。単に「整形疑惑の代名詞」として名前を出したのかもしれないが、実在の人物名が唐突に放り込まれ、ドキリとする。
また、麻田はりりこを「タイガー・リリー」になぞらえる。『ピーターパン』に出てくるインディアンの娘、タイガー・リリーだろうか。
『ピーターパン』といえば、ネバーランド。ネバーランドといえばマイケル・ジャクソン。それぞれのモチーフは緻密に絡み合っている。
りりこは一世一代の記者会見で、自らの右目をナイフで突く。降り頻る赤い羽根。
大衆に求められ、それに応えて自らを差し出してきた彼女が振りまいた、最後の羽根である。
彼女は頂点を極めたように見えて、巨悪の機構を成立させるための歯車のひとつに過ぎない。しかもその歯車は、いくらでも替えがきく。
りりこの失踪後、女子高生らの間でまことしやかに「りりこを待受画像にすると二重になるらしいよ〜」などと語られ、写真集が復刻されるなど、彼女は伝説的存在となり、神格化される。人々の記憶にある限り、りりこは永遠に求められ続けるのだろう。
ラストシーンでこずえは、撮影の打ち上げで訪れた海外の「ヤバいショーをする店」で、真っ赤なドレスに身を包んだ、眼帯姿のりりこの姿を目撃する。
消費されるのではなく、笑いながら自分という商品を「与えてやる」存在になる。彼女は勝ったのだ。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

