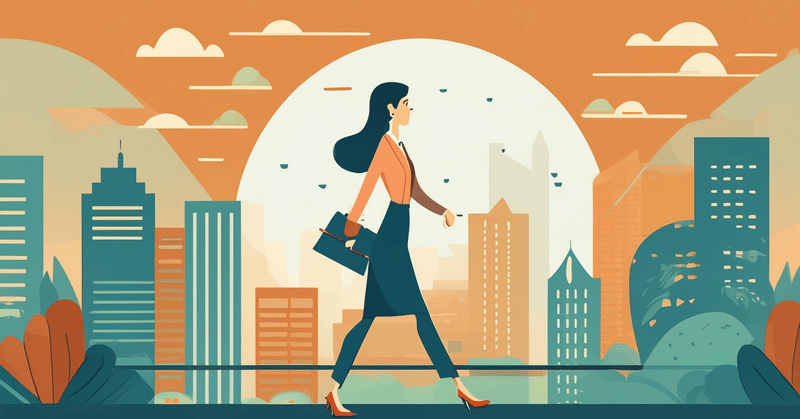
走れ! アンドーナツ
[あらすじ]
安藤奈津ことアンドーナツは31歳、登録5年目の弁護士だ。
東京の外資系の大手事務所に勤めていたが、ある事情から地元の大阪に戻ってきた。マチ弁の父の事務所で、世話になりイソ弁として心機一転働くことになった。
そんな奈津に、梅ヶ枝小学校のスクールロイヤーの仕事が舞い込んだ。しぶしぶ引き受けることにしたのだが……
いじめ、スクールカースト、小学生が抱える問題をアンドーナツが、個性豊かな教員に支えられつつ、彼女なりの論理で解決していく。
◇◇◇
「いっぱいのお運びで、厚く御礼申し上げます」
何故か落語のマクラが口を衝いて出た。安藤奈津は被告席から立ち上がると、頭の中が真っ白になった。顔の表情筋が金縛りにあったように固まり動かない。国立大の法学部卒、そのままロースクールに進み二度目の司法試験で合格した。三十一歳、今年で弁護士登録五年目になる。
大阪地方裁判所の五三七号法廷では、民事事件の口頭弁論期日が行われている。被告代理人として奈津が法廷に立ち、原告側は、まだバッチがキラキラしてる若手弁護士と、恰幅のいい年配の男性弁護士のふたり連れだった。いかにもボスと「イソ弁」のコンビだ。イソ弁は居候弁護士の略で、事務所から給与を貰う雇われ弁護士だ。
傍聴席は制服姿の男子学生たちのグループと傍聴マニアとおぼしき中高年のオジサン数人と、裁判所見学ツアーの婦人部のグループで埋まっている。たしかにいっぱいのお運び、つまり傍聴席は満席だった。奈津の意味不明な発言に法廷は一瞬にして凍りついた。
裁判員制度が始まってからは、裁判への関心が高まり、町内会の婦人部や中学、高校など、団体単位で裁判所見学ツアーなるものが企画され、随分と傍聴する人が増えた。老若男女が気軽に足を運ぶようになり、敷居が低くなった。
誰もが予想だにしなかった場面展開に傍聴人たちにも固唾を呑む。黒い法衣を着た女性判事が突如、意味不明な発言をした被告席の奈津をジロリと睨む。冷たい視線だった。その状況が更に奈津を窮地に追いつめた。緞帳が下り、目の前が真っ暗になった。目をあけているのに、何も見えない。意識はあるので、法廷内がざわついている様子がわかる。
「女の弁護士が倒れたよ」
「貧血かしら?」
「法廷戦術だったりして。ドラマみたい」
「これからどうなるの?」
傍聴席から発せられる言葉を遮るように、判事が、「休廷します」と告げた。スタスタと足音と布ズレの音がして、遠のく。
「チッ」と誰かが舌打ちした。おおかた、原告席の年かさのボス弁が、期日が延期になることに苛立っているのだろう。
奈津が医務室へと運こばれようとしている時だった。
「ちょっと、どいてどいて。その弁護士の関係者です。事務所のもんです」
案里さんの声がした。事務員の山﨑(やまさき)案(あん)里(り)さんだ。人だかりを押しのけて、ドタバタと法廷内に入ってくる気配がし、ギュッと腕をつかまれた。――痛い! ちと力が入りすぎだよ、案里さんってば。
遠のく意識の中で「奈津センセ、奈津センセしっかり!」という声を聞きながら奈津の手は、案里の掌にすっぽりと包み込まれていく。
体温を感じてほっとするのと同時にふんわりした安心感が奈津の不安を軽くする。意識がだんだん薄れていく。
「まだ、早かったか。法廷に立つのは……」
「奈津先生、泡吹いて倒れました」
「ちょっと……泡なんてふいてません。案里さん大げさ」
と奈津はふくれっ面でいう。
あの後、医務室で少し休ませてもらい回復した奈津は案里とふたり事務所に戻って来たのだった。
安藤忠志は大げさに頭を抱える。案里が緑茶を淹れた湯飲みを忠志のデスクに置いた。美濃焼で寿司屋でよく見かける魚へんの漢字が全面に書かれてあるものだ。奈津が父の日にプレゼントにしたものだ。忠志は湯飲みを口に運び、ズーズーと音を立てて茶をすする。はぁーっと体の奥から絞り出すような溜息をついた。
忠志はいわゆるマチベンだ。裁判所近くの築ウン十年のレトロといえば聞こえがいいが、老朽化した雑居ビルの一室に「安藤綜合法律事務所」を構えている。刑事事件から民事、会社の法務まで依頼者から頼まれれば、オールマイティにこなす。国選事件も受けるし、市役所の無料法律相談にも派遣されていく。市民の味方、正義の味方、市民派の弁護士だった。だから事務所の経営は芳しくない。恰幅がよくて、フサフサした白髪頭と豊かなひげを蓄えた風貌はライオンみたいだった。
そんな父の背中をみて育った奈津は、その父を反面教師にしたかのように、正反対の外資系の事務所に就職した。司法試験に合格した奈津は東京で司法修習を終えると、そのまま丸の内にある東京オフィスに配属された。東京だけでも弁護士が五十人以上、パラリーガルと事務員を併せると百人を超えるファームだった。そんな順風満帆に思えた弁護士人生が一転した。憂き世は何があるかわからない。
現在、奈津は病気療養中で無職だった。ニート弁護士。去年、依願退職扱いで事務所を退職し、逃げるように帰阪した。そのまま大阪弁護士会に登録替えしたものの、会館負担金会費四十万円、入会金三万円、入会調査賊賦金一万円、あわせて年間五十万円ちかくの弁護士会費を払う必要があり、忠志が立替払いするのを条件に、奈津は給料なしで軒先だけ借りる「ノキ弁」として「安藤綜合事務所」の所属弁護士となった。
「ほんとは接見、そんなに急いでなかったんですよね。奈津先生を復代理で法廷に立たせるなんて、だまし討ちですよ。まだ療養中の身なんですから」
お盆を持ったまま、案里は忠志にやんわり抗議する。奈津に対する扱いは腫れ物以上だ。
「獅子の子落としっていうじゃないか。可愛い子には旅をさせよ、とか」
「にしても、ですよ。そもそも失語症になった原因わからないですよね? 事務所を辞めた本当の理由だって聞いてないんじゃないですか? そこらへんどうなんですか」
案里は安藤綜合事務所を開設してからずっと事務員として働いているので、忠志に遠慮がない。ずけずけ思ったことをいう。
――あの、全部聞こえてるんですけど。
まるでふたりは奈津がいないかのように、話をしている。奈津も知らんふりしてデスクワークをこなす。
奈津は母親を早くに亡くし、小学校入学前から忠志が男手ひとつで育ててきた。学校帰りは事務所に「ただいま」と帰ると、「お帰りなさい」と案里がむかえてくれた。母親のような存在だった。いつも優しいまなざしで奈津を見守ってくれていた。
案里が安藤綜合法律事務所に勤めはじめた頃は、まだ若くて奈津にとっては独身のお姉さんであったが、人に歴史あり、でこの三十年の内に結婚し出産し、一度は事務所を退職した時期もあったが離婚し、またいつの間にか事務員として戻ってきた。奈津が帰阪すると聞いて一番喜んだのは父親の忠志より、案里の方だった。
「そもそも綜合事務所にしたのって、ゆくゆくは奈津先生と親子で事務所をしたいっていうセンセの願望ですよね」
「あの頃は綜合とか総合とかつけるのが流行ってたんだ。事務所名に」
「はいはい」
案里は軽くいなす。奈津は勿論、聞こえているがだんまりを決め込む。
「センセ、ちょっと早いですけど私たちランチにいってきます」
案里は財布とハンカチをミニトートに入れると、鼻歌交じりで忠志の返事も聞かぬ間に、「さあ、行きましょう」と奈津の手を引き、半ば強引に連れ出した。
ふたりは少し早めのランチをとることにしたのだった。
邪魔にならない程度にクラシックのBGMが流れている。大阪弁護士会の地下にある洋食倶楽部ENは、外壁を囲むように掘り下げられたドライエリアが設けられていて、地上からの自然光で店内はいつも明るい。地下にあるとは思えないほどだ。外から見える心配もなく通りかかる人の視線も気にしなくてすむ。カーテンもなくスッキリしていて開放的だった。インテリアも落ち着いている。認知度が低く一般人が出入りしない店なので、昼時もあまり混み合わない。客は弁護士ばかりで、ゆったりした雰囲気だった。奈津のお気に入りの場所だ。ただ同業が多いのが気になるといえば、気になるところだった。
アイロンがけされ、シミ一つない白いクロスが敷かれたテーブルに、サラダとシンプルな白磁のスープカップに入ったミネストローネが奈津の前に置かれる。まだ、ゆらゆらと湯気がたっている。目を瞑り思いっきり鼻腔に湯気を吸い込むと、トマトと野菜の香りを感じることにだけに集中する。スプーンは使わず、そのままカップを口に運ぶ。トマトの酸味と細かくカットされた人参と玉葱とズッキーニとキャベツ。トマトの風味が混ざり合い口の中に広がる。スープの温かさがそのまま胃の腑に落ちていくのを感じる。体の芯から温まる。ほっこりする。
ドレッシングがほどよくかかったくし切りのトマトにフォークを刺し、口に運び咀嚼する。湯引きしてトマトの薄皮は剝かれているから、口当たりがなめらかだった。サラダはまずトマトから食べると決めている。シャキシャキのレタスも瑞々しくておいしい。奈津は今どきの女子らしくベジファーストだ。
ミネストローネの最後のひとくちを名残惜しい気持ちで飲み干すと、ほぼ同時に、できたてほやほやのオムライスが奈津の前に置かれる。白い大皿に黄色とデミグラスソースのコントラストが美しい。スプーンを手に取ると、シルクのように滑らかな柔肌にメスをいれる外科医のように、慎重な手つきでデミグラスソースのかかったオムライスにスプーンをいれて、すくう。ランチに没頭している奈津を現実世界に引っ張り出すのは、またしても案里だった。いつもひとりにしてくれない。と奈津は思う。
「おいしい! 奈津センセはオムライス食べさせとけば機嫌がいいですもんね」
案里の声量が悪目立ちしている。案里は粗暴というか、動作が大きく行動が雑だった。ちょっと動けば花瓶を倒し、掃除機をかければ机に積み上げられた記録ファイルがバランスをくずし雪崩れ落ちる。
好物のオムライスに集中させてもらえず、不満げに案里を睨もうと視線を向けると、そこには心底心配そうな表情の案里がいて肩透かし食らってしまう。法廷で倒れたことを心配して、奈津を励まそうと明るく振る舞っているのだ。それでも「ごめんなさい」とは素直にいえないのは子どもの頃のままだった。
「もう! 案里さん、声大きいよ。みんな見てるじゃない。恥ずかしいんだけど」
気持ちとは裏腹に強気に振る舞ってしまう。案里は既にサラダもスープも食べ終え、白いお皿にのったオムライスも最後の一口分を残すだけとなっていた。スプーンで豪快にすくうと口一杯に頬張る。
「案里さん、食べるのん、はやっ!」
「なーに悠長なこといってるんですか。早飯早糞早算用。これ弁護士の鉄則ですよ」
「やだやだ。それ父さんの口癖マンマ。耳ダコだよ。せめて早飯も芸のうち、とかいえないかね。案里さんすっかり毒されちゃってるね」
「ですね。センセとは夫婦以上に長い付き合いですから」
奈津は落ち込んでいる時、オムライスを食べる。食べると元気になるし、気がふさいでる時は食欲がなくなるけれど、唯一オムライスだけは食べることができる。奈津の母親が亡くなった時もそうだった。泣いてばかりいる奈津に「オムライス食べるか?」と、忠志は奈津の手をとり中之島まで連れて行ってくれた。奈津にとってオムライスはポパイのほうれん草パワーのようなものだった。運動会で転んでビリになった時も、高校受験で本命の公立高校の入試に落ちた時も「オムライス食べるか?」と、忠志は何でもない風に奈津を誘い、ふたりは無言でオムライスを平らげた。奈津にとっての世界一のオムライスは子どもの頃に食べた食堂のオムライスだ。旧中之島公会堂には大阪ホテル中央公会堂食堂部があった。ほとんどのメニューが五百円ぐらいで、オムライスもやっぱり五百円だった。食堂はもうない。公会堂の改修工事の時に、食堂も一緒に取り壊された。リニューアル後は高級感溢れるレストランになってしまった。ベストに蝶ネクタイのおじいちゃんウェイターさん、英国のメイド服を着たおばあちゃんウェイトレスさんはもういなくて、ホール係も一新され若い人になっていた。あのおじいちゃんたちは何処に行ってしまったんだろうか。
中之島公会堂の『オムライス』に涙の再会をしたのは、弁護士になり、大阪に帰ってきてからだった。こんな近くでいちばん好きだったメニューが引き継がれていた。あの中之島公会堂のレシピが洋食倶楽部ENで再現されていたからだ。
「ごちそうさまでした~」
手を合わせ、ふたりの声がユニゾンする。ここは私が、いや私がというオバチャンあるあるの行動をひととおり終え、最終的に案里が年の功で伝票を奪い取ると会計した。
「案里さん、ご馳走様でした」
「お気遣い無用ですよ。今度、奈津先生の個人事件の報酬がはいったら、しっかりご馳走してもらいますから」
「え?」
「仕事の依頼、きてますよ」
さーさーさーっと、お尻を叩かれ、奈津は追い立てられるように案里と事務所に戻る。振り返るとドライエリアから見える空も、植栽も降り注ぐ日差しも、ワントーン優しく感じた。
案里に引きずられるように事務所に戻ると、忠志は奈津に仕事の依頼があったことを伝える。忠志の大学の同窓で梅ヶ枝小学校の校長からスクールロイヤーとして、奈津に来て欲しいと依頼があったという。
「スクールロイヤー?」
「まさか、知らないのか?」
「知ってます。何でまた……私が」
忠志の声にかぶせるように奈津がいう。
「断れないんですよね?」
「どうせ暇だろ? ここから近いし」
事務所から梅ヶ枝小学校は徒歩五分で行ける。目と鼻の先だ。
「距離の問題じゃなくて……」
奈津は黙る。勿論、スクールロイヤーのことは知っている。文科省平成三十年度概算要求書によると、法律の専門家である弁護士が、その専門知識・経験に基づき、①法的側面からのいじめの予防教育、②学校における法的相談への対応、③法令に基づく対応の実施状況の検証、をおこなうというものだ。米国では一般的に導入されているけれど、大阪府教育庁では大阪府いじめ防止基本方針に基づき、スクールロイヤーを派遣する事業がやっと始まったばかりで、まだまだ手探り状態だった。
「司法試験の科目に教育法規は含まれていないし、教育法令も知らない。子ども好きじゃないし、そもそも学校が嫌いなの」
「ノキ弁の癖して、仕事選んでる場合か!」
「ハウスロイヤー(企業内弁護士)の就職先が決まったらさっさと出て行きます。借金も返します。借り作りたくないんで!」
「まーまーまー。はい! そこまで」
と案里が奈津と忠志の間に体ごと割ってはいる。
「ほらほら、親子げんかは犬も食わないって……いうじゃありませんか」
「それをいうなら夫婦喧嘩でしょ!」
奈津と忠志の声がシンクロする。こういう時、親子の息はぴったりだった。
大阪市立梅ヶ枝小学校は大阪市内でも古くて歴史がある学校だった。児童数は二百八十七名、教員十六名とこぢんまりした規模の小学校だった。
校庭は都会のど真ん中なので、猫の額しかない。バックネットには白い布の横断幕で「たくましく、希望に満ちた学校」と、スローガンが掲げられている。
奈津はスクールロイヤーとして週に二日勤務することになった。職員室の片隅には奈津専用の机が用意された。校長先生から紹介され全教員を前に簡単な自己紹介をした。
法廷以外なら人前でも普通にしゃべることが出来るとわかった。やっぱり心療内科のドクターがいうようにメンタルの問題なのか、と奈津はやや落ち込む。
今度は児童たちの前でのお披露目だった。七センチヒールのパンプスを履き、カツンカツンと音を響かせてアルミ製の階段を数段あがる。朝礼台から全校児童を見下ろす。黒のパンツスーツでキメた奈津の表情は硬い。
「いっぱいのお運びで、厚く御礼申し上げます。イヤ、違う違う。間違えました」
緊張している。校庭の児童たちは目を丸くしている。奈津は深呼吸し、気を取り直すと硬い表情のまま話し出す。
「いじめは犯罪です。殴る蹴る行為は「暴行」「傷害」にあたり刑法二〇八条、二〇四条。みんなの前で悪口をいう行為は刑法二三一条の「侮辱」にあたり、脅してお金をとったら「恐喝」で刑法二四九条に該当し逮捕されます。みなさんのまわりにいじめはありませんか?」
水を打ったように静まりかえっている。教員たちもしれっとしている。もう一度、奈津は深く息を吸う。
――これも違うか
今度は無理矢理、口角をあげ笑顔を作ると、
「今日からこちらの学校で、みなさんと一緒に過ごすことになった弁護士の安藤奈津です。あんドーナツって覚えて下さい。アンコがたっぷり入ったパンを油で揚げたアレです。あ、知ってるか。いじめとか困ったことがあったら職員室にいるので来て下さい」
「アンドウナツ?」
「あんこより、カスタードがいい!」
「美味そう。餡ドーナツやってさぁ」
空気が緩む。静かだった児童が口々に話しだす。一瞬にして緊張の糸がほぐれ、わいわい騒いでいる。
――ウケた! 奈津は安堵する。
奈津はここぞという場面で、いつも自分の演じ方を誤るけれど、今回ばかりは正解の札をつかんだと確信する。
◇◇◇
一ヶ月が過ぎた。
児童は誰も奈津のもとにはやってこなかった。たまに男子と廊下ですれ違いざま「ドーナツ、ドーナツ」と、からかわれる。ドーナツじゃない「あんドーナツ」だ! と心の中でツッコミを入れる。職員室でもみんな自分の仕事で精一杯なのか、奈津に話しかけてくる教師は誰一人としていない。訳の分からない弁護士と関わるのがやっかいだと思っているのかもしれなかった。
視線が合いそうになってもむこうがすぐ目を逸らす。そもそもスクールロイヤーが自分たちの味方なのか、敵なのか判断しかねるのだろう。教師たちは目立たないよう淡々と与えられたタスクをこなす。査定に×を付けられないことが最優先事項なのだ。奈津は職員室でも校内の何処にいてもアウェイな空気に包まれていた。
ぽんぽんと右肩を叩かれた奈津は、驚いて右に振り返ると、何故か誰もいなくて、六年生学年主任の島田多江が左側に立っているのが視界に入る。
「なんです? 島田先生。見えてますから。肩とんとんほっぺ、とか膝カックンとか」
といいながら、やっと多江の姿を捉えた奈津に、してやったりと茶目っ気たっぷりに多江が微笑んでいる。意外と俊敏だった。奈津は心の中で、小学生の悪戯か! と呟く。
「児童の間ではやってるんよ。よくやられるから、試してみた!」YouTuberのバズり企画でもあるまいし、と皮肉る。
多江は奈津より一回りちょっと年上の女性教員で、二度の産休・育休からの復帰を経て教職を続けているキャリア組だ。子どもらはふたりとも大学生だという。梅ヶ枝小に勤務して十数年になるベテランで、六年生の学年主任をしている。快活で明るい。アウェイな空気が少しだけ和らいだ気がした。
「教員ってね、授業するだけじゃないんだよね。むしろ、それ以外の雑務が仕事のメインといっていいかも」多江は、声を潜めていう。
「朝、担任する教室に入ってから出席とって、授業して児童の下校指導が終わるまで、職員室の机にほぼ戻ることはないんだよね」
確かにチャイムがなって職員室に帰ってきても慌ただしく出て行くので、教員に何か聞こうにも、聞けない。話しかけようとしてもみんな忙しそうで声をかけるのが、はばかられる。
「給食だって、児童たちと一緒に食べるし、その後は掃除だしね」
「自分が小学生の頃って、先生がそんなに忙しいって思ったことないですけど」
奈津はうん十年前を振り返るが、小学生の記憶がほとんどない。
「そんでさ、児童が下校してからやっと自分の仕事ができるの。テストの採点、明日の授業の準備、成績つけ、学級通信の作成、保護者面談の日程調整ってもう次から次から仕事が沸いてくんの。ひとりひとり、細やかに指導するなんて出来るわけがない。そもそもそんな精神的余裕がないわ」
奈津は同情してしまう。
「テレビとか新聞の報道では聞いてましたけど、ここまで学校がブラックとは。あ、すみません」奈津は不用意なことをいってしまい、恐縮する。
「いいの、いいの。ほんとそうだもん」多江は全く気にしていないそぶりでいう。
「職員室にいると暇そうにしているのが、自分だけでなんか申し訳なくなります」
「奈津センセはほら、教員じゃなく弁護士さんだから。教師の仕事は教師に任せておけばいいの」
スクールロイヤーは、いじめの防止だけが仕事ではない。教員たちの悩みを聞いたり、モンスターペアレンツ化した保護者との交渉の間に入るのも仕事だ。でも誰も奈津には相談を持ちかけてきたり、助けを求めたりすることはなかった。人徳がないからなのかと、奈津はまたしても落ち込む。
居たたまれず、職員室を出ると校内を散策する。パトロールだ。途中、中庭のベンチで休憩する。卒業生が寄贈した木彫りのベンチだ。ペンキがところどころ剥げている。ハンカチを広げ、座るとこっそり持ってきた耐油角底袋からガサガサと音を立て『はらドーナツ』を取り出す。
――あれ?
いつもひとりで花壇の水やりをしている女子児童だった。お昼休みは大抵ここで見かける。給食食べ終わるの早っ! と思っていつもみていた。
「おーい、よく会うね。キミ、何年何組?」
「わぁアンドーナツや! あっ、ごめんなさい。安藤先生」
「いいよ、安藤(アンドー)奈津(ナツ)で!」
奈津がドーナツをかじるのを見ていて、
「なーんや。穴のあいたドーナツかい。ここはお約束でアンドーナツちゃうんかい」
と女の子は心底がっくりして、漫才の様なツッコミでつぶやく。滑舌がいい。
「だって共食いになるでしょ? ほら、しょうがないなぁ、一個あげよう」
「わぁー『はらドーナツ』だ!」
いくら大人びて見えても小学生は、小学生だ。まだまだ幼い。差し出されたドーナツを躊躇なく、ぱくぱくと口いっぱいに頬張ると、
「はらドーナツ、うちの近所にもある」
とモグモグしていう。
六年一組の渕田アリス。小学校のすぐ裏のカゴメの跡地に出来たトマト色のタワーマンションに住んでいる子だった。タワマンカーストはママ友だけじゃなく、児童たちの間にも影響を及ぼしていて、いじめにも繋がっていると職員会議で問題視されている。その騒動の中心的人物がアリスだった。
アリスは子役のタレントをしていると紹介されたらそのまま信じて疑わない容姿だった。みんなと同じ制服を着ているのに、ひとりだけ手足が長く何処か垢抜けている。容姿の美しさも、愛らしい仕草も自分のかわいさを自覚している証拠だ。
彼女が昼休みにひとりぼっちの理由がわからない。いじめられっ子のキャラではないはずだ。むしろタワマンカーストでは位が上ではないのか。
「女子で群れるのがイヤ」とアリスはいう。
「……そうなんだ」
給食を食べた直後に、べつばらとはいえ子どもがドーナツ一個をぺろりと平らげるのは信じがたい。並外れた胃袋の持ち主か、給食を食べていないかのどちらかだ。食べっぷりからいって、何らかの理由で給食を食べていない可能性が高い。いじめられてる? 奈津の表情が曇る。
「ねぇねぇ、安藤奈津! 朝礼の時、『いっぱいのお運びで、厚く御礼申し上げます』っていってたよね? あれって落語のマクラだよね?」
「そうそう、高座でいう決まり文句。寄席行くの?」
「うん。じーじとね。うち母子家庭だからいつもママが忙しくていつもじーじんちにいくの。じーじが好きだから繁昌亭によくいくよ。誕生日プレゼントに米朝と枝雀のDVD買ってもらったもん」
とキラキラした目でいう。同級生とは話が合わないはずだ。ふたりは松鶴の「らくだ」が傑作だとか、春團治の羽織を脱ぐしぐさに萌える! とか、文枝の「立ち切れ」に出てくる花柳界の女たちの演じ方が艶っぽいだとか、枝雀の絶妙の間とオーバーアクションがサイコーとか、話題が尽きない。
「キミ、私より年上なんじゃないの? 私よりよく知ってるもん。昭和生まれがタイムスリップしてきたんじゃないの! 昭和博士ちゃんだ」
アリスは昭和の噺家が好きらしく中でも上方落語が好みらしかった。奈津も同感だ。
チャイムが鳴った。時間切れだ。アリスは「またね!」と巣穴に帰るリスのように素早く昇降口の方へと走っていった。奈津は校舎の窓に写っているゆるゆるの表情をした自分の顔と遭遇し、驚く。アウェイで孤独な世界にいて一瞬、心が和んでいた。アリスに親近感が沸いた。仲間がいる喜びで少し心が満たされている。
――ぼっちはやっぱり辛いよね
◇◇◇
「では、裁判を始めます」
六年一組では模擬裁判が行われている。教壇に立つ奈津が口火を切る。教壇から児童たちを見渡す。視界の端に渕田アリスをみつける。
職員室で暇そうにしている奈津に校長先生が「安藤先生、授業してみませんか?」と持ちかけた。断る理由も思い浮かばず、引き受けた。
スクールロイヤーの報酬をもらっている以上、働かなくてはならないと奈津は自覚している。仕事がないからといって漫然と机に座っているだけでいいとは思っていない。幼い頃から父に「働かざる者食うべからず」といわれて育った。安藤家の家訓でもある。
とはいえ、弁護士会からの派遣で高校生相手に法教育の授業はしたことがあるものの、小学生相手というのは想定外で途方に暮れていた。「気軽にやってよ!」と校長はにこにこしていう。児童に馴染んでもらうため、法律を身近に感じられる授業を、というのが校長から出された唯一の条件だった。
黒板には「さるカニ合戦事件」と書かれた画用紙がマグネットで貼られている。カニとさるの絵が、カタチもどことなくいびつなのは奈津の手作りの教材だからだ。工作感満載で、アナログだった。そのせいで、前日は「カンテツ」だった。
裁判長役の奈津が事件の概要を話す。昔話「さるカニ合戦」をもとにした裁判だ。
「カニの母子が体を砕かれて殺害されました。逮捕されたのは、さる。まだ青くて硬い柿を木の上から執拗に投げつけ、死に至らしめました。罪を認めるさるに、検察官は死刑を求刑しました。弁護人は、さるが反省している点などを主張し、死刑ではなく無期懲役で「生きて償うべきだ」と訴えています」
児童たちは検察官と、弁護人と、証人として生き残った子ガニと、さるの妻、被告人のさるにわかれている。アリスはひとり、さる役だった。役割は予め児童たちで決めてもらうようクラスの担任にお願いしていた。
――アリス、さるなんだ! 意外な配役に奈津は驚く。
「し・け・い! し・け・い!」
何処からともなく、誰かが言いだした死刑コールが教室中に響く。ひとり、ふたりと声が重なる。それに手拍子が加わる。
「静粛に! 死刑で本当にいいの? 何の理由も弁明も聞かずに殺せっていってるのと同じだよ」
「人を殺したら死刑だろ」
そうだ、そうだ! と同意する声があちこちからあがる。
「殺しておしまいでいいの? もう少し考えよう」
勢いに飲まれそうになりながらも、奈津は冷静に諭すようにいう。
「はい弁護人、何か反論はないのですか?」
弁護人役の女子に水をむける。
「ありません」
いけしゃあしゃあと弁護人役の女子が答える。これじゃあ出来レースだ。
「休廷します」
奈津はぴしゃりというと、今度は、おかしい! なんでだよと、奈津の声はブーイングでかき消される。アリスは唇をぐっと噛み被告人席でひとり黙って立っている。微動だにしない。
「今日はここまで!」
奈津はみんなに自分の席につくように促すが、いうことを聞かない。あっちでもこっちでも小競り合いが発生し、口げんかになり、とうとうつかみ合いのけんかが始まった。
――これって学級崩壊ってやつ?
「こらこら、騒がしいですよ」
校長先生が教室のドアを開け、ニコニコ顔で立っていた。児童たちは「あ、校長先生だ!」「センセー」とかいって、いつの間にか校長は児童たちに囲まれていた。いつだって校長先生は優しくて子どもたちの人気者だ。「はいはい、みんな自分の席に戻りましょう」となだめると、崩壊しかけたクラスは一気に収束する。
――ハーメルンの笛吹き男? 校長は笛を吹かずにして簡単にことをおさめた。奈津は自分の無力さを思い知った。大声で怒鳴って、こめかみに青筋立てて怒ってもそれでも効果なんてなくて、ただの怒り損。馬鹿みたいだ。空回りしているじゃないか。ぽつんと奈津は突っ立っているばかりだった。
職員室の片隅の自席に戻った奈津は、プリントアウトした「いじめ防止対策推進法」をぼんやり目で追っている。無力感と敗北感が沸々とこみあげてくる。
ポンポンと肩を叩かれて振り返るとホトケの笑みを浮かべた校長先生が立っていた。
「校長先生! 先程は……お恥ずかしいところをお見せしてしまって」
奈津はしどろもどろになる。口が渇く。暑くもないのにたらたらと汗が首筋から背中に流れていく。
「安藤先生、ほら肩の力を抜いて。深呼吸ですよ。子どもたちは大人をよく見ていて、ここまでは、いいだろうって間合いをはかってるんです。力で押さえつけてもいずれまた違ったカタチで爆発します」
「じゃあ、どうすればいいんでしょう」
「子どもだからとこちらの考えを押しつけるだけではだめです。しっかり意見を聞いてやらないと、彼らは納得しません。そこは大人より難しい」
「じゃあ、校長先生はいじめを見て見ぬふりをしろと? 放置するのですか?」
「勿論、いじめはどんな理由があろうと、あってはいけません。学校教育の役割のひとつは、困難を乗り越える力をつけることだと私は思います。いじめた方もいじめられた方も」
奈津は引きつった表情になる。
「いじめがあっても、双方がそれを乗り越える力をつけてもらいたいんです」
校長先生は表情を崩さない。
「私は、子どもたちが過ちを犯すのをみすみす見ていられません。きっと教師にはなれません」
「奈津先生、管理することをやめてみませんか? 彼ら彼女らは意外と逞しい」
奈津は黙ってしまう。異論は浮かばないが納得した訳でもない。
――学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校に在籍する児童等及びその保護者並びに当該学校の教職員がいじめに係る相談を行うことができる体制を整備するものとする。
「いじめ防止対策推進法」の条文が頭に浮かんだ。
「助けるべきです。声を上げられない子らの声に耳を傾ける努力が必要です」
職員室は相変わらずの喧噪だった。みんな自分のことで精一杯なんだろう。奈津は校長に会釈すると職員室を飛び出した。
放課後の中庭のベンチには先客がいた。アリスだった。
「ねぇ、アリス。恐いもんある?」
アリスの横に座ると、奈津は答えを待つ。
「恐いもん? 別にないけど」
アリスは素っ気ない。
「いやいや、おまっしゃろ、おまっしゃろ、言いなはれ、言いなはれ、何恥ずかしいことおますかいな」
アリスは狐につままれたみたいにぽかんと口を開けて固まっている。奈津は続ける。
「アリが恐いなんてやつもいてまんねんで、おっしゃれや、おっしゃれやぁー。なぁ」
時代めいた奈津の言葉遣いに不審な顔をしていたアリスはふと、何か思いついたように手を打ち、キラキラした目をしていう。
「〝饅頭こわい〟だ!」
「はい! ご名答」
奈津は拍手すると、噺の後を続ける。
「いや、こればっかりは口に出して言うのも恐い」というと今度は下を向き、表情を変えていう。
「だいぶんと恐いもんやなぁ、それは。な、なんでんねん、あんさんがそれほど恐がるモノっちゅうのは。気になりまっしゃないかいな! おっしゃれや、おっしゃれやぁ~」
二人の会話を上(かみ)と下(しも)とで、演じ分けているのだった。誰の台詞なのか、わからせる落語の手法だった。
「実は……面目ない話でんねやけどな、あのぉ、お饅が恐い……」
「饅頭恐い」は、有名な落語だ。みんなで集まっている時に恐いもの自慢が始まり、そこでひとりが、饅頭が恐いといい出す。それを真に受けて、怖がらせてやろう! と、みんなで寄って集って、ありとあらゆる種類の饅頭、普段食べないような高級な饅頭までを揃えて「どうだ!」とばかりに差し出す。何故か、恐い恐いといいながらも美味しそうに食べる。怖がるどころか、喜んで食べている。実は饅頭が大好物でそれを逆手にとる噺だ。
「今度は、濃いぃお茶がいっぱい恐い」
と、奈津のサゲが決まる。
アリスは歓喜し、スタンディングオベーションする。
「上方バージョンかぁ……枝雀の饅頭恐いだね」
「アリス、詳しいね」
「だって、YouTubeでみてるもん」
最近の子どもは侮れない。情報化社会にしっかり溶け込んでいる。ジジババが知らないアイテムを使って苦もなくマスターする。奈津が子どもの頃は、落語を稽古するなら音源をCDで聴くか、高座に連れて行ってもらうか、新聞のテレビ欄をチェックしてビデオ録画してみるかだった。演芸番組は概ね早朝か深夜枠での放映だった。
「落語ってさぁ、何度も聞いているうちにいつの間にか覚えちゃってて、つい、台詞を口ずさんでるんよね。覚えたら今度は誰かに披露したくなっちゃうし。完コピした成果を見せて観客を笑いの渦へ導く。ドカンって笑わせるの。笑いで人を幸せにする」
「やりたい。私もみてくれてる人の前で、や・り・た・い!」
地団駄を踏み、だだっ子のようになったアリスがいう。
「高座じゃないとヤダ。ギャラリーがいないとヤダもん」
とアリスがわがままをいう。
「落語は何処でだって出来るよ。あっ、そうだ。いい小屋あったわ」
「えー、どこ? どこにあるの」
アリスが食いついた。奈津はしめしめ罠に引っかかった! とばかりに、にんまりする。
「さぁて、どこでしょう?」
奈津は煙に巻くと、間髪入れずに
「じゃあ素直に言うこと聞く?」
と聞くと、アリスは
「はーい」
と返事だけはいい。急に素直なよい子へと変貌を遂げる。
「じゃあ小屋、案内するからついておいで」
奈津が背を向けてスタスタと歩き出すと、アリスも慌てて奈津の後ろを追いかけてくる。背負ったピンクのランドセルが左右に揺れる。
「アンドーナツ待ってよ~。ねぇ、小屋ってどこなの? ここから遠いの?」
◇◇◇
奈津とアリスは「安藤綜合法律事務所」の応接室にいた。
奈津がアリスを事務所に連れてきた。事務所に誰かを連れてくるのは小学校六年生以来だった。奈津から「事務所に梅ヶ枝小の児童を連れて帰る」と連絡を受けた案里は、近くのコンビニに買い出しに走った。ジュースやお菓子をたんまり買い込む歓迎ぶりだった。
「こんにちは」とアリスがよそ行きの表情で挨拶する。案里に早速、応接に案内される。
応接室のテーブルは大きかった。来客はそんなに多くはないのに、設えだけは立派だった。八人ぐらいなら打ち合わせできる大きなテーブルの中央にアリスが畳んだブランケットを座布団代わりにして正座している。高座さながらだ。ギャラリーは奈津と忠志と案里の三人だった。
アリスは「緊張する」といいながら寿限無をやった。
「じゅげむ、じゅげむ、ごこうのすりきれ、かいじゃりすいぎょのすいぎょうまつ、うんらいまつ、ふうらいまつ、食う寝るところに住むところ、やぶらこうじのぶらこうじパイポ、パイポ、パイポのシューリンガン、シューリンガンのグーリンダイ、グーリンダイのポンポコピーのポンポコナの長久命の長助」
アリスは一気に言い終えると、溺れてあっぷあっぷとなった人が水面に顔を出した時みたいに大きく口を開け息を吸う。段々と呼吸が整ってくる。アリスの寿限無はなめらかだった。声もよく通るし、滑舌もいい。スピード感もあり、声の質、発声もいい。何より度胸がある。
「アリス、やるね!」
奈津が褒める。
「お嬢ちゃん、凄いねぇ」と心底、感心したように忠志がいうと、案里はまだ拍手をやめようとしない。そして、うっすら目頭に涙を浮かべている。ハンカチで目頭を押さえた。案里は人より涙腺がゆるくて、人の倍、情に厚く、感動しいで感激屋さんなのだ。
「素晴らしい! 奈津さんのちっちゃい頃を思い出しました。今はこんなですけど、昔はアリスさんみたいに可愛かったんですよ。素直で、聡明で、純粋で……」
「案里さん、なにげにディスるのやめてもらますか」
「だってぇ……いたいけな奈津先生の小学生時代を思い出したら、つい。なんでこんな風に育ってしまったんだろう? どこでどう間違えてこんなひねくれ者になっちゃったんでしょう。安藤センセの育て方がきっと悪かったんですね」
そしてアリスの正面に立ち、かがむと視線を合わす。
「奈津先生はね、こども落語チャンピオンになったんですよ」と自分の事のように誇らしげにいう。
「案里さん、もういいってばぁ」
「こども落語、知ってます! 小学生の落語大会ですよね?」
アリスは勿論知っているようで、食いつきがいい。落語好きが集うマイナーな大会だ。
宮崎県日向市は「お笑い発祥の地」といわれる。その昔、天照大御神が「天の岩戸」に隠れてしまい、世界が暗闇におおわれてしまった。
天の岩戸の前で、宴会を開くことになり、天鈿女命が岩屋の前で踊り始めると、騒ぎに気づいた天照大御神が、その様子をこっそり覗こうと岩戸を少し開けたところ、手力雄命がその岩戸を投げ飛ばし、世界に再び光が戻ったという伝説がある。
この伝説がお笑いの聖地となったいわれだ。毎年、日向市の主催で7月の土日の二日間、小学生の部と中高生の部にわかれ「こども落語全国大会」が開催されている。
「あの当時、奈津先生は天才落語少女といわれました。新聞にも載ったんですから。ほら」
といって、スクラップブックを机の引き出しから取り出すと素早く頁をめくり、見せた。経年と日焼けでセピア色になった新聞の切り抜きだった。「天才落語少女あらわる」の見出しと、揚亭(あげてい)アンドーナツさん八歳(本名・安藤奈津)女子で初の快挙! という文字が躍っている。ガッツポーズする金魚模様の浴衣姿の奈津の写真がある記事だった。
「この通り。二十歳過ぎればただの人だけどね。はい、この話はこれでおしまい」
奈津は収束をはかる。
「あのー、私を弟子にして下さい」
神妙な顔で、アリスは深々と頭を下げた。
「アンドーナツ師匠!」
アリスは奈津の手を掴むと、ギュッと握って離さない。
「冗談でしょ?」
アリスはありったけの力で握ってくる。
「離して。アリス、痛いってばぁーっ」
奈津は手を振りほどこうとするが、全身のありったけの体重をかけてくる。すごい力だった。床にしゃがみこむと、子泣き爺のように重い。
「もう、離してってば。怒るよ」
「弟子にしてくれるまで、絶対離さないもん!」
アリスも負けていない。
「まるで年の離れた姉妹みたいですねぇ」
案里は目を細めてふたりを見ながらいった。ふたりの間に割ってはいると、
「はい。ふたりともここまで。奈津先生、アリスさんをお弟子さんにしてあげたらどうですか?」
奈津はずっこけそうになる。体勢を立て直すべく、頭の中で論理的思考を整理する。職業柄、議論は得意とするところだ。弁も立つ。
「申し訳ないけど、弟子はとってません。それに噺家ではないので」
アリスはその場に崩れ落ちた。そして、シクシクと泣き始めた。肩を震わせしゃくりあげる。それには、奈津と忠志と案里は動揺する。中でも忠志の狼狽ぶりはひどい。
「奈津、泣いてるじゃないか。こんないたいけな女の子を泣かせてどうするんだ!」
忠志は女の涙に弱い。それもちっちゃな子が泣くのを見ていられないと自分まで泣きそうな顔をする。
「わかった、わかった。弟子にすればいいんでしょ?」
「師匠、じゃあ名前つけてよ」
「えー。いいじゃんアリスで」
「だって普通、師匠が命名するでしょ? 高座名ないと落語家として精進できないもん」
とアリスは生意気な口をきく。
――リスナーにねだられてラジオネームをつけるDJじゃないんだからさぁー! と奈津は心の中で悪態をつく。アリスは高座名を貰うまで納得しないだろう。致し方ない。半分、やけっぱちになりながら、脳みそをフル回転させる。
「今日からキミの高座名は揚亭バニラアイスだから。ホラ、めそめそ泣くんじゃないよ、アイス。泣いたら溶けて台無しになっちゃうだろ」
パチパチとちっちゃな控えめな拍手がわき上がる。案里と忠志だった。丸く収まってホッとした表情のふたりを尻目にフンと奈津の鼻息が荒い。
「アイス、通いの弟子で頼むね」
「はい、師匠!」
アリスは満面の笑みを浮かべている。
――今泣いたカラスがもう笑った? いや、はなっから泣いてない?
アリスの頬にも、澄んだ瞳にも一滴の涙の痕跡さえ見つけられない。
「コラ! アリス。さては、嘘泣きして私たち大人を騙したなーっ」
「師匠、今日からアリスじゃないって、揚亭バニラアイスですってばぁ」
奈津はアリスの頭に優しくゲンコツを落とす。アリスは悪びれず笑っている。学校では見たことがないような屈託のない、いい笑顔だった。
「梅ヶ枝小に落語クラブを作ろっか」
「やったー!」
翌日、奈津は校長に許可をもらい昇降口の掲示板に落語クラブの部員募集のポスターを貼った。子どもじみた絵はとても大人が描いたものとは思えない。
「なんじゃこりゃ? へんな絵」
「落語ってなに?」
違った意味で児童たちの注目を集めていた。会社で辞令が張り出されたみたいに廊下にはちょっとした人だかりができていた。その人だかりにグイグイと入り込み、奈津はチラシを配る。
「今日の放課後、体育館で説明会をおこないます。案内のチラシですよ~」
声を張る。見る見るうちに用意した五十枚のチラシがなくなった。
「こら、一人一枚ですよ!」
あちこちから手がでてくる。
「チラシがない人は職員室にあるので、休み時間にでも取りに来て下さいね」
反応は上々だ。奈津はにんまりする。
放課後、緊張の面持ちの奈津とアリスのふたりは体育館に入った。体育館は全校集会までとはいわないが、半分ちかい児童たちが集まっていた。教師もちらほらのぞきにきているようだった。
壇上に立ち、奈津は落語とはなんぞや、の話から始める。扇子と手拭いをジャケットのポケットから取り出す。
「手ぬぐいは本や財布、煙草入れになります」
折りたたんである手ぬぐいを広げ、両手のひらにのせ本に見立てる。
「『浮世床』、『稽古屋』、『紙屑屋』なんかでは本が出てくるので、こんな風に本みたいに扱ったり、『鰻のたいこ』では、こんな風に勘定書きになったりします」
おーっという地響きのような、感嘆のどよめきが起こる。
「変わったとこだと、焼き芋とかね」
手ぬぐいを無造作に丸めるとあちあちっと手の中で転がし、はふはふしながら美味しそうに囓ってみせる。
おー、と更なる歓声があがる。
「長いものは扇子で代用します。煙管(きせる)、昔の煙草とか、そろばん、手紙を書くときの筆とかね」
といいながら、左手をひらき右手は筆に見立てた扇子でさらさらと書く仕草をする。
「すげー。ほんとに何か書いてるみたい!」
「いいぞ。アンドーナツ、演技うまい! エアーでうどん食ってるー」
感嘆の声があがり、パチパチと拍手までおこる。舞台の袖から金魚柄の浴衣姿のアリスが「お茶子」に扮し、登場する。座布団と見台をテキパキと中央に設置すると、『揚亭アンドーナツ』と演者の名前が書かれた「名ビラ」をめくり退く。同時に、タイミングよく三味線でアレンジされたドレミの歌のテープが流れる。揚亭アンドーナツの出囃子だ。
児童たちが「ドーはドーナツのド~♪」と叫ぶようにテープの音源に合わせて口ずさむのが聞こえる。出囃子が終わり、奈津は深々とお辞儀すると、膝の前で手をハの字に置き、手のひら全体を床につける。顔をあげ、舞台の上から体育館全体をゆっくりと見渡す。
児童らは、思い思いの場所で体育座りして、奈津を見ている。奈津は視線を受けとめると、ゴクリと唾を飲み込む。深呼吸すると、
「いっぱいのお運びで、厚く御礼申し上げます。では、ここで一席。名前の由来というのは実に興味のあるものでして、人の名前ならそれこそ親御さんの思い入れが込められて、ひとつの物語が出来上がってしまおうかというもので……」
奈津は、「登場人物が少なく」「話の短い」「内容の簡潔」な児童たちがとっつきやすい『つる』を演じた。
職員室の自席に戻り、一息ついていると、「なかなかの盛況ぶりでしたね」と校長がニコニコしていた。見学会の終了時に入会届けは配った。が、まだ入会届けの提出は一枚たりともない。担任を通じて提出する子、また直接、奈津の元に持ってくる子もいるだろう。
◇◇◇
一週間が経った。落語クラブの入会届は、まだ一通も奈津の手元には届いていなかった。さすがにおかしいと思い始めたていたら、六年一組の中山果奈(かな)が奈津のもとにやってきた。
「もしかして、入会届け?」
奈津ははやる気持ちを抑えるようにして、聞く。
「いいえ。違います」
とんでもないというように、首と手を左右にブルブルと横に振る。
「先生にちょっとご忠告しておこうと思って……」
果奈は一組の学級カーストでは一番上のランクの児童だった。顔もそこそこかわいくて、頭もいい。クラスではリーダー的な存在だ。母親がPTAの役員をしているらしく、学校行事に熱心で、なにかと学校側は気を遣う存在らしかった。笑顔であるが、口元がゆがんでいる。含みのある笑みだった。まるで悪代官に耳打ちする越後屋の主人のようだ。
「なになに?」
「渕田アリスさんのことです」
奈津は思わず、身を乗り出してしまう。その反応に手ごたえを感じた果奈は不敵な笑みを浮かべた。
「先生、落語クラブに入った人いますか?」
果奈はいきなり確信をズバズバと衝いてくる。子どもだと侮っていたら痛い目にあうと奈津は察する。
「うーん。まだ届いてないみたいね。担任の先生方が預かってるのかな?」ととぼける。
「なんでだかわかりますか?」
あんなに説明会では見学者がやってきたし、反応も上々で手応えもあった。はずだ。
「わかんない。中山さんにはわかるの?」
「わかんないんだぁー。意外と先生、鈍いね。弁護士のくせに。子どもの頃、女子の友達いなかったんじゃない?」
――土足で人の心の中に踏み込んでくるな。女子特有の意地悪さがプンプン漂ってくる。
「やだ! 先生もアリスも同じ匂いがするー。女子のコミュニティで生きてけないタイプ。女子に嫌われる似たもの同士!」
果奈は鼻で笑うと踵を返して机から遠ざかる。このまま果奈を逃してはダメだと、奈津は直感的に感じると、必死に引き留めようとする。
――どうする? どうしたらいい?
奈津は働かない思考にムチを打ち、フル回転させる。
「ちょっと待った! ほら、入会届忘れてる。中山果奈さん、あなたを落語クラブにスカウトします。ほら、ここに名前書いて。その洞察力の鋭さ、押しの強さ、物怖じしない性格。向いてる。絶対、落語家に向いてるから。欲しい逸材。喉から手が出るほど必要な人材だわ」
とまくし立てるような早口で奈津がいう。論理がはちゃめちゃだ。後ろめたい時こそ、人間って饒舌になるよなぁ、と反省しつつも不円滑な思考を奮い立たせる。
「はぁ?」
果奈はまんざらでもない。褒められたと受け取ったようだった。「落語家に向いている」といわれたことと、自分が必要とされたことで、自尊心をくすぐられ果奈は心を揺さぶられたようだった。単純。まだまだ子どもだ。
「お願い! 果奈ちゃん。君ならトップスターになれる」
両手を合わせ拝むようなポーズをとる奈津。
「わかった。入会します」
果奈はえんぴつと入会届を受け取ると、氏名の欄に丁寧な字で中山果奈と署名した。
「きれいな字。硬筆二段ってとこかな」
「三段です」
果奈は鼻を膨らます。
「それは失礼しました。字には人柄が表れるんだよね。とっても素直で力強い、美しい字だと思う」
奈津は心底そう思い、しみじみいう。
――こんな字を書く人間に悪人はいない
「先生、褒めすぎだって」
果奈は案外、素直だった。単細胞でわかりやすい。早速、部室にしている空き教室に連れて行くと、アリスとも普通に話している。
果奈がアリスの耳元で囁き、アリスが笑う。アリスがあんな風に友だちと冗談をいって笑っているのをあまり目にすることがないので、驚く。
果奈との折り合いは拍子抜けするぐらいすんなり馴染んでいた。
アリスが「果奈の練習する噺を決める!」といい、果奈も「ありがとう」とすんなり受け入れている。
「暗記力ビミョーだから短いのにしてよ」と果奈がリクエストすると、「それが落語だと覚えられるんだってばー」とアリスが答え、「短いけど、かっこいいヤツがいいな」と果奈が追加の注文をする。ふたりの間に入る余地がない。そもそもふたりは初対面でもなく、クラスメイトで、元は同じグループの仲良しだったのだから当然だった。女子はすぐに意気投合し、すぐ仲違いするからややこしい。単純なようでとても複雑だ。
ふたりは「あめんぼあかいなあいうえお」と発声練習を始めた。
「かきのき くりのき かきくけこ」
ふたりの声がユニゾンする。とりあえず、奈津は胸をなで下ろす。
落語クラブの噂を聞きつけたのか、毎日、ひとり、またふたりと入会希望者が訪れては入会した。男子もぼちぼち入会しだした。
男子がふえると、良くも悪くもわちゃわちゃとしだす。じっとしていられないようで、追いかけっこしたり、漫画を広げて大騒ぎしている男子もいる。同学年でも男子の方が圧倒的に精神年齢が低い。
それでなくても、落語の指導なんて奈津にとっては初めてのことで、どう教えるのがいいのか試行錯誤だった。
本来なら、ひとりひとり稽古つけるとか、好きな落語家のテープやDVDを何度も見てストーリー、台詞、身振り手振りを覚えるのだけれど、小学生には難しいだろう。
まずは手始めにみんなで同じ課題「寿限無」をやることにする。
前日に寿限無を平仮名でパソコン打ちして、みんなに配布する。この暗記で何人かの脱落者が出てしまうかもしれなかった。本当に落語をやりたいと残った子がいれば彼らの才能の芽をなんとか伸ばしてやりたい。
最終的には奈津も子どもの頃に出場したこども落語全国大会出場のエントリーが目標だ。スポットライトが当たる華やかな舞台に立って欲しい。
「ただの文字の羅列だと思うから、覚えられないんだよ。ちゃんと意味を把握してみて。寿限無は子どもの幸せを願った親の話です。みんなの名前にもご両親の願いが込められているんだから。いつの時代も親の子を思う気持ちは一緒ってことです」
寿限無は、上方落語では「長名」といわれていて、代表的な前座噺のひとつだ。奈津はストーリーをかみ砕き、子どもたちにわかやすく解説する。
「むかし、むかし、あるところになかなか子どもが生まれない夫婦がいました。でも、ある時、ようやく可愛い男の子の赤ちゃんが生まれました」
「おいおい昔話始めるのかよっ」と間髪入れずに、男子がチャチャを入れる。
「こら、ちゃんと聞かないと……わかんないよ」
「シーーーっ!」
果奈が顔の前に人差し指を立て、男子らを制止する。
「みんな、ちゃんと聞こうよ!」
奈津は続ける。
「子どもの幸福を願って夫婦は、お寺の住職にいろいろ縁起のいい子どもが長生きする名前を考えてもらうことにしました。
どれかひとつに絞れない夫婦は、書いてもらった名前をぜーんぶその子につけることにしました。つまり「寿限無寿限無」に始まる長い名前がこの子の本名です。子を思う親の強い気持ちがこの落語の主題です」
なんとなく、納得したように児童たちは頷いている。
「寿限無の名前を全部いえた人から次に進みます」
「えーー無理」
「まじ?」
口々に不平不満が溢れ出す。
「続けます。さて、その男の子は、長いありがたい名前のおかげか、病気も怪我もすることなく、すくすくと元気に育ちました。やがて友だちもできて、一緒に外で遊ぶようになりました。ある時、寿限無は友だちとケンカになってしまって、その子の頭をぽかっとなぐってしまいました。友だちの頭に大きなたんこぶができました。泣きながら寿限無のお母さんのところへ言いつけに行きました」
察しのいい男子児童が騒ぎ出す。
「もしかして、じゃないの?」
奈津は無視して続ける。ちょっと舌っ足らずな口調で、
「じゅげむ、じゅげむ、ごこうのすりきれ、かいじゃりすいぎょのすいぎょうまつ、うんらいまつ、ふうらいまつ、食う寝るところに住むところ、やぶらこうじのぶらこうじパイポ、パイポ、パイポのシューリンガン、シューリンガンのグーリンダイ、グーリンダイのポンポコピーのポンポコナの長久命の長助」
と寿限無の本名をいい終えると、息継ぎして深呼吸する。
「がね、ひどいの。えーん、えーん」と幼い男の子の声色で泣き真似をする。今度は反対をむき、大人びた表情をうかべると、早口で一気にまくし立てる。
「じゅげむ、じゅげむ、ごこうのすりきれ、かいじゃりすいぎょのすいぎょうまつ、うんらいまつ、ふうらいまつ、食う寝るところに住むところ、やぶらこうじのぶらこうじパイポ、パイポ、パイポのシューリンガン、シューリンガンのグーリンダイ、グーリンダイのポンポコピーのポンポコナの長久命の長助、があんたに何かしたのかい?」
「なげぇーよ。名前いうだけ疲れちゃうじゃん」
「もう、省略して寿限無でいいじゃん」
ブーイングの嵐が起こる。が、奈津はひるまない。方向をかえるとまた目に手を当てて泣き真似をする。
「えーん、えーん。あのねぇ、じゅげむ、じゅげむ、ごこうのすりきれ、かいじゃり……がね……ぼくと喧嘩になって、ぼくの頭をポカッとなぐってねぇ、おっきなこぶができたんだよぉ」
「アンドーナツ、名前省略すんなよぉ~」と、今度は間髪入れずはやし立てる。勝手なもんだ。
「みんなは省略しないでちゃんということ! はーい、続けます」
奈津は母親の口調に戻ると、続けた。
「なんですって。うちのじゅげむ、じゅげむ、ごこうのすりきれ、かいじゃりすいぎょのすいぎょうまつ、うんらいまつ……うーん以下省略! が、あんたの頭をなぐって、おっきなこぶを作ったですって? どれどれ。あら、こぶなんてないじゃないの?」
奈津は髪の毛をかきわけこぶを探す仕草をした後、深呼吸するとゆっくり五秒心の中でカウントする。
一瞬、場が静まる。誰かがゴクンと唾を飲む音が聞こえる。固唾を呑みみんなその後の進展を待っている。
奈津はいったん目を瞑ると、今度はぱっと目を見開き、男の子の声色でいう。
「おばちゃん。名前が長すぎるから、もうこぶが引っ込んじゃったよ」
サゲが決まる。どっとどよめくような笑いが起こった。パチパチと誰かが拍手する音がまばらに聞こえ、その拍手の渦がだんだん大きくなっていく。
合わさってひとつの拍子になっていく。「すげー」「やるじゃん」と声が上がる。手拍子に合わせた「アンコール、アンコール!」と、カーテンコールらしきものがポツポツと奈津の耳に届き始めた。子どもたちの賞賛の声だった。
――緊迫性がサゲによっていっぺんに緩められる。緊張がほぐれ、な~んだぁというのが笑いを生む。奈津のバイブルである米朝師匠の「上方落語ノート」を頭の中の引き出しからひっぱりだす。
「こんな感じです。ほら、早く寿限無の名前を全部覚えるように」
寿限無の名前が全部覚えられない子は、絶望の表情を浮かべているし、一生懸命紙をみて暗記する子、机で何度も繰り返し書いて覚えている子、既に空でいえる子、色んな子どもたちがいるのを奈津は微笑ましく見守っている。
アリスをみつけた。彼女は、クラスメイトの女子と向き合いその子の暗唱にじっと耳を傾けている。果奈もリーダーシップをとり男子数名を従えて賑やかに指導している。
――クラスのヒエラルキーは簡単に覆らない。
奈津は子どもたちの人間関係を単純なものだと見誤っていた。クラスでは勉強以外の能力や容姿などにより格付けされ、階層が形成される。
階層間の交流は分断され、上位の者が下位の者を軽んじるスクールカーストがうまれる。いじめの原因ともされていて問題視されている。
子どもたちには彼らなりのフィルターがあるみたいだった。
運動会で一等をとればいきなり人気者になる。レアもののゲームをゲットすれば、羨望のまなざしで見られる。そんな反面、ひとつの発言が波紋を呼び一軍の「イケてる子」が、いきなり最下層に脱落することもある。
一度、最下層まで落ちてしまうと地位の挽回は難しいようだった。 落語クラブでの活動では、アリスの周りにだんだん人が集まりつつあった。それでもまだ、ひとりで給食を食べ、移動教室も、トイレもいつもひとり行動だった。
放課後、職員室に日誌を持ってきた果奈を捕まえる。いつも果奈は誰かと一緒なので、彼女がひとりになるタイミングを伺っていた。奈津はさりげなさを装いつつ、話しかける。
「中山果奈さん、ちょっといいかな?」
不意を突かれて果奈は立ち止まる。
「君はアリスのことが嫌いなの? ずっと彼女の事、怒ってるよね」
「はぁ?」
「君はまっすぐな子だから理不尽な事で怒らないはず。教えてよ、その理由をさぁ」
「なんで? カンケーないでしょ」
果奈はつれない。
「だって、怒る方も怒られる方も疲れるじゃない。そろそろ手打ちにしようよ」
「手打ち? ……そば? 私、蕎麦アレルギーなんですけど」
ぽかんとした表情を浮かべる果奈はやっぱり小学生だなぁと奈津は思う。かみ砕いて説明する。
「手打ちは、仲直りするっていう意味ね」
「ふーん……そうなんだ。でも、決めてるから」
果奈は強い口調でいい切った。
「理由だけでも教えてくれない?」
「なんか、刑事みたい。渕田さんに聞けばいいじゃないんですか」
「聞いてもアリスは、絶対にいわないから」
「容疑者は完黙か」
「完全黙秘。よく知ってるね。警察の専門用語だよ」
「だって、刑事ドラマ好きだし」
「『踊る大捜査線』、よかったよねー。事件は会議室で起こってるんじゃない!」
「なにそれ。知らないんですけど」
「……うそ。織田裕二のドラマ知らない? 青島は? 室井もすみれさんも知らないの?」 いささか奈津はショックを受けた。ジェネレーションギャップ。世代が違うのか。
一世風靡し高視聴率をたたき出したあの伝説のドラマを知らないだなんて。視聴者は架空の湾岸署を実在すると思っていた。
「渕田さん、チクッてないんだ。それともアンドーナツに知られて嫌われたくないんだね。黒歴史だからさぁ」
笑みを浮かべる果奈の口元は右は口角は上がり、左は下がり、歪んでいる。表情筋からも意地悪さが溢れている。交渉決裂か、と奈津はいったん引き下がることにする。
「相棒は再放送もママに録画してもらって撮り溜めて観てるから初代の相棒だった亀山薫時代から知ってるよ。最近だと『MIU404』が好きだったなぁ。今は『ハコヅメ』みてる。交番勤務もいいかなぁって」
「あ、私も科捜研はみてるかな。あの時間帯って食事時でいつも惰性でみてる」
と奈津も負けじと応戦する。
スクールロイヤーには捜査権はない。でも、事情を聴取して事実関係の調査をするのは果奈がいうように、刑事の仕事と似ているかもしれない。修習生の頃、奈津は検事志望だった。昔のことすぎて、自分でもすっかり忘れていた。
「じゃあヒントね。学校の裏サイトみてみなよ」
果奈は逃げるように職員室を後にした。学校裏サイトとは、学校の公式サイトとは別に児童などが作成した非公式のサイトだ。掲示板など、利用者がコメントを書き込める方式になっている。
部外者が入れないようにパスワードがかかっていて、学校名で検索をかけてもヒットしないし、携帯電話でしかアクセスできないなど、保護者や教師にみつからないための工夫が施されている。
——小学生にまで、こんなにネットが普及しているとは思わなかった。
デジタルネイティブ世代との知識の差に、奈津はお手上げだった。そもそも裏サイトにたどり着けない。
2ちゃんねる、やYahoo!掲示板のスレッドなら発見できたとしても、独立したサイトとなると、どう見つけていいかさえわからない。
ネット上でアリスが標的になっていると思うと、いてもたってもいられない気持ちになる。
今、この瞬間さえもアリスの悪口や噂が書き込まれているかもしれない。実名を出していなくてもイニシャルやあだ名など、個人が特定できる書き込みは名誉棄損や侮辱罪などの犯罪にあたる可能性だってある。
ネット上では、相手の顔が見えないのをいいことに、攻撃的な言葉を実際に声にだしていうわけではないので、いじめを行っているという感覚が希薄で行為がエスカレートしやすい。実生活では、いじめに加担しないような児童でもネット上、しかも匿名となれば、相手を攻撃しやすくなってしまうのは当然だ。
現にアリスは実際の学校生活においていじめのターゲットになっているようだった。大人の世界だって、ネット上での誹謗中傷があとを絶たないのだ。同期で、ネットに詳しい弁護士に連絡をとり、裏サイトを探してもらうことにした。
——もう後悔したくない。
そう強く思ったところで、心の堰から溢れ出てきそうになる流水を必死でとめようとする。
それでも少しずつ流れだすのは、思い出したくない過去であり、罪の意識や重い記憶だった。それらのすべてがネガティブな感情だった。
堰き止めなければいけない。意識をそらそうとするが、既に遅かった。昔、初めて付添人をした少年への罪悪感が溢れ出ていた。
彼は奈津が初めて担当した少年事件の被疑者だった。当番弁護士で初めて面会した時も斜に構えて、質問にも素直に答えようとしなかった。足しげく鑑別所に通って面会した。彼は終始不機嫌だった。
無愛想でこちらの話を聞いているのか、説明を理解しているのか、いないのか、全くわからなかった。コミュニケーションがとれないまま、審判の日を迎えた。
「本当のことをいってくれないと情状は望めない。このままだと少年院送致になってしまうよ」と何度も繰り返し伝えたが、態度は改められなかった。出身中学の校舎に忍び込んでガラスを割った器物損壊罪。
スーパーの精肉売り場に置いてある牛脂を何個も口にいれ「スタッフが美味しくいただきました」というテロップを入れたいたずら動画を作成し、ネット上にアップした悪ふざけが過ぎたいたずらは偽計業務妨害。
「ねえ、どうしてそんなことをしたの」
問いには返事はなく無言だった。この沈黙が永遠に続きそうだと奈津は思う。動機も、余罪、共犯の少年の氏名についても、彼は一向に口を割らない。事務所の他の事件も同時進行で抱えているから、時間に追われて余裕がなく、ついイラッとしてしまう。「折角、時間を作ってきたのに」といいそうになり、言葉を飲み込む。「のに」がつくとそれは愚痴になる。
少年が思うように対応してくれないからといって怒るのは筋違いだ。冷静なもうひとりの奈津がたしなめる。
この子を叱っても一緒だ。大人を信用していないのだから。じゃあどうすれば信用してもらえる? 奈津は精一杯考える。スケジュール調整して、家庭裁判所の調査官に掛け合い、彼の両親にも、高校の担任に会うために学校まで行った。
みんな口を揃えていうのは「あいつはどうしようもないワルだ」と、匙を投げていた。誰からも見放されていた。奈津も理解不可能な人種、サイコパスだから仕方ないと自分を納得させるようになっていった。
彼が実際にサイコパスかどうかは問題ではなく、奈津が理解に苦しむ人間をサイコパスという言葉で定型化し分類しただけのことだった。精神的にも肉体的にも、限界を感じていた。
事務所に戻ってもみな自分のことが精一杯で相談する相手もいなかった。国選の少年事件はプロボノ、つまり弁護士資格を活かした社会貢献の意味合いがある。事務所の雇われ弁護士でありながら個人事件で動いているから、同期のアソシエイトには愚痴れない。「事務所の仕事で成果をあげろよ」とか「ボランティア活動なんて余裕だな!」と鼻で笑われるのがオチだ。
誰にも弱音を吐けず、相談も出来ず、孤独だった。みんなタイムチャージで動いて成果をあげている。アソシエイツの同期たちはライバルでしかなくて、蹴落とし自分がのし上がることに必死だった。同期の誰よりも早くパートナーになることが、彼らのマテリアリティだった。
あの日も慣れっこになった行程の少年鑑別所の道のりを奈津は急いでいた。受付が午後五時までなので、あと数分しかない。
間に合ったとほっとしたのもつかの間、面会室に入ってきた少年はやっぱり無愛想だった。
奈津のことを鼻で笑い「先生じゃ、何もできないよ」といった。馬鹿にされている。心がポキっと折れる音が聞こえる。
初めての少年事件でテンパっていた新人弁護士としては痛いところをつかれ、それが図星だっただけにプライドを傷つけられた。こんな奴どうにでもなれ、と思った。付添人失格だ。
奈津は付添人なのに、最後まで彼の心の声を掬い取ることが出来なかった。審判は予想どおり少年院送致だった。保護観察にできなかったことを悔いる気持ちはなかった。反抗的な態度だし、仕方ない、とむしろ自己弁護した。
数年後、彼が起こした傷害事件の記事を新聞でみつけた。あおり運転だった。車の割り込みでカッとして暴行事件に発展した。
今度は実名報道だった。前歴が前科になった。少年院にいっても彼はまともな人生を歩めなかったのだなぁと人ごとみたいに思った。やはり自分には責任がなかったのだと、むしろホッとした。
それからひと月ぐらいたった頃に、その思いは覆された。あおり運転の特集記事で彼を追跡取材した週刊誌を偶然目にしたのだった。てっきり、暴行に及んだ犯人を非難する記事だろうと軽い気持ちで読み始めてそれがとんでもない見当違いだったことを知った。
奈津は食い入るように読みふけった。記事は犯人、つまり彼の生い立ちから奈津が担当したあの少年事件の事、少年院から退院した後の彼の人生についてなぜ、あの事件に至ったのか? までが、丁寧に取材され書かれていた。記事は彼の生い立ちに同情的で、ともすれば擁護する内容だった。
父親から暴力を振るわれ、母親も姉も怪我が絶えず、酒浸りで働かない父の代わりにバイトに明け暮れる日々だったこと。誰も彼に救いの手を差し伸べなかったこと。
こうした犯罪を止めるには、事件の背景を解明し、社会で広く認識すべきであると記事は締めくくっていた。事件の根底には社会全般への不満や、不満を生み出す格差や貧困があり、類似の事件が起き続けていることも問題視していた。
家庭訪問に行った時のことを全力で思い出そうとしたが、当時の記憶はあいまいだった。ただ、その時に不自然に思ったり疑問に思ったりはしなかった。母親からはあまり発言がなく、父親の独断場だった。特に何かを隠している様子は見受けられなかった。
あれはもしかしたら父親のDVにおびえて黙っていたのに、気づかなかっただけではないのか? そう思うと状況はガラリと変わる。彼について何も知らなかった事、彼の窮状に気づいてやれなかった事に、奈津はショックを受けた。
必死に助けを求めていた彼を「無愛想で反抗的で何を考えているのかわからない少年」とレッテルを貼り、自分の都合がいいように決めつけていただけだった。
もし、あの時、彼が抱える家庭の問題に気づいていたら? だとしたら何ができたのか? 審判の結果は変わっていたのかと問われれば、自信がない。気づこうともしなかった自分の怠慢と理解しようとしなかった傲慢さに落胆し、弁護士としてあるまじき行動だと嫌悪感を抱いた。
胸からこみ上げてくる吐き気にあらがえず、奈津は駆け込んだトイレの洗面台に嘔吐した。透明な吐物が咽喉から噴水みたいに飛びだした。
その吐物にひっぱられてまた胃の奥から吐き気がこみ上げてくる。きゅっと胃が縮こまって痙攣する。
何度吐いても吐き気が治まらず、もう吐けるものがなくて、胃液しか残っていない。それでも嘔吐く。苦しくて目尻を涙が伝った。
彼に一言謝りたかった。当時の事件記録をひっぱりだして彼の母親の携帯電話にかけてみたが、既に番号がかわっていて話すことは叶わなかった。
それからだった。法廷に立つと言葉が出なくなった。貝のように固く閉じてしまった口は脳が命令しても開かない。言葉は頭に浮かんだそばから消えてしまう。事務所の先輩に勧められて、心療内科を受診すると、場面緘黙だと診断された。
カウンセリングを何度か受けて、あの少年の事を忘れることはできないが、彼に対する罪の意識については、心の堰で感情を止めるというイメージを持つことで折り合いをつけることができるようになった。
少年の事で激しく動揺する事は減ったが、場面緘黙は依然として治らない。奈津は自分には法廷に立つ資格がないと烙印をおされた気がした。ずっとこの先、十字架を背負って弁護士を続けていくのだと思うと、仕事を続る意味がわからなくなる。
◇◇◇
翌日、同期のネットに強い弁護士から連絡があった。依頼していた裏サイトの検索の件で、成果があったという。中山果奈がいったように学校裏サイトは存在した。
小学生なのでそこまでひどい悪意や、誹謗中傷には至らず、どちらかというと噂ばなしレベルのもので、教員のあだ名や悪口といったものがほとんどであった。
アリスへの批判もあった。アリスがいじめたとされるA子は奈良の小学校に転校したという記載もあった。奈津は混乱する。
——いじめの加害者がアリスで、別にいじめの被害者がいたということか?
どういうことだろうか。今、見えている事実と、真実は違うのだろうか? パラレルワールドに迷い込んだみたいだった。いずれにしても、A子なる人物がキーパーソンのようだった。イニシャルなので、フルネームまではわからない。
でもこの一年以内に奈良の小学校に転校した女子児童であれば、特定は難しくないはずだ。
奈津はスクールロイヤーとはいえ、学校では部外者扱いなので児童たちのデータベースにアクセスするパスワードを教えてもらっていない。これ以上、秘密裏に動くには限界がある。
「なあ、安藤。秋翔とは連絡とってないの?」
突然、予想だにしない問いかけに、奈津は思考停止してしまう。
小柴秋翔。奈津の元彼で、ロースクール時代をともに過ごした同士。
「おまえらさ、そのまま結婚するかと思ってたけど……あ、ごめん。こないださ、さいたま家裁で秋翔とばったり会ってさ。あいつ調査官してるんだよ。ほら、少年事件とか子どもたちのこと詳しいだろうし、俺よりあいつ頼りになるだろし相談してみたらどうかと思って」
「ごめん、ちょっと急ぎの用思い出した。ほんと、ありがとうね」
奈津は一方的に会話を終わらせた。ふーっとため息をつく。過去を過去と言い切れないまだ瘡蓋になっていないジュクジュクしてる傷口。
秋翔とは一緒に司法試験合格を目指した仲で恋人だった。一日十時間以上勉強しても、モチベーションを保てたのは彼がいたからだった。弱音を吐き、励まし合った。この環境におかれた者にしか、わからない不安やつらさを分かち合った。喧嘩もした。
だから、二度目の試験で奈津が合格し、一足先に弁護士生活をスタートさせ、秋翔も合格を目指し、共に同じ方向をむいていた。ふたりの仲は揺るぎなかった。どんどん仕事量が増え成果主義の外資系のファームで追い詰められる奈津と秋翔の五度目の司法試験が重なった時、最大の危機が訪れた。ふたりは乗り越えられなかった。
出会ったばかりの頃は、お互いに見つめ合い、微笑み合うことが多かったふたりも、長く付き合ううちにいつしかお互いに別の方向をみていたのだった。
奈津が体調を崩し事務所を辞め大阪に帰ったことも秋翔は知らないはずだった。今も場面緘黙という病を抱えていることも。
「何を嗅ぎまわってるの? アンドーナツ先生」
「完全に行動読まれてますね。私……」
「あ、自白した」と嬉しそうに多江がはやし立てる。いつもニコニコしていて、肝っ玉なところがある。教員の中でも中間管理職ながら頼れる姉貴分の位置づけだった。
校長以外で、奈津に話しかけてくる唯一の教員なので、奈津も心を許している。内容が内容だけに、学校で話すのは憚られるので、学校終わりに近くの居酒屋で待ち合わせすることにする。
「乾杯!」
ふたりは軽くジョッキをあわせる。奈津と多江は駅前のチェーンの居酒屋にいた。多江は、いっきに中ジョッキのビールを半分ほどあけると、ぷはーっと息を吐いた。
「家ではさ、一日に缶ビール一本って夫と決めてて抜け駆けすると叱られるの。外で飲むビールはうまい! ねー」
「先生たちって、飲み会したりするんですか」
「そりゃするよ。でも、小学校の教員って男女比率が微妙に女子の方が勝ってて、男の先生たちが肩身狭いらしくて、事あるごとに男子会、男子会って男性教諭のみでこそこそ集まって飲み会してるわ」
「へぇ、知らなかった」
「で、何か聞きたいことあるんじゃないの? 児童のこと?」
「そうなんです。実は……六年一組の渕田アリスのことなんです。彼女クラスでも浮いていて、ちょっと気になってしまってて」
「うんうん」多江は、相づちをうちながらお通しのたこの塩辛を箸でつまんで口にいれた。辛かったのか、鼻にシワを寄せて、またすぐビールを喉に流し込む。
「ちらっと耳にしたんですが、渕田アリスがいじめの主犯格で、被害者の児童が奈良に転校したという話もあって、どうにも混乱していて。クラスの子たちは誰も話そうとしないですし、当人はその話題に触れられるのも嫌なようで、全く状況がつかめなくて困っているんです」
「いじめっていう程でもないと思うけどね。あまり、教員が介入するとこじれるから気をつけた方がいいよ。これはアドバイス」
「でも……もし彼女がいじめを苦にして万が一ってことも、ないとは限らないですし」奈津は、はいそうですね、とは肯定できない。
「校長に何かいわれた? 学校っていじめについてはすごく敏感だから。何かあってからでは遅いって」
「むしろ寛容すぎないかって心配になちゃって。自分で考えみなさいっていわれて、そのままになってました」
「校長はね、子どもたちには失敗の経験も必要だってことがいいたいんだと思う。失敗してどう対処するかとか、どう立ち直るか、その過程が学びなんよ。だから転んで、怪我して、もう自力ではどうにもならないって助けを求めている子に、教師は手をさしのべてやればいいってことかな」
「スパルタですね」
「放任ではないの。あの子たちに考える余地を与えてるんだよね。見守っているというか」
多江は空になったジョッキを手にもったまま所在なさげに眺めている。
「そりゃ、問題になりそうなことを先廻りして、危険な芽を摘みとってやる方が楽だよ。それでも、失敗しちゃうのが人間なんだよね。どんどん失敗すればいい。子どもはやり直しがきくし。大人はそうはいかない。でしょ?」
「ですね」奈津が同調すると、多江はおかわりのビールを店員に頼んだ。
「奈良に転校した子は、いじめが原因ではなかったの。でも、どこからともなくそんな噂が流れてるみたいね。確かに渕田アリスとその子の間にはいざこざがあったのは事実だけど」
「いじめが原因じゃないなら何故、アリスは否定しないんでしょうか」
「なんでだろ」といいながら多江はビールを店員からうけとるとジョッキに顔をもっていく。ごくごく喉をならしながら飲むと、口の周りについた白い泡を舌でかすめとる。
「子どもの世界って大人以上にわからないんよね。複雑怪奇。だから理解しようとしても無駄なの。気づいてるよー、あなたのことちゃんと見てるよって子どもたちに必死で合図送ってさ、相手がアクション起こしてくれるのをひたすら待ってるの。教師って授業して一方的に教えるだけが仕事じゃないから。待つのも仕事なの」
と多江はわけぎのぬた和えをつまみに、またビールをぐびぐび飲む。
「たった一度でもさぁー、魂がふるえるような瞬間を経験したら、それだけで後の人生、生きていける気がするなぁ。悲しみとか、苦しみとかあってどんなにつらくてもも『よし!もう一度やるぞ』ってファイトが沸いてくるんじゃないかな。教師ってまさにそれなんだよね。失敗して凹むこともあるけど、長くやってると救われる瞬間も確かにあって、あー、続けててよかったって思う。嫌なことも帳消しにしちゃうようなミラクルなことってあるんよ。二十年選手になって、やっとそれがわかる気がする」
しみじみいうと、照れ隠しのように、わざと明るく「さあ、食べちゃおう」といってテーブルの料理をかたづけ始める。
奈津も自家製コロッケを取り皿にとると、箸で半分にわり、口に入れる。まだ、ほんのり温かい。粗くつぶされたじゃがいもは、ほっこりしていて甘みが口に広がる。思わず旨い! と唸る。
「ここのコロッケ美味しいんだよね。じゃがいも、バイヤーが北海道の農家に買い付けに行くらしいよ」
「それ、誰の情報ですか?」
「うちの夫情報。居酒屋通なのよ。それよか、恋バナしてよ。奈津先生だっていい人ぐらい、いるでしょ? 東京ラブストリー、あったんじゃないの。カンチー! リカって」
「多江先生、それ世代違うかも。ロースクール時代はほんと勉強ばっかでした。寝ても覚めても六法開いてました。六法が恋人って」
あの頃は一日、十時間以上、勉強していた。
「だって上京したら観光ぐらいするでしょ? はとバスとかさ」
「東京タワーは行きました」
ふと、奈津の脳裏にオレンジ色の光を放つ東京タワーの夜景がフラッシュバックする。
◇◇◇
「東京タワー、下から見るか? 横から見るか?」
と秋翔がいうと間髪入れずに奈津がいう。
「それいうなら、『打ち上げ花火、下から見るか、横から見るか』じゃないの」
岩井俊二の映画の題名だった。ふたりはびっくりするぐら映画の好みがドンピシャだった。映画の題名から「じゃあ、東京タワーはどの角度からみるのが一番いいか?」ということになり、実証検分だとふたりは急遽、東京タワーを見に来たのだった。
奈津も秋翔もまだ東京タワーをみていなかった。まずは下から見てみあげようと、JR山手線に乗ると浜松町の駅で降りた。北口改札を出る。前方に東京タワーがちっちゃくオレンジに光っているのが見える。そっちに向かって真っ直ぐ、ふたりは歩いた。
ビルの隙間からタワーが覗いている。大通りの交差点を渡って更に進むと、東京タワーがだんだん、大きくなっていく。
左手に世界貿易センタービルの夜景が見える。オフィス街とはいえ夜だから人通りも少ない。どこからともなく、魚の干物を焼く香ばしいにおいがする。ビルの一階が立ち飲みになっていて、サラリーマンたちが楽しそうに飲んだくれている。
「これ山門かな? この先にお寺があるのかな?」
と道路の中に突如現れた山門を見上げ、奈津がいうと、「増上寺の山門だよ」物知りの秋翔が答える。
山門をくぐり、歩道をふたりして歩く。信号が青に変わり横断歩道を渡ると、増上寺の本堂が正面に見えた。その斜め後ろに随分大きくなった東京タワーが見えた。
「夜だけど、中に入ってもいいよね?」
お寺と東京タワーの組み合わせはミスマッチだったけれど、「こんなところから?」という驚きがあった。
「知る人ぞ知るの東京タワーっぽいね。ここって秘密のスポットじゃない?」
奈津がはしゃぐと、秋翔はポケットからスマホを取り出すと東京タワーと奈津のツーショットを撮る。
「いつか、東京タワーにのぼってみたい」と奈津がいうと、「馬鹿と煙は高いところへ上るっていうな」「それってひどくない?」「わかったわかった。合格したら記念にふたりでのぼろう」と秋翔が最後は折れた。淡くほろ苦い想い出だった。
◇◇◇
「でもね結局、わたしたち東京タワーは下から見上げただけで、上らずじまいだったですよ。ふたりが合格したらのぼる約束は叶わず、でした。あの頃は共に同じ方向を見つめてました」多江に答えるでもなく、奈津はしみじみいう。
「やだ、ごめん。もしかして地雷踏んじゃった? 恋は、甘酸っぱいよね」
奈津はうなずく。満腹とほろ酔いで、感傷に浸りつつ、思考を正常値に戻す。まだぼんやりとした脳のまま、アリスのことを思う。結局、思考はそこに行き着く。
ずっと引っかかっているのだ。彼女が話してくれるのを待つほかないのだろうか。八方ふさがりだった。奈津からため息が漏れる。料理も尽きて、会話も途切れがちになってくると、ふたりは潮どきとばかりに会計を割り勘し、それぞれの家路につく。
帰り際に多江は奈良の小学校に転校した児童、A子の情報を教えてくれた。転校先とフルネーム。日高あかり。五年生の時、渕田アリス、中山果奈、日高あかりの三人は同じグループで仲がよかったらしい。
あかりは、大和郡山小学校で元気にやっているとのことだった。奈津は大和郡山小を訪ねあかりを探してみようと思う。折角つかんだ手がかりだ。どんな小さなことも見逃しはしないと心に誓う。
翌日、奈津は下校時刻、大和郡山小学校の正門前にいた。スマホには多江先生が送ってくれた五年一組の集合写真がうつし出されている。アリス、果奈、となりにはショートカットでボーイッシュな女の子が写っている。
ピンチアウトするとショートカットの女の子がアップになる。下校する小学生の児童の中に、奈津はその子をみつけると、
「日高あかりさ~ん! あかりちゃん!」
と呼びかけ手を振る。ショートの女の子は声の主を探してキョロキョロしている。やがて奈津と目が合い立ち止まる。
課外活動の落語クラブはつづいている。いっときは教室に入りきれないぐいらの児童たちがやってきたが、次第に淘汰され今では定期的に訪れる生徒は六、七人といったところだった。
ある程度は予想していたものの、ここまで脱落者が続出するとは予想だにしなかった。小学生には暗記はハードルが高すぎたかもしれないと、奈津は落胆の色を隠せない。「つまんねぇ」とか「覚えられるかよ!」とか、捨て台詞を吐いてそのうち来なくなる。その中で熱心に落語を学んでいるのは、アリスと果奈のふたりだった。
仲よくというよりはライバル的な存在だった。お互いが相手より上手くなりたいという気持ちが強いのだ。奈津は部員も定着してきたし、そろそろ何か活動の成果を出したいと考えていた。
「みんなに相談があるの。こども落語全国大会に参加してみようと思うんだけど、どうかな? 参加してみようと思う人いるかな」
アリスと果奈が競うように手をあげた。他の部員たちはどうしようか、迷っているようだった。
「あのね、大会出場するのはピアノの発表会みたいに、ひとつの課題曲を完璧に弾けるようにするってことなの。ひとつの噺を完璧に演じられるようになったらいいなって思うからです」
奈津はできるだけ、子どもたちにわかるように説明する。
「私もこども落語全国大会に出場して優勝しました。あのね、山のてっぺんに登らなきゃ、向こうは見えないよ!」
「自慢かよ?」
茶々と冷やかしがはいる。奈津は子どもらに挑戦を促す。みんなに勇気をだして頂点を目指して欲しいと願いを込めたつもりだ。
アリスと果奈はもう早速、演目を何にするか、あーでもないこーでもないと話しているようだった。乗り気なのはこのふたりのみで、他のメンバーたちは、大会出場には及び腰で結局、アリスと果奈以外、参加を表明しなかった。
ふたりが報告にきた。アリスは『猫の皿』を果奈は『饅頭こわい』を演じることに決めたらしかった。奈津はやれやれと思う。それから自主練、市立図書館で借りてきたDVDを一緒にみて研究したり、とりあえずはひととおり噺を覚えることに集中した。
「さすが小学生は暗記力がすごいわ」奈津が舌を巻く程に、ふたりは持ち前の暗記力を発揮したし、頑張った。もう、奈津の手助けは必要ないようだった。
奈津は居酒屋での多江とのやりとりを思い起こす。困難に立ちむかうことは決して楽なことではないけれど、きっとその苦労や努力がのちのち「人生は素晴らしい」と思える瞬間につながるはずだ。「青くさくて綺麗事だ!」といわれようが、そう思うことで奈津は解放され自由になれる気がした。
――いいじゃない。私の夢見る空はいつだって雲ひとつない青一色なんだ。
もしかしたら、こども落語全国大会ではアリスと果奈の努力は実らないかもれない。でも、ふたりにとって「人生は素晴らしい」と思える瞬間や経験になるかもしれない。
今の自分なら過去の自分を受け入れることができそうだと奈津は思う。失敗も成功もあるがままの姿を。自分のすべてを。ありのままの姿で生きようと思う。忌々しい刑事事件の失敗も、尻尾を巻いて大阪に逃げて帰ったきたことも含めて自分だ。決して楽ではない人生だけど、あるがままの姿で生きてみたいと思った。
また当番弁護士に登録してみようか。奈津は自問自答する。少年事件を受ける勇気が少しだけ沸いてきた。ブランクを埋めるために、まずは弁護士会の『改正少年法』のウェブ講義の予約をいれた。
少年事件を受けるとなると、必然的に家裁に出向くことが多くなる。審判は勿論、調査官との関わりも大きい。調査官が処遇意見を書くからだ。それに沿って裁判官が審判を下す。
調査官の少年事件に関する役割は大きい。どこかの家庭裁判所で秋翔と再会することも、もしかしたらあるかもしれない。奈津は不完全燃焼に終わった彼とのことを後悔していて、ちゃんと向き合いたいと今ならいえる。心の片隅でずっと引っかかっているのは、秋翔とのことだった。奈津は彼との再会を望んでいる。
◇◇◇
大会の一週間前。リハーサルを兼ねて体育館でふたりが練習の成果を全校生徒にお披露目することになった。
「壮行会兼ねて、盛大にやろう! ふたりもぶっつけ本番じゃ緊張するでしょ? ギャラリーの前でも慣れておかないと」と多江が率先して、お膳立てしてくれた。
居酒屋で飲んで以降、多江は落語クラブの陰の顧問のごとく、何かと動いてくれている。校長の許可、体育館を借りる手配から児童への声をかけ、集客から舞台の設営まで手配してくれた。
学校のシステムにうとい奈津をサポートしてくれている。実は、多江は無類の落語好きであるということもわかった。ひいきの噺家がいるようで、推し活をしているらしいけれど、噺家の名前は何度聞いても教えてくれなかった。アリスと果奈は舞台で演じるのは初めてだった。ふたりの着付けも多江がこなしてくれた。
舞台袖でアリスと果奈はじゃんけんする。果奈がパーでアリスがチョキをだした。
「やったぁ!」とアリスは飛び上がって喜び、「じゃあ先攻で!」と先に舞台の中央へと歩いていく。揚亭バニラアイスの出囃子のテープが流れる。
「武士の世も江戸時代も末期になりますとすっかり変わってきまして……」
とアリスが噺を始めると、ざわついていた体育館が静かになっていく。高座に吸い寄せられるように、みんなの視線が集まる。天性のものなのか、アリスには人の目を惹きつける華やかさがある。
『猫の皿』は江戸の道具屋が田舎に掘り出しものを探しにでかけて、たいした収穫もなく戻ろうと立ち寄った茶屋で一休みしていると飼い猫が餌を食べていた。
その餌の皿が目に入って驚いた。名品の「絵高麗の梅鉢」だったからだ。三百両はくだらない。さては、この皿の価値がわからないに違いないと、さも猫好きであるかのように装って猫と一緒にこの皿を手に入れようとする噺だ。滑稽話で、道具屋と茶屋の店主との駆け引きが見せ場であり、会話のテンポとキレのよさ、演技力も要求される。小学生にはちょっと難しいネタかもしれないと思ったけれど、アリスが挑戦したいというので、その気持ちを優先させた。
序盤はスムーズにすすんでいた。中盤に入り、ペースが落ちた。まだ覚えたてのネタが記憶に定着せず、消化されずに自分のものになっていない。
――落ち着いて。早口になってるよ。なんとかこのまま最後まで畳みかけて。
という奈津の願いは聞き入れられない。突然、アリスがフリーズした。
――嗚呼 飛んだ!
アリスだけ時間が止まっている。頭の中がショートしたのだ。きっと彼女は頭の中が真っ白で思考停止している。奈津は舞台袖から必死に次の台詞をさけび、助け船をだすが、聞こえているはずの声には反応せずだった。アリスは完全にパニックに陥ってしまった。
だんだん、周りもざわつき始めた。「どうしたん?」「何か固まってるやん」「演出ちゃうの?」観客の児童たちが騒ぎ出した。
――このまま終わらせる? 受け囃子を流そうか。強制的に舞台袖に連れてこよう。
その時だった。
「アリスーーーっ! フレーフレー、ア・リ・ス」
場違いな応援のフレーズが聞こえる。女子児童の声だ。舞台まで一直線に届く透き通った声だった。声の主を奈津は探す。観客席ではない。児童たちもあちこち振り向き、必死に探している。体育館の入り口に小柄なショートヘアの女の子と母親らしきふたりが立っている。
日高あかり、だった。あかりは手メガホンで、顔を真っ赤にして叫んでいる。「アリスーっ! ファイトー」「ガンバレー」と。
アリスの耳にも届いた。はっとして冷静さをとりもどし始めると、スラスラと続きを噺しだした。随分途中がショートカットされてしまっているが。
「『猫ってやつは食いつけねぇ皿じゃ食わねえもんだっていうからね。この皿もらっていくよ』『こっちにお椀ありますから。これ持ってって下さい』『いいじゃねえか、こんなこぎたねぇ皿なんか』『それ高麗の梅鉢でなかなか手に入らない皿でございまして、黙ってたって三百両ぐらいで買い手があるんですから』『じゃあなんだってあんな高ぇ皿で猫にめし食わしてるんだ』『ときどき猫が三両で売れます』」
頭を下げるアリス。サゲが決まる。一瞬、音が消える。間があってわぁっと一斉に拍手が沸き起こる。慌てて奈津は受け囃子を流す。鳴り止まない拍手の中、袖にはけるアリスを奈津が抱きしめる。「よくやった! でも、本番ではトチんないでよ」「あんなの初めて。びっくりしたぁ~」と笑っている。トラブルがリハーサルでよかったとつくづく奈津は思う。そして、タオルを投げなかったことも。セコンドがタオルを投げたら試合終了だ。
◇◇◇
体育館にはさっきの手メガホンの少女でアリスを応援した日高あかりが、みんなにとり囲まれていた。和やかで和気あいあいと話をしている。さっきの緊迫感が嘘みたいだ。その輪にアリスと果奈もいる。
「あかり、久しぶり」「急に転校したからみんなびっくりしてたんだよ」口々に話しかけている。あかりはみんなの問いにひとつずつ答える。
「ごめん。お別れいわずに転校したのは、両親が……」
一呼吸置くと、一気に話し出した。
「お父さんとお母さんが離婚したの。それで、奈良のおばあちゃんの家でお母さんと暮らすことになって……アリスだけには、そのこと、いえたんだけど。みんなにはいわないで欲しいってお願いしたの」
あかりは「ごめん」とばかりにアリスを見る。アリスはじっと俯いたまま黙っている。あかりは続ける。
「ごめんね、果奈。果奈んちはいつも家族仲良しだから……いえなかったんだ」
アリスの家は一人親家庭だった。バリキャリの母親は稼ぎはいいけれど、毎日帰宅が遅く、さみしいときは近くの祖父母の家で過ごすことが多いと奈津にいっていた。だから落語が友だちなんだと。
あかりも子供心に同じ境遇のアリスには、両親の離婚のことをすんなりと打ち明けられたのかもしれない。
「あのね、弁護士さんが……奈津先生がね、アリスと果奈がこども全国落語大会にでるよって教えてくれたの。それで応援にきたの。お母さんと」
「ねぇアリス、何で黙ってたの?」果奈の表情は厳しい。怒りで声がうわずっている。アリスに詰め寄る。
「ごめん。約束したから。いわないってあかりと、約束したから……」アリスは声を押し殺していう。
「ごめんね。ふたりとも。みんなもごめん!」あかりがいう。
「ばっかみたい。私、ひとりで馬鹿みたいやん!」
果奈はそういうと、うずくまり泣き出した。果奈も深く傷ついているのだ。アリスとあかりが果奈に駆け寄り、寄り添う。でも、ふたりはどうしていいか、わからない。
「誰も悪くない。だーれも悪くないんだってばぁ! むしろ偉いよ。みんな」
奈津は女子三人をハグしようとする。が、小学六年生三人をひとりで抱えきれない。お互いがお互いを思って、それ故にすれ違ってしまった。絡まった糸は、今やっとほどけはじめた。
三人をみていると奈津までもらい泣きしてしまい、涙で顔がぐしょぐしょになった。
――声をあげて泣いたのは何十年ぶりだろうか?
枯渇していた感情が息を吹き返したみたいに復活する。フィルターがかかっていた世界がにわかにクリアになる。いつのまにかアリス、果奈、あかり、奈津たちはお互いの顔を指さし、泣きべそをかいた顔が不細工だと、互いを笑っている。
多江先生が「今泣いたカラスがもう笑った」というと、「多江先生、意味不明」「わかんない!」「なんじゃそれ」と子どもたちから声があがる。
「えー? もしかしてジェネレーションギャップとか? てへ」と、多江はかわいこぶる。
散々なリハーサルだったけれど、あれからふたりとも本番に向けて猛特訓を積み、無事に地区予選を勝ち抜いた。アリスも果奈も初出場にして、果敢にも優勝を狙っている。梅ヶ枝小でワンツーフィニッシュするんだと豪語している。
◇◇◇
事務所に電話のコール音が鳴り響く。
案里はいつも通りワンコールで電話をとると「安藤綜合法律事務所でございます。はい、安藤でございますね? えっと、弁護士二名おりますが……忠志でしょうか? 奈津の方でしょうか?」と応対し、通話を保留する。
案里は一瞬、不安そうな表情を浮かべたが、なんでもないように、
「奈津先生、弁護士会からお電話です。当番弁護士の要請で少年鑑別所だそうです」
奈津は深呼吸すると、受話器を取った。
「はい、お電話かわりました。弁護士の安藤です!」
奈津は電話の相手に相づちを打ちながら、メモをとっている。忠志も案里も、固唾を呑んで見守った。
「鑑別所に行ってきます!」
奈津は思いの外、元気な声が出たことに、安心する。忙しく頭が回転していると立ち止まってくよくよ考えずにすむ。
発車オーライなのだ。駅に向かう奈津の足取りは早足からだんだん小走りになると、いつの間にか走り出していた。
〈了〉
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

