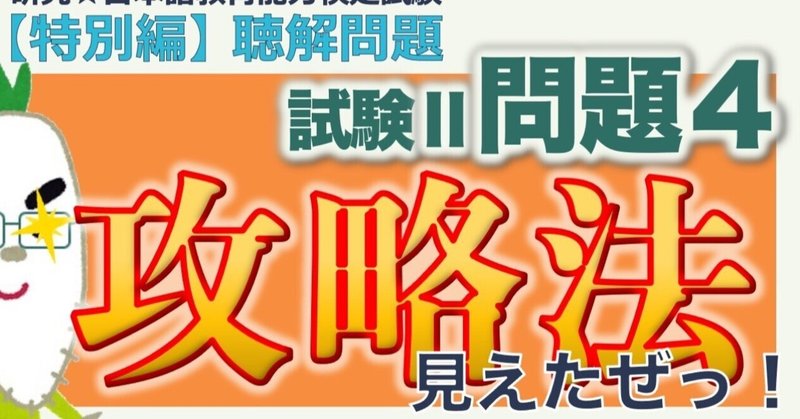
【特別編・試験Ⅱ問題4】日本語教育能力検定試験まとめ
みなさん、こんにちは。大根です。この記事は、以下の動画の原稿を公開しているものです。(全8058文字)
以下の表は、動画の中でお伝えした”過去9年間の選択肢に出た用語のうち、僕が難しいと感じる用語の一覧表”です。表をヒントに、ぜひご自身でそれぞれの用語の意味を調べてみてください。

以下の表は、動画を作るにあたってまとめた、”平成25年度から令和3年度までの問題4を分析した結果をまとめた一覧表”の抜粋です。一覧表の全てをご覧になりたい方は、この記事を購入していただき、記事の最下部のPDFをダウンロードください。みなさん自身が過去問研究するのに役立つと思います。

*2023年7月5日に、”平成25年度から令和4年度”までの問題4を分析した結果をまとめた一覧表を以下のリンク先の記事にて有料公開し始めました。最新の一覧表が必要な場合は、以下のリンク先の記事にてご購入ください。
オープニング
今日は特別編、「試験Ⅱ 問題4」の研究です。
試験Ⅰ・試験Ⅲは筆記試験ですが、試験Ⅱは、いわゆる「聴解問題」と言われる問題です。昼食休憩後の一番眠い時間帯に“聞くこと”に集中しなきゃいけないなんて、けっこうハードです。であれば、いかに脳のリソースを節約して「問題を聞くこと」に全集中できるかが勝負の分かれ目です。
また、今回扱う問題4は、その前の問題1〜3とは明らかに違う点があります。それは何かわかりますか?
この問題には例がありません。問題1〜3までは例がありましたが、この問題4と次の問題5だけは例が無いんです。まぁそんな人はそうそういないと思いますが、1度も過去問や練習問題集を解かずにぶっつけ本番で試験に臨むような方がいるとすれば、問題4がどういう問題かということを理解するので精一杯!点数は伸びないと思います。この動画を見ている時点で、まだ一度も問題4を解いたことがないという方は、この動画を見た後に、すぐにでも解いてみましょう!
それからもう1点。この問題4では、音声を聞くことができるのは1度だけです。この点も問題1〜3とは異なります。問題2は、厳密には同じ人の音声が2度流れませんが、問題で問われている部分を学習者と教師が1度ずつ読んでくれるので、音声は2回聞けます。問題4では問題文が1度しか読まれない。
ということは、集中力が切れるなどして少しでも聞き漏らしたら致命的ということです。
そんな特徴のある問題4。絶対にミスはしたくないですよね!できれば満点取りたいですよね!そんなみなさんのために、平成25年度から令和3年度までの9年間の過去問を徹底分析!その結果を、次の4つのトピックにまとめてお届けします!
1.問題4ってどんな問題?(問題4の流れ)
2.問題4の真実が判明!(問題4の設問分析結果)
3.これで満点ゲット!必勝の4テクニック!(試験当日のテクニック)
4.問題4は〇〇を準備せよっ!(試験勉強の仕方)
動画の最後、まとめの部分で、重要なお知らせを3点します!この動画をぜひ最後までご覧ください!
では、1つ目のトピックに行きましょう〜!
1.問題4ってどんな問題?(問題4の流れ)
解いたことがある方ならもうお分かりだと思いますが、設問が1番〜3番まであり、その中にさらに問1、問2という2つの設問があります。1番〜3番×2問の合計6問(6点)ということです。
問題冊子には、1番〜3番で流される音声の状況について書かれた文章(この動画の中では「大きい設問」と呼びます)と、実際にみなさんが解かなければならない設問(この動画の中では「小さい設問」と呼びます)とその選択肢a〜dが印刷されています。
僕たちがこの問題4で行う基本的な行動の流れは、次の4ステップです。
ステップ1:問題冊子に書かれている大きい設問と、小さい設問・選択肢を読む
ステップ2:小さい設問で問われていることの観点で会話の音声を聞く。
ステップ3:聞き取った音声を根拠に適切な選択肢を選ぶ。
ステップ4:選んだ選択肢をマークシートに塗る。
4つのステップそれぞれについて補足します。
ステップ1ですが、実は、設問と選択肢を読む時間が設定されています。
例えば、「教師と学習者が、授業で乗り物について話しています。最初に話すのは教師です。」のように、問題冊子にも書いてある大きい設問が読まれ、その直後に10秒間の沈黙時間があります。この10秒間の間に小さい設問2つとそれぞれの選択肢を読んでおけ、ということです。
でも、たった10秒しかありません。僕にはとても短すぎます…。
そこで、問題4の冒頭に流れる、問題4自体の説明時間(約1分〜1分20秒あります)も有効活用するのがおすすめです。毎年同じ説明なので聞かなくても大丈夫です。
1番〜3番の問題それぞれの大きい設問、小さい設問と選択肢から、音声の内容を予想しておきます。「そんなことできるの?」と思われるかもしれませんが、できます!
具体的な予想のやり方については、今日の動画の3つ目のトピック「これで満点ゲット!必勝の4テクニック!」の中でお話しします。
ステップ2「小さい設問で問われていることの観点で会話の音声を聞く。」とさらっと言いましたが、それができれば苦労はありませんよね。過去9年間の検定試験を分析したところ、この問題4で流れる会話の音声は大きく3パターンしかなく、小さい設問で問われる観点もいくつかに限られていることがわかりました。それをこの後2つ目のトピック「問題4の真実が判明!」で詳しくお話ししますので、小さい設問で問われていることの観点で会話の音声を聞けるようになりましょう。
ステップ3はそのまんまです。フィーリングではなく、根拠を持って解答を選べるようになりましょう。そのためには、とにかくメモしましょう!それと、試験本番まで過去問を使ってひたすら練習するのみです!
ステップ4は、選んだ選択肢をマークシートに塗ること。そのための時間が、何秒間あるか知っていますか?
会話の音声が終わるとすぐに、「プーン」という低い音が流れます。そして、20秒間の沈黙時間があります。この20秒間で、小さい設問2つの答えを選び、マークシートを塗りつぶさないといけません。
みなさんは、「20秒」という時間が長いと思いますか? 短いと思いますか?
Youtubeのわずか6秒間の広告ですら煩わしく感じるんですから、20秒間はけっこう長いはずですが、必死に問題を解いている時の20秒間は…あまりにも短い!
この「20秒間」という時間を長くすることはできません。では、どうするか?
小さい設問で問われていることの観点で会話の音声を聞き、聞き終わるころには答えをある程度絞り込んでおくことです。そうすれば、会話の音声の終了と同時にすぐにマークシートを塗り始めることができ、次の問題の準備もできます。
「じゃあ、小さい設問で問われる観点って何があるのさ?」と言うわけで、2つ目のトピックに移りましょう。
2.問題4の真実が判明!(問題4の設問分析結果)
過去9年間の「会話の音声 27回分」と「問題冊子に記載された小さい設問 54問」を徹底分析しました!
その結果、問4の会話の音声は次の3パターンしかないことが分かりました。
ここから先は
¥ 590
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
