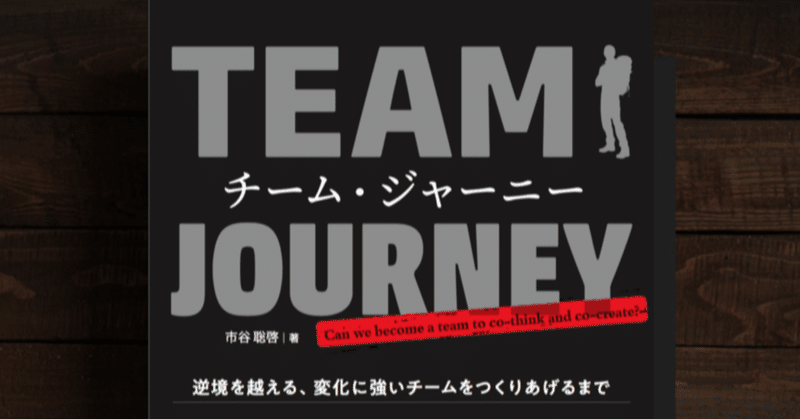
「チーム・ジャーニー 著者による本読みの会 第12話『チームの間の境界を正す』」に参加しながらまとめてみた
7時にアラームで起き、7時30分までそのままゴロゴロする至福の時を過ごした後は、頭を切り替え読書会さ!
チームの境界を越えてチームをつくる
こぼれ球が抜けまくるチーム
チーム編成を変えるためにとチームから2人を引っぺがそうとして揉めているところからスタートです。
現状のチーム編成では乗り越えられない
遅れが出ることは確実なのに社長への状況説明がされておらず、社長は次から次にアイデアを出している状況。馴染みがあるぞ🙄
御室のチームがボトルネックになっているらしく、プロダクトオーナーと開発メンバーがまったくかみ合っていないようです。ユーザに価値を提供できていない機能追加ばかりで複雑になってしまい、ユーザ離れが起こっているとか。
統合化の前提案件も太秦のチームが拾っていて、他のチームは拾わず、それどころか押し付けているような動き。。。
「そこで、今の3チームとは別に横断チームをつくろうと思います」
「うちから、常盤と嵯峨くんを出します」
とはいえ完全には切り離さずに、兼任としてやってもらい、他のメンバーを選出するまでの一時しのぎとしてみたいです。
ここで冒頭に繋がってきます。
チームを横断するチームの立ち上げ
他のメンバーが選出されましたが、新人に近いメンバーが数名とのこと。
そして結局タスクの押し付けが発生してしまい、当初の球ひろいという役割を逸脱してしまうことになりました。
横断チームでチーム全体をリードしよう
別のメンバー補充を頼りにし、常盤と嵯峨くんに横断チームに専任してもらうようにし横断チームを完全分離をすることに。
そして御室のチームに乗り込み、本気になった御室と協力し開発を進めていくことになりました。即戦力の新メンバーも追加されました。
最初のスプリントでモブプログラミングを多用し、開発環境やコードにも慣れてもらう工夫をし、さらにはコミュニケーションの向上もうまくいったみたいです。
一方で抜けっぱなしのフォースチームは限界を迎えていました。ただそこに御室のほうからエースの仁和を連れて行ってもかまわないとの提案が! ツンデレかな?
状況特化型チームを結成する
専門特化型チーム
専門性に特化したチーム。専門性の分散を防ぐことでまとまった成果を上げることを担う。
状況特化型チーム
状況(共通機能開発、移行、フィーチャーチームの支援など)に特化したチーム。ミッションを達成した時点で解散する。
横断チームが必要になる状況と直面する問題
横断チームが必要となるのは、フィーチャーチーム側で引き受けられないタスク(専門性の不足)や、どのフィーチャーチームが担うか判断しにくいタスク(いわゆるこぼれ球)が山積みしている場合です。
ただし、横断チームならではの問題に直面することもあると書かれていました。フィーチャーチームと横断チームの間での確執と横断チームの稼働問題で、タスクを押し付けてしまいがち、兼任させると時間が取れないという問題が起こります。
状況特化型チームの結成
ミッションの実現に対して、リソースの効率性を最大限高めようとするならば兼任で、フローの効率性を取るならば専任でという選択をすることになります。
状況特化型チームの運用
既存チームとの関係をどのように設計するかが重要で、ミッションの主管がどっちのチームにあるかでまた変わってくるようです。またチーム間の対立にも留意しておくべきで、ミッションが異なったり、コミットメント度合いに差があると対立や衝突へ繋がります。そのためにはむきなおりを実施し「われわれはなぜここにいるのか?」に答えるといいみたいです。
専門特化型チームのメンバーが手が空いたからと、他の事に手を付けてしまうのはあまりよろしくないと書かれていました。
人は余裕があると仕事を自ら作り出してしまい、時間をただ浪費してしまう、というパーキンソンの法則
空いた時間をチームの将来に向けた投資に使うべきとも書かれています。
---
この本では割とメンバー増員という手段を使っていますが、増員を全く期待できず、既存メンバーのみで回していかないといけないパターンとか気になっちゃいますよね。
来週は「チームとチームをつなげる」です!
😉
