
スピリチュアルケア師って何してくれんの?
人生の危機に助けとなる
スピリチュアルケア師は、欧米でいうチャプレンの日本版です(チャプレンというのは教会や寺院に属さずに働く、つまり宗教の布教はしない牧師さんのこと)。欧米ではチャプレンは病院に配置されているだけでなく、学校、消防署、軍など多岐にわたるフィールドに職員として存在し、スピリチュアルケアを提供しています。でもスピリチュアルケアって、具体的に何をしてくれるんでしょうか。日本のホスピス・チャプレンの第一人者のひとりである窪寺俊之先生はこう述べます。
チャプレンは患者・家族の存在を支え、残された”いのち”を意味あるものにする働きをする。そのチャプレンは患者と家族の死や死別という危機の時に最も大きな助けになる。(窪寺)
しかしですね… 自分の存在が揺らぎ、支えを必要とするような【危機】なんて、人生の中でそうそう出遭わないですよね。
どこにいった? 危機
幸いなことに科学の発展とともに様々な問題解決方法が編み出され、不治の病、事故、災害の頻度は減り、平均寿命は延びました。だから昔の人たちと比べ、私たちは人生の中で危機に出遭うことは少なくなってきたようです。

未曽有の災害(危機)がスピリチュアルケアの必要性を顕在化させた
私が学んだ上智大学グリーフケア研究所は、関西の福知山線脱線事故の遺族ケアに関わり、その必要性を認められ支援を受けて発足したと聞いています。また東北大学で始まった臨床宗教師養成は、東日本大震災で宗教者たちが垣根を越えてケアとは何かを考える中で発足したと聞いています。これら未曽有の事故、災害は私たちに強烈なメッセージを発しました。
『人生には危機が来るんだ』
というメッセージを…。
スピリチュアルケア師の養成カリキュラム
今日的な意味でのチャプレンという専門職ができたのはそれほど昔ではない。昔は修道院や寺院で神父、牧師、僧侶が病人の世話をし、看取りを行っていた。それらの聖職者は死の看取りのための特別な専門教育を受けたわけではなく、聖職者の日常業務の一つとして看取りが行われていた。(窪寺)
もともとは牧師の養成カリキュラムは聖書学などを中心に行われていましたが、心理学、社会学、文化人類学などの発展に伴って、机上の学問だけでなく、フィールドワークとして人々の苦悩、困難、悲しみに触れながら助けとなる方法を学ぶ臨床牧会教育(Clinical Pastoral Education=CPE)が生まれたそうです。
具体的な教育方法は二段階の教育を受けることになる。最初は一般の4年制大学を終えて聖職者としての専門基礎教育を受ける(中略)。第二段階は聖職者としての資格をとったあとに更に1年以上の専門的上級教育である臨床牧会教育(CPE)を受けなくてはならない。このCPEは神学校ではなく、 もっぱら病院やホスピスなどの医療機関でスーパーヴィジョンを受けて専門的臨床家としての訓練を受ける。そこではチャプレンとして専門職としての知識と共に、臨床能力を身につける個人的な教育が行われる。(窪寺)
現在、欧米ではこれらの教育を受けた人が、人生の危機にある人へスピリチュアルケアを提供しています。
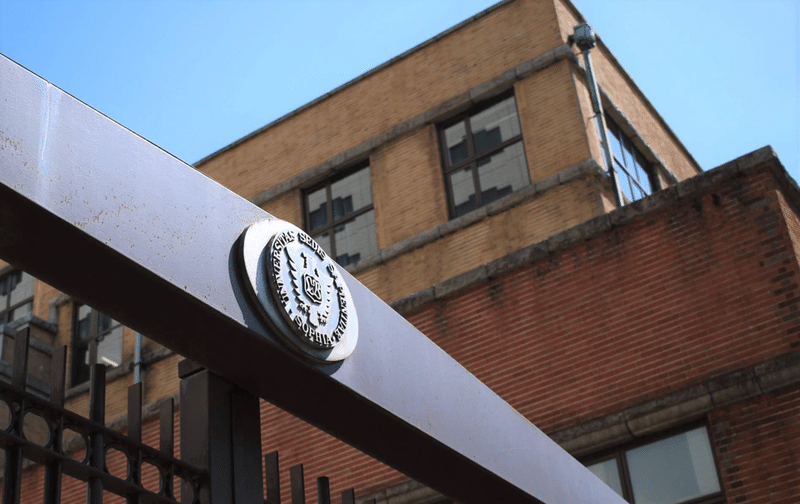
日本独自のClinical Pastoral Education
現在、日本スピリチュアルケア学会が動き、日本独自のCPEプログラムで資格認定を行っています。私が学んできた上智大学グリーフケア人材養成講座(臨床コース)は欧米でいう第二段階にあたるものでした(補足:日本スピリチュアルケア学会では第一段階で宗教性を問うていない)。私が受けたスーパーヴァイズは対象者との会話の仕方、ニーズの捉え方を通して自分自身を徹底的に見つめさせられるものでした。その中でスピリチュアルケア師としての資質や限界、そして自らの可能性などを洗い出されたように思います。
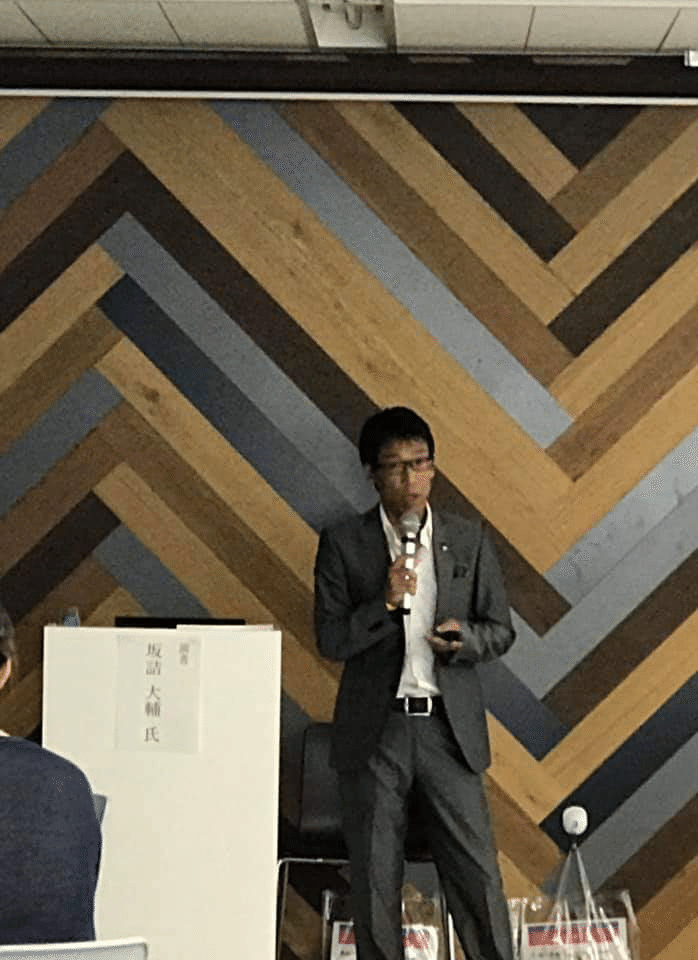
スピリチュアルケア師にできること
私のフィールドは医療畑です。しかし私に連絡をくださる人は病を抱える人に限りません。大切な人を亡くした(病、自死など問わず)、虐待、離婚、リストラ、生きづらさ(人間関係や障がい)などの様々な危機にある人たちです。私たちスピリチュアルケア師は、そんな人たちの”生きる力”(Spirit、Spirituality)にアクセスし、危機の助けとなります。
まだ日本ではスピリチュアルケア、スピリチュアルケア師の存在意義が認知されてるとは言い難いものですが、社会に認められ、必要とする人が必要な分だけスピリチュアルケアを受けられるように、私は今日も活動を続けています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
