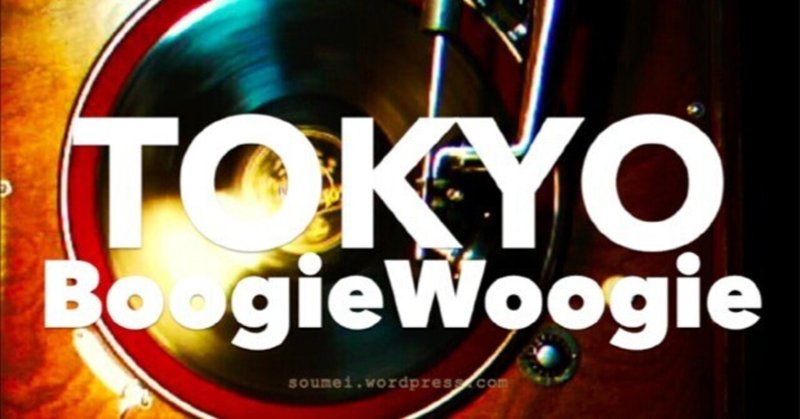
笠置シヅ子「東京ブギウギ」をSP盤と蓄音機で聴く
西荻窪こけし屋。
1947年の映画「春の饗宴」劇中歌ともなる「東京ブギウギ」という大ヒット曲が(レコード発売は翌48年)、作曲は服部良一、作詞は鈴木勝、そして歌は笠置シヅ子。
では当時のSP盤と蓄音機で「東京ブギウギ」。蓄音機は日本コロムビアの"No.G-150"で、これは盤と蓄音機の年代がほぼ合致します。ちなみに日本コロムビアの場合、この"G"型式が一つの目安、G=後期=戦後の機種に分類されるそうです。
レコード品番"484(C1177)"。録音ママ無加工、マイクは約50cmの位置。サウンドボックスは15番(ストック)で針圧調整。盤に難あり、劣悪なほどでは。
楽曲のバックグラウンドを少し紹介。当時、焼け野原ママの復興期、作曲家の服部良一は、いわば時代に活力を与える曲を模索していたそうです(服部良一に於ける、ブルースからブギへの転向)。それに合わせて笠置シヅ子再起の目論見も。天才と云われた笠置シヅ子ですが、当時はパートナーを失い失意に(私生児のシングルマザーとして)。
その閃きは突然に、中央線の車内で、そのアイディアをまとめるために、即、下車。それは今の西荻窪駅でのこと、その駅前の喫茶店で「東京ブギウギ(当初は"東京ブギー")」の原型が誕生します。
(車内での閃きとは、吊り革が揺れているのを眺めていて、その揺れるリズムに触発されて。それと駅前の喫茶店とは最初期の"こけし屋"で、杉並では銘店としても知られている洋菓子店であったが、当時の店舗は現存しない)
そして新たな時代の感覚に従う作詞家として上海時代(戦中)に親交のあった鈴木勝を迎えます。歌詞の「東京ブギウギ リズムウキウキ」はすでに服部良一のアイディアとしてあり、それを基に指定したそうです。その依頼を承諾したものの、ところが鈴木勝は譜が読めない(すでに楽譜があった?)。
そこで旧知(戦前の英会話サークルでの縁)である歌手の池真理子に助けを求めた、そして二人の共同作業により最初の作詞が完成。それは例えば「池のまわりを...云々、これには服部良一からクレームが。そして作戦練り直し、実質、服部良一も加えた三人の共同作業として作詞は完成します。
(この曲以前、すでに二人はコンビを組んでも、それが1947年の「東京ロマンス」で、服部良一作曲、鈴木勝作詞、歌は池真理子。ちなみにWikipediaには「東京ブギウギ」は、勝のアイデアを元に..云々とあるが、勝のアイデアは「東京ロマンス」の方)
禅とブギウギ。
この作詞は池真理子を想い描かれた節が。当時、勝は池真理子にぞっこんだったそうです。実際、後に二人は結ばれる、が、留意は、勝は妻帯者=不倫関係ママ挙式?=ここに重婚疑惑が。なんとも謎が多い人物で、出生不明でもあります。否、育ての父ともなる人物は明白、それはかの鈴木大拙、そう、西洋に於いても"禅"を認知させた。
これまで鈴木大拙との関係は曖昧ママに語られてきました。それは鈴木勝の素行に起因するもので、簡単&端的には不良。後年ゴシップ誌に"昭和最大の不肖の息子"とまでも書かれた存在でもあり(61年「週刊新潮」)、大拙の養子として、そのようなエトセトラはアンタッチャブルなのでしょう。「東京ブギウギ」の大ヒット後も大拙は勝を無視に等しく、却って苦言を呈すかのような一文を寄せても(51年「浅間嶺」)。
親子関係は勘当に近い時期もあれど、しかし池真理子と結ばれた後は、大拙と勝に於いて最も安定した時期かと(これは池真理子の人徳に依るところが大きい)。そこに暗雲が、またもや女性問題(池真理子の曲に例えると「ボタンとリボン」のヒット後)、さらに後年、前述、不肖の...云々が(これも女性問題)。容姿に恵まれ、また才能にも恵まれ、にもかかわらず、それが却って災いか、女と酒で身を滅ぼした典型に思われます。
でも考え所は、破茶滅茶な素地もある人物故、あの時代に、あのような詞が書けたのでは(それがわかっていたからこそ勝に依頼では?)。でもそこも謎、どこまで勝のオリジナルか怪しい...と、勘ぐりたくも。しかし才能&文学的センスが優れていたことも確かだと思われます。女性問題はともかく(他にもまだ...)、その人柄は(シラフでの)少なくとも業界内での評価は高い。ただ、服部良一も薄々は感づいていたのか結婚式(再々婚)の出席は断っています。
家事は天才を殺す。
詳しくは山田奨治著「東京ブギウギと鈴木大拙」を参照していただければ。異色の大拙研究であり、親としての大拙に、鈴木勝という人物を介してスポットを当てた功績は大きいのでは。憶測を交えても差し支えない年月がたっていると思うので記していますが、読み取れるのは養父として苦悩する姿であり、これまでの大拙本にみられるような明鏡止水に霊性を説く姿とは乖離しています。
大拙は家庭よりも仕事を選んだと思われるのですが(また渡航期間も長い、自ずと家族との距離が)、でもその是非ではなく、人間万事塞翁が馬、正解はないでしょう。ただ傍から見れば、子育てに失敗では? 何をもって失敗とするかは分かれるところですが、勝は晩年に於いても幸せとは言い難い。そして今もなおアンタッチャブルである点が、却って肯定しているようで。
(留意は、大拙は終生、勝のことを気にかけていた。そして勝は、親としての大拙を尊敬していた)
悟りにふれた大拙でさえもです(開眼は1896年旧暦12月)。そこに(親子関係云々に於いて)禅的な哲学の弱点があるのかもしれません。そして依然、謎は残ります。クリエーターとしての鈴木勝が何を考えていたのかがわからない。ここでのテーマはともかく、鈴木大拙&鈴木勝に興味があれば必読であります。
笠置シヅ子に関しては次回に続きます。
その2[笠置シヅ子「買物ブギー」をSP盤と蓄音機で聴く]
石の会(追記)。
このような機会でもないと忘れてしまうので。こけし屋は"石の会"の例会の場でも(毎回ではない、メインは有馬邸)。それは秘密裏な親睦会(サロン)、その首謀者はかの有馬頼義(作家)、有馬頼寧の三男であり、有馬頼寧は"有馬記念"の有馬、そして"西荻窪"という町名の命名者。
メンバーは、主に、高橋昌男、色川武大、武田文章、高井有一、佃実夫(世話人)、萩原葉子、室生朝子、後藤明生、森内俊雄、渡辺淳一、梅谷馨一、早乙女貢、五木寛之、中山あい子、北原亞以子、立松和平などなど...。と、錚々たる顔ぶれ、色川武大の名前がある時点で只事ではない。
