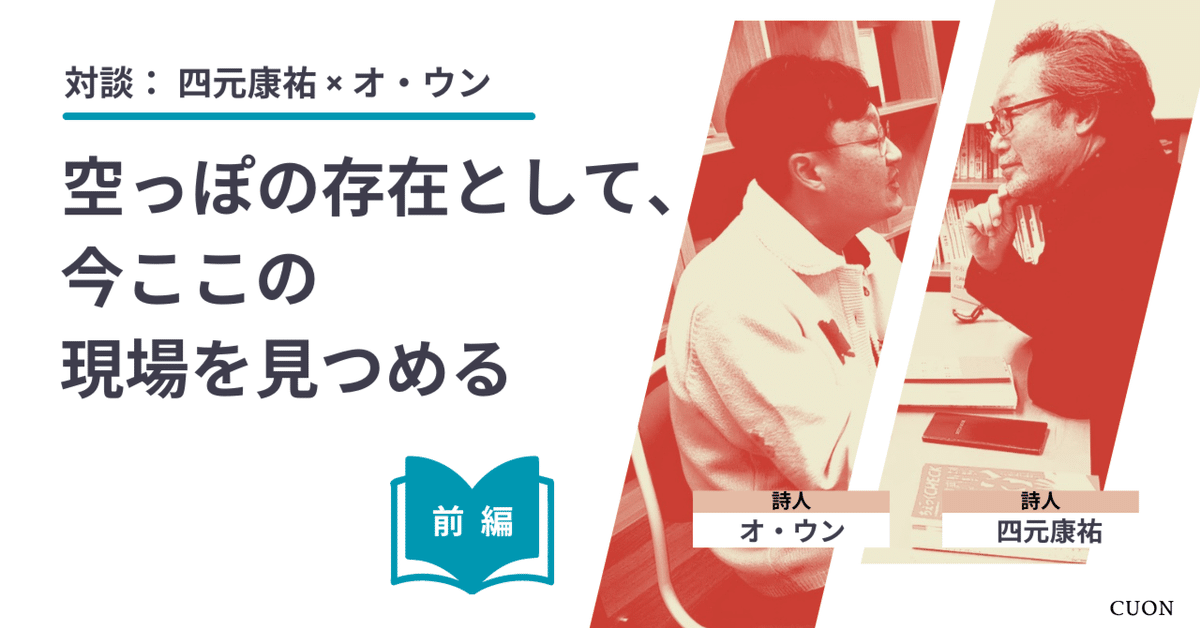
【対談】四元康祐×オ・ウン :空っぽの存在として、今ここの現場を見つめる(前篇)
世界中の詩人と交流し、連詩や対詩、翻訳などで様々な話題を呼んできた詩人の四元康祐さんと、詩人、エッセイスト、ポッドキャスト司会者などオールマイティに活躍する韓国の若手詩人オ・ウンさんとの対談が行われました。オ・ウンさんの邦訳詩集『僕には名前があった』(吉川凪訳、クオン)の感想から始まり、「詩人という存在」「詩と散文」「言葉遊び」など話題があっという間に広がった、詩と詩人を巡る対談の模様をお届けします。
詩人としてのギャップ
四元 オ・ウンさんの詩集『僕には名前があった』を読ませてもらいました。ほんと、面白くってね。すべて「人」についての詩集なんですよね。だから、観念的ではなくて、どの詩からも人という存在が浮き上がってくる。32篇あるので、32人の人がいるんだよね。それがとても新鮮だけれど、ストーリーテリングのほうには行かず、手前で留まっている。哲学や認識、詩としか言いようがないような、ある種の感慨になっているところが、さらに面白かったですね。

オ・ウン 32篇あるので32人いると言えるのですが、すべて異なる人で、少しずつ自分が入っています。私はどちらかというとネガティブで小心者です。弱かったり、怒りっぽかったり、ひねくれたりしているのですが、そういう属性の私がちょっと入っているんです。ほかの人について書いたり、自分がいるここではないどこか別の場所を書いたりしても、自分自身がどうしても入ってきます。
四元 僕たちはまだ会ってから2時間しか経っていないけれど、実際のウンさんはすごく明るくて、人に対してオープンだよね。だから、たった2時間前に初めて会ったとは思えない、古い友達みたいな印象があるけれど、確かに、この詩集の中の人には、みんな影があるよね。
オ・ウン 表面的にはすごく明るいので、ある時期から、必ずムードメーカーの役割を任されているような感じです。「1人でいる時もひとり言をいろいろ喋っているでしょう?」とよく人に訊かれます。
でも、ひとりの時はいつも、「さっき、なんか変なこと言って、人を不快にさせなかったかな」と心配しているんです。外では明るい人間ですが、家に帰ると地味に詩を書いているような気がします。このギャップが詩人としての私と、生身の人間としての私を支えているのでしょう。
四元 それは、僕にもちょっと思い当たります。
オ・ウン 私も四元さんは楽天的に見えます。だから、同じようなギャップがあるのではないかと思います。
四元 日本で詩を書いている人の多くは、どちらかというと、そういうギャップはないんだよね。本当に人が好きで人に興味のある人は、ストーリーテリング、小説のほうに進むんじゃないかと思うし、一方で、詩を書いている人は、付き合いがあまり良くないような、内向的な人が多いです。そして、自分の中に入っていって、内面の孤独な世界を表現するというのが、日本の詩のかなり一般的なあり方かなと思うんですね。
こうして考えてみると、この対談を企画した人は、僕たちの性格を見て、あの2人を合わせてみようと思いついたんだろうね。鋭い観察眼だね。
僕が最初に出した詩集のテーマは、人ではなかったんです。いわゆる伝統的な詩の主題ではなくて、より社会的な、当時の経済とか、ビジネス活動とか、そういうものをテーマとした詩集です。小説のテーマになりそうなものを詩にしました。だから当時は、小説を書かないかと随分誘われました。
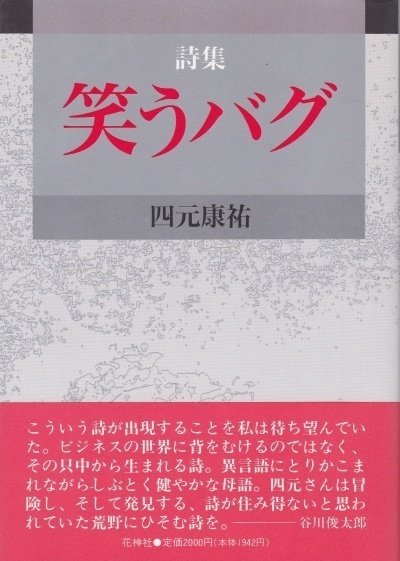
オ・ウン 四元さんの詩選集を見ていても、興味のあるものがその時々で変わっているんだなというのがわかります。
四元 その興味の対象は自分の外なのだけれども、だからといって、それをネタに小説が書けるかというと、書けなかったですね。というのも、どうしても小説だと、登場人物の名前を考え、この登場人物とあの登場人物の人間関係を考え、それからドラマを生んでいくということをやらなきゃいけない。それは退屈で退屈で。苦痛以外の何者でもないということがわかった。
オ・ウン 詩を書くときに、私がいつも重要視しているのは、ある対象になってみること、その対象たちの気持ちになってみることです。四元さんの詩集で言えば、コピー機になってみたり。そういうところがとてもよく表されていて、私と似ている点があると思いました。
四元 そうなんだよね。それを、ウンさんの詩集で言うと、32人の人が出てくるのだけれど、誰も名前を持って……、あ、タイトルは『僕には名前があった』だけれども、1篇1篇の詩には個々の具体的な名前がない。抽象的な存在ですよね。もしかしたら、この人は全てウンさんなのではないか。だからこそ、固有名詞がいらないっていうかね、邪魔になってくる。
オ・ウン 通りすぎる人を見ながら、考えました。この人たちも、誰かにとっては大切な人であり、会社に行けば何か重要な職に就いている人かもしれないけれど、私にとっては、ただの人なのです。そういう風に書きたかった。
『僕には名前があった』が5番目の詩集で、最新作の『無いことの代名詞』が6番目になります。『無いことの代名詞』に、「人は固有名詞で生まれて、普通名詞で生きていく」という一節があります。自分が持っていた問題意識がこの詩集で深まったのではないか。『無いことの代名詞』に収録した詩それぞれのタイトルを紹介しますと、「あそこ」「あそこ」「あそこ」「それ」「それ」「それ」「それ」「彼ら」「彼ら」「彼ら」という感じです。
四元 みんな代名詞だね。
オ・ウン すべて代名詞で同じタイトルが続くのですが、第1部が「氾濫する明朗」で指示代名詞をタイトルにした詩を収録し、第2部が「無表情の表情」で人称代名詞をタイトルにした詩を収録して、第2部の最後に「私」というタイトルの詩を1篇置きました。最初が「あそこ」ですが、最後が「私」で、一番遠いところから自分に戻ってくることを意識しました。
詩と散文と余白
四元 ウンさんの詩も僕の詩も散文性があると思います。散文的なものと詩的なものが融合したり対立したりしていて、散文そのものでもなければ、いわゆる詩そのものでもない。このハイブリッドな感じが面白い。だから、小説も書けるのではないかと思う人もいるかもしれないけれど、でも、僕たち2人とも、本質は詩なんです。じゃあ、その詩が何かと言うのは難しい。
外の世界との関係性、自分自身の内面世界、いろいろな言い方ができると思うけれど、仮に散文と詩という対比をするならば、ウンさんは詩をどのように捉えていますか。
オ・ウン きっちりジャンルを分けるのは難しいです。散文と詩に差違があるとしたら、詩を書くときは固有のリズムがあるのではないでしょうか。詩の場合は、余白をたくさん作るようにしています。ストーリーをぎっしり入れないのは、余白で読み手が想像できるようにするためです。よい詩というのは、読み手自身が加える、加担できるような作品がいい詩だと思っています。
例えば、私の詩に「それ」という作品があります。短いのでご紹介します。
그것
온다 간다 말없이 와서
오도 가도 못하게 발목을 붙드는,
손을 뻗으니 온데간데없는
それ
来るとも帰るとも言わずに来て
来ることも行くことも出来ないように足首を掴む、
手を伸ばすと来た形跡も行った形跡もない
オ・ウン この詩を朗読すると、「“それ”は何ですか?」と質問されます。でも、私は「“それ”を何だと思いましたか?」と逆に質問するんです。
四元 僕も空白についてはとても意識します。特に自分が散文ではなく詩に属している人間だなと思う時に。では、自分は何かというと、その本質は空っぽではないかと思いますね。
オ・ウン 空白に属しているということですね。
四元 先ほど、小説は書けなかったとお話ししたのですが、実は2作の長編小説を書いています。その小説を読み返してみると、結局、自分のことを書いている。一見すると人当たりが良くて、人付き合いもいいけれども、本質的には根暗で、ひとりでいるのが好きな自分。この自分は何だろうということを主題にすると、小説が書けるんです。そして、結論として浮かび上がってくる自分は空っぽな存在だということに、僕は段々気付いてきました。空っぽということが詩人というものの本質じゃないかと、今は思っています。
日本に新川和江さんという優れた詩人がいます。彼女が「欠落」という詩を書いたのですが、丼のようなものが空き地に棄てられているんです。中は空っぽ。でも、空っぽだからこそ、そこに雨が降ったら水が溜まり、その水が空や世界そのものを映し出したり、鳥の羽根があったり、月の光が差し込んだり、空っぽだから何でもそこに盛ることができる。彼女は詩の理想的な一つの姿として「欠落」を書いているのですが、僕にとっての詩人像というのは、まさしくそういう何でも受け入れることができる空っぽな存在なんです。
オ・ウン 私も刺激が外から来たときにきちんと受け入れられるよう、心身ともに柔軟にしておくことを心掛けています。
四元 だからこそ、このように32人の他者にある種の憑依ができるんだよね。でも、憑依して、自分を空っぽにして、他者に没入していくと、そこにまた、本当の自分が現れてしまうというパラドックスもある。自分を空っぽにして他人に没入するというプロセスの中に、自分でも知らなかった自分自身が現れてくる。
オ・ウン (拍手を一つ) 私が詩を書く理由を正確におっしゃってくださいました。自分でも知らない自分自身を発見するために、詩を書いています。
四元 僕もまさにそうなんだけれど、この詩の中に32人の他人がいて、その他人を描いているオ・ウンがその背後にいる。そして、描いた言葉の向こうに、オ・ウンの知らなかったオ・ウン自身が浮かび上がってくる。それは、いわば、ウンさんの後ろ姿なんですよね。自分の後ろ姿が、この32種類の角度から見えてるんだと思いますね。
そうではない詩、自分の正面から鏡で見て、これが私ですというふうに、ある種の告白のような詩のほうが、伝統的にも今でも多いと思うんだけれども、ウンさんのように対象に没入しようとすると、人に見せたい自分のフロントイメージではなくて、後ろ姿が出てくる。とてもいいと思います。
オ・ウン 映画が終わると、エンドクレジットが流れますが、最後まで残ってすべて観ます。なぜかというと、誰かに自分の後ろ姿を見られるのが嫌で、映画館に残っているんです。
言葉遊び
四元 人間にはどうしても自意識というものがあるので、ただ漫然とものを書くと、自分を忘れることができなくて、むしろ自分が意識している自分を出してしまう。ウンさんはこの詩集だけではなくて、他のもそうだと思うのですが、言葉遊びをよく使いますよね。言葉遊びは、音や意味の偶然の一致を使ってジャンプすることによって自意識を捨てる、そのための装置として機能しているのではないかと思ったのですが。
オ・ウン 最初から最後まで詰め込みすぎた詩を書くよりも、読み手が一息つけるような詩が好きで、それが私にとって言葉遊びやユーモアのようなものです。ユーモアを交えて、ちょっと笑えるようなところも作るというのが、私の書き方なんです。悲しいことを悲しく書くのではなく、ちょっと嬉しそうに表現したり、嬉しいことを憂鬱に表現したりするというように。
四元 なるほど、ユーモアについてはそうなんだね。言葉遊びについては、どのように捉えているんだろう。
オ・ウン 「オ・ウンと言ったら言葉遊び」というのがトレードマークのようになっていて、いつも影のようにくっついて消すことができない。最初はこのように言われるのが嬉しくなかったんです。言葉遊び以外にも鑑賞できるところはたくさんあるのに、そればかりで腹が立つこともありました。
でも、長く詩を書いてきたので、今では受け入れていて、言葉遊びの先に何があるかなということを考えています。「遊び」というとゲームを連想させますが、勝ち負けではなく、ゲームの結末がどうなるのかを考えながら、言葉遊びをしている感じです。
四元 ウンさんの言葉遊びは、意味の連なりで詩が重くなってしまうのを避けるための安全装置で、詩を子供の純真な遊びの世界に近づけてくれるものではないか。それから、自意識にとらわれることから解放してくれる、自由にしてくれるための装置だと思います。
オ・ウン そのとおりです。
四元 先ほどウンさんは、自分を柔軟にしておくことを心がけていると言っていたけれど、ヨガをやるとか、座禅を組むとか、生活の中で具体的に何かをしているんでしょうか。
オ・ウン 散歩をしています。多いときは、1日で2万歩ほど散歩をします。今回の日本でもよく歩いていて、福岡では2万5000歩、水俣でも2万歩。旅行でたくさん歩くのは目的がありますが、私の散歩は目的がなく、自分のリズムを確認したり、自分の感覚を確認したりする、そういうことのために散歩があります。
先ほどの「欠落」の詩、あの空っぽの丼の話みたいに、私も何か道で見かけたものに目を留めて、誰が持ってきたのかなと想像したりして、散歩を中断し、詩を書くこともあります。
面白いのは、新川さんもそうだし、僕もそうですが、道ばたの丼だったり、ポストだったり、リサイクル品の回収箱だったり、自分より下にあるものに目がいく。普通だったら、ランドマークになるような高い建物を見たりするんでしょうけれど、詩人というのは、人があまり重要に考えないものを見るために散歩をするんじゃないでしょうか。
四元 なるほど。散歩する犬の視線ですね。
オ・ウン 犬よりもうちょっと上です(笑)
>>後篇に続く
2023年11月26日クオンにて
通訳:吉川凪|構成:五十嵐真希
プロフィール
四元康祐 (ヨツモト ヤスヒロ)
1959 年、大阪生まれ。86 年アメリカ移住。94 年ドイツ移住。2020年3月、34年ぶりに生活の拠点を日本に戻す。
91年第1 詩集『笑うバグ』を刊行。『世界中年会議』で第3回山本健吉賞・第5回駿河梅花文学賞、『噤みの午後』で第11 回萩原朔太郎賞、『日本語の虜囚』で第4回鮎川信夫賞を受賞。そのほかの著作に、詩集『単調にぼたぼたと、がさつで粗暴に』『小説』、小説『偽詩人の世にも奇妙な栄光』『前立腺歌日記』、批評『詩人たちよ!』『谷川俊太郎学』、翻訳『サイモン・アーミテージ詩集 キッド』(栩木伸明と共著)『ホモサピエンス詩集 四元康祐翻訳集現代詩篇』『ダンテ、李白に会う 四元康祐翻訳集古典詩篇』、編著『地球にステイ! 多国籍アンソロジー詩集』『月の光がクジラの背中を洗うとき』など。現在、日本経済新聞に「詩探しの旅」を連載中。
オ・ウン
1982年、韓国全羅北道井邑生まれ。
2002年『現代詩』にて詩人としてデビュー。
詩集に『ホテルタッセルの豚たち』、『私たちは雰囲気を愛してる』、『有から有』、『左手は心が痛い』、青少年詩集『心の仕事』、散文集に『君と僕と黄色』、『なぐさめ』など。
朴寅煥文学賞、具常詩文学賞、現代詩作品賞、大山文学賞などを受賞。邦訳作品に『僕には名前があった』(吉川凪訳、クオン)がある。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
