
青春小説|『塩素と浴衣と打ち上げ花火』
<ChatGPTによる紹介文>
『塩素と浴衣と打ち上げ花火』は、一九八三年の夏、中学生の少年が織りなす切なくも純粋な恋の物語です。背景には懐かしい時代の風物詩が描かれ、読者は当時の懐かしさと共感を味わうことでしょう。
ーー中略
『塩素と浴衣と打ち上げ花火』は、夏の切ない恋心と懐かしい時代背景を巧みに組み合わせた作品です。読者は主人公の心の成長や恋の芽生えに胸を打たれること間違いなしです。夏の日差しと共に、青春の心躍る瞬間を思い出すことができる素晴らしい小説です。
ーーChatGPT
◇
◇
◇
ここから本編がはじまります
『塩素と浴衣と打ち上げ花火』
作:元樹伸
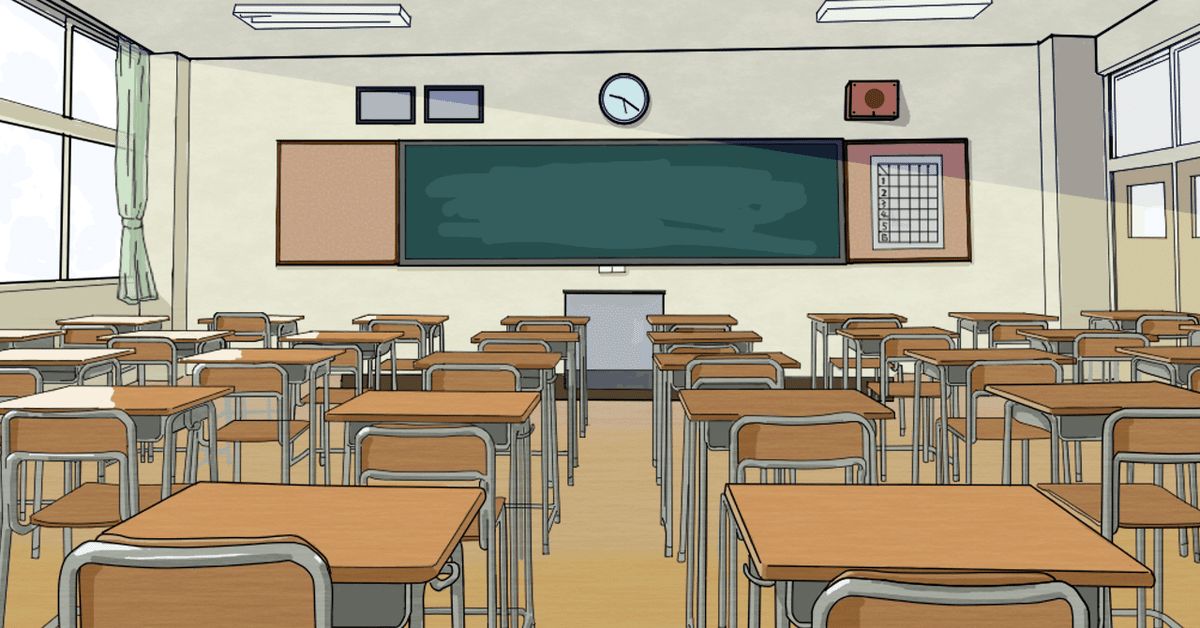
第一話 僕と服田さん
一九八三年。千葉県のはじっこに大規模なテーマパークが開園し、子どもなら誰でも欲しがる家庭用ゲーム機が発売されたこの年。中学二年の僕は待ちどおしかった夏休みを迎えたはずなのに、普段と代わり映えのない平凡な日々を送っていた。
今日も電話で友だちと会う約束をして、朝食もとらずに家を出た。待ち合わせ場所はいつも通り駅前の本屋。自転車を漕ぐとすぐに汗が噴き出して、さっき飲んだ麦茶が瞬く間に蒸発した。
外の気温は三十度。午前中はエアコンが効いた本屋で漫画を立ち読みして、午後からはゲーセンで時間を潰すのがいつものコースだ。ただ今日がいつもと少しだけ違うとすれば、夕方から近所の公園で盆踊りが行われることくらいだった。

本屋の冷房で身体が冷えた頃、今週発売の漫画雑誌も読み終わったので、河野くんに声をかけて店を出た。ちなみに河野くんは靴屋の息子で、学校指定の上履きや今履いている靴も彼の実家で買ったものだった。
お昼ご飯を食べに引き返そうと自転車に乗ると、夏らしい恰好をした二人の女子が駅から出てくる姿が見えた。二人ともお揃いのような白いワンピースを着ている。片方は知らない子だけど、麦わら帽子を被っているもうひとりの子は同級生の服田さんだ。
「昼飯食ったら、二時にゲーセンな」
河野くんが自転車に鍵を挿しながら念を押す。でも僕はすっかり服田さんに気をとられていて、了解の返事がワンテンポだけ遅れた。
「なぁ聞いてるか?」
河野くんに背中を突つかれて我に返り、「わかってるよ、午後の二時だろ?」と答えて自転車を発進させた。

前を歩いている彼女たちの背中が近づくにつれて、先頭を走る僕の自転車は徐々に速度を落とした。声をかける勇気はないけれど、ゆっくり追い抜けば服田さんが気づいてくれるかもしれなかった。つまり有り体に言えば、僕は以前から服田さんに好意を持っていた。
* * *
服田さんは笑顔が似合う、とても可愛らしい子だ。彼女は休み時間に同級生とおしゃべりをしながらよく笑っていた。そんな時は色白な頬がほんのりと赤くなって、僕にはそれがとても美しく見えた。
夏休みが始まる少し前、男女合同で体育の授業を行う日があった。天井から吊るされたネットで体育館を半分に区切り、男子はバスケットボール、女子はバレーボールの練習をしていた。授業の後半は演習試合となり、控え組の自分たちは間仕切りネットの前で選手を応援していた。
「おれもバレーボールの方が良かったなぁ」
河野くんが羨ましそうに女子の方を見てぼやいた。バレーボールのコートでは、背の低い服田さんが類まれなる身体能力を活かして、相手のコートに強烈なスパイクを打ちこんだところだった。レシーブで弾かれたボールがこちらに飛んできて、ネット越しで見ていた僕の顔面に激突した。

「おーい窓木、大丈夫かぁ」
コートの反対側にいた湯沢くんが揶揄い半分で僕の名前を呼んだ。湯沢くんは格闘技のジムに通っていて身体も大きく、たぶん学校で一番喧嘩が強い男子だ。そんな彼には、新しい技を覚えると僕を実験台にする悪しき習慣があった。だけど女子には優しかったから、彼はクラスの人気者だった。
「ご、ごめんなさい!」
顔を押さえてしゃがみ込む僕の元に、服田さんが慌てて駆け寄ってきた。
「窓木くん、大丈夫だった?」
「打たれ強いので全然平気です……」
鼻がジンジンしていたけど、やせ我慢をしてそう答えた。それにボールが当たったのは彼女のせいじゃないので、余計な心配をさせたくなかった。
服田さんは目の前でしゃがみ込むと、僕の手を鼻からそっとよけて顔を覗き込んだ。彼女の方からふわっと甘い香りがして、僕はとたんに照れくさくなった。
「顔が赤くなってるよ。保健室に行こうか?」
「でも酔ってないから大丈夫」
痛がっているとみっともないので、くだらない冗談を言ってみた。だけど服田さんはきょとんとしていて、意味が伝わっていないみたいだった。
「ごめん。今のは『顔が赤いのはお酒を飲んでるからじゃないよ』っていう冗談のつもりで……」
「ふふっ、窓木くんって面白いね」
しょうもない冗談でも笑ってくれる。そんな服田さんが天使に見えた。
「窓木、大丈夫か。服田は早く女子の方に戻りなさい」
「じゃあ窓木くん、バスケ頑張ってね」
体育の教師に促され、彼女はバレーボールのコートに戻って行った。
こうして服田さんの笑顔を間近で受け取ってしまった僕は、まるで恋の魔法にかけられたかのように、いつの間にか彼女のことが好きになっていた。
第二話 膨らむ期待
まだ記憶に新しい記憶を巡っているうちに、自転車が服田さんを追い越した。背後から「窓木くん?」と服田さんの声がして、僕は神様に感謝しながら自転車のブレーキをかけた。

自転車から降りると服田さんたちが駆けつけてくれた。河野くんは付き合いで停まってくれたけど、サドルに跨ったままハンドルに肘を預け、つまらなそうに遠くを眺めていた。
「彼女は浅倉さん。一年生の時に同じクラスだったの。窓木くんたちは今のクラスで一緒なんだよ」
服田さんが、連れの女子と僕たちを交互に紹介してくれた。けれど連れの浅倉さんは、一度もこちらに目線を合わせようとしなかった。
「窓木、早く行こうぜ!」
「もうちょっと!」
河野くんが後方で急かしたけど、まだ服田さんと話がしたかったので反射的に抵抗した。
「今からどこかに出かけるの?」
服田さんが僕らの自転車を見て聞いた。
「本屋に行っただけだよ。服田さんは?」
「見ればわかるでしょ?」
服田さんの隣で不機嫌そうにしていた浅倉さんが代わりに答えた。言われてみれば服田さんはノースリーブのワンピース姿で、赤いプールバッグを肩からぶら下げていた。

濡れ髪でほのかに蒼い塩素の匂いもして、確かに彼女たちがどこで遊んでいたのかは一目瞭然だ。それに色白だった服田さんが、見ない間にすっかり日焼けしていたので、僕は何よりもそのことに驚いていた。
「えっと、私に何かついてる?」
視線に気づいたのか、服田さんが照れくさそうにして言った。
「いや、日焼けしてるなって思って」
「やらしいな、ふくちゃんの何処見て言ってんの?」
いやらしい目で見たつもりはないけれど、朝倉さんに軽蔑の眼差しをむけられ、僕は穴があったら入りたくなった。
「もう行くぞぉ!」
しびれを切らせたのか、うしろで河野くんが叫んだ。

「あ、呼び止めちゃってごめんね」
「いいよ、どうせこれからゲーセンに行くだけだし」
「夏休みにゲーセンって。よっぽど暇なんだね」
「うるせーな、おまえらに関係ないだろ?」
苦笑する浅倉さんに返す刀で河野くんが抗議した。どうやら彼女の発言が癪に障ったみたいだった。
「だってゲーセンなんて暇人が行く場所じゃん」
「プールもな」
「夏にプール行って何が悪いの?」
「夏にゲーセン行って何が悪いんだ?」
「あんなの不良のたまり場でしょ!」
「ちょっと、二人ともやめなよ」
口喧嘩が始まって服田さんが仲裁に入った。それでも彼らの興奮は収まらず、僕たちは暫くの間、その争いを傍観することになった。ただこれで服田さんと二人きりで話す時間ができたのも事実だった。
「そういえば夕方から、近所で盆踊りがあるみたいだよ」
とりあえずお祭りの話をしてみたけど、思いきって誘う勇気はなかった。
「私たちは行くよ。窓木くんは?」
「近所だからたぶん行くと思う」
「じゃあむこうでまた会えるね」
なんという幸運な展開だろう、とその時は思った。これはもしかしたら、今日は服田さんと一緒にお祭りを楽しめるかもしれない。僕はそんなことを期待して、ウキウキと心が躍り出していた。

彼女たちとの別れ際、浅倉さんが「なんで男子に声かけたの?」と服田さんにクレームを入れている声が聞こえた。
「だってクラスの人だよ?」
「でも男子じゃん」
「男の子だとダメなの?」
「だって男子だよ?」
二人の話はかみ合わずに平行線のようだった。一方の河野くんは彼女たちの姿が見えている間、ずっと不機嫌だったけど、自転車に乗って走り出す頃にはこんなことを口にした。
「なんか浅倉って、背がちっちゃいのに胸でかいのな。それに小学生みたいなアニメキャラの可愛いプールバッグだったぜ」
「そ、そうなんだ」
どうやら河野くんは憎まれ口を叩きながらも、服田さんの友だちのことがすごく気になっているみたいだった。
第三話 予期せぬ災難
夕方、ゲーセンから戻った僕たちは、そのまま盆踊りにむかった。会場は住宅街にある小さな公園で、周辺の道路も狭くて辺りは混雑していた。設営されたスピーカーから流れる東京音頭。浴衣を着た大人たちが、やぐらを囲んでお手本のように揃って踊っていた。
「田舎の祭りなのに東京音頭かよ」
河野くんが会場に着くなり、お約束のツッコミを入れた。
「定番だからじゃないの?」
僕は適当に答えながら、人混みの中に服田さんの姿を探した。
「よくあんな所で踊れるよな。そうまでして目立ちたいか?」
砂利が敷かれた駐輪場に自転車を置いた。会場の方では、小学生くらいの子たちが大人に混じって踊っている姿が見えた。
「目立ちたいから踊るんじゃないと思うけど」
「じゃあ何で踊るんだよ?」
「楽しいから?」
じつは僕もよくわからなかった。ただ服田さんと一緒に踊れるなら、この夏一番の想い出になるような気がしていた。
「行こうぜ」
河野くんと出店が並ぶ通りを歩いた。焼きそば、りんご飴、かき氷、金魚すくい。町内会の小さなお祭りなので数は少ないけど、どの店にもお客さんがたくさんいて繁盛していた。

小腹が空いたので焼きそばを買った。でも会場内はどこも人だかりができていて、落ち着いて食事ができそうな場所がない。そこで僕たちは駐輪場に引き返して、自転車に跨って食べることにした。
「町内会の祭りなんてあまり面白くないな」
河野くんがたこ焼きを頬張ったままぼやいた。
「他にすることもないしね……あれ?」
焼きそばを食べようとして、僕は割り箸がないことに気づいた。
「おじちゃん箸忘れてる」
「これなら余ってんぞ?」
河野くんがたこ焼き用の長い楊枝をくれたけど、それ一本で焼きそばを食べるのは難しそうだ。
「やっぱり貰ってくるよ」
「じゃあここで待ってるわ。食い終わったら帰ろうぜ」
お腹が満たされて眠くなったのか、河野くんは大きなあくびをした。

彼を残して通りに戻ると、人の往来がさらに増えていた。いくら避けても人とぶつかりそうになるので気が滅入った。だから人混みは苦手なのだ。
どんっ。
周囲に気を配っていたのに、誰かの肩が大きくぶつかった。
「すみません」
「なんだおまえ?」
人でごった返しているにも関わらず、ぶつかった相手が無遠慮に立ち止まって、こちらを睨みつけた。
「ちょっと面貸せよ」
絡んできたのは、ガラの悪い二人組の少年たちだった。暗がりに連れ込まれたとたん、顔を殴られて目の前に火花が散った。脚に力が入らなくて尻もちをつくと、襟首を掴まれて無理やり起こされた。もうひとりの少年は金髪でガムをくちゃくちゃ噛みながら、無言で僕を見下ろしていた。

「ごめんなさい……」
謝ってもまたすぐに殴られた。昔から打たれ強いので痛みは平気だったけど、鼻の奥が熱くなって鉄の匂いがした。でも湯沢くんの関節技の方が数倍痛いと思った。
「ごめんなさい、じゃねぇんだよ」
今度は金髪の少年に腹を二回続けて蹴られた。それから彼らは、無抵抗の僕を面白半分に殴り続けた。なんでこんな時に河野くんがいないのだろうと思ったけど、もしいたとしても、二人ともサンドバックになるだけか。
「おーい窓木、大丈夫かぁ」
聞き覚えのある声がした。でも河野くんじゃない。少年たちの暴行が止んだので目を開けると、大きな人影が見えた。顔を殴られたせいで視界がぼやけて最初はわからなかったけど、目を凝らして見ると湯沢くんだった。そして彼のうしろには、浴衣姿の服田さんがいた。

なるほど、そういうことか。
昼間は服田さんが「私たちは行くよ」と言っていたので、浅倉さんと一緒に来るものだと勝手に決めつけていた。でも彼女の相手は湯沢くんだったんだ。
「なんだてめぇ?」
少年たちは僕を地面に捨てると、湯沢くんににじり寄った。このままじゃ服田さんも危ないと感じたので、少年の脚を掴んで「逃げて!」と叫んだ。でもすぐに空いた足で蹴られて意識が飛びかけた。
「こんな雑魚にボコられるとか、君はそれでも俺さまの実験台かい?」
湯沢くんは彼らを意に介せず、倒れている僕に声をかけた。
「おまえ、偉そうにしてるから死刑」
少年が死んだ魚のような目で唾を吐いた。彼らと対峙した湯沢くんは首をコキコキ鳴らしてからにやりとして、「でも服田を守ろうとしたのは偉い」と言いながら、格闘家のようなファイティングポーズをとった。
第四話 ゲームオーバー
それから一分後。尻もちをつく自分の目の前で、少年たちがぶっ倒れたまま呻いていた。僕を殴り始めた少年は湯沢くんのカウンターで一発KO。金髪の方は寝技で脚を決められて悲鳴を上げていた。そりゃあそうだろう。あの技がどれだけ痛いかは、僕自身が誰よりもよく知っていた。
「これは最後通告だ。二度とこの町に現れるんじゃねぇぞ」
湯沢くんが動けない少年たちにむかって、びしっと決めポーズを作った。それは僕が彼に貸した漫画に登場する、ヒーローの決めポーズとまったく同じものだった。

僕と湯沢くんは、この町に住むご近所さんで昔から交流があった。互いに進む道が違い過ぎて親友にはならなかったけど、今でも適度に仲の良い幼馴染同士だ。だから僕が彼の関節技を甘んじて受けているのは、痛いのが好きとか、不本意に弄られているわけではなかったのである。
「窓木くん、血が出てるよ」
三人で会場の明るい場所に戻って来ると、服田さんは和装の巾着袋からハンカチを出して、血が出ている鼻の下を押さえてくれた。
彼女は昼間のワンピースとはうって変わって、花火の模様があしらわれた空色の浴衣を着ていた。その姿は見惚れてしまうほどかわいかったけど、彼女を褒めていいのは僕ではなく、無敵のヒーローである湯沢くんだった。
「いろいろごめん」
ハンカチを汚した上に、デートの邪魔をしたことが申し訳なくて謝った。何よりも彼女の前でこんな姿を晒している自分が惨めだった。
「気にすんなよ。じゃあおばさんによろしくな」
湯沢くんが手を上げて背中を見せたので、「助けてくれてありがとう」と二人にお礼を言った。でも服田さんは何故か、「湯沢くん、また学校でね」と彼を見送ってその場にとどまった。
「行かなくていいの?」
僕が聞くと服田さんは「何で?」と聞いた。
「だってデートだったんじゃ……」
「ふふっ、窓木くんって面白いね」
「違うの?」
「違うよ。窓木くんを見つけて助けを呼ぼうとしたら彼がいたの。町内会のパトロールを手伝っているんだって」
話を聞いて全身から力が抜けた。でもよく考えてみれば、もし服田さんが今日デートだったなら、「じゃあむこうでまた会えるね」なんて言うはずがない。殴られて動揺していたとはいえ、考えが浅はかだった。とにかくこれで、僕は正々堂々と彼女の浴衣を褒めることができると思った。

「あ、いたいた!」
声のした方を見ると、遠くで浅倉さんが手を振っていた。服田さんが振り返したので倣ったら、浅倉さんは僕に気づいたのかサッと手を下ろした。
「ふくちゃん、何でそいつといるの?」
朝倉さんはこっちに来るなり文句を言った。きっとこの場で服田さんの浴衣を褒めたなら、「そんないやらしい目で見てたの?」と言われてしまうに違いなかった。
「たまたま、偶然会ったんだよ……ね?」
「あ、うん」
気を遣ってくれたのか、服田さんは僕がさっき絡まれていたことには触れなかった。
「だからってさ。あたしがトイレ行った隙にいなくならないでよぉ」
「だよね、ごめんなさい」
服田さんは彼女を待っている間に、連れていかれる僕を見かけたのだろうか。だとすれば浅倉さんにも悪いことをしてしまった。
「ちょっと待って。まさかあんたたち……」
何を思ったのか、浅倉さんが僕と服田さんを交互に睨んだ。すかさず服田さんが、「何?」と彼女の顔色を伺った。

「あたしに何か隠してるでしょ?」
「何も隠してないよ?」
あっさり否定したものの、服田さんの目は泳いでいた。たぶん彼女は嘘をつくのが苦手な人なのだと思った。
「わかった! 本当はこいつと付き合ってるんでしょ!」
浅倉さんが大きな声を張り上げ、周囲の人たちが何事かとこちらを振り返った。服田さんが「ち、違うってば!」と狼狽する。僕は二人にこれ以上迷惑はかけられないと、朝倉さんにこれまでの経緯を話して誤解を解いた。
「そっか、ふくちゃんに救われて良かったね。だけど連れはどうしたの? 見当たらないじゃん」
そういえば河野くんを駐輪場に待たせたままだった。腕時計を見ると駐輪場を出てからだいぶ経っている。ただ服田さんと別れるのは寂しかったので、僕はこの夏一番の勇気を出した。
「知ってるかもしれないけど、祭りの最後に花火が上がるんだ。よかったらみんなでそれを一緒に見ない?」
「でも、どうせそんなの大したことないんでしょ?」
かなり無理をして誘ったのに、服田さんの前には浅倉さんという大きな壁が立ちはだかっていた。それに花火は沢山上がると答えたかったけど、親の話によれば用意した花火は二十発だけ。それでも予算がない町内会としては大奮発なのだという。
「親は二十発上がるって言ってた」
「やっぱりね。それって一瞬じゃん」
「だけど夏といえば花火だよね。綺麗だろうな」
浅倉さんは引いているけど服田さんが話に乗ってくれた。彼女と一緒に花火を観るチャンスは、まだ残されているように思えた。
「お祭りは九時までだから、八時半くらいには上がると思うんだ」
もうひと押しと意気込んで続けたら、服田さんの表情がふっと曇った。
「そっか、残念。うちの門限が八時までなんだよね」
「そうなんだ……じゃあ仕方ないね」
これにてゲームオーバー。さらにこれは現実なので、ゲーセンのようにコインを投入して、コンティニューすることはできなかった。
第五話 ハンカチと五円玉
「おせーな、今まで何してたんだよ」
駐輪場に戻ると、河野くんが砂利で山を作りながら時間を潰していた。

「ごめん、ちょっとトラブってて」
「焼きそばは食ってきたのか?」
手ぶらだったからか、そんな質問が飛んできた。焼きそばは殴られた時に落としてしまった。今頃はあの少年たちと一緒にカラスや野犬の餌になっていることだろう。
「いいからもう帰ろう、今日は疲れたよ」
自転車に乗って駐輪場を出たところで、盆踊り会場にいるはずの服田さんと浅倉さんに遭遇した。よく見ると、浅倉さんが草履の片方を手にして立往生していた。
「あの二人、困ってるみたいだ」
自転車を停めて、僕は服田さんたちがいる方向を指差した。
「おい、俺たちを暇人扱いしたやつらだぞ?」
「だからって放っておけないよ。行ってみよう」
河野くんは昼間の件を根に持っているみたいだけど、僕には妙案があった。だから嫌がる河野くんの腕を強引に引っ張って、服田さんたちの元に駆けつけた。
「窓木くん」
服田さんが気づいて手を振った。浅倉さんは河野くんを見てむっとした。
「鼻緒が切れちゃったの?」
そっぽをむいたままの浅倉さんに聞いた。答えない彼女の代わって服田さんが「でも上手く直せなくて」と答えた。
「それなら大丈夫、河野くんが直してくれる。彼の家は靴屋さんなんだ。そうだろ?」
僕に名指しされた河野くんが目を丸くした。顔を上げて「そうなの?」と尋ねる浅倉さんと河野くんの目がぴったり合った。
「まぁな。ハンカチと五円玉あるか?」
「あるけど本当に直せるんでしょうね?」
「当たり前だろ!」
浅倉さんは少しの間だけ逡巡していたけど、このままじゃ帰れないと観念したのか、草履と修理に必要なものを河野くんに渡した。河野くんは彼女の目を見ずにそれを受け取ると、慣れた手つきで草履を直し始めた。彼は照れていたけど腕はたしかで、浅倉さんの草履は間もなく修復された。
その後、草履のお礼に浅倉さんが奢ると言い出し、僕らは彼女たちと一緒に出店通りを歩くことになった。浅倉さんは張りきって全員分のりんご飴を買って配った後、すぐに「こんなの大きすぎて食べきれない」と文句を言い出した。

「もういらないからあげる」
浅倉さんが持て余した自分のりんご飴を河野くんに押しつけた。
「おい、こんなの二つも食えるかよ」
河野くんは愚痴りながらも、何故か嬉しそうに見えた。
「ねぇ窓木くん、せっかくだから踊ろうよ」
服田さんが盆踊りのやぐらを見て僕を誘った。
「みんなの前で踊るの?」
「だって盆踊り大会だよ?」
昼間の妄想が現実になりかけていた。なのにいざとなると、僕はすっかり腰が引けていた。
「だけど踊りは苦手なんだ。遠慮しておくよ」
「じゃあひとりで踊って来てもいいかな。毎年恒例なの」
「じゃあここで待ってるよ」
やがて服田さんがやぐらの前で踊り出し、これまで霞んでいた会場が華やいで輝き始めた。彼女の浴衣姿に見惚れていると、うしろから河野くんに肩を突つかれた。
「窓木も踊ってこいよ。服田のことが好きなんだろ」
「え?」
「バレてないとでも思ってたのかよ?」
河野くんはそう言って、二個目のりんご飴にかじりついた。
最終話 浴衣と打ち上げ花火
「でも盆踊りなんて一度も踊ったことないし」
「っていうか頼む。俺も浅倉と二人きりになりたいんだ」
浅倉さんは少し離れた場所で、金魚すくいに興じる子どもたちを眺めていた。
「ねぇ、早く金魚すくいしようよ!」
彼女がむこうから河野くんを呼んで、彼は僕を拝んだ。
「……わかったよ」
ヒュルルルルルル~……ドド~ン。
ちょうどその時、夜空に華が咲いて歓声が上がった。盆踊りの曲が止んで、予定よりも早い打ち上げ花火にみんなが空を見上げた。服田さんも花火に夢中で、僕が傍に来ても最初は気づいていないみたいだった。

「花火が見られてよかったね」
近寄って声をかけると、服田さんは僕に顔をむけてから呟いた。
「うん、とってもきれい……」
それから二人は無言のまま花火を見物した。ただこうしている間にも彼女の門限は刻々と近づいていて、浴衣を褒めるなら今しかないと思った。
「おや、今年から浴衣にしたのかい?」
ちょうどそこに浴衣姿のお年寄りが来て、服田さんに話しかけた。
「あ、こんばんは」
「やっぱり似合うわぁ。だから毎年、浴衣にすればって言ってたのよ」
「えへへ。でも下の方がすーすーして、少し落ち着かないです」
知り合いのおばあちゃんらしく、服田さんは少し照れくさそうにしていた。
「それに今日は、恋人さんと一緒なんだね」
おばあちゃんはそう言って、僕にペコリとお辞儀をした。
「あ、ただの同級生です。恋人なんかじゃなくて……」
「まあまあ、恥ずかしがっちゃって初々しいこと」
「本当に違うんです! だって僕と彼女じゃ全然釣り合わないでしょ?」
懸命に否定する姿が可笑しかったのか、服田さんが声を出して笑った。
「デートの邪魔をしちゃ悪いわね。じゃあごきげんよう」

おばあちゃんがいなくなると、服田さんが花火を見ながら口を開いた。
「ここの盆踊り大会は毎年参加していて、去年までは洋服で踊っていたの。浴衣は着るのがめんどくさいし、帯が苦しいと思ってたから」
「なら今日はラッキーだったのかな。服田さんの貴重な浴衣姿が見れたから」
「もしかしたらそうかもね」
彼女は言いながら、腕の時計で時間を確認した。
「ごめんなさい、そろそろ帰らないと」
「門限があるんだよね」
もう時間がなかった。たぶんこれが最後のチャンスだ。焦って変なことを口走らないように、頭の中で褒め言葉を反芻していると、浅倉さんたちが駆けてきた。
「そんなふうに走ってっと、また鼻緒が切れんぞ!」
浅倉さんのうしろで河野くんが叫んだ。
「そうしたら、また直してくれるんでしょ?」
浅倉さんに言い返されて河野くんが「ちぇっ」と舌打ちした。短い時間にも関わらず、どうやら二人の仲はだいぶ進展しているみたいだった。
「ふくちゃん、そろそろ帰る時間だよ」
浅倉さんに促されて服田さんが頷いた。
「じゃあ窓木くん、また学校でね」
「うん、学校で」
ここで服田さんと別れたら次に会えるのは新学期だ。でもその時に今日の浴衣を褒めても遅すぎるに決まっていた。
「服田さん!」
彼女の背中にむかって呼びかけると、彼女は驚いて振り返った。
「なに?」
「その浴衣姿。すごく似合ってるって、ずっと思っていたんだ。だから次のお祭りでも着てくれたら、僕としてはすごく嬉しいんだけど!」
すると服田さんは立ち止まって振り返り、黙ったままこちらに戻って来た。それからつま先立ちで僕の耳元に顔を近づけると、こんな風に小さく囁いた。
「なら、大変な思いして着てきた甲斐があったよ」
ドーン、パラパラパラ……。
二十発目の花火が華々しく散って、盆踊りの曲がふたたび流れ始めた。

「窓木くん。せっかくだし一緒に踊ろうか?」
夢心地の中、服田さんが僕の袖を掴んで引っ張った。
「でも門限は?」
「少しくらい怒られても平気。さあ行こ」
服田さんと手を繋ぎ、盆踊りのやぐらにむかって歩き出す。
こうして平凡だった僕の夏休みは、彼女のおかげで打ち上げ花火のように、鮮やかで特別な想い出へと変わろうとしていた。
おわり
最後まで読んで頂きまして、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
