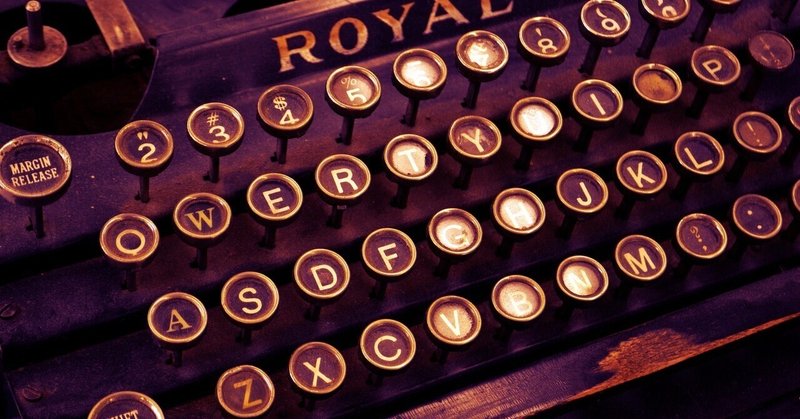
Big4コンサルティングの歴史 第3話(コンサルティング誕生編 1890~1900年代アメリカ)
本編(第3話)のあらすじ
19世紀後半、アメリカの経済が急速に発展すると、イギリスの会計事務所はクライアントの要請でアメリカへ進出しました。イギリスとは違ったビジネス環境で会計事務所は事業を拡大し、そこから、後の経営コンサルティングにつながるような仕事も始まりました。会計業務の機械化が進むなか、会計士は伝統的な決算書作成・会計監査業務に留まらず、業務改善のアドバイザーとしても関わるようになりました。
会計士、海を渡る
イギリスからアメリカへ
19世紀後半、世界の工場の座からイギリスは陥落しました。代わってその座に着いたのはアメリカでした。アメリカの成長は著しく、ヨーロッパを中心に新大陸へ人と資本が流入していました。アメリカの産業の発展を受け、イギリスで成功した会計事務所の中にはアメリカでの事業を拡大していくところがありました。そこにはどのような背景があったのでしょうか。
当時のイギリス産業や経済状況について『近代イギリスの歴史』(木畑洋一/秋田茂)では次のように書かれています。
19世紀後半にはイギリス資本主義の構造変化と、世界経済全体の再編が起こった。アメリカ、ドイツなどの急速な工業化と、アルゼンチン、カナダなどからの農畜産物輸出が拡大した結果、工業の面ではアメリカ、ドイツに追い抜かれイギリスは「世界の工場」から「三大工業国」の一つに転落した。農業の面でもカナダなどからの安い農畜産物との競争にさらされ、イギリス国内は農業大不況に直面した。
代わりにイギリスの貿易構造の改善に貢献したのは利子・配当収入での埋め合わせだった。その背景には、イギリスから世界各地への資本(カネ)の輸出の急増があった。その海外投資先はカナダなどの農畜産物輸出国とアメリカに集中しており、投資の対象は各地の鉄道建設や公共事業などの整備に関わる債権や、鉄道会社の証券などが中心であった。
こうしてイギリスは「世界の工場」から「世界の銀行家」(金融サービスの中心地)へと変わっていった。このようなイギリス資本主義構造の変化を支えたのが大土地所有者(地主階級)を中心とする伝統的なジェントルマンであった。農業大不況により経済的基盤に大打撃を受けた大土地所有者は農業投資を控え、代わりに地代と土地資産の売却利益を海外の有価証券の保有に切り替え、利子や配当収入を得る金融資産の所有者に転じることができたのである。
このジェントルマンの変化は『イギリス近代史講義』(川北稔)でも述べられています。
1850年頃にはものづくりの産業資本家ではなく、財産を貸してその利潤で生活をするというタイプの資本主義に変わっていった。ものづくりのような実物経済より、金融や情報といったバーチャルな分野に依存するジェントルマンの性格が強くなっていった。かつてジェントルマンは地方の地主だと言われていたが、19世紀中頃を境に、ジェントルマンの中核はシティに移り、ジェントルマンを見たければシティに行けとまで言われるくらいになった。
アメリカの状況について、アメリカ史関連の書籍ではおよそ次のようなことが書かれています。
経済が急激に発展したアメリカでは、国内の銀行だけでは事業者の資本がまかなえきれなくなったため、イギリスを始めとするヨーロッパ諸国の銀行から、多くの資本が投入されるようになった。特に1869年に完成した大陸横断鉄道は産業の発展に大きく貢献した。鉄道網は19世紀末までに全国津々浦々に張り巡らされることになる。鉄道は物流を支えただけではなく、鉄鋼などの関連産業を大いに潤した。その結果、アメリカは急激に大国へと成長し、企業同士の競争も激化、強者は様々な形で企業の連合・統合を進め、弱者を次々と買収し独占する巨大企業が生まれてきた。特に鉄道業、鉄鋼業、石油産業などで独占形成は活発に行われた。
イギリスの資本主義構造の変化と南北戦争(1861〜1865年)後のアメリカの急成長を背景に、1870年代、1880年代を通じてイギリスの資本家達はアメリカ経済に多額の投資を行いました。資本家達は自らの経済的利益を守るため、イギリス(イングランド、スコットランド)の会計事務所に対して、アメリカへ定期的に訪問することを要求してきました。
当時のロンドンの金融プロモーターは、投資家に対して様々な投資先を紹介しつつ、スコットランドやイングランドの会計事務所に対しても仕事を発注し、アメリカの投資先会社の財務情報について調査を依頼してきました。そのため、会計事務所が会計士をアメリカに派遣することが多くなりました。例えば、プライス・ウォーターハウスの場合は1873年を皮切りに、1880年代には繰り返し渡米するようになりアメリカでの業務が増えていました。
投資家がイギリス人であるということにより、アメリカ企業でありながら現地アメリカ人による会計調査が好まれないと考える面もありました。また、1880年にイングランドとウェールズでも勅許会計士が制度化されていることで、イギリス人会計士への信頼が増していたという状況であったと考えることができます。
イギリスの会計士が大挙して大西洋を渡った背景には他にも当時のアメリカ国内の会計士事情も考えられます。
当時のアメリカの会計士業界はイギリスに比べ未成熟で専門的な会計士が少なかったと思われます。例えば、会計士の人数を見ても、1870年には、ニューヨークに12人、フィラデルフィアに14人、シカゴに2人、合計28人が自称会計士として登録していたに過ぎなかったという記録が残っています。16年後の1886年でも、ニューヨーク45人、フィラデルフィア33人、シカゴ6人、計84人に増えているに過ぎません。ロンドンでは1860年にすでに300人以上の会計士が登録されていたことを考えるとその差は歴然です。そのような中、イギリスから専門性の高い、高度な会計技術を持った会計士達が押し寄せてきたのです。
イギリスの会計事務所はアメリカでの仕事をするために何度も何度もイギリスからアメリカに会計士を派遣していました。当時はイギリスからニューヨークまで船で8日程度かかったようです。出張の移動だけでも相当なものだったわけです。
1.1880,1890年代イギリス-アメリカ間は船でどれくらいかかりま... - Yahoo!知恵袋
当初はイギリス本土からアメリカでの業務を管理していたイギリスの会計事務所が、アメリカに事務所を構えた方が賢明だと考えるのは自然なことでした。最初にマンチェスターの会計士が渡米しニューヨークに事務所を開設したと言われていますが、その後に続くように、現在のBig4に繋がるイギリスの会計事務所が次々とアメリカに進出していきました。

(参考資料)
『イギリス近代史講義』(川北稔 著)
『一冊でわかるアメリカ史』(関眞興 著)
『大学で学ぶ アメリカ史』(和田光弘 編著)『アメリカの歴史』(有賀夏紀/油井大三郎 編)
『近代イギリスの歴史』(木畑洋一/秋田茂 編著)
『闘う公認会計士』千代田邦夫 著
『ACCOUNTING FOR SUCCESS』DAVID GRAYSON ALLEN / KATHLEEN MCDERMOTT
会計士とコンサルティング・サービス
19世紀後半にイギリスからアメリカに渡った会計事務所、会計士達は、好調なアメリカ経済に支えられたこともありアメリカで事業を拡大していきました。手にかける仕事の範囲も広げ、会計システム業務などの新しい分野に進出し、革新的な仕事を受けるところも出てきました。そのような仕事のなかには、後の経営コンサルティングにつながるものもありました。
アメリカのビジネス界で生きていくため、イギリスでの伝統的な会計事務所の流儀をアメリカ流に変えていくことが求められました。イギリスでは名が通っていたプライス・ウォーターハウス会計事務所も例外ではありませんでした。
ロンドンでは座って待っていても仕事が舞い込んで来ましたが、ニューヨークではそうはいきません。マーケティングやプロモーションを試みて事務所を売り込んでいく必要がありました。イギリスでは事務所の告知、宣伝は公認会計士協会の原則に反すると受け取られましたが、アメリカの会計事務所は、皆、当然のように行っていました。
アメリカでは積極的に仕事を取りにいくことを求められたことから、イギリスからきた会計事務所は自然と本業の監査以外にも業務を拡大していきました。そういうことも会計事務所がコンサルティング・サービスを始めた理由の一つと考えられます。当時、会計事務所が始めたコンサルティング・サービスは主に「財務調査」と「会計システムのアドバイザー」でした。
財務調査サービスは、アメリカで合併事業やベンチャー企業への資金を提供する銀行(J.P.モルガン等)が、投資先を評価するために財務情報の調査を会計士等の専門家に頼るようになったことから始まりました。
また、会計システムのアドバイザーサービスは、19世紀末に企業のオフィスで急速に進んでいた事務作業の機械化、例えばパンチカードの導入やタビュレーティングマシーンの導入の支援のために帳簿の専門家である会計士を頼ったということでしょう。
ロンドンからニューヨークに渡ったプライス・ウォーターハウス会計事務所(後のPWC)も20世紀初頭には様々なコンサルティング案件に関わっていました。そこには、合併調査、簿記システム、予算編成、業務改善、原価計算などのコンサルティング、会計システム導入のアドバイス等が含まれていました。
記録が残っている中から、プライス・ウォーターハウスが担当した具体的なコンサルティング案件をご紹介します。
・J.P.モルガンからの農機具メーカー5社の会計調査案件(1902年)
・ミネアポリス市の会計・簿記システムのコンサルティング案件(1903年)
・生命保険会社の財務調査、業務改善コンサルティング、会計システムの導入案件(1905年)
・アメリカ郵便局の会計調査と改善コンサルティング、会計システムの導入案件(1907年)
・映画会社の会計調査、会計システム導入案件など
事業の順調な発展により、アメリカのプライス・ウォーターハウスのオフィスの従業員数は1901年の24人から1903年には73人に増え、10年後の1911年には145人に増えました。オフィスの数も2ヶ所(ニューヨーク/シカゴ)から11ヶ所に増え、その成長ぶりが伺えます。
当時の会計システム
オフィス再構築
19世紀末、アメリカ社会は経済活動の多様化を受け、新たな中産階級の登場やホワイトカラー事務職が急増しました。『アメリカの歴史』(有賀夏紀・油井大三郎 編)では次のように説明されています。
都市化が進み、巨大株式会社が誕生し、専門化が進行する19世紀末になると、企業の会計・販売担当の事務職や管理職、技術者、法律家などのインテリ層が中産階級に加わった。
市場経済の浸透は、より多くの所得を求める女性の労働参加を促した。経済活動の多様化に伴って、これまであったブルーカラー的な職種のほかに、店員、タイピスト、帳簿係、事務員、といったホワイトカラー事務職が急増し、それらの多くが女性によって占められた。 1910年には就業する女性数は760万人、女性全体の中の労働参加率は20%に近くなった。
また、企業のオフィスは新たなホワイトカラー層が登場しただけではなく、アメリカという土地柄からオフィス事務作業の機械化が急速に進んでいきました。このオフィス革命は特に会計分野において顕著であり、会計士がコンサルティングを推進することになった歴史的背景の一つと考えることができると思います。19世紀末のアメリカでオフィス革命が進んだ背景を『コンピューター200年史』では次のように説明しています。
19世紀末における事務機器の氾濫は、まったくアメリカ社会だけの現象だった。ヨーロッパでは20世紀になるまでこのようなことは起こらなかったし、大多数のビジネスでは第一次世界大戦の後までそうはならなかった。
アメリカの事務機器に対する愛着には2つの理由がある。 第1はヨーロッパに比べてアメリカのオフィスが遅れてスタートを切ったことがあげられる。したがって旧式なオフィス、 昔風に固まった業務手順を引きずりながら前進するというハンデは背負っていなかった。もう一つは、アメリカ人がひどく機械好きで、機械化されたオフィスの魅力に抵抗できなかったからだ。アメリカの会社はしばしば事務機器を、ただそれが目新しいというだけの理由で購入している。
新しいタイプの科学的管理者は、オフィスの再構築を推進した。タイプライターと加算機の導入、複式記帳とルーズリーフを使うファイリングシステムの採用、旧式な大福帳方式から機械式勘定書作成システムへの移行などなど。これらの新しいタイプの科学的管理者は今日の情報テクノロジー・コンサルタントの前身であった。
プライス・ウォーターハウス会計事務所が20世紀初頭に関わったコンサルティング案件の中に、会計システムの導入というものがいくつかありました。恐らく、上記に記載したようなオフィス再構築のようなものだったと思います。
手書きの契約書や請求書などのビジネス書類の作成を、タイプライターを使った作成へ変えることで、書き手の癖はなくなり文字や数字の読み間違い、それによる帳簿記載ミスは各段に減ります。また、加算機(初期の計算機)も同様で、伝票の計算であったり帳簿の集計やチェックにおいて、人手で起こっていたミスと人手でかかっていた作業時間を同時に減らすことができ、会計業務を一気に効率化させることができたのでしょう。
タイプライター・加算機・キャッシュレジスター・パンチカードシステムの普及により、19世紀末から20世紀初めのアメリカでは、事務作業や会計業務の機械化が急速に進み、そこには民間企業や国、自治体向けに会計システム機械化の導入支援をコンサルティングサービスとして展開する会計士達がいました。
タイプライター
タイプライターは事務機器の中でも導入時期が早く、1870年頃から各方面への導入が進んでいました。それまでの手書き文書を機械化することによって、ビジネス文書を書く時間と経営者がそれを読む時間の両方が何倍も速くなり、ビジネスのスピードが急速に上がる結果になりました。そして、タイピングができる人(特に女性)が求められ、女性の職業選択肢の一つとなったと位置づけられています。当時の代表的な会社の中にレミントン社がありました。1874年にレミントン社はタイプライターの最初の商用化に成功しています。

加算機
加算機は計算を行う機械で、タイプライターより少し後の1880年代に出てきています。一般事務用の加算機は手書きよりも速く数字を入力でき、入力すると同時に紙に印刷するという機能を備えていました。
加算機の代表的な会社にはバローズ社がありました。バローズ社は20世紀に入るとセールスを驚異的に伸ばし、1904年には年間4500台を生産、1年もたたないうちに年間生産量は8000台にまで増え、3年後には年間1万3000台を売り切っていました。

バローズ社がこれほどの加算機を販売できた理由として、加算機を売るだけではなく、それを顧客の業務にどのように組み入れるかというノウハウ・サービスも提供していたことが挙げられます。ビジネス面の経験を積み重ね、やがてバローズ社は機械と一緒にビジネスシステムを売る会社になり、2つの大戦を経て、加算機を超えた完全な会計機械メーカーとなったと評価されています。
アメリカで加算機産業が発達した背景には国内での累進税率の適用であったり、給与の源泉課税など、1913年に導入された新しい税制も引き金の一つになっているという考えがあります。その後の第一次世界大戦中にもアメリカでは法人税が拡大され、それに伴う事務量の増大により加算機の需要はいっそう拡大したようです。また、新しい税制の導入は、機械産業の発展だけではなく、会計事務所が税務アドバイスのサービスを新たな事業として展開していくことにも大きく影響しました。
キャッシュレジスター
売上金を管理するこの機械により、店員が売上をちょろまかすのを防ぎ、売上集計が簡単にできるようになりました。代表で紹介する会社はもちろんナショナル・キャッシュ・レジスター社(NCR社)です。
1884年に事業を始めたNCR社は、2年後に既に年間1000台以上の機械を売り上げています。さらに1900年には2500人の従業員を擁して年間約2万5000 台のキャッシュレジスターを販売し、1910年には従業員5000人で年間10万台、そして1922年には200万台のレジスターを売り上げていました。

その後の話を少しすると、NCR社は製品を多角化して会計機械の分野に進出していきます。1926年に発売を開始したクラス2000会計機は、送り状の発行、給与計算をはじめ、あらゆる業務を網羅した会計機能を持ちます。これは、当時市場にあったいかなる会計機にも引けを取らず、バローズ社の会計機とも完全に対等でした。
コンサルティングとも関係するのでNCR社についてもう少し話します。この会社が事務機械で行った最大の功績は、この産業での機械の販売方法を生み出したことだと言われています。機械の販売は、顧客ニーズの分析・アフターサービスの提供・ユーザーのトレーニングによって強化されるという販売方法です。これはNCR社が1890年代に開発し、その後のコンピューター/情報システム産業で繰り返し実践されてきました。
パンチカードシステム
このシステムはパンチカードに打ち込まれた穿孔(穴)を読み取り、集計結果を表などに印刷する機械です。電子コンピューターが世の中の主流を占める20世紀中頃まで会計システムの中心を担っていたものでした。
他の機械に比べパンチカードシステムの普及は遅く、1905年には、タイプライターと加算機産業は大きく成長していましたが、パンチカードシステムはまだまだこれからの産業でした。世界中にタイプライターは100万台、加算機は何十万台も普及していたのに比べて、 パンチカードシステムは数えるほどしか設置されていなかったのです。
パンチカードシステムの代表として紹介する会社はタビュレーティング・マシン・カンパニー社(TMC社)です。TMC社は1908年までに30社の顧客を獲得しました。それに続く数年間、会社は半期に20パーセントの割合で成長を続け、1911年には顧客数は約100社に達しました。


このシステムが使われていたのは、製鉄所、保険会社、鉄道等の当代きっての産業から、地方自治体、政府機関とあらゆる企業に渡っていました。労働コストの記録、販売の分類、原材料の調達、生産の統計等の様々な集計に使われ、保険のリスク計算、企業の経費や公共サービス部門の業務分析等でも活躍しています。売上やコストをセールスマンや部門、 顧客、地域、商品等、他いろいろな分野別に分類することもできたので、 このシステムが無かったらかかったであろう膨大な時間に比べると、ほんのわずかな時間で結果を得ることを可能にしました。
事務機器メーカーのその後
それでは最後に、事務作業機メーカー各社のその後に簡単に触れておきたいと思います。というのも、この半世紀後の20世紀半ばにアメリカの大手会計事務所がコンピューターを使ったコンサルティング事業に進出するとき、各社の製品と再び深く関係してくるからです。
タイプライターのレミントン社はいくつかの事務機器メーカーとの合併を経て、第二次世界大戦後にアメリカ最初の商用コンピューターであるUNIVACを販売します。加算機のバローズ社は会計機の事業を拡大し、同じく大戦後にメインフレームコンピュータのメーカーとなっていきます。そして今はユニシス社として知られている会社になっていきます。バローズ社はその過程でレミントン社を買収します。
キャッシュレジスターのNCR社はその後POSシステムや銀行ATM機でも有名になり、コンピューターメーカーとしての地位を築いていきます。
パンチカードシステムのTMC社は1911年にコンピューティ ング・タビュレーティング・レコーディング社(CTR社)という新会社の一部門になり、1914年にトマス・J・ワトソン・シニアを社長として迎えます。そして1924年にワトソン氏は会社名をインターナショナル・ビジネス・マシンズ社(IBM社)に変えて、ご存知の通りコンピューター産業の伝説となっていきます。
(参考資料)
『アメリカの歴史』(有賀夏紀・油井大三郎 編)
『コンピューター200年史』(M.キャンベル・ケリー/W.アスプレイ 著 山本菊男 訳)
(参考)コンサルティングの誕生
経営コンサルティングにつながる仕事を20世紀初頭の会計事務所が行っていたことを見ましたが、アメリカのコンサルティング全体の歴史の中で、19世紀末~20世紀初頭はどのような時代だったのか。『The World's Newest Profession -20世紀の経営コンサルティング-』(クリストファー・マッケナ著)では当時のアメリカにおけるコンサルティングの様子を次のように説明しています。
19世紀末のコンサルティングはどこから始まったのか。それは大手コンサルティング会社の本拠地であるシカゴでもなく、大企業の本社があったニューヨークでもなく、フレデリック・テイラーが初めて科学的管理法を開発したフィラデルフィアでもない。それは、アメリカで第二次産業革命の先陣を切ったマサチューセッツ工科大学(MIT)の技術者たちが、コンサルティング・エンジニアリング会社を設立したボストンで始まった。
1870年代以降、アメリカで第二次産業革命が起こると、化学、物理の学者や専門家が、新興メーカーでコンサルタントとして仕事をするようになっていた。企業は技術者を短期間のコンサルタントとして、あるいは長期的な研究スタッフとして雇った。デュポンやイーストマン・コダックのような技術的に最も進んだ企業が、19世紀末に主要な工学部、特にMITと密接な関係を築いていった。
このことは、1880年代にMITの卒業生がボストンで設立した2つのコンサルティング・エンジニアリング会社の急成長からも分かる。化学エンジニアのアーサー・D・リトルが1884年にMITを中退して設立したアーサー・D・リトル社と、電気エンジニアのチャールズ・ストーンとエドウィン・ウェブスターが1888年にMITを卒業して設立したストーン&ウェブスター社である。それぞれ最先端の技術について大企業と協力し、ハイテクへの投資について金融機関に助言を行うようになった。
ボストンを拠点とするこの2社は、MITやハーバードの教授との強いつながりとボストンの銀行が新興メーカーへの融資で優れていたということもあり、特に成功した。
ボストン以外にはフレデリック・テイラーがいた。テイラーは、アーサー・リトル、チャールズ・ストーン、エドウィン・ウェブスターが大学を終えるおよそ10年前の1874年にエンジニアとしてのキャリアをスタートさせている。テイラーはフィラデルフィアの機械工として教育を受け、ボストンのコンサルタントとは一線を画すことになる。テイラーはやがて、新興メーカーの研究開発ではなく、鉄鋼などの伝統的な産業における労働生産性のコンサルティングによって、ボストンのライバルたちよりもはるかに有名になった。
(Christopher D. McKenna 著)
当時のアメリカでは、ボストンのアーサー・D・リトル社とストーン・アンド・ウェブスター社、フィラデルフィアのフレデリック・テイラー等がアメリカで最初のコンサルティングを企業に提供し始めていました。これはコンサルティングの起源を説明するものとしてはあまりに有名な話です。我々日本人も書籍やインターネット上で目にしていることでしょう。著者のマッケナ氏(Dr Christopher McKenna | Faculty of History (ox.ac.uk))の説明で興味深いのは、これらの会社や人物はアメリカで最初のコンサルタントであったとしても、現代のコンサルタントにつながるものではないと言っていることです。
1944年、フォーチュン誌が、経営コンサルティングの特集を組んだとき、その記事には、この分野の起源に関するありきたりな説明が含まれていた。フォーチュン誌は「米国での経営コンサルティングの発展は、フレデリック・W・テイラー、 ヘンリー・L・ガントなどの科学的管理のパイオニアたちから始まった」と説明した。注意しないといけないことは、1930年代以降急成長するアメリカの主要な経営コンサルティング会社は、テイラー主義の会社から発展したのではなく、科学的管理とはほとんど、あるいはまったく関係がないということだ。
ボストンのアーサー・D・リトル社やストーン&ウェブスター社を、経営コンサルティングの原型と考えるには無理がある。アーサー・D・リトル社は研究開発との結びつきが強く、コンサルタントは技術者であった。これに対して、ストーン・アンド・ウェブスターは、発電産業という特定産業でしか活動できなかったからだ。テイラーの科学的管理にも、労働者心理、職場と道具のデザイン、賃金システム、原価計算という少なくとも4つの異なる研究分野があるが、おそらくテイラーの中で最も認識されていない要素である原価計算においてこそ、ボストンやフィラデルフィアのエンジニアとその後に続く現代の経営コンサルタントが結びついている。1901年から1915年にかけて、アメリカでは著名な科学的管理の推進者たちが200社近いアメリカの企業に科学的管理を導入したが、その後は徐々に衰退していった。
(Christopher D. McKenna 著)
ボストンやフィラデルフィアでエンジニアを中心としたコンサルティングが行われ、一方で会計士を中心とした会計アドバイザリー業務も始まっていた、19世紀末~20世紀初頭のアメリカはそのような時代でした。
(参考資料)
『ACCOUNTING FOR SUCCESS』(DAVID GRAYSON ALLEN / KATHLEEN MCDERMOTT )
(第2話)
(第4話)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

