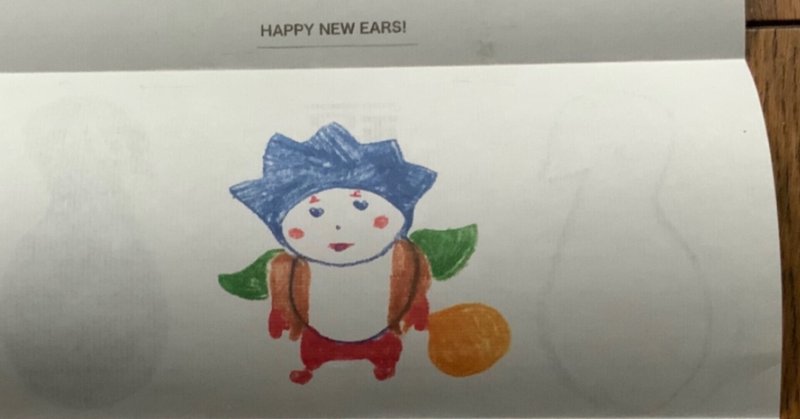#ミタマノフユ
まなかい; 冬至 『第66候・雪下出麦(ゆきわたりてむぎいづる)』
冬至から1週間ほど経って、斜めに挿し込む陽光が透かす樹影が揺れるのを見るともなく見ていた。ちらちらゆらゆら陽炎のような動きは止むことはない。光と風の永久運動に見惚れているうち、冬至でしばししんとした命がもう動き出している、そんな小さな音が波が寄せるように聞こえてきた。
今年の大晦日は、都心から出ていない。とても静かだった。電車が深夜走っていなかったこともあったが、外出を控える人が多かったのだろう
まなかい; 大雪 第63候 『鱖魚群(さけのうおむらがる)』
「母川回帰」というそうだ。
鮭の仲間が生まれた川の匂いを覚えていて、三年以上回遊した海から生まれた川に戻ること。それは最後の旅で、多くの種類は生涯に一回だけ放精あるいは放卵して死んでしまう。
渡鳥とか、海亀の産卵など、そうした母なる場所へ帰ってくるセンサーというのは、地球の律動のままに生きている彼らならきっと特別なことではないのだろう。
震災後はじめた「めぐり花」は、花の連句。
上の句とし
まなかい;大雪 第62候「熊蟄穴「くまあなにこもる)」
平安時代から江戸時代まで長く使われた唐の時代の暦「宣明暦」では「虎始交(とらはじめてつるむ)」だったそうだ。日本には虎はいないから、身近な熊の生態に目を向けたのだろう。
都会でも、早い春にお庭や畑の手入れをすると、冬眠中の蜥蜴や蟾蜍の穴を開けてびっくりすることがある。変温動物の彼らはほぼ仮死状態で動けないので「あ、ごめん、、、」とそのまま元に戻して、なんとなく後から思い出して申し訳ないと思いつつ